家賃収入で悠々自適に暮らす人を見ると、「本当にそんなに儲かるの?」と疑問に感じるかもしれません。まして物価高と金利変動が続く2025年、余計に迷いが深まるでしょう。しかし不動産投資が長年、多くの人に選ばれてきたのには明確な理由があります。本記事では「不動産投資 なぜ儲かる」をテーマに、収益の仕組みから税制優遇の活用法までを丁寧に解説します。読み終える頃には、利益が生まれる構造と初めの一歩を踏み出すポイントがはっきり見えてくるはずです。
不動産投資が生む二つの収益源
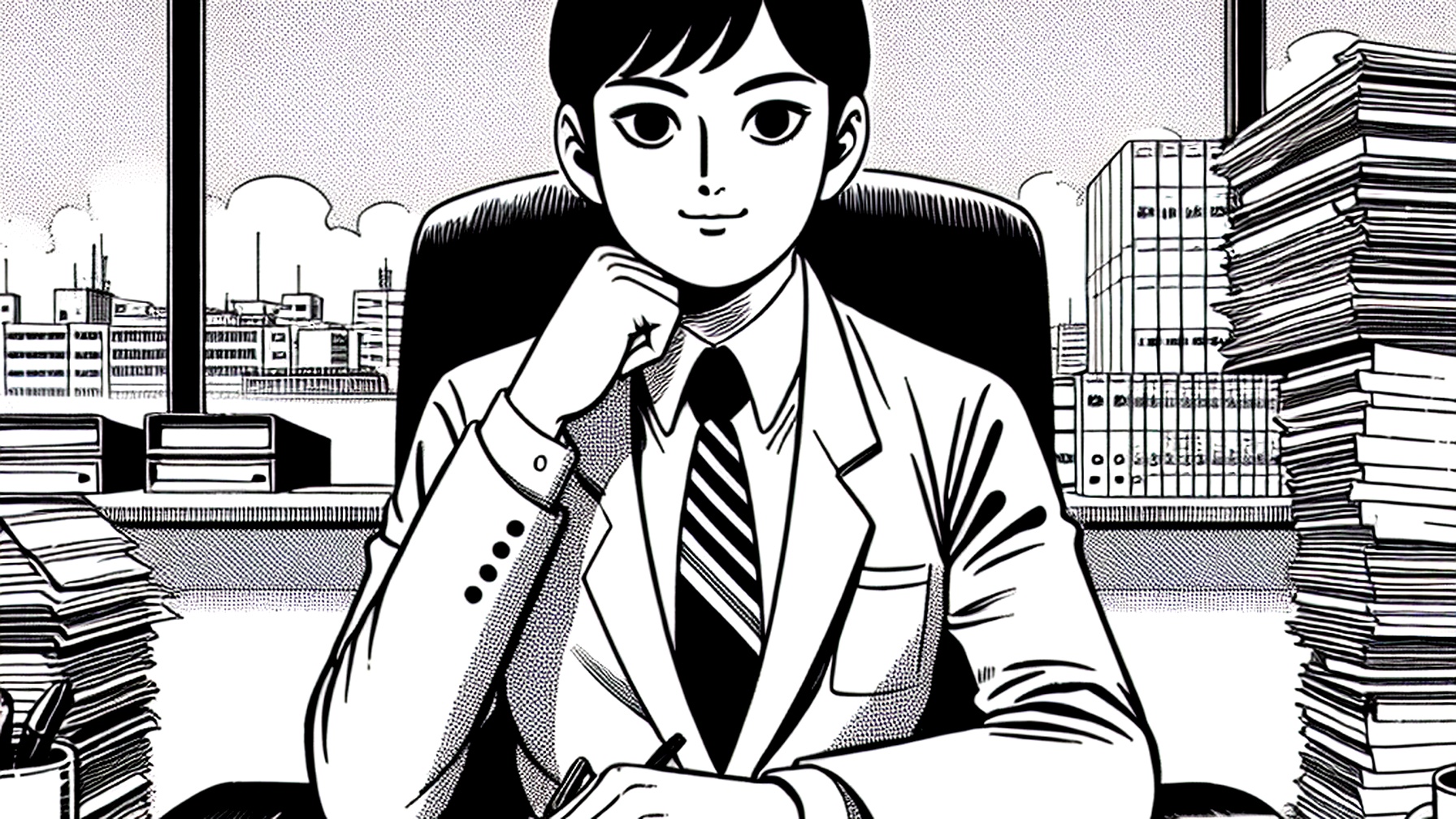
重要なのは、不動産投資で得られるお金が一種類ではないという事実です。家賃という継続的な収入に加え、売却益という一時的な利益が存在します。
まず家賃収入は、入居者がいる限り毎月入ってくるキャッシュフローの源泉です。国土交通省の「住宅市場動向調査2024年版」によると、全国平均の空室率はおおむね13%前後で推移しており、立地と賃料設定さえ適切なら安定した賃貸需要が見込めます。また入居契約は半年から二年程度が主流なので、株のように日々価格が変動するわけではありません。
一方、売却益は物件の価値が上昇したタイミングで手にする利益を指します。東京都心六区の中古マンション価格指数は2020年比で約18%上昇しており(一般財団法人日本不動産研究所調べ)、適切な出口戦略を取ることで大きなキャピタルゲインも狙えます。つまり二つの収益源を組み合わせることで、短期と長期の双方で利益を伸ばせる点が、不動産投資の強みなのです。
レバレッジ効果とキャッシュフローの仕組み
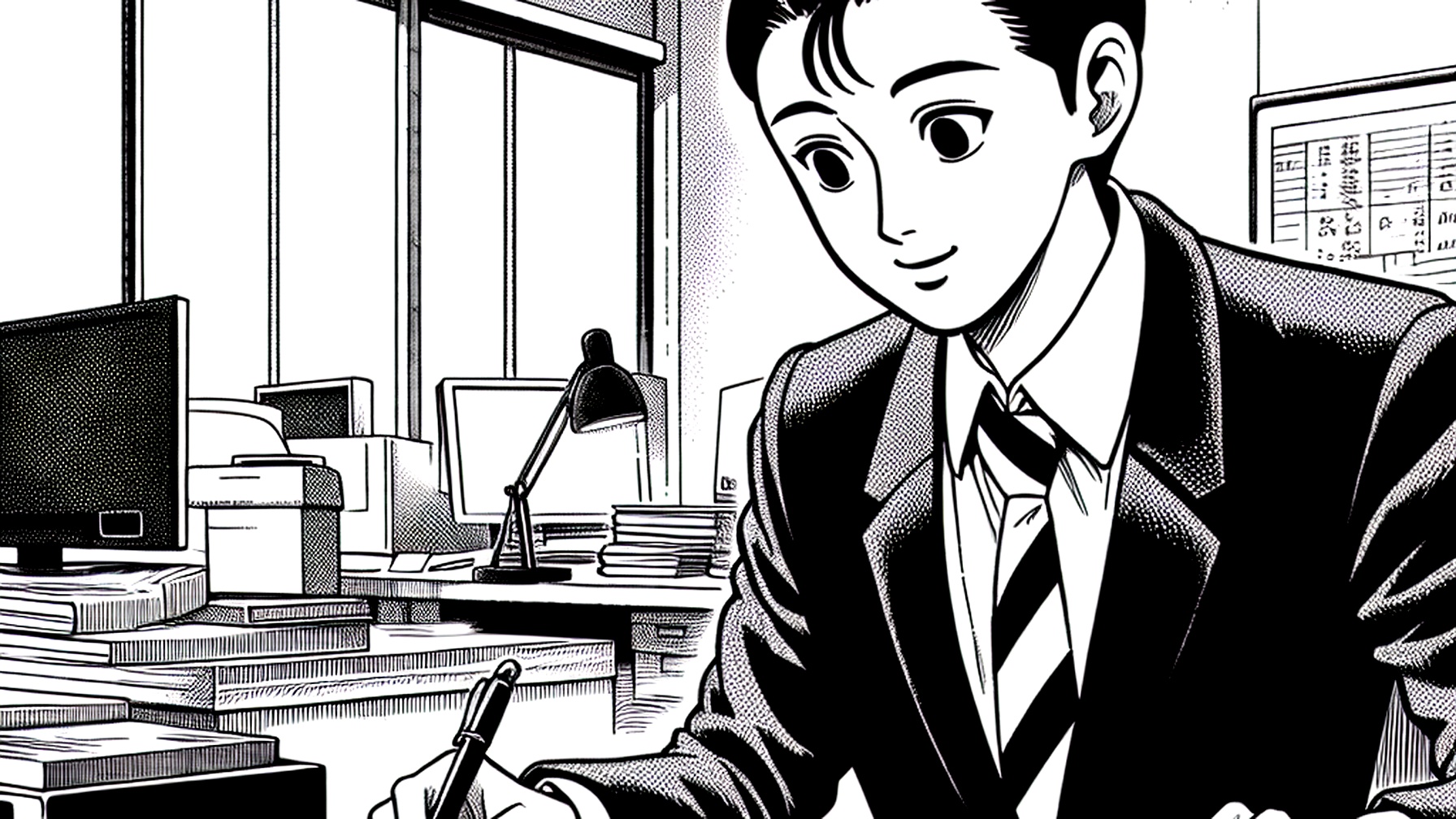
実は、投資家が自己資金以上のリターンを得られる背景にはレバレッジ効果があります。レバレッジとは金融機関からの融資を活用し、自己資金の数倍から十倍程度の物件を購入することを指します。
家賃は物件価格に比例して大きくなるため、投下資本に対する利回りが高まります。例えば自己資金500万円で3000万円の物件を購入し、年間家賃収入が180万円、諸経費を差し引いて手元に60万円残れば、実質利回りは12%です。日本政策金融公庫のアパートローン平均金利(2025年4月時点)は2.1%前後で推移しており、金利負担を差し引いてもプラスが見込みやすい水準と言えます。
さらにキャッシュフローを安定させるコツは、返済期間と繰上げ返済のバランスを取ることです。期間を長くすれば月々の返済額は減りますが、総支払利息は増えます。そこで、開始数年は長期返済で流動性を確保し、十分な自己資金が貯まった時点で繰上げ返済を選択すると金利とキャッシュフロー両面のメリットを享受できます。この柔軟性こそ、株式投資にはない魅力です。
物件価値を押し上げる市場メカニズム
ポイントは、不動産価格がただの運まかせで動くわけではないという点です。人口動態、再開発、交通インフラの整備といった明確な要因が価格形成に影響を与えます。
総務省の「令和7年国勢調査速報値」によれば、都道府県別で人口が増えているのは東京、神奈川、福岡など限られた地域です。これらのエリアでは居住需要が底堅く、家賃下落リスクが抑えられます。また、国土交通省が推進する都市再生特別措置法に基づく再開発では、駅前の容積率緩和により新築・中古ともに資産価値が底上げされる傾向があります。
交通の利便性も見逃せません。たとえば2024年に開業した相鉄・東急直通線は沿線物件の成約価格を平均7%押し上げました(東急リバブル調査)。このように、マクロのデータとローカルな開発計画を重ね合わせることで、未来の価値上昇を高い精度で予測できます。言い換えると、市場メカニズムを読み解く力があれば、値上がり益はある程度コントロール可能なのです。
2025年度の税制優遇を味方にするコツ
まず押さえておきたいのは、税金を抑えることがそのまま利益増につながるという事実です。不動産投資では所得税、住民税、消費税、固定資産税と多岐にわたる税負担が発生しますが、適用できる優遇策も豊富に用意されています。
2025年度も住宅ローン控除は継続しており、賃貸併用住宅や長期優良住宅に該当する場合、年40万円(認定長期優良住宅は年50万円)が最大控除額です。さらに取得時の登録免許税は、2027年3月末まで軽減措置が延長され、建物保存登記は0.15%、移転登記は0.3%に抑えられています。これだけでも数十万円単位の差が生じます。
また個人事業主として青色申告を行えば、最大65万円の特別控除に加え、家族への給与支払いを経費に計上できます。国税庁「所得税基本通達」によると、不動産所得は規模に応じて事業的規模とみなされ、戸建なら5棟、マンションなら10室以上が目安です。この基準をクリアすれば、専従者給与や30万円未満の資産の一括償却も可能になります。つまり税制を理解し使いこなすことで、実効利回りは大きく改善するのです。
リスクを抑えて継続的に儲けるために
一方で、空室や修繕、金利上昇といったリスクがあるのも事実です。重要なのは、これらを事前に数値化し、シミュレーションに組み込む姿勢です。
まず空室リスクについては、平均入居期間を三年、退去後の募集期間を一カ月と仮定し、年間想定家賃の約3%を空室損失として計上すると保守的です。次に修繕費は、築年数や構造によって異なりますが、木造で年5%、RC造で年3%を積み立てると急な出費に対応しやすくなります。
金利上昇はストレスシナリオで確認しましょう。2025年10月時点で長期プライムレートは1.5%台ですが、過去20年の最高水準である3%まで上昇させてもキャッシュフローが黒字かを検証します。もし赤字になるなら、繰上げ返済や固定金利への借り換えを事前に計画しておく必要があります。
こうした備えを行うことで、レバレッジ効果の恩恵を保ちながらも破綻リスクを最小限に抑えられます。不動産投資が長期にわたり儲かる理由は、収益とリスクを数値で管理しやすい点にあると言えるでしょう。
まとめ
本記事では、家賃収入と売却益の二本柱、レバレッジによる利回り向上、価格を押し上げる市場メカニズム、2025年度税制優遇の活用法、そしてリスク管理の具体策を順に解説しました。不動産投資が「なぜ儲かる」のかは、複数の収益源と制度メリットを組み合わせ、数値に基づいて判断できる点にあります。行動に移す際は、まず小規模でも実践的な収支表を作り、信頼できる金融機関や管理会社へ相談することをおすすめします。準備を怠らなければ、あなたも安定したキャッシュフローを手にする未来を描けるでしょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅市場動向調査2024年版 – https://www.mlit.go.jp
- 日本不動産研究所 不動産価格指数2025年7月 – https://www.reinet.or.jp
- 総務省 令和7年国勢調査速報値 – https://www.stat.go.jp
- 日本政策金融公庫 融資金利情報2025年4月 – https://www.jfc.go.jp
- 国税庁 所得税基本通達(不動産所得) – https://www.nta.go.jp

