親から譲り受けた現金のままでは相続税が心配、しかし高額なアパートをいきなり購入するのは不安。そんな悩みを抱える方に注目されているのが「不動産クラウドファンディング 相続対策 始め方」というキーワードで検索される少額不動産投資です。本記事では、相続対策の観点からこの新しい投資手法を活用するメリットと実践手順を、2025年10月時点の最新制度をふまえてやさしく解説します。読み終えたとき、少額からでも家族の資産を守る具体的な行動イメージがつかめるはずです。
不動産クラウドファンディングの仕組みと魅力
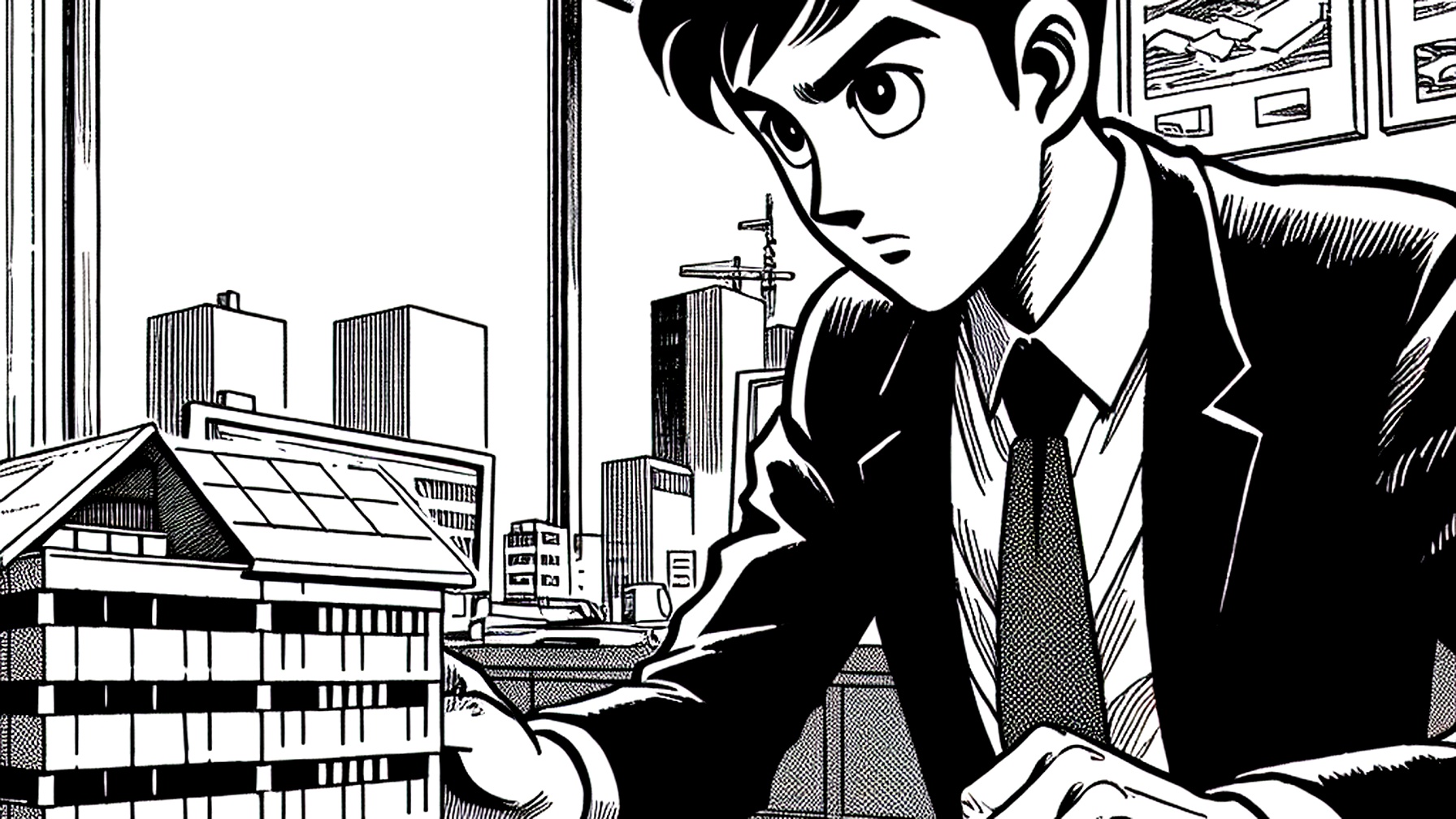
重要なのは、クラウドファンディングが複数の投資家から小口資金を集め、開発会社や不動産特定共同事業者が物件を運用する仕組みだという点です。投資家は1口1万円程度から参加でき、運用期間終了後に売却益や賃料収益を分配金として受け取ります。金融庁の統計(2025年6月公表)によると、国内の不動産クラウドファンディング市場規模は前年同期比35%増と拡大を続けており、個人投資家のすそ野が広がっています。
一方、上場不動産投資信託(J-REIT)は証券取引所で機動的に売買できますが、価格変動が株式市場の影響を受けやすい特徴があります。それに対し、クラウドファンディングは運用期間中の価格変動がなく、満期まで保有すれば予定利回りを確定的に享受できるケースが多い点が支持されています。つまり、ハイボラティリティを嫌う相続対策の資金としては親和性が高いといえます。
相続対策として有効な理由
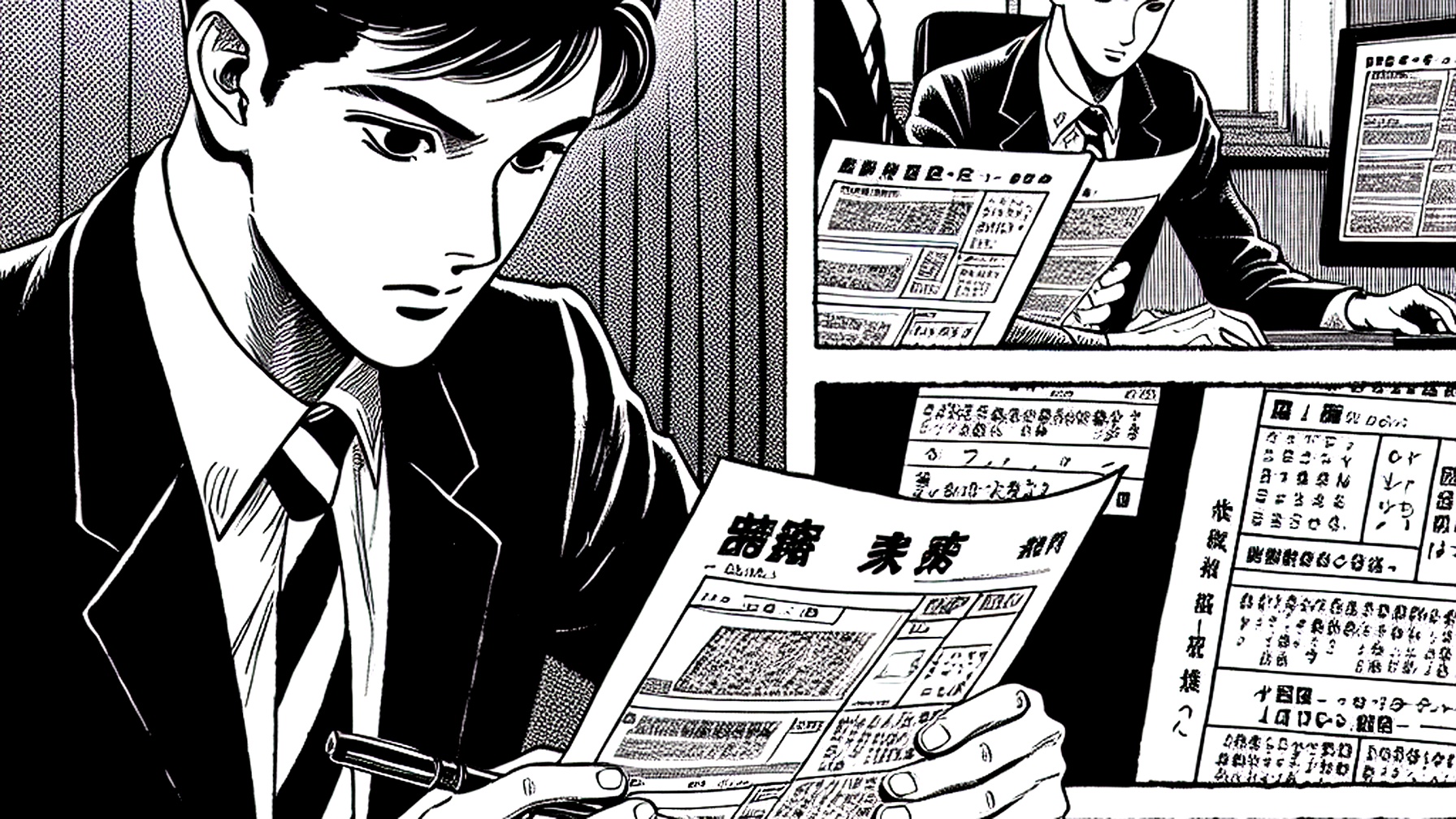
まず押さえておきたいのは、現預金で保有すると額面通りの評価額で相続税が課されるのに対し、不動産クラウドファンディングの匿名組合出資持分は「非上場会社の出資持分」と同様に、原則として出資額評価で計算される点です。現金と同額の5,000万円を出資に振り替えた場合、評価額そのものは変わらないものの、賃料収益を得ながら時間的に資産を分散できるため、将来の贈与計画や納税資金準備の柔軟性が高まります。
さらに、2025年度の相続税法では「小規模宅地等の特例」が従前どおり存続しており、クラウドファンディング物件が区分所有マンションで、相続人が一定要件を満たして居住を継続する場合、土地評価を最大80%減額できる可能性があります。もちろん、匿名組合出資では対象外ですが、任意組合型や不動産特定共同事業法型ファンドでは該当する事例が出始めています。実は、これら多様なスキームを組み合わせることで、現金のみ保有している状態と比べて相続税負担を抑える選択肢が広がるのです。
まず押さえておきたい始め方のステップ
ポイントは、オンライン完結で口座開設から投資まで進められるサービスを選び、少額で仕組みを体験してみることです。ここでは代表的な流れを三つにまとめます。
1. 事業者選定と口座開設 金融庁登録の不動産特定共同事業者か、第二種金融商品取引業者であることを確認し、マイナンバーと本人確認書類を用意してオンライン申し込みを行います。申請から1週間ほどで投資口座が開設されるのが一般的です。
2. ファンド比較と初回投資 予定利回り、運用期間、担保・優先劣後構造をチェックします。2025年10月時点の平均表面利回りは4~6%ですが、想定損失を吸収する劣後出資割合が20%以上あるファンドほど初心者向きといえます。最初は10万円程度に抑え、運用報告書の読み方に慣れましょう。
3. ポートフォリオの拡大と再投資 同一事業者に集中するとファンドの募集停止や償還遅延の影響を受けやすくなります。複数事業者で東京・大阪・福岡など立地を分けることで、地震リスクや賃料下落リスクを水平分散できます。分配金は再投資することで複利効果も期待できます。
このように段階を踏むことで、大きなレバレッジをかけずに相続税評価を意識した資産形成をスタートできます。
リスク管理と税務のポイント
まず、元本保証がない点を認識することが大前提です。ファンドの運営会社が破綻した場合、信託保全が採用されていなければ投資元本が毀損する恐れがあります。また、賃貸需要の変化や天災による損害で予定利回りが下振れることもあります。重要なのは、物件ごとのLTV(ローン比率)や修繕積立計画を確認し、リスクレイヤーが公開されているかをチェックする姿勢です。
税務面では、分配金は原則「雑所得」として総合課税され、累進税率が適用されます。高額所得者が相続対策目的で継続投資する場合、2025年度から創設された「雑所得の3年間損益通算」が使えます。これは、赤字が出た年度の損失を翌年以降2年間繰り越せる制度で、損益のブレが小さくなる効果があります。言い換えると、賃料が想定を下回った年でも税負担を平準化できる可能性があるわけです。
相続発生時には、匿名組合出資持分を「その他財産」として申告し、原則額面評価で計上します。ただし、ファンドが満期前の場合は流動性ディスカウントを考慮する余地があります。具体的な評価減を適用できるかどうかは国税庁通達だけでは読み切れないため、税理士との事前相談が不可欠です。
2025年度に使える補助・優遇制度の活用法
実は、直接的な補助金はないものの、周辺制度を上手に利用することで投資効率を高めることができます。まず、2024年に拡充された「相続時精算課税制度」は2025年度も継続しており、2,500万円までの贈与を非課税で行えます。これを活用して子や孫にクラウドファンディング口座の初回投資資金を贈与すれば、贈与税を抑えながら生前から資産移転を進めることが可能です。
また、新NISAは上場商品が対象ですが、クラウドファンディング事業者の中には、NISA対象のJ-REITと組み合わせたラップ型サービスを提供する例もあります。たとえば、分配金を月次で自動的にETFに再投資する仕組みを使えば、クラウド型の安定収益と市場商品の成長性を両取りできます。さらに、金融庁が2025年度から義務化した「顧客本位の業務運営」の開示項目によって、事業者の手数料や運用実績が比較しやすくなりました。透明性が高まった分、投資家が情報武装すればするほどリスクは低減できるのです。
最後に、国土交通省が2025年4月に改正した「不動産特定共同事業法」のオンライン締結特例が本格施行され、契約書類の電子交付が完全解禁されました。紙のやり取りが不要になったことで、遠隔地の親世代が自宅にいながら契約を完結できるため、家族全員で情報共有しやすい環境が整っています。
まとめ
結論として、不動産クラウドファンディングは少額で始められ、運用期間中の価格変動が小さいため、相続対策の入り口として非常に有効です。現金のままでは避けられない相続税を、時間をかけて分散投資しながら賃料収益で納税資金を蓄えるという二重の効果が期待できます。まずは信頼できる事業者の口座を開設し、10万円から1ファンドに投資して運用報告書を読む習慣をつけましょう。リスクと税務を学びつつポートフォリオを拡大すれば、家族の資産を守りながら将来の選択肢を増やすことができます。
参考文献・出典
- 金融庁 – https://www.fsa.go.jp
- 国土交通省 – https://www.mlit.go.jp
- 国税庁 – https://www.nta.go.jp
- 総務省統計局 – https://www.stat.go.jp
- 日本クラウドファンディング協会 – https://www.jcfa.jp

