競売物件は一般の売買より安く買えると聞いても、「本当に高い利回りが得られるのか」「買ったあとにトラブルはないのか」と不安を抱く方は多いはずです。実は、準備と調査を丁寧に行えば、東京23区平均表面利回り4.2%を上回る案件を確保することも十分に可能です。本記事では、利回りの基礎から競売特有のリスク管理、そして2025年10月時点で活用できる資金計画までを具体的に解説します。初心者でも一歩ずつ実践できるように構成しましたので、最後まで読み進めれば、競売投資で失敗しないための要点が手に入ります。
利回りの基本と競売物件が注目される理由
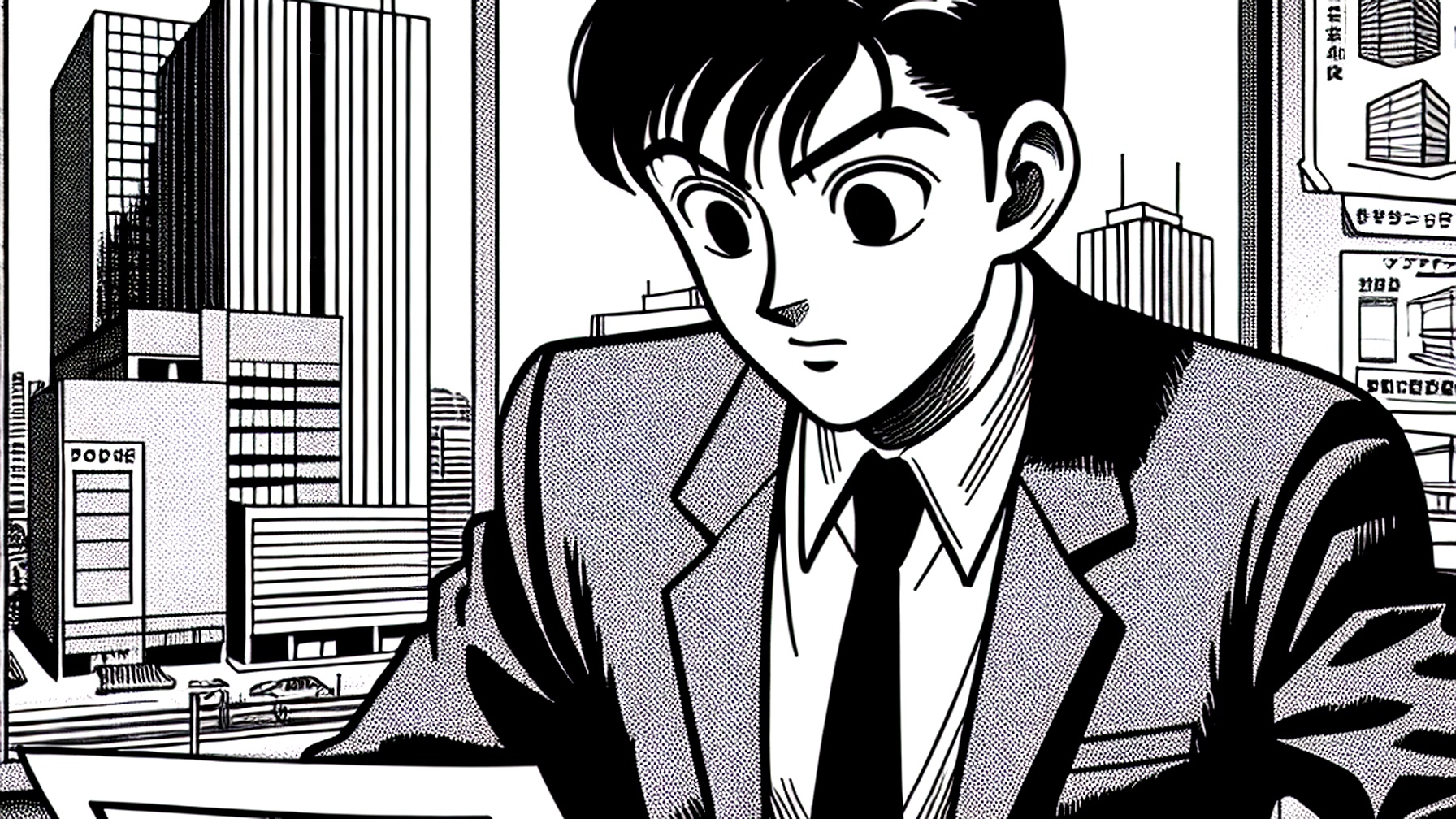
まず押さえておきたいのは、利回りが「投資効率」を測る最重要指標であるという点です。表面利回りは年間賃料収入を物件価格で割って算出しますが、実際の手取りを示す実質利回りは諸費用と空室リスクを差し引いて評価します。競売物件は落札価格が市場価格より平均15〜25%低いとされるため、同じ賃料でも分母が小さくなる分だけ利回りが跳ね上がりやすいのです。
次に、競売市場には築年数が古い物件が多いものの、リフォームを前提に購入すれば価値を押し上げる余地があります。日本不動産研究所の調査でも、築25年以上の区分マンションをフルリフォームした場合、賃料を平均12%上げられた事例が報告されています。つまり、取得コストの低減と賃料改善を同時に実現できれば、利回りを大幅に高めることが可能になります。
一方で、競売は内覧ができない、瑕疵担保責任がないといったハードルが存在します。したがって物件資料の読み込みや現地外観調査は欠かせません。また、落札後のリフォーム費用を適切に見積もらないと利回り計算が崩れるため、事前に複数の業者へ概算見積もりを依頼しておくと安心です。
競売物件のメリットとリスクを数字で読み解く
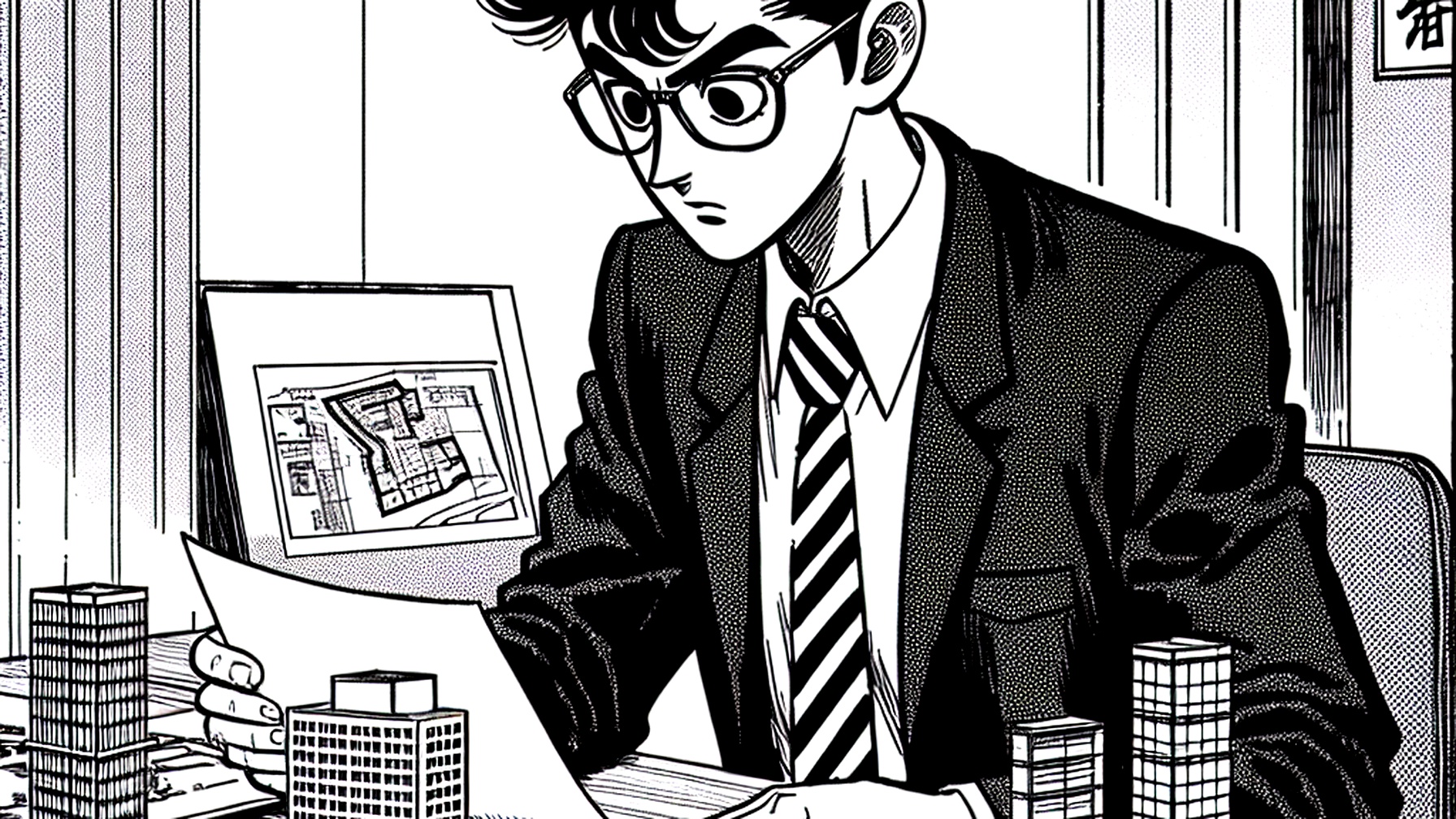
ポイントは、メリットとリスクを同一レベルで数値化し、投資判断の物差しを揃えることです。金融機関の融資を受ける際も、具体的な想定利回りとコストを提示できるかどうかで審査結果が分かれます。
まずメリットを具体的に見ていきます。東京地裁で2024年度に競売になった区分マンションの平均落札率は開札価額に対して83%でした。仮に市場価格3,000万円の物件が2,490万円で落札できた場合、年間賃料が150万円であれば表面利回りは6.0%になります。これは前述の23区平均4.2%を1.8ポイント上回る水準です。
しかしリスクも同時に把握する必要があります。競売物件の30%前後は滞納管理費や未実施の修繕が存在すると言われ、追加費用が100万〜300万円発生するケースが多いです。先ほどの例でリフォームと諸費用に200万円を投じると、総取得費は2,690万円に増え、利回りは5.6%に低下します。それでも平均より高いものの、想定外のコストが利益を削る事実を数字で理解することが重要です。
さらに、競売では入居者が残っていることもあります。2025年10月現在、明け渡し交渉にかかる平均期間は2〜4カ月で、仲介会社を通じた場合の費用は家賃2〜3カ月分が目安です。これらを反映したキャッシュフロー計算を行い、最低でも実質利回り5%を確保できるか検証しましょう。
物件選定と調査の手順で利回りを高めるコツ
実は、利回りを左右する最大の要因は落札前の情報収集にあります。裁判所が公開する「物件明細書」「現況調査報告書」「評価書」の三点セットを読み解き、数字と現場感覚の両方から物件を選別することが欠かせません。
最初のステップとして、評価額と予想賃料のバランスを把握します。最近では国土交通省の「不動産取引価格情報」を利用し、近隣の成約賃料を確認する投資家が増えています。統計上、同エリア同築年の賃料差は±10%に収束する傾向があるため、これを超える賃料設定は過大評価のサインです。
次に、現地外観と周辺環境の調査を行います。昼と夜で人通りや騒音が変わる地域もあるので、時間帯を変えて2回訪れると空室リスクを減らせます。また、役所で築年の台帳を取り寄せ、1981年以前の旧耐震基準の場合は耐震補強費用を織り込む必要があります。この費用は区分マンションでも専有部だけで100万円前後かかることがあるため、利回り計算に組み込んでおきましょう。
最後に、入札価格の上限を冷静に設定します。オーバービッドは利回りを直撃するため、予想賃料と修繕費を基に「総投資額×実質利回り5.5%以上」という自分なりの基準を持つことが肝心です。入札書に金額を記入する瞬間が勝負ですが、基準を超える場合は潔く見送ることが長期的な成功に繋がります。
2025年度の融資動向と資金計画
重要なのは、競売物件でも金融機関の融資を引き出し、自己資金を効率的に使うことです。2025年度はメガバンクが区分マンション向け投資ローンの変動金利を年1.7〜2.2%で提供しており、日本政策金融公庫の不動産担保貸付は固定2.0〜2.3%で利用できます。借入期間は最長35年ですが、築古物件の場合は耐用年数残存期間が上限になる点に注意しましょう。
資金計画では、まず自己資金として物件価格の25%程度を用意すると審査がスムーズです。競売の入札保証金(通常は売却基準価額の10〜20%)や落札後の諸費用を自己資金で賄い、残りをローンでカバーする形が一般的です。例えば総投資額2,700万円で自己資金700万円、借入2,000万円の場合、金利2.0%・期間25年なら毎月返済は約85,000円になります。この金額と想定賃料の差額がキャッシュフローです。
補助金については、投資用物件は住宅取得支援の対象外となるケースが多いため、税制メリットを軸に考えると実務的です。減価償却費やローン利息は不動産所得の必要経費に計上でき、2025年度の所得税率を踏まえると、年間20〜30万円前後の節税効果を見込める場合があります。また、新築アパートなら固定資産税が新築後3年間半額になる軽減措置が2025年度も継続しているため、築浅競売物件を狙う戦略も有効です。
収支シミュレーションで浮かび上がる落とし穴
まず押さえておきたいのは、シミュレーションを楽観的・中立的・悲観的の3パターンで作ることです。空室率15%、金利上昇1%といった厳しい条件でも黒字を確保できるか検証しておくと、想定外の市況変化に耐えられます。
具体的には、年間賃料150万円、空室率10%、運営費15%で計算すると手取りは約114万円です。ここからローン返済85万円を引くと、年間29万円のキャッシュフローが残ります。ところが空室率20%、運営費20%に悪化すると手取りは96万円に減少し、キャッシュフローは11万円まで縮小します。さらに金利が1%上昇すると返済額が約10万円増え、最終的に赤字転落する可能性もあるのです。
一方で、賃料を上げる工夫も忘れてはいけません。Wi-Fi完備や家具付きに改装することで、東京都心では賃料を月5,000円上積みできた事例が国交省「賃貸住宅市場調査」に掲載されています。年間6万円の増収は利回りを0.2ポイント程度押し上げる効果があるため、小規模でも確実に実行したい施策です。
最後に、出口戦略としての売却益も視野に入れましょう。競売で取得しリフォームを施した物件は、市場での評価が高まる分だけ売却価格が上がる傾向にあります。平均すると取得額の110〜120%で売却できたケースが多く、その差額がトータルリターンを底上げすることになります。
まとめ
本記事では、競売物件を活用して平均以上の利回りを実現するための視点と手順を整理しました。落札価格の低さは魅力ですが、追加費用やリスクを数値化し、シビアな実質利回りで判断する姿勢が欠かせません。また、2025年度の低金利環境と税制を上手に利用すれば、自己資金を抑えつつキャッシュフローを厚くすることも可能です。まずは小規模な物件からシミュレーションを試し、実際に入札を経験してみることで、競売投資の感覚を身につけてみてください。最終的に、数字と現場調査を両輪にした投資判断が安定的な不動産収益への近道となります。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp
- 最高裁判所「不動産競売物件情報サイト」 – https://bit.sikkou.jp
- 国土交通省 不動産取引価格情報 – https://www.land.mlit.go.jp
- 国土交通省 賃貸住宅市場調査 2024年度版 – https://www.mlit.go.jp
- 日本政策金融公庫 業種別融資制度 – https://www.jfc.go.jp

