子どもの進学費用をどう捻出するかは、多くの家庭にとって切実なテーマです。学費は年々上がり、奨学金への依存も高まる一方で、銀行預金ではほとんど増えません。そこで近年、「不動産クラウドファンディング 教育資金 おすすめ」と検索する保護者が急増しています。本記事では、運用難の時代に教育費を準備する新しい選択肢として、不動産クラウドファンディングの仕組みと使い方を解説します。読み終えるころには、サービス選びの基準からリスク管理まで具体的な行動イメージが得られるはずです。
教育費が家計を圧迫する時代の新常識
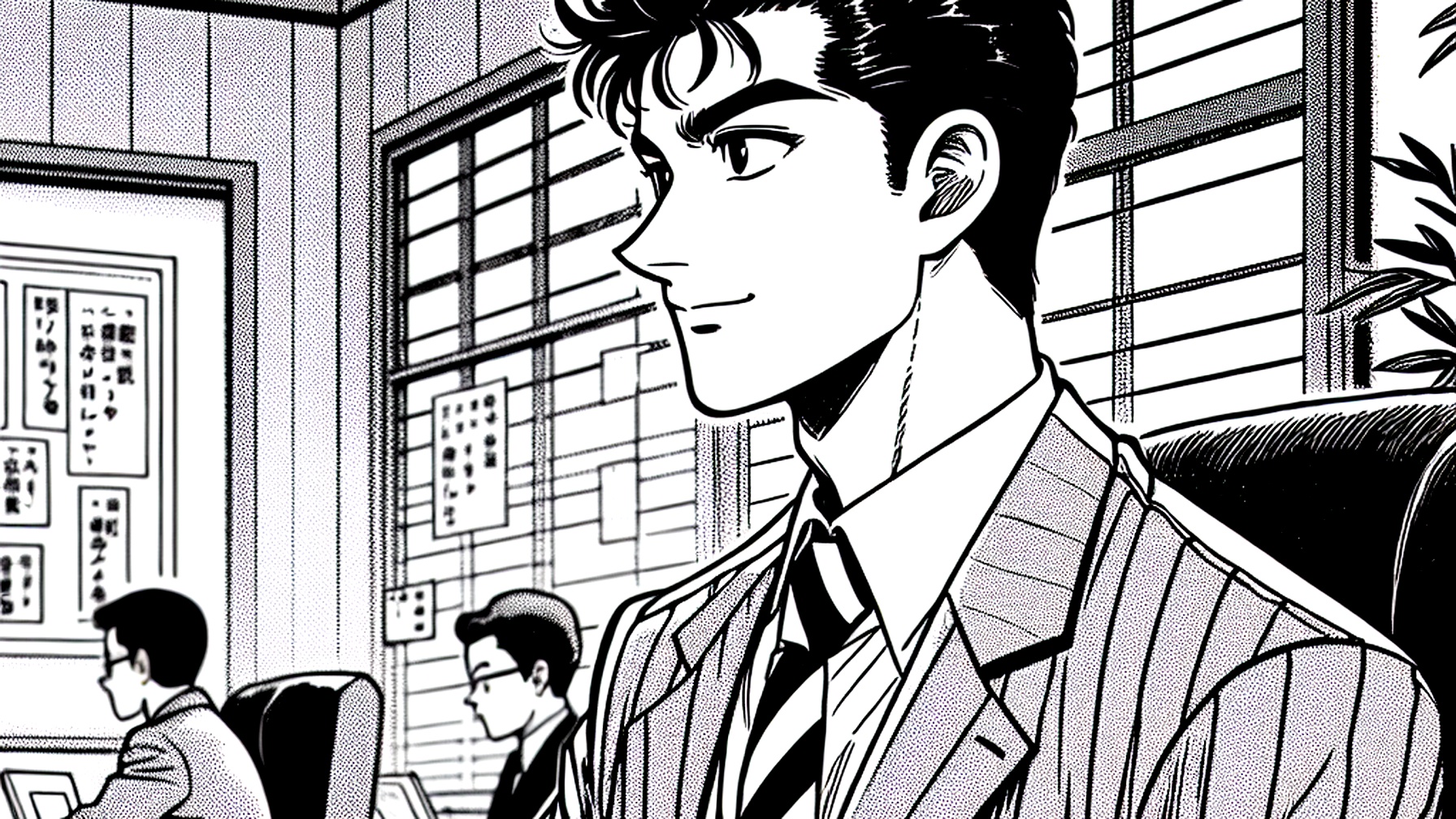
まず押さえておきたいのは、教育費が長期化・高額化している現状です。文部科学省の「子どもの学習費調査」によると、私立大学進学までを想定した場合、幼少期からの総費用は平均1,800万円を超えています。また、総務省家計調査では、大学在学中の仕送り額が年120万円前後で推移し、生活費負担も無視できません。つまり教育資金は一度に準備するのではなく、早期から積み立てる視点が欠かせないのです。
一方で、預金金利は2025年10月時点でも0.001%前後にとどまり、大手ネット銀行の定期預金でも0.3%程度にすぎません。物価が緩やかに上昇する環境下では、実質的な資産価値が目減りする恐れがあります。そのため、リスクを取りつつも、定期預金より高い利回りを狙える金融商品への関心が高まっています。不動産クラウドファンディングは、そうしたニーズに合致する選択肢として注目されているのです。
不動産クラウドファンディングの基本と特徴

重要なのは、不動産クラウドファンディングが「少額で始められる不動産投資」である点です。一般的な物件購入には数千万円の資金とローン審査が必要ですが、クラウドファンディングなら1口1万円から出資でき、物件の運用は事業者が代行します。投資家は分配金と償還益を受け取るだけなので、時間的な負担が少なく、教育資金準備と家計管理を両立しやすい仕組みです。
また、2020年施行の不動産特定共同事業法改正により、インターネット完結型の「電子取引業務」が正式に認められました。これに合わせて、2025年10月時点で登録済みのオンライン事業者数は100社を超え、運用期間も6か月から3年と幅広い商品が流通しています。さらに、元本と利回りを優先的に受け取れる「優先劣後方式」が一般化し、投資家が劣後損失を事業者より先に負うリスクを軽減している点も魅力です。
一方で、クラウドファンディングは株式や投資信託と異なり、途中解約が原則できません。また、分配金は雑所得に該当し、給与所得者でも年間20万円を超えると確定申告が必要になります。したがって、最終的な手取り利回りを把握し、教育費の支出時期と投資期間を必ず照合することが成功のカギとなります。
2025年注目の主要サービスと比較ポイント
ポイントは、事業者選びで利回りだけを追わないことです。ファンドの安全性、運用実績、手数料体系を総合的に確認しましょう。以下では、2025年10月時点で人気の高いサービスを最低限の箇条書きで比較します。
- CREAL(クリアル)
想定年利4〜6%、運用期間1〜2年。運用資産残高が500億円を超え、住宅・ホテルなど物件の分散が進む。
- FUNDROP(ファンドロップ)
想定年利5〜7%、運用期間6〜12か月。家賃保証付きファンドが多く、キャッシュフローが読みやすい。
- オーナーズブック
想定年利3〜5%、運用期間12〜36か月。東京都心オフィスビル案件に特化し、優先劣後比率が30%と高い。
実は、同じ利回りでも課税後の手取りや償還方法で差がつきます。たとえばCREALは元本を満期一括で返す一方、FUNDROPは分配時に元本の一部を償還してくれるため、再投資サイクルが早まります。教育資金を10年後に使う場合、複利効果を高めるなら前者、途中で他の出費が見込まれるなら後者が向いています。
加えて、ファンドが保有する不動産のエリアと用途も要確認です。国土交通省の「不動産価格指数」によると、2024年から2025年にかけて住宅系は前年比2%上昇、一方オフィス系は横ばいでした。したがって、今後の金利上昇リスクを考慮すると、賃料安定度の高い住居系を組み入れ、オフィス系は比率を抑えるとバランスが取りやすいでしょう。
リスクを抑え収益を高める運用テクニック
まず押さえておきたいのは、運用期間をずらして複数ファンドに分散する手法です。たとえば毎月3万円ずつ異なるファンドへ12か月連続で投資すると、1年後には満期が均等に訪れるポートフォリオが完成します。こうした「ラダー型運用」は、教育費の支出時期が読みにくい場合でもキャッシュフローを安定させる効果があります。
さらに、劣後出資比率が20%以上の案件を選ぶことで、物件価値が下落しても元本毀損を回避できる可能性が高まります。一般に、劣後比率が10%未満だと事業者側のリスク負担が小さく、利回りが高くても安全性は低下します。一方、比率が30%を超える案件は募集枠が小さく、クリック合戦になりやすい点に注意が必要です。
なお、利回りを追い過ぎて不用意に海外不動産ファンドへ傾斜するのは避けたいところです。為替変動が加わると、せっかくの円建て教育資金が目減りする恐れがあります。日本国内の円建て案件で3〜6%の想定利回りを複利運用するほうが、目標額をブレなく達成しやすいというメリットがあります。
教育資金計画に役立つ税制と制度の基礎知識
重要なのは、クラウドファンディング単体ではなく、税制優遇と組み合わせる発想です。まず、2025年度も継続している「教育資金一括贈与の非課税特例」は、祖父母からの資金援助を1,000万円まで非課税で受け取れる仕組みです。贈与資金を直接投資に回すことは制度上できませんが、生活費や学習塾代に充当することで、手元資金を投資に振り向ける余地が生まれます。
また、2024年に刷新された新NISAは非課税投資枠が最大1,800万円に拡大され、2025年も利用可能です。不動産クラウドファンディング自体はNISA対象外ですが、株式や投資信託で安全資産を積み立てつつ、上限を超えた資金をクラウドファンディングに振り分けると、ポートフォリオ全体の税引後リターンが底上げされます。
加えて、分配金が雑所得になる点を踏まえ、ふるさと納税やiDeCo(個人型確定拠出年金)と併用して所得控除枠を確保する方法も有効です。控除額が増えればクラウドファンディングの課税負担を相殺でき、手取り利回りが実質的に向上します。つまり、教育資金の準備は単一商品ではなく、制度と商品を組み合わせた総合戦略が鍵となるのです。
まとめ
本記事では、教育費の高騰に悩む家庭向けに、不動産クラウドファンディングを活用した資金形成の流れを紹介しました。少額から始められ、優先劣後方式でリスクを抑えられる点が大きな特徴です。サービス比較では利回りだけでなく、劣後比率や運用期間をチェックし、ラダー型で分散投資すると安定感が増します。さらに、教育資金一括贈与の非課税特例や新NISAと組み合わせることで、税負担を抑えながら目標額に近づけることができます。結論として、計画的な分散と制度の併用が、10年先の学費を守る最良の方法です。今日から少額でもスタートし、将来の進学資金を着実に積み上げていきましょう。
参考文献・出典
- 文部科学省「令和5年度子どもの学習費調査」 – https://www.mext.go.jp/
- 総務省「家計調査年報2024」 – https://www.stat.go.jp/
- 国土交通省「不動産価格指数(住宅・商業用)」 – https://www.mlit.go.jp/
- 金融庁「新しいNISAの概要(2025年度)」 – https://www.fsa.go.jp/
- 国税庁「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置(2025年度版)」 – https://www.nta.go.jp/

