金利がじわじわと上がり始めた今、「変動金利で借りて大丈夫だろうか」「銀行の審査が厳しくなるのでは」と不安に感じる投資家は多いはずです。実際、金利上昇期は返済負担が増えるだけでなく、融資の間口そのものが狭まる傾向があります。しかし適切な知識と戦略を持てば、収益物件を取得しながらもキャッシュフローを守ることは十分に可能です。本記事では、収益物件 融資条件 金利上昇期という三つのキーワードを軸に、背景の理解から物件選び、資金計画、2025年度に利用できる制度までを総合的に解説します。読み終えたときには、上昇局面でも落ち着いて判断できる土台が身につくでしょう。
金利上昇局面のいま起きていること
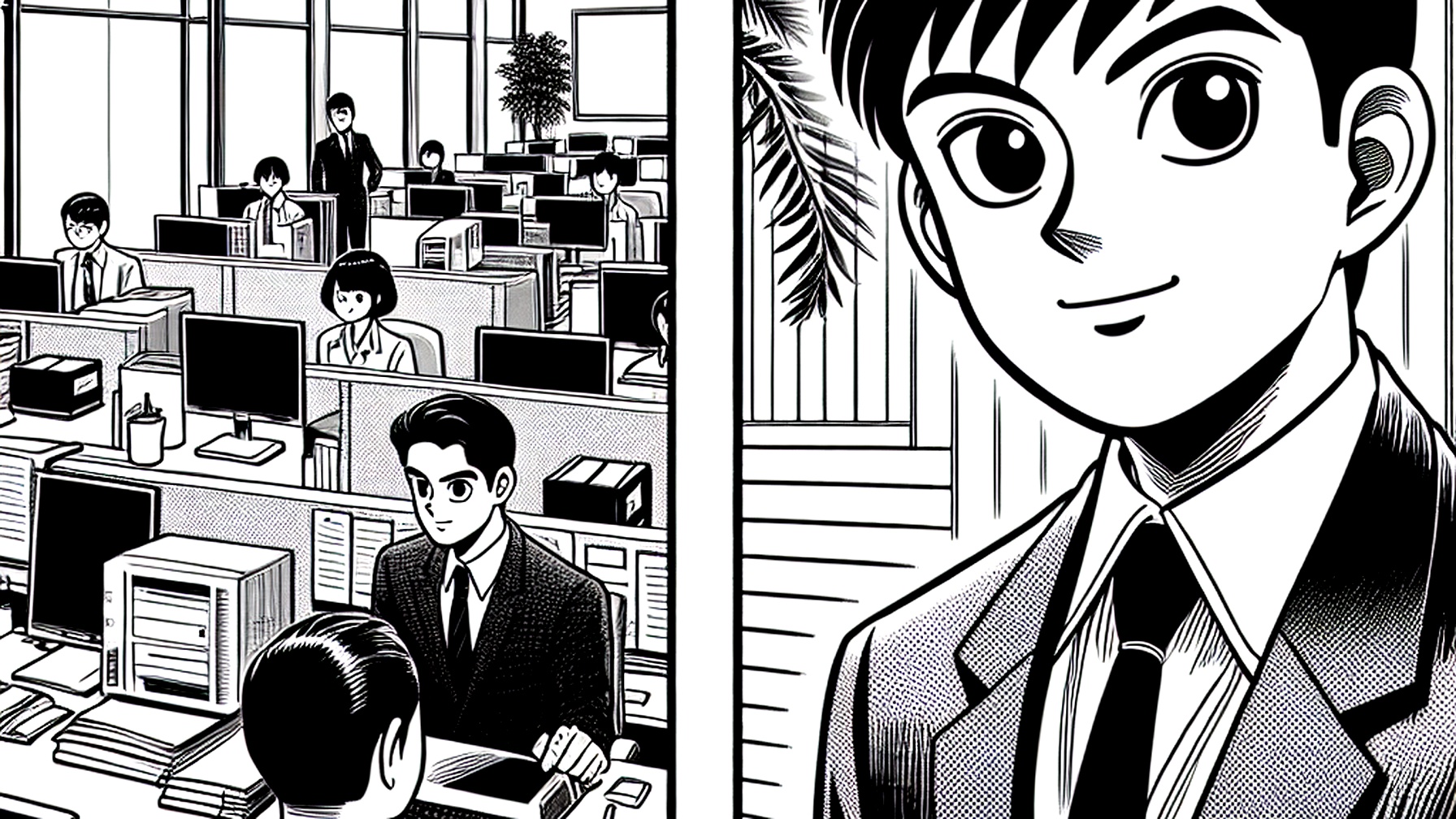
まず押さえておきたいのは、なぜ金利が上昇に転じたのかという背景です。日本銀行は2024年3月にマイナス金利政策を終了し、2025年10月現在は政策金利を0.5%程度で推移させています。長く続いた超低金利環境が終わりを告げ、金融機関は調達コストの上昇を融資金利に反映し始めました。つまり投資家にとっては、同じ条件でも数年前より返済総額が増える局面に入ったということです。
一方で、金利の上昇ペースは緩やかで、不動産市場全体が急減速したわけではありません。国土交通省の2025年上半期「不動産価格指数」によると、全国の住宅系物件価格は前年比で3%前後の上昇にとどまっています。賃料指数も横ばいから微増の動きで、家賃収入の安定性は維持されているといえます。重要なのは、金利だけを恐れるのではなく、賃料動向と価格トレンドを同時に読む姿勢です。
さらに、日本銀行の「貸出約定平均金利データ」を見ると、2023年末に1.0%だった不動産業向け長期金利は、2025年9月時点で1.5%を超えました。わずか0.5ポイントでも、借入額が1億円なら年間約50万円の支払増となります。キャッシュフローがタイトな物件を選ぶと、この差が命取りになりかねません。したがって、上昇局面では金利上げ幅を想定したシミュレーションを行い、耐性を確認しておくことが最初の防衛線になります。
融資条件はこう変わる
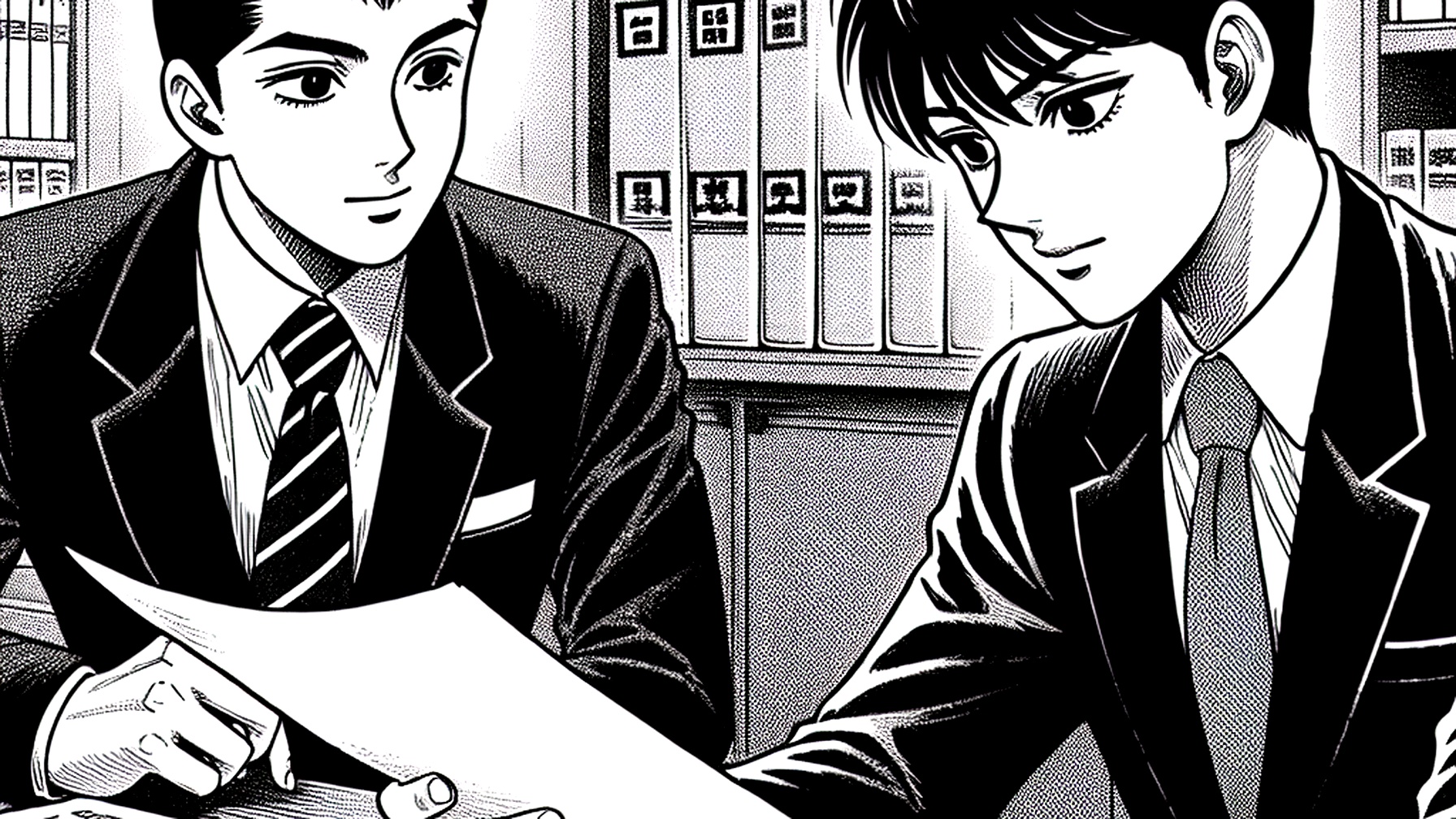
ポイントは、金融機関がリスク許容度を調整する過程で、融資条件が細かく改訂される点です。金利そのものだけでなく、自己資金比率や返済比率(返済額が家賃収入に占める割合)への要求が厳しくなる傾向があります。たとえば都市銀行では、アパートローンの自己資金を2割から3割に引き上げたケースも報告されています。
また、審査の焦点は「実質利回り」に移行しつつあります。表面利回りは10%でも、修繕費や空室損を差し引いた実質利回りが7%を下回ると、融資評価が一気に低くなります。銀行は金利リスクに備え、より安定したキャッシュフローが見込める案件を選別しているのです。つまり、経費や空室率を甘く見積もると、審査ではじかれる確率が高まります。
さらに、2025年から施行された「信用リスク準備金ガイドライン」の影響で、金融機関は投資用不動産向け貸出の与信管理を強化しました。結果として、借入期間が物件の耐用年数と厳密にリンクされ、木造アパートなら最長25年、RCマンションでも30年以内が主流となっています。返済期間が短くなるほど月々の返済額は増えるため、収支計画をより慎重に組む必要があります。
加えて、個人属性の評価も細分化されました。年収だけでなく、手取り額や家族構成、他ローンの残高まで細かくチェックされます。金利上昇期は、金融機関が「いざとなれば自己資金で返せるか」を重視するためです。したがって自己資金の比率を高める、既存ローンを圧縮するなど、バランスシートを整える作業が欠かせません。
収益物件の選定基準を再点検する
実は、金利上昇期こそ物件の質が結果を大きく左右します。利回りが同じでも、賃貸需要が強いエリアなら空室期間が短く、実質利回りが長期的に安定します。総務省「住民基本台帳人口移動報告」では、東京都・福岡県・愛知県の都心部で人口流入が続いており、地方主要都市もコンパクトシティ化が進行中です。人口増加エリアは賃貸ニーズが根強く、家賃下落リスクを抑えられます。
一方で、表面利回りだけを追って郊外や人口減少エリアに手を出すと、空室率上昇でキャッシュフローが悪化しやすい点に注意が必要です。金利が上がる局面では、空室が一月伸びるだけで返済比率が一気に跳ね上がります。つまり、利回りよりも空室リスクの低さを優先する姿勢が鍵となります。
さらに、建物の維持費も重要です。築古木造は購入価格が安く利回りが高いものの、修繕周期が短く、金利負担と修繕費が同時に重なる可能性があります。逆に築浅RCは修繕計画を長期で組めるため、金利上昇期でも資金繰りが平滑化しやすいメリットがあります。ただし購入価格が高いため、利回り確保には緻密な家賃設定が欠かせません。
最後に、出口戦略の再考も忘れないでください。金利が上がると買主の融資条件も厳しくなるため、将来売却する場合の想定価格が下がるリスクがあります。このとき立地と建物の競争力が高い物件であれば、価格下落を最小限に抑えられます。つまり「出口に強い物件」は金利上昇期にこそ真価を発揮します。
キャッシュフローを守る資金計画
基本的に、金利上昇局面では手元資金の厚みが安全弁になります。自己資金を3割以上入れると返済額が抑えられ、金利変動の影響を受けにくくなります。さらに、毎年のキャッシュフローの10%程度を「金利緩衝用」として別口座に積み立てる方法も有効です。これにより、数年分の金利上昇コストを先取りで確保できます。
返済方法の選択も重要です。2025年時点で多くの銀行は、変動金利と固定金利のハイブリッド型ローンを提供しています。たとえば借入額の半分を10年固定、残りを変動にすることで、金利上昇リスクと金利差益の両方をバランス良く取り込めます。ただし固定部分が多すぎると初期の返済額が増えるため、長期のシミュレーションでキャッシュフローに無理がないか確認しておきましょう。
家賃設定の見直しも欠かせません。国土交通省「賃貸住宅市場レポート」では、都心部の築10年以内物件で家賃改定率が年1〜2%上昇しています。賃料相場を細かく調査し、設備投資による家賃アップが見込める場合は早めに実施することがキャッシュフロー改善につながります。また、管理会社と連携して空室期間を最短化する戦略も合わせて検討しましょう。
最後に、保険と税制を活用して支出を平準化します。火災保険や地震保険の長期契約は保険料の割安感があり、保険料の上昇リスクを一定期間固定できます。また、減価償却費を活用して課税所得を圧縮し、金利上昇によるキャッシュアウトを税負担軽減で補完する考え方も有効です。
2025年度に活用できる制度と金融商品
重要なのは、利用可能な制度や商品をフルに使い、実質金利負担を下げることです。2025年度の「中小企業経営強化税制」は、賃貸住宅を法人で保有する場合、一定の省エネ性能を満たした設備投資を即時償却できるため、節税効果でキャッシュフローを向上させる手段になります。個人オーナーでも適用要件を満たせば活用が可能です。期限は2026年3月末までとなっているため、計画的な取得とリフォームが必要です。
一方、住宅金融支援機構の「フラット35アパートローン」は、2025年度も融資メニューが継続しています。全期間固定金利で最大20年とやや短いものの、金利を予見できるメリットがあります。金利上昇期では固定金利が心理的な安定材料になり、長期計画を立てやすくなります。
さらに、地方銀行や信用金庫は地域創生を目的とした「地域連携アパートローン」を展開中です。自治体と連携し、子育て世帯向けや大学新設エリアの物件に対して、金利優遇や保証料減免を実施しています。対象エリアや物件用途が限定されるものの、該当する場合は通常より0.3〜0.5ポイント低い金利で借りられるケースが見られます。
また、サステナブルファイナンスの一環として、金融機関が「環境性能評価ローン」を導入しています。太陽光発電や高断熱仕様を備えた物件は、金利優遇だけでなく、入居者募集でも差別化しやすい利点があります。環境性能を上げる初期費用はかかるものの、家賃プレミアムと金利優遇で回収できれば中長期的にはプラスとなるでしょう。
まとめ
結論として、金利上昇期でも収益物件投資を継続する道は十分に残されています。鍵になるのは、金利変動を前提にしたシミュレーションと、金融機関の審査基準に沿った資金計画です。さらに、安定需要のある立地と出口戦略を意識した物件を選べば、多少の金利上昇でもキャッシュフローは崩れません。
この記事で取り上げた融資条件の変化、物件選定の視点、そして2025年度の制度活用策を踏まえ、まずは自分の資金計画を見直してみてください。金利を恐れて行動を止めるより、準備を整えて好条件の物件を選び抜くほうが、長期的な資産形成につながります。金利上昇局面を逆手に取り、堅実な不動産投資を続けていきましょう。
参考文献・出典
- 日本銀行「貸出約定平均金利等の推移」 – https://www.boj.or.jp
- 国土交通省「不動産価格指数」 – https://www.mlit.go.jp
- 国土交通省「賃貸住宅市場レポート」 – https://www.mlit.go.jp/totikensangyo
- 総務省「住民基本台帳人口移動報告」 – https://www.stat.go.jp
- 住宅金融支援機構「フラット35アパートローン」 – https://www.jhf.go.jp
- 中小企業庁「中小企業経営強化税制」 – https://www.chusho.meti.go.jp

