資産運用を考え始めたものの、「自己資金が少ない」「相続税が心配」という理由で一歩を踏み出せない方は多いものです。実は、アパート経営は少額からでもスタートでき、さらに相続対策としても高い効果を発揮します。本記事では、2025年10月時点の最新データをもとに、初めてでも理解しやすい形で「アパート経営 少額 相続対策」のポイントを解説します。メリットと注意点、具体的な資金計画、活用できる税制までを順序よくまとめていますので、読み終えるころには行動の指針が見えるはずです。
少額から始めるアパート経営の魅力
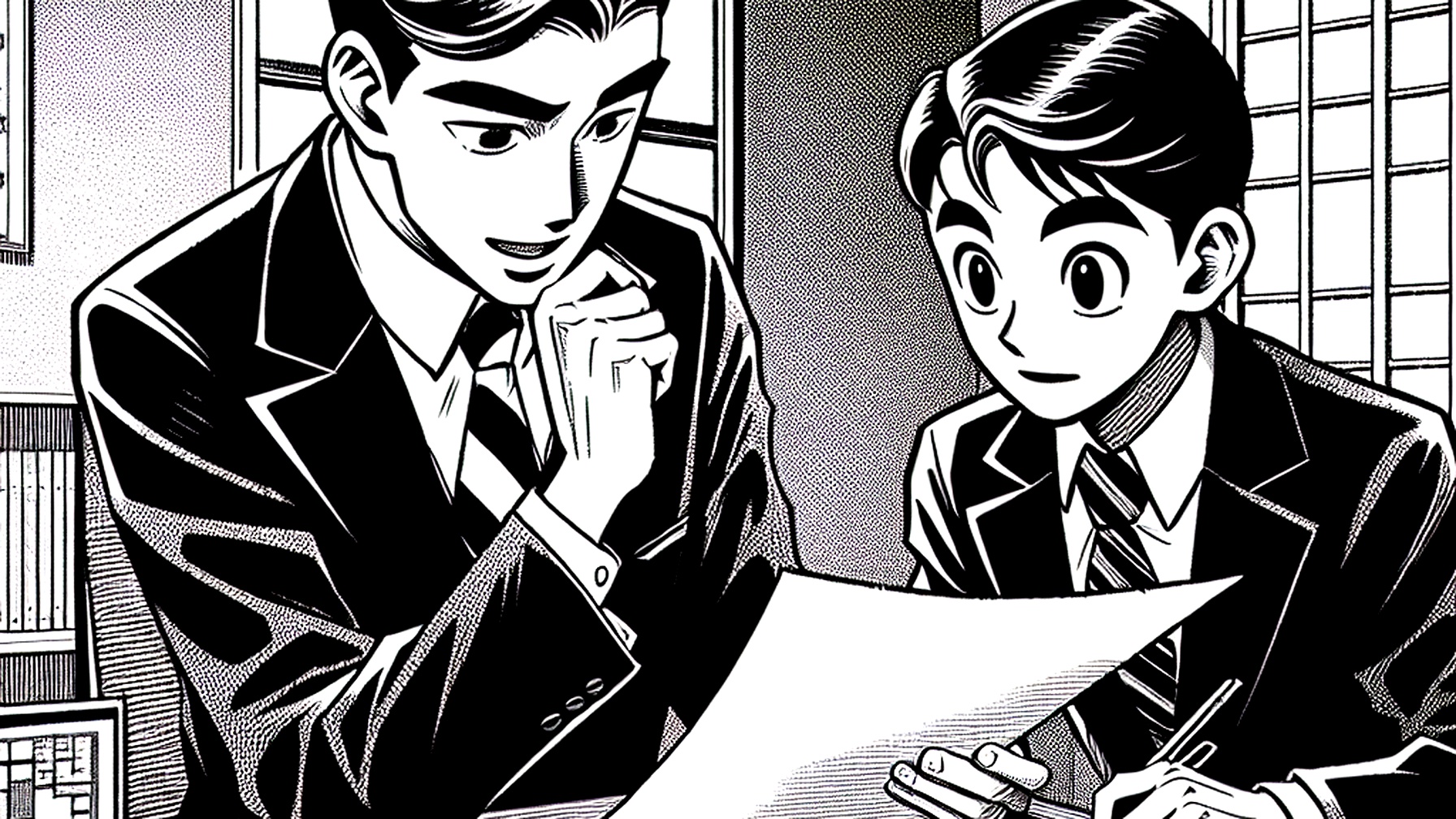
まず押さえておきたいのは、少額投資でもアパート経営が可能になってきた背景です。日本政策金融公庫の「2025年度創業融資枠」では、事業計画が妥当と認められれば自己資金1割程度でも融資が受けられます。これにより、1,000万円前後の木造アパート一部屋購入や小規模一棟物件への参入が現実的になりました。
さらに、国土交通省住宅統計によると2025年8月時点の全国アパート空室率は21.2%で、前年比0.3ポイント改善しています。需要の回復傾向は小規模投資家にも追い風です。ただし、立地とターゲット層を見誤れば空室リスクは高まるため、物件選定は慎重に行う必要があります。
ポイントは、賃貸需要が安定している大学周辺や駅徒歩圏など、エリアを絞って情報収集することです。仲介会社のヒアリングに加え、自治体人口動態を確認し、長期的な入居ニーズを見極めましょう。
相続対策としてのアパート経営の基本
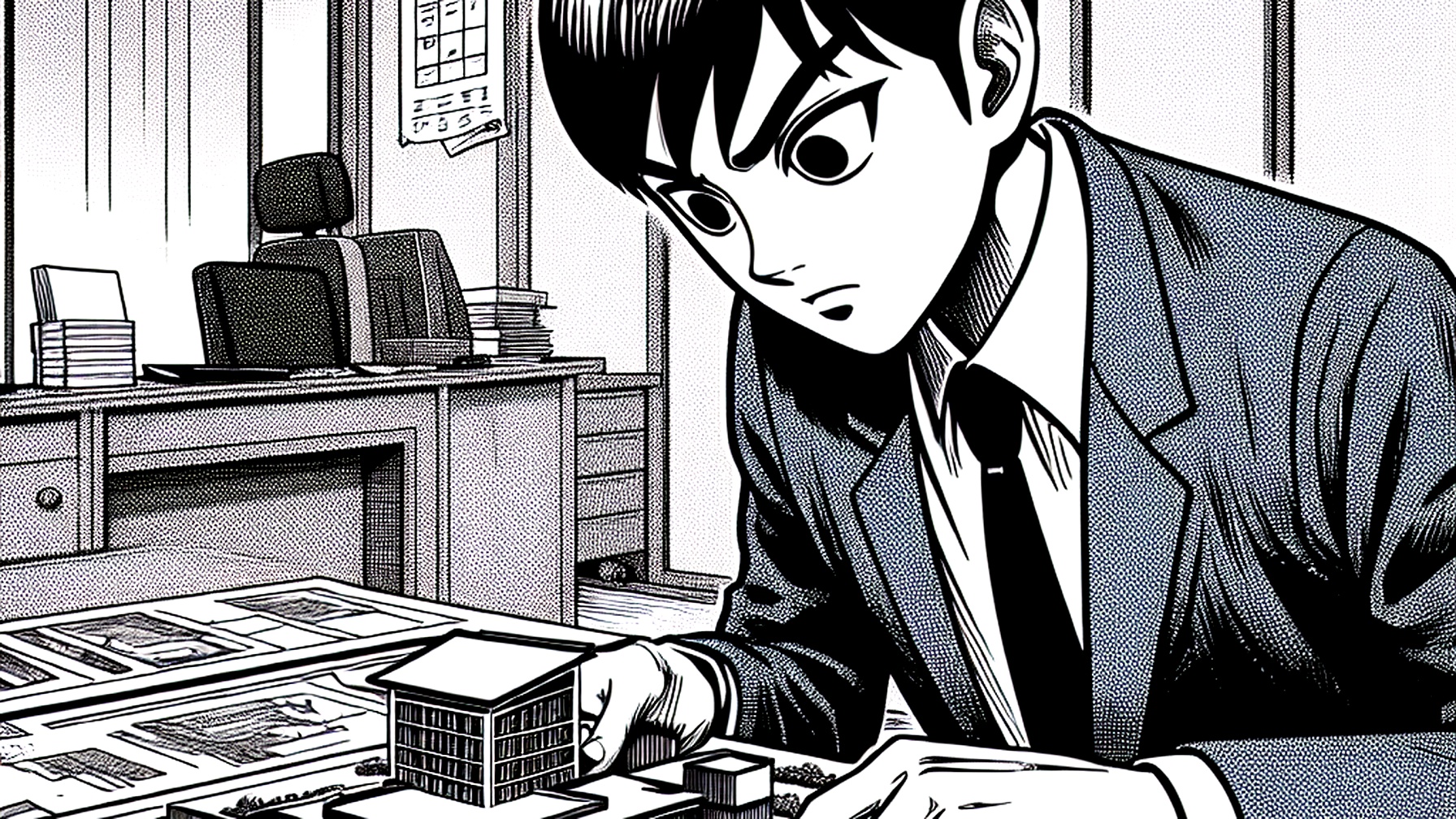
相続税評価額を圧縮できる点は、アパート経営が富裕層だけでなく、資産形成期の世代にも注目される理由です。土地は自用地評価から貸家建付地評価へと変わり、建物は固定資産税評価額で算定されるため、現金で保有するより課税対象額が下がります。
重要なのは、被相続人と推定相続人が早い段階で資産移転の方向性を共有することです。生前贈与とアパート新築を組み合わせるケースでは、贈与税の非課税枠110万円を活用しながら、建物の持分を子に移す手法がよく用いられます。また、家賃収入を子名義口座へ送金すれば、所得分散による節税効果も期待できます。
ただし、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算される点がネックです。計画は5年、10年単位で立て、税理士とシミュレーションを行うことで、後悔のない資産承継が可能になります。
初期費用を抑えるための資金計画
ポイントは、自己資金一部+金融機関融資を組み合わせ、キャッシュフローを安定させることです。自己資金は物件価格の20%を目安にすると、返済比率が下がり、想定利回りとの差分がリスクヘッジになります。たとえば、1,500万円の中古アパートを金利2.0%、期間20年で購入した場合、自己資金300万円を投入すれば月々の返済は約7万円に抑えられます。家賃収入が10万円なら、管理費・修繕費を差し引いても手元に1万円前後が残り、年間ベースでは黒字が維持しやすくなります。
また、少額投資では修繕積立の準備金を軽視しがちです。実は、築15年以降の物件は外壁塗装や屋根防水で100万円以上かかることも珍しくありません。毎月家賃の1割を別口座に積み立てておけば、急な出費にも慌てずに済みます。
金融機関選びは金利だけでなく、団体信用生命保険(団信)の内容も比較してください。万一の際に残債が完済され、家族へ家賃収入が残る仕組みは、相続対策としてもメリットがあります。
リスク管理と出口戦略
実は、少額のアパート経営ほどリスク管理が成功を左右します。最初に検討すべきは空室と家賃下落です。国立社会保障・人口問題研究所の将来推計によると、地方圏の総人口は2030年までに平均5%減少する見込みです。人口減少エリアで運営する場合、家賃を5%下げても収支が持ちこたえられるかを試算しておくとよいでしょう。
一方で、耐用年数が尽きる前に売却する「出口」を描くことも大切です。築20年の木造アパートを利回り8%で買い、10年後に表面利回り10%相当の価格で売却できれば、家賃収入に加えて売却益を得られる可能性があります。東京23区や政令市の駅近物件は需要が底堅く、出口を取りやすい傾向があります。
保険の活用も忘れてはいけません。火災保険・地震保険に加え、家賃保証保険を導入すると、入居者が賃料を滞納した際のキャッシュフローが安定します。保証料は年間家賃の1〜2%が相場で、経費算入できるため税負担は限定的です。
2025年度の税制・補助活用術
基本的に、2025年度の税制改正では賃貸住宅の減価償却ルールに大きな変更はありません。しかし、住宅取得等資金の贈与非課税制度(2025年12月まで延長予定)を利用すれば、子や孫への資金移転が最大1,000万円まで非課税になります。木造アパート建築費を負担させる形で活用すると、将来の相続税対策と同時に、建築費用の軽減が可能です。
また、環境性能を高めた賃貸住宅に対しては、2025年度も引き続き「ZEH-M支援事業」の補助が利用できます。条件を満たすと1戸あたり最大50万円の交付を受けられるため、長期保有を前提とする投資家には魅力的です。ただし、公募期間が例年5〜6月ごろに限定されるため、スケジュール管理は必須です。
最後に、固定資産税の住宅用地特例も押さえておきましょう。敷地面積200㎡以下の部分は課税標準が6分の1に軽減され、200㎡超部分でも3分の1になります。土地を更地で持つよりも、アパートを建てて貸し付ける方が、保有コストを抑えながら収益を得られる点が相続対策と直結します。
まとめ
ここまで、少額から始めるアパート経営が相続対策として有効な理由と、その実践方法を解説しました。重要なのは、自己資金を抑えつつも長期視点で資金計画とリスク管理を行うことです。立地選定、税制活用、補助金申請を丁寧に進めれば、家賃収入でローンを返済しながら、相続税評価額も下げられます。まずは信頼できる金融機関や税理士に相談し、5年後、10年後の資産形成マップを描くことから始めてみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計調査 2025年8月速報 – https://www.mlit.go.jp
- 国税庁 相続税法令解釈通達 2025年版 – https://www.nta.go.jp
- 日本政策金融公庫 創業融資制度の手引き 2025年度 – https://www.jfc.go.jp
- 国立社会保障・人口問題研究所 将来人口推計 2024年版 – https://www.ipss.go.jp
- 環境省 ZEH-M支援事業 公募要領 2025年度 – https://www.env.go.jp

