マンション投資は少額から始めやすく、長期で安定した家賃収入を得られると語られます。しかし、表面利回りだけを信じて購入し「想定外の空室で赤字になった」「修繕積立金が跳ね上がった」と後悔する声も後を絶ちません。本記事では、不動産投資歴15年以上の筆者が実際に見聞きした失敗例を整理し、どこに落とし穴が潜んでいるのかを解説します。さらに2025年9月時点で活用できる制度やデータを交え、初心者でも再現できるリスク回避策を提示します。読み終える頃には、マンション投資で損しないための視点と具体的な行動手順がクリアになるはずです。
よくあるマンション投資の落とし穴
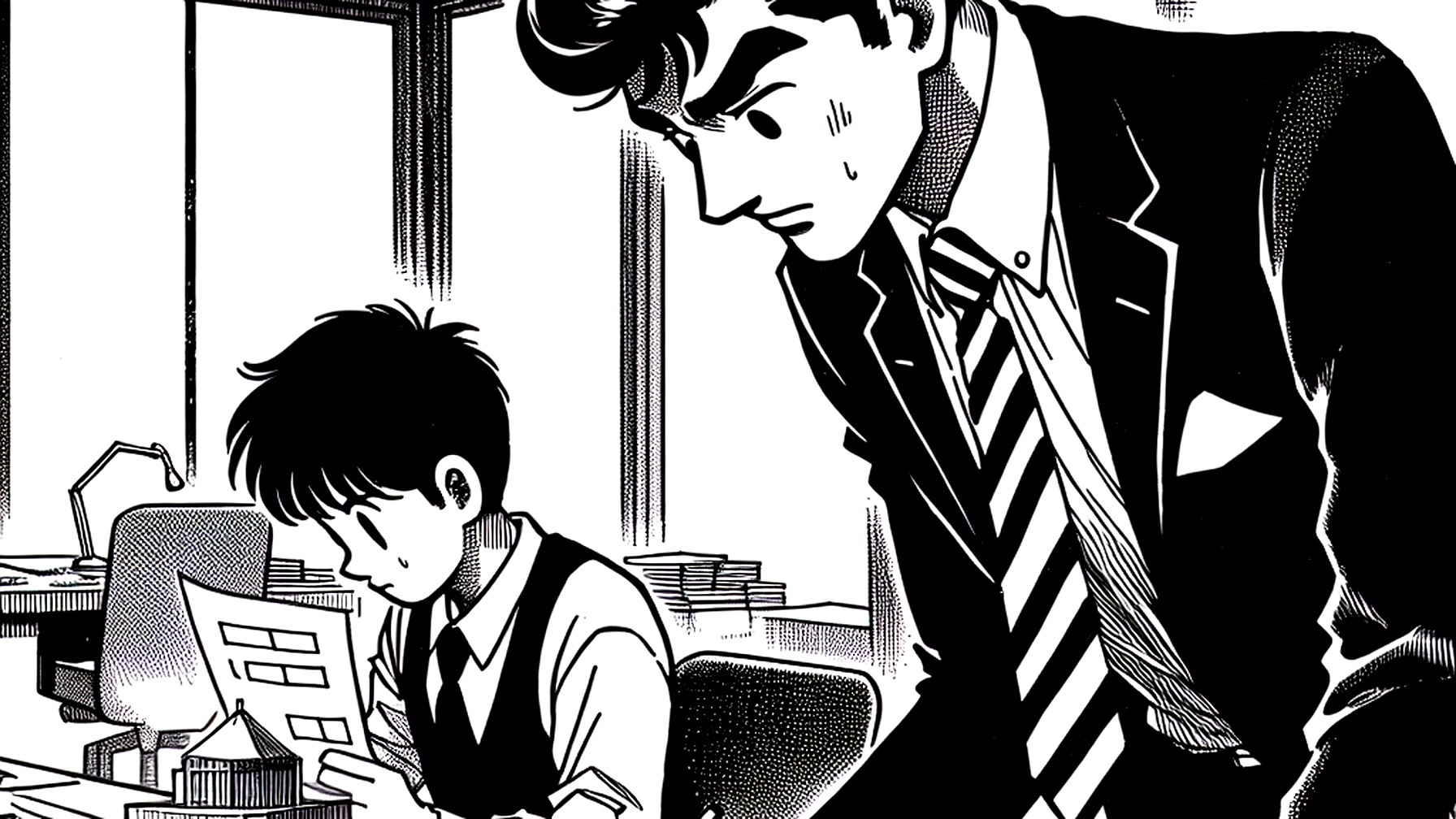
重要なのは、初心者が見逃しやすい初期費用と運用コストの全体像を把握することです。表面利回り8%の中古ワンルームでも、購入時にかかる仲介手数料や登記費用、固定資産税清算金を合わせると物件価格の7〜9%が上乗せされます。さらに管理費・修繕積立金・火災保険を足すと、手取り利回りは簡単に2〜3ポイント下がります。
次に見落とされやすいのが出口戦略です。築古物件は当初の購入価格が低くても、将来値下がりしやすく、売却時にローン残債を下回る「オーバーローン」に陥る危険があります。実際、筆者が相談を受けた例では10年前に1,900万円で買った築20年ワンルームが、現在1,200万円でしか売れず200万円の追い金が必要になりました。このように購入前から売却シナリオを描くことが欠かせません。
最後にサブリース契約への過信も典型的な落とし穴です。家賃保証が20年続くと説明されても、契約書には「家賃は2年ごとに見直し」と明記されるのが一般的です。つまり家賃保証とは名ばかりで、周辺相場が下落すれば保証賃料も下がります。保証料率と契約解除条件を精査しないまま契約すると、収支悪化に気づいた時には違約金で身動きできなくなります。
キャッシュフローが崩れる典型パターン
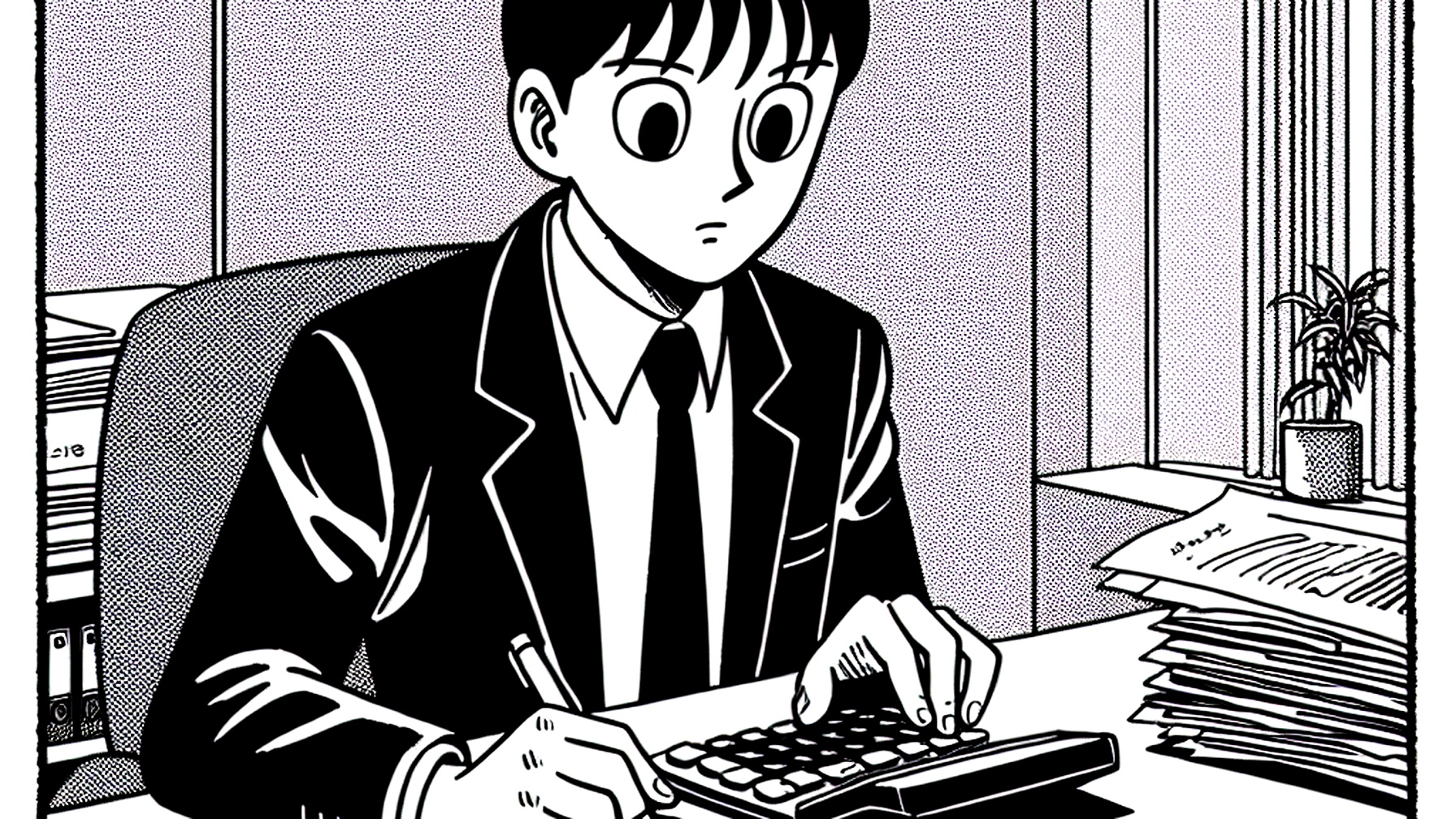
まず押さえておきたいのは「空室」「金利上昇」「突発修繕」の三つが収支を直撃するという事実です。東京都心の新築マンション平均価格は2025年9月時点で7,580万円(不動産経済研究所)に達し、購入者の多くがフルローンを利用しています。金利が0.5%上がると月々の返済は約2万円増え、年間で24万円の支出増となります。家賃が想定より下がった時、この差額が致命傷になります。
空室リスクも侮れません。総務省の住宅・土地統計調査によると、全国の賃貸住宅空室率は2023年で19.0%でした。都心は平均より低いものの、ワンルーム特化エリアでは供給過多になりやすく、築5年を超えると賃料下落が顕著です。筆者が管理する物件でも、入居者の入れ替えに2か月要しただけで年間キャッシュフローが40万円悪化した事例があります。空室期間を保守的に想定し、募集手数料や原状回復費も予備費に含めておくことが肝心です。
また、築15年を過ぎると給湯器やエアコンなど設備更新が一気に重なります。1Kタイプでも給湯器交換は15万円、エアコンは8万円が相場です。「修繕積立金があるから安心」と思いがちですが、共用部と専有部の区分を理解していないと、自己負担分が計画外支出となります。設備更新時期を一覧にして5年先までの現金収支を可視化すれば、資金ショートを未然に防げます。
立地と価格のミスマッチが招く空室リスク
実は、立地選択で最も重要なのは「駅距離」より「需給バランス」です。駅徒歩3分でも、同じようなワンルームが周辺に大量供給されていれば、賃料競争に巻き込まれます。国交省の不動産価格指数を見ると、2024年以降、郊外ターミナル駅直結の大型開発エリアが価格上昇率で都心を上回る事例が増えています。つまり資産性は単純に都心志向だけでは語れません。
具体例として、埼玉県某駅徒歩2分の築浅ワンルームを取り上げましょう。購入時の想定利回りは6.5%でしたが、同駅周辺で3棟500戸規模の学生向けマンションが一斉供給され、2年で賃料が8%下落しました。一方、千葉県の快速停車駅から徒歩8分、ファミリー向け2LDKは同期間で賃料横ばいを維持しています。この違いはターゲット層の広さと供給状況の差に起因します。数字だけでなく、人口動態や再開発計画も合わせて確認することが必須です。
結論として、購入前に「将来供給が増えにくいエリアか」「賃料の下落余地はどの程度か」をシミュレーションすることで、多くの空室リスクは回避できます。地価公示や都市計画図をチェックし、競合物件の建設予定がないかを役所の建築指導課で確認するひと手間が、数百万円の損失を防いでくれます。
法律・管理の知識不足が生む思わぬ損失
ポイントは、所有者責任を正しく理解し管理体制を整えることです。区分マンションでは区分所有法により、専有部の修繕義務と共用部の管理責任が明確に分かれています。しかし、総会議事録を読まずに購入すると、大規模修繕の積立不足や管理会社の委託契約更新問題に後から気づくケースが多いです。
たとえば、修繕積立金が平米あたり月200円しか設定されていない築12年物件では、国土交通省の「長期修繕計画ガイドライン」が目安とする月250〜300円に届きません。結果として10年後に一括追加徴収が必要になり、区分所有者が数十万円を負担する事態が起こります。議事録と長期修繕計画書を精査し、資金不足リスクを数値で把握することが不可欠です。
さらに、入居者トラブルへの対応も盲点です。2024年の改正民法により、オーナーには設備不具合への修繕義務が明文化されました。対応が遅れると家賃減額請求や損害賠償につながるため、24時間駆け付けサービスを提供する管理会社を選定し、一次対応フローを契約書に明記しておくと安心です。
2025年度の制度を活用してリスクを抑える
まず、2025年度も継続される住宅ローン減税は、一定の省エネ基準を満たす新築・築後2年以内の物件が対象です。控除率は年末借入残高の0.7%、上限は新築で4,000万円、中古で2,000万円となります。省エネ基準適合証明書の取得費用は10万円前後ですが、10年間の税控除総額と比較すると費用対効果は高いです。
また、個人での不動産所得は他の給与所得と損益通算が可能です。初年度に発生しやすい減価償却費を活用すれば、課税所得を圧縮し実質利回りを向上できます。税務署への青色申告承認申請書を取得すると、65万円の特別控除と30万円未満の少額減価償却資産が即時償却できるメリットがあります。
一方、固定資産税の負担を減らすには、耐震性能の高い物件を選ぶのが現実的です。2025年度の東京都「マンション長寿命化促進事業」は、1981年以前の旧耐震基準マンションを対象に耐震診断費用を補助しますが、投資用区分は対象外です。そのため、取得前に新耐震基準(1981年6月以降確認済証)かつ省エネ基準を満たす物件を選定し、税制メリットと維持費削減の両面で優位性を確保しましょう。
まとめ
マンション投資で失敗する原因は、初期費用の見落とし、キャッシュフローの過信、立地選定の誤り、法律・管理知識の不足に大別できます。この記事で紹介した失敗例を自分事として捉え、購入前に出口シナリオと長期収支表を作成してください。さらに2025年度の住宅ローン減税や青色申告特別控除など確実に活用できる制度を組み込み、手元資金と予備費に余裕を持たせることが成功への近道です。読者の皆さんが、学んだ教訓を実践し、堅実で持続可能なマンション投資をスタートさせることを願っています。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudosankeizai.co.jp
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 住宅・土地統計調査 – https://www.stat.go.jp
- 国土交通省 長期修繕計画作成ガイドライン – https://www.mlit.go.jp/common/001178692.pdf
- 国税庁 タックスアンサー「住宅借入金等特別控除」 – https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm

