不動産投資に興味はあるものの、自分で物件を持つのはハードルが高いと感じる方は少なくありません。そこで手軽に始められるREIT(不動産投資信託)が注目されますが、「本当に安全なのか」「事故物件とどう違うのか」といった疑問も多いようです。本記事では、REITの仕組みとメリットだけでなく、見落とされがちなデメリットを深掘りし、事故物件投資との比較を通じてリスクと対処法を整理します。読み終える頃には、自分に合った投資スタイルを選ぶための判断軸が明確になるはずです。
REITを理解するための基本知識
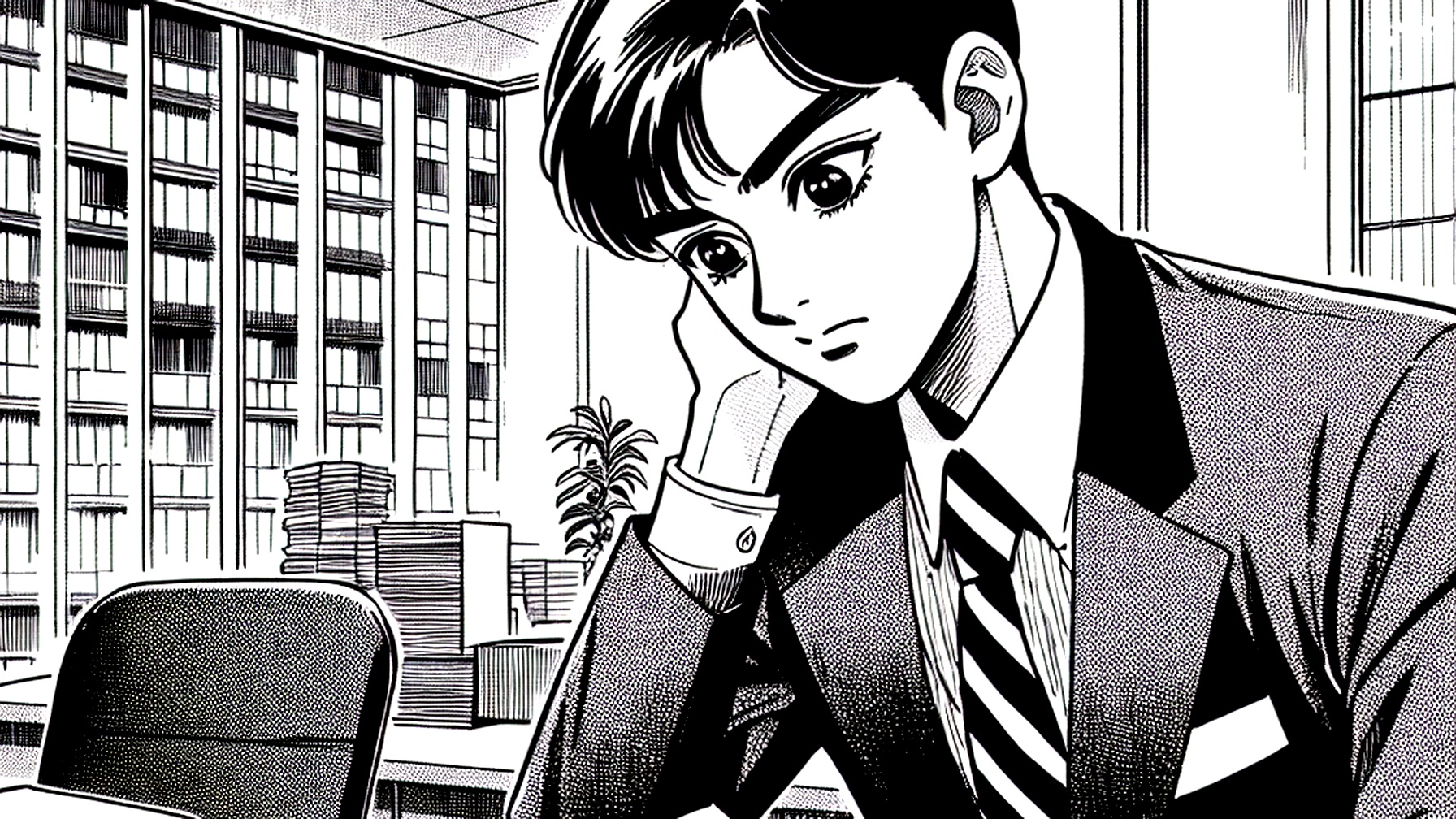
まず押さえておきたいのは、REITが「複数の収益物件に分散投資できる金融商品」である点です。投資家は証券取引所を通じて一口数万円から参入でき、家賃収入や物件売却益が分配金として受け取れます。東京証券取引所のデータによると、2025年9月末時点で上場REITの平均分配利回りは3.8%前後で推移しており、国債より高い利回りを求める個人投資家の資金が流入しています。
一方で、REITは金融商品であり、価格は日々変動します。総務省統計局が公表する消費者物価指数の上昇局面では、不動産のインフレヘッジ効果が期待される半面、金利上昇に伴う借入コストの増加が懸念材料となります。つまり、市場動向をウォッチする姿勢が欠かせません。
さらに、物件選定からテナント管理までを運用会社が代行するため、投資家は「時間と労力を取られにくい」というメリットを享受できます。ただし、後述するようにこの構造がデメリットにもつながる場合があります。まずはREITの基本を理解し、次のステップとしてリスクを洗い出すことが重要です。
見落とされがちなREITのデメリット
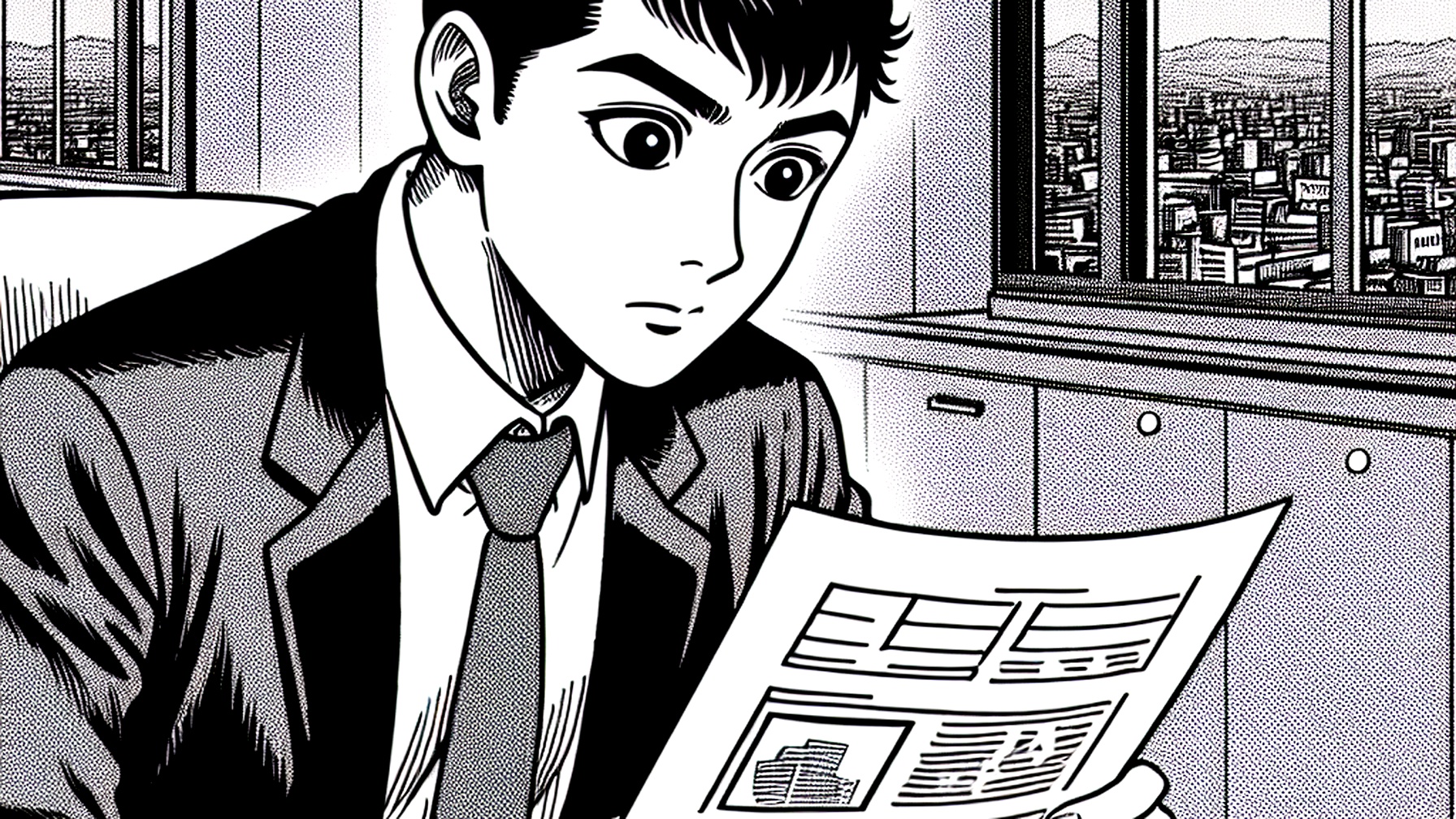
ポイントは「値動きのブレ」と「情報の非対称性」です。上場REITは株式と同じく市場のセンチメントに左右され、実物不動産の価値が安定していても価格が急落するケースがあります。金融庁の統計では、2023年末からの金融引き締め局面で一部REIT指数が半年間で15%下落した例が示されました。実物を持つ場合に比べ、短期ボラティリティが高い点は覚悟が必要です。
次に、運用会社が開示する情報だけでは物件の細部までは把握しづらい問題があります。例えば物件の築年数、テナントの賃料水準、修繕計画などは詳細資料を読み込まないと分かりません。つまり、目立つ利回り数字の裏側に隠れたリスクを見落とす可能性があるのです。
加えて、手数料構造にも注意が求められます。REITは間接的に不動産を保有するため、資産運用報酬や物件管理費が差し引かれ、表面利回りどおりの収益を手にできない場合があります。国土交通省の「不動産証券化実態調査(2025年版)」によれば、運用報酬は純資産の年0.3〜0.6%が一般的で、長期保有すると見えないコストが効いてきます。
最後に、環境性能の低い旧耐震物件を組み込むREITも存在します。SDGsに配慮した資産入れ替えが進む一方で、耐震補強や省エネ改修の費用が分配金を圧迫するリスクは残ります。情報を読み解き、ポートフォリオの質を自らチェックする姿勢が欠かせません。
事故物件投資とどう違うのか
実は、REIT デメリット 事故物件という三つのキーワードは密接につながっています。事故物件とは、室内で死亡事故や事件が起き、心理的瑕疵(かし)があると見なされる物件を指します。市場価格が下がるため、投資家には高利回りのチャンスに映りますが、空室リスクや再売却の難しさがつきまといます。
REITの場合、組み入れ物件が事故物件であるかどうかは運用会社が適切に開示する義務があります。投資家は目論見書や有価証券報告書を読み、ポートフォリオ一覧に変則的な高利回り物件が含まれていないか確認できます。つまり透明性は一定程度確保されていますが、実際の現場を自分の目で見るわけではないため、情報の解釈力が求められます。
一方で、個人が事故物件を直接購入する場合、租税特別措置や保険活用によって初期投資を抑えられる可能性があります。しかし室内のリフォーム費用や近隣への説明対応など、手間がかかりやすい点が難点です。再度の事故が起きた場合は保険適用外になることもあるので、利回り計算を慎重に行う必要があります。
結局、REITと事故物件は「分散された間接投資」と「集中した直接投資」という対照的なモデルです。事故物件で成功するには自主管理スキルが必須であり、REITで成功するには情報開示を読み解く力が鍵となります。投資目的とライフスタイルの双方を考慮し、自分に合うリスクテイクの形を選びましょう。
2025年度の制度と市場環境を踏まえた選択基準
重要なのは、最新制度を利用してリスクを抑えながら収益を高める視点です。2025年度は不動産取得税の軽減措置が延長され、一定の耐震基準を満たす物件であれば税率が1.5%に抑えられるため、事故物件でも改修済みなら恩恵を受けられます。また、住宅金融支援機構が提供する「フラット35リノベ」の優遇金利(2026年3月まで)が使える場合、長期固定金利で資金調達しやすくなります。
一方、REITに投資する際は、金融庁が2024年に導入した「上場投資信託ガバナンスコード」が実務に根付いてきており、運用会社の説明責任が強化されています。2025年10月時点でガイドラインに適合していないREITは分配金の成長鈍化が見込まれるため、銘柄選びのチェックポイントになります。
金利環境も見逃せません。日銀は2025年4月にマイナス金利を完全解除したものの、段階的引き上げにとどめる方針を示しています。日本銀行の公表値では10年物国債利回りが1.3%前後で推移しており、REITの利回りと比較することで期待収益に見合うリスクかを判断しやすくなりました。事故物件の融資金利は個別審査によってさらに上乗せされる傾向があるため、トータルコストを必ず試算してください。
つまり、市場と制度の両面を把握したうえで、「分配金成長が見込めるREIT」と「改修により資産価値が回復した事故物件」のどちらを選ぶか、あるいは両方を組み合わせるかを考えることが、2025年以降の戦略といえます。
まとめ
本記事ではREITの魅力とデメリットを整理し、事故物件投資との違いを比較しました。REITは手軽さと分散効果が強みですが、価格変動と情報の限界を理解しなければなりません。一方、事故物件は高利回りの可能性があるものの、管理の手間と再売却リスクが大きい点に留意が必要です。制度面では2025年度の税制優遇やガバナンス強化が追い風となっており、最新情報を活用すればリスクを抑えつつ収益機会を広げられます。まずは自己資金、時間、リスク許容度を整理し、複数の選択肢をシミュレーションしたうえで、一歩を踏み出してみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産証券化実態調査2025年版 – https://www.mlit.go.jp
- 金融庁 上場投資信託ガバナンスコード – https://www.fsa.go.jp
- 東京証券取引所 REITマーケットデータ – https://www.jpx.co.jp
- 総務省統計局 消費者物価指数 – https://www.stat.go.jp
- 住宅金融支援機構 フラット35リノベ – https://www.jhf.go.jp
- 日本銀行 金融政策決定会合資料 – https://www.boj.or.jp

