不動産投資に興味はあるものの、いきなり物件を買うのはハードルが高いと感じていませんか。実は上場不動産投資信託(REIT)なら、数万円からでも分散投資ができ、配当としての利回りも比較的わかりやすいメリットがあります。しかし「REIT 利回り」と検索すると、数字の見方や他の投資商品との比較があいまいで、結局手が出せないという声が多いのも事実です。本記事では、REITの基礎から利回りの計算方法、さらに2025年時点の市場平均や税制まで初心者にも理解しやすく解説します。読み終えたとき、あなたは自分の資金計画にREITをどう組み込むか具体的に判断できるようになるはずです。
REITと利回りの基礎を押さえる
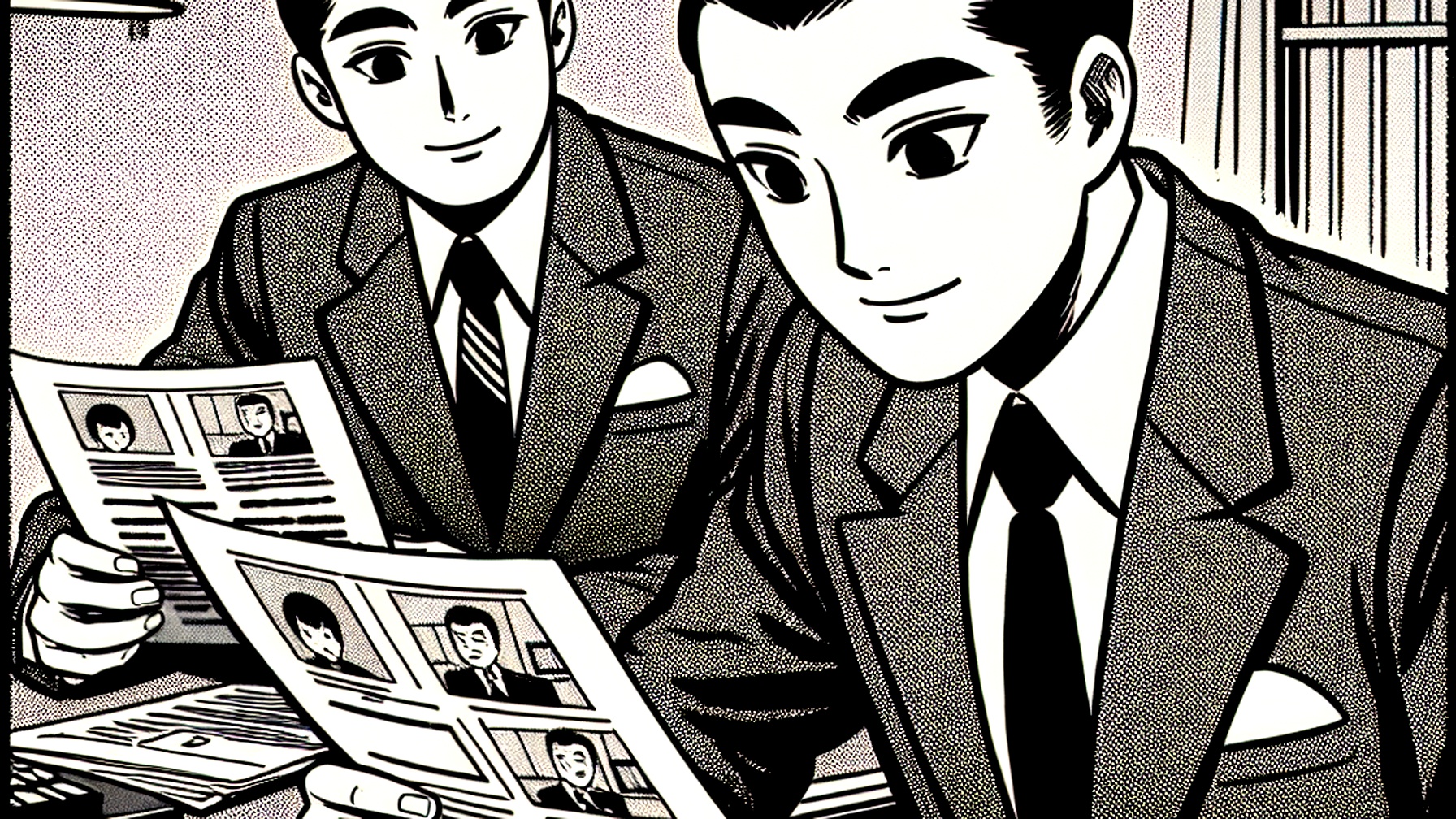
重要なのは、REIT自体の仕組みと利回りの定義を混同しないことです。REITは投資家から集めた資金でオフィスビルや商業施設などを購入し、その賃料収入を原資に分配金を支払います。分配金を株価で割った数字が「分配金利回り」で、銀行預金の金利と近い感覚で比較できます。さらに値上がり益を含めた「トータルリターン」を考慮すると、長期的な運用成績をより正確に把握できます。つまり利回りは配当部分の指標であり、価格変動まで含めた総合評価とは区別することが第一歩です。
まずJ-REIT(日本版REIT)は法律上、利益の九割以上を分配することで法人税が実質的に免除されます。そのため分配金に回る割合が高く、株式と比べて利回りが見えやすい特徴があります。一方で分配原資が賃料収入に偏るため、景気やテナントの入退去による影響は避けられません。分配金が減ると利回りも低下するため、物件ポートフォリオの質が銘柄選びの要となります。またJ-REITは東証に上場しているため、株式と同様に売買できる流動性がある一方、価格は日々変動します。この値動きリスクをどう受け止めるかが、利回り以上に重要な意思決定ポイントになります。
J-REITの利回りはどう決まるのか
ポイントは、分配金の決定プロセスと市場価格の変化が二重に絡むことです。運用会社は半年に一度、保有不動産の賃料収入や売却益を勘案して分配金を決定します。ここでテナントの退去や修繕費の増加があれば、分配金は減少し利回りが下がる構造です。さらに投資家心理や金利動向で株価が上下すれば、同じ分配金でも利回りは変動します。
たとえば2025年9月時点、東証REIT指数の平均分配金利回りは4.1%前後で推移しています。日銀が長期金利を1.0%前後で維持している現状では、相対的に魅力的な水準といえます。しかし2024年末に米国長期金利が上昇した局面では、国内REIT価格が下落し、見かけ上の利回りが一時的に5%台に達しました。このように利回りの数字だけを追うと価格変動要因を見落としやすいため、過去数年間の平均や物件入替の方針まで確認する姿勢が大切です。
また分配金の原資に一時的な不動産売却益が含まれるかどうかもチェックポイントです。売却益でかさ上げされた分配金は再現性が低く、翌期に減配リスクがあります。運用報告書のキャッシュフロー計算書を見れば、営業活動によるCFと投資活動によるCFのバランスがわかります。営業CFが安定的に伸びている銘柄ほど、利回りの持続性が高いと判断できます。
個別銘柄の利回り差と見るべき指標
実は、物件タイプや地域特性で利回りの平均値が大きく異なります。オフィス特化型は供給過多の懸念があるため3%台後半、物流施設はEC需要を背景に4%台前半、ホテル系はコロナ後のインバウンド回復で5%台を記録する銘柄もあります。ただし高利回りだけを追うと価格変動リスクが大きくなる傾向が強いため注意が必要です。
まず押さえておきたいのは、LTV(Loan to Value=負債比率)が高すぎないかという点です。一般にLTVが50%を超えると金利上昇時の財務負担が増え、分配金の減少リスクが高まります。2025年度は金融庁がREITの資本健全性を注視しており、LTV60%超の銘柄に対し情報開示の強化を促しています。そのため投資家はIR資料でLTV推移を確認し、40%台に収まる銘柄を中心に検討すると安心感があります。
またNAV倍率(株価純資産倍率)も重要な手がかりです。株価が純資産価値の一口当たり額を下回る場合、理論上は割安とされますが、物件評価の下落懸念が織り込まれていることもあります。逆にNAV倍率が高い銘柄は市場が成長性を期待している証拠ともいえますが、利回りは低下しやすい点に注意が必要です。利回りとNAV倍率を同時に比較することで、収益性と成長期待のバランスを見極められます。
REITと直接不動産投資の利回り比較
まず前提として、直接物件を購入する場合の平均表面利回りは、日本不動産研究所によると2025年9月時点でワンルームマンション4.2%、アパート5.1%となっています。数字だけ見ればREITと近い水準ですが、運営コストや空室リスクを自己負担する点が大きな違いです。
一方でREITはプロが運営し、空室や修繕対応を投資家が直接担う必要はありません。その代わり、管理報酬や信託報酬として年0.3〜0.5%程度のコストが内部で控除されています。言い換えると、REITの利回りはすでに諸費用が差し引かれた「ネット利回り」に近い数字で表示されているわけです。
さらに資金流動性の観点でも両者は大きく異なります。不動産を売却するには数カ月の時間と仲介手数料がかかりますが、REITは市場で即日売却が可能です。この点は金利上昇局面やライフプランの変更時に大きなメリットとなります。ただし短期売買を繰り返すと配当狙いの効果が薄れるため、長期での安定運用を前提とした利回り目標を設定することが望ましいと言えます。
2025年度の税制と補助的制度
ポイントは、利回りを手取りベースで考えると税金の影響が無視できないことです。REITの分配金は株式配当と同じく20.315%の申告分離課税が原則ですが、NISA口座を利用すれば年間360万円までの投資枠に対して非課税となります。2024年に抜本改正された新NISAは2025年度も継続しており、成長投資枠でREITを購入した場合、配当も譲渡益も非課税なのが大きな利点です。
またiDeCo(個人型確定拠出年金)ではREITを直接組み入れることはできないものの、REITを対象とした投資信託を選択肢に含める運営管理機関が増えています。iDeCo口座内での運用益は全額非課税で、掛金も所得控除の対象になるため、利回りの向上に寄与します。加えて、2025年度まで延長が決まった「上場株式等の配当等受領時の配当控除」も活用すれば、総合課税を選択することで一定の税額控除を受けられるケースがあります。
ただし補助金やポイント還元のような直接的な金銭給付制度は、2025年9月時点でREIT投資に対しては存在しません。そのため税制優遇と手数料の低い証券会社を選ぶことが、実質的な利回りを高める王道施策となります。
まとめ
ここまでREIT利回りの読み解き方を、仕組みの理解から個別銘柄分析、税制まで幅広く見てきました。配当原資の安定性を確認し、市場価格の変動要因を把握することで、表面の数字だけでは見えないリスクを減らせます。またLTVやNAV倍率、運用コストを総合的に検討すれば、利回りの持続性をより精密に評価できます。結論として、REITは少額で始められ流動性も高い一方、価格変動と金利の影響を受けやすい商品です。まずはNISA枠や低コスト証券会社を活用し、長期投資を前提にポートフォリオの一部として組み入れることをおすすめします。将来の資産形成に向け、今日から具体的な銘柄比較と口座開設の準備を始めてみてはいかがでしょうか。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp
- 金融庁「REIT情報開示の手引き」 – https://www.fsa.go.jp
- 東京証券取引所「J-REIT市場統計」 – https://www.jpx.co.jp
- 日銀「金融政策決定会合資料」 – https://www.boj.or.jp
- 国税庁「令和7年度税制改正のポイント」 – https://www.nta.go.jp

