都市部の空室率が気になる、金利が上がったら返済が大丈夫か、こうした悩みを抱えつつも「やっぱり不動産で資産形成をしたい」という人は少なくありません。しかしメリットだけに目を向けると、思わぬ落とし穴にはまるおそれがあります。本記事では、不動産投資の代表的なデメリットを整理し、ほかの資産運用と比較しながら対策を解説します。読めば、自分に合った投資スタイルを見極める手がかりが得られるでしょう。
不動産投資の代表的なデメリットとは
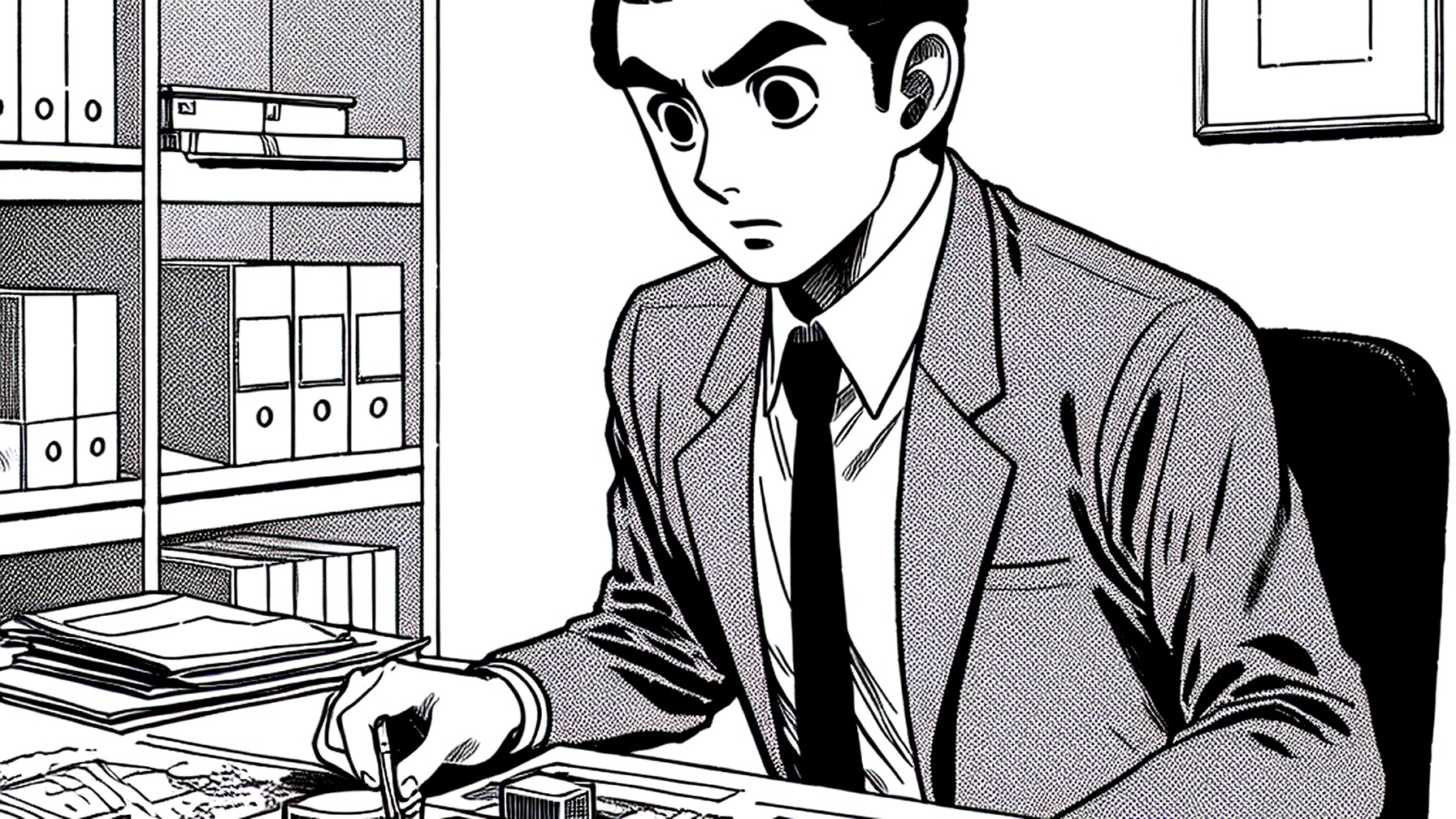
重要なのは、リスクを「知らなかった」では済まされない点です。不動産投資には価格変動や空室といったイメージしやすいものから、修繕積立金の不足など見えにくい負担まで幅広いデメリットが存在します。
まず価格変動リスクですが、都市部でも築年数が古くなると資産価値は確実に下がります。国土交通省の不動産価格指数を見ても築二十年超の区分マンションは新築時の七割を切る水準まで下落するケースが一般的です。また空室リスクは地方だけの話ではなく、東京都でも総務省の住宅・土地統計調査(二〇二三年速報値)で空き家率が一〇%を超えました。需要がある地域でもターゲット層を外せば収益は一気に悪化します。
さらに、突発的な修繕費が家計を圧迫します。二〇二四年度に公表された国交省「マンション大規模修繕コスト調査」では、一戸あたり平均一二〇万円の負担が必要との結果でした。この費用を見込まずに利回りだけで判断すると、長期的な収支は成り立ちません。つまり、運営コストを正しく織り込む姿勢が欠かせないわけです。
他の資産運用と比較したときの位置づけ
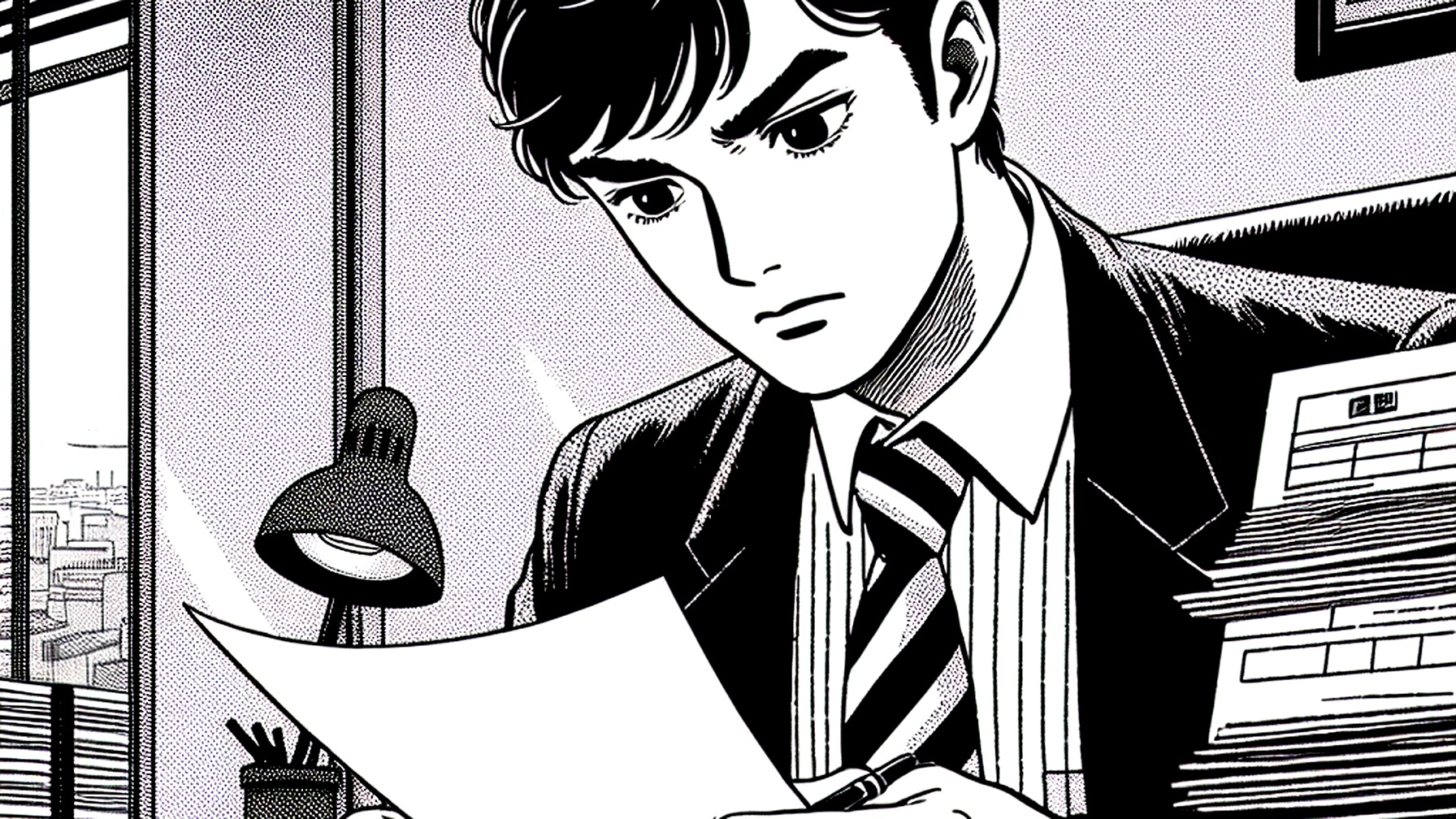
実は「不動産投資 デメリット 比較」をするうえで、株式や投資信託といった流動性の高い商品とどう違うかを押さえると理解が深まります。ポイントは換金性、価格変動幅、そしてコスト構造です。
株式や上場投資信託(ETF)は売却注文を出せば二営業日後には現金化できます。一方、物件売却には平均三〜六か月が必要で、仲介手数料や譲渡所得税も発生します。日本銀行の資金循環統計によると、株式の標準偏差は年率一五%前後に対し、住宅系不動産は約六%と緩やかですが、流動性が低いため「逃げ遅れる」リスクが潜みます。
また配当と家賃収入はどちらもインカムゲインですが、維持管理費が発生するかどうかが大きな違いです。投資信託の信託報酬は年〇・五%前後で固定されますが、物件の管理費や修繕積立金は築年数に連動して増える傾向があり、国交省のデータでは築三〇年で新築時の一・八倍になるとされています。言い換えると、時間がたつほど出口戦略の設計が重要になるのです。
デメリットを軽減するキャッシュフロー管理
まず押さえておきたいのは、収支がマイナスにならない安全域を計算することです。家賃収入から管理費、ローン返済、税金、修繕費を差し引き、手元に残る金額が「キャッシュフロー」と呼ばれます。金融庁の「事業用不動産向け融資に関するガイドライン」では、年間返済額を家賃収入の五〇%以内に抑えると安定しやすいと示唆しています。
さらに、自己資金と借入金のバランスも大切です。二〇二五年時点で地方銀行の投資用ローン金利は変動一・八%前後ですが、借入比率が八割を超えると金利が〇・三%ほど上乗せされるケースが増えています。わずかな金利差でも三〇年返済では総返済額が数百万円変わるため、自己資金二〜三割を用意する方が長期的に有利です。
予備費の確保も忘れてはいけません。空室率一五%、修繕費年間五〇万円という厳しめのシナリオでも三年間は赤字にならないかを試算しておくと、景気後退期にも耐えられます。つまり、キャッシュフローモデルを複数用意し、最悪ケースで黒字を維持できるプランを選ぶことがリスク軽減の近道です。
法制度・税制面で押さえるポイント(2025年度版)
ポイントは、合法的に負担を減らす制度を活用しつつ、期限切れに注意することです。二〇二五年度の住宅ローン減税は投資用物件には適用されませんが、短期賃貸住宅のうち省エネ性能が一定基準を満たすと固定資産税の減免対象になる自治体があります。とくに東京都の「ゼロエミ住宅促進税制」は二〇二六年三月末までの取得が条件なので、スケジュール管理が欠かせません。
また所得税の損益通算は有効な節税策ですが、赤字幅が大きいと税務署から確認を受ける割合が高まります。国税庁は二〇二四年度の事務年度報告で、不動産所得の調査件数を前年度比一五%増やしたと公表しました。青色申告特別控除六五万円を活用する場合も、帳簿付けと修繕費の資本的支出判定を適切に行う必要があります。
さらに、二〇二五年四月に改正される相続登記の義務化も見逃せません。相続開始を知った日から三年以内に登記をしないと一万円以下の過料が科されるため、長期保有を前提とする投資家ほど家族への情報共有が重要となります。こうした制度面のデメリットは対策を講じればコストに直結する損失を防げるため、早めのアクションが不可欠です。
物件選びで差が出るリスクコントロール
基本的に、立地と築年数がデメリットの大半を左右します。都心五区のワンルームは利回り四%前後と低めですが、空室率は三%程度にとどまります。一方で地方政令市の築二十五年アパートは利回り九%でも空室率二〇%というデータが総務省「住宅市場動向調査」にあります。数字だけを見ると後者が魅力的に映りますが、修繕費と空室補填を考慮すると手残りは前者の方が大きい場合が多いのです。
物件情報を読み解くうえで、周辺の将来人口は欠かせない指標です。国立社会保障・人口問題研究所の推計では、二〇四五年にかけて人口が増えるのは東京二三区とごく一部の政令市に限られます。将来人口が減少する地域で購入するなら、土地値が高い物件を選び、最終的に戸建てとして売却する出口を描く戦略が有効です。
内見時には建物だけでなく、管理組合の収支報告書も必ず確認しましょう。修繕積立金が足りず、毎月の費用が数年内に倍増するマンションも珍しくありません。この情報を見落とすと、想定利回りが一気に崩れます。言い換えると、書類を読み込めば将来のコスト増をかなりの精度で予測できるわけです。
まとめ
以上、不動産投資には価格変動、空室、修繕費、流動性の低さなど複数のデメリットが存在し、株式や投資信託と比べて現金化の難易度が高い点が大きな違いです。しかし、キャッシュフローを保守的に見積もり、制度面の期限を守りながら立地と管理状況にこだわれば、これらの弱点は大きく抑えられます。次に物件を検討する際は、ここで示したチェックポイントを参考に、自分のリスク許容度と資金計画を照らし合わせてみてください。準備と情報収集を徹底すれば、長期にわたり安定した収益を手にする可能性は十分にあるでしょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 統計局 住宅・土地統計調査 – https://www.stat.go.jp
- 日本銀行 資金循環統計 – https://www.boj.or.jp
- 金融庁 事業用不動産向け融資ガイドライン – https://www.fsa.go.jp
- 国税庁 事務年度報告書 – https://www.nta.go.jp

