不動産投資信託(REIT)は株式と同じように証券口座で売買でき、少額から分散投資を始められる点が魅力です。しかし、分配金や売却益には税金がかかり、「どこで REIT 税金 が差し引かれるのか」「確定申告が必要なのか」という疑問を抱く人は少なくありません。本記事では、2025年10月時点で有効な税制を前提に、税金が発生するタイミングや控除制度の使い方を具体例とともに解説します。読後には、自分に合った口座を選び、無駄なく税金を管理する方法が分かるはずです。
REITの税金は何に対してかかるのか
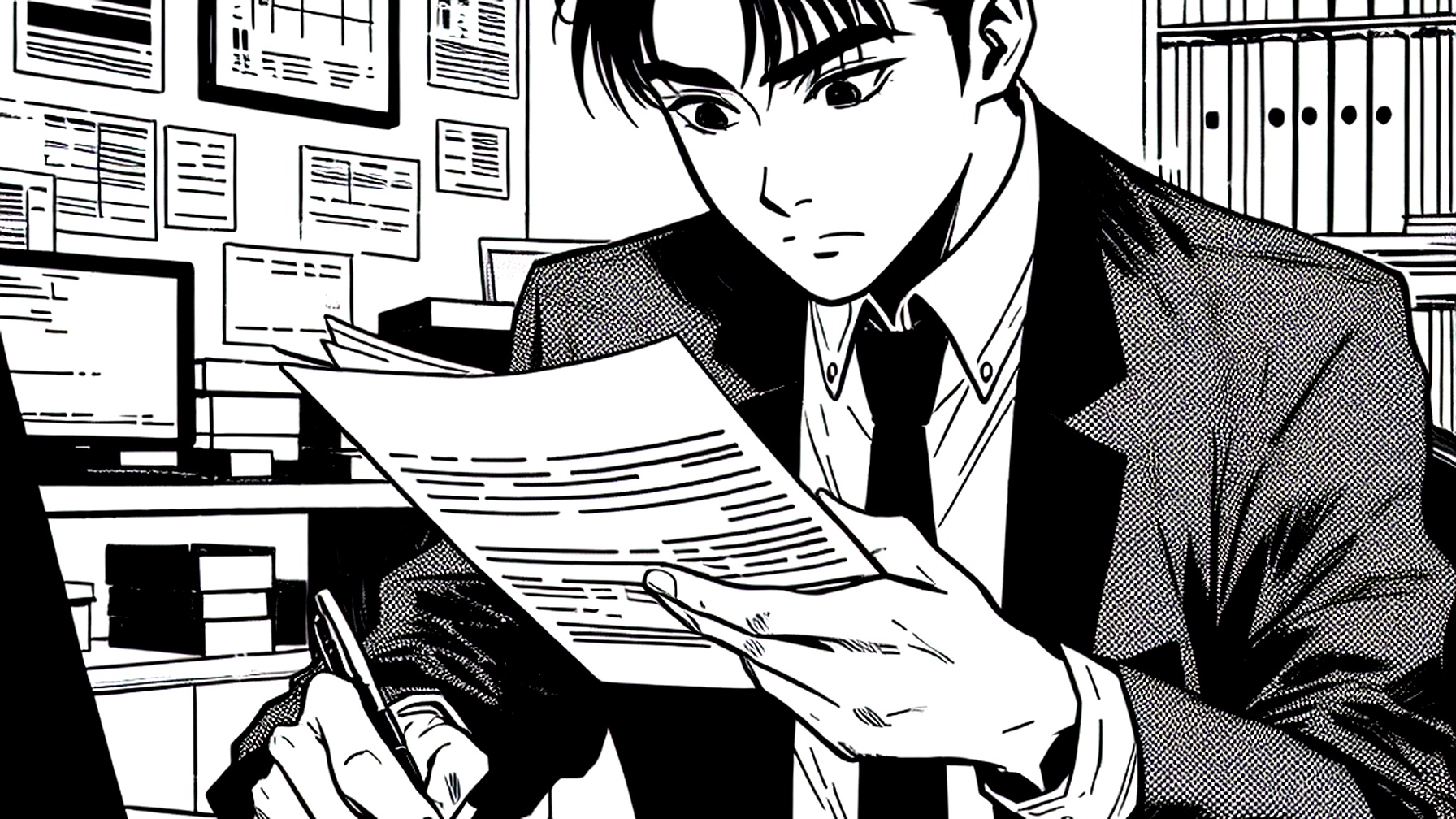
重要なのは、REITでは二種類の利益に税金が課されるという点です。ひとつは分配金、もうひとつは売却益です。
まず分配金は、物件から得た賃料収入や売却益を投資家に分配したものです。国税庁の資料によると国内REITの平均分配利回りは3〜4%で推移しており、安定収入を期待する人には魅力的です。しかし、それが口座に入金される時点で所得税15.315%と住民税5%が合計20.315%源泉徴収されます。また復興特別所得税も含まれるため、税率は小数点以下まで設定されています。
一方、売却益とは取得価額より高い価格で売れた場合の差額です。売却時にも同じ20.315%が課税される点は株式と同じですが、含み益の時点では税金は発生しません。つまり「利益確定」するまで課税を繰り延べできるわけです。この仕組みを理解しておくと、タイミングを見計らった出口戦略を組みやすくなります。
最後に、海外上場REITでは現地で課税された後に国内でも課税される「二重課税」が起こり得ます。外国税額控除を使えば重複分を一定額まで差し引けるため、後ほど詳しく説明します。
税金はどこで差し引かれるのか―口座別の違い
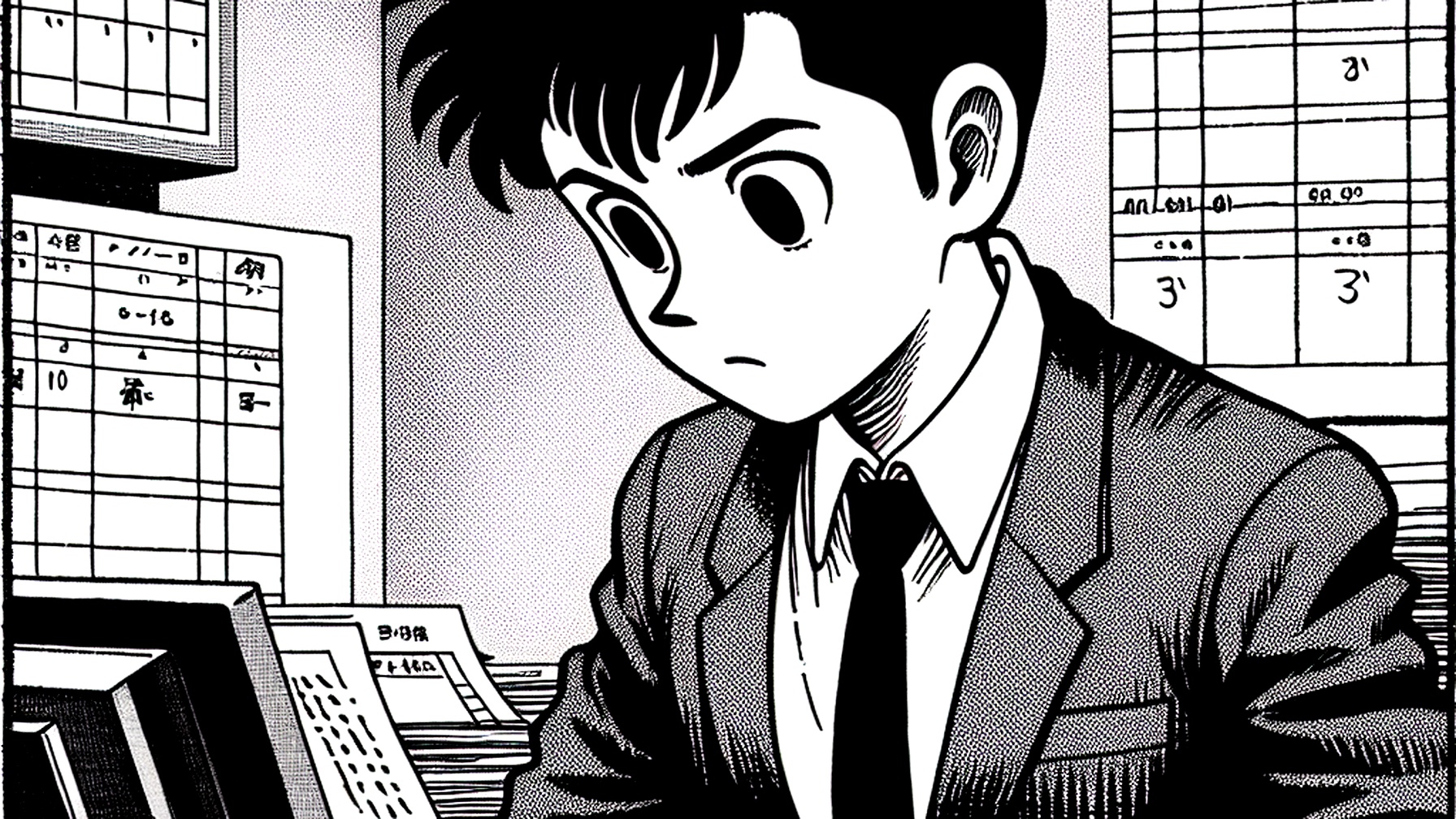
ポイントは、使う証券口座によって税金の扱いが大きく変わることです。
特定口座(源泉徴収あり)では、証券会社が年間の損益を自動で計算し、税金を月ごとに天引きします。給与所得のみの会社員で他に申告すべき所得がなければ、確定申告を省略できます。手間を減らしたい初心者には最も利用者が多い方式です。
一方、特定口座(源泉徴収なし)や一般口座を選ぶと源泉徴収は行われません。年間取引報告書を基に自分で損益を計算し、確定申告で納税します。経費計上や損益通算を細かく行いたい人、あるいは給与以外の副収入が多い人には自由度が高い方法といえます。
2025年度の新NISA(少額投資非課税制度)は、つみたて投資枠と成長投資枠を合計1,800万円まで非課税で保有でき、そのうち年間360万円が投資上限です。J-REIT ETFやREIT関連投信も成長投資枠の対象に入っているため、この枠内で得た分配金と売却益は期間無制限で非課税になります。つまり「どこで REIT 税金 が差し引かれるのか」といえば、新NISA口座ならそもそも差し引かれないのです。
海外REIT投資で押さえたい外国税額控除
実は、海外上場REITを買うときは現地課税が発生し、国内で再び課税される可能性があります。たとえば米国REITの分配金には10%の現地源泉税がかかり、その後に日本の20.315%が控除前の金額に対して課税されます。二重課税を避けるには、確定申告で外国税額控除を申請し、国内税額から一定額を差し引く必要があります。
国税庁の2024年版「外国税額控除に関する手引き」では、対象となる外国税は配当所得や利子所得に限定されます。控除上限は総所得に応じた算式で決まり、全額が取り戻せるとは限りません。それでも、たとえば年間10万円の米国REIT分配金に対して差し引かれた1万円の外国税の大半を取り戻せるケースもあります。
海外REITの魅力は、国やセクターをまたいだ分散効果です。しかし税金面で手続きを怠るとリターンが目減りします。NISA口座で購入すれば国内課税は回避できますが、現地課税分は戻りません。したがって、米国REITを多く保有する場合は特定口座(源泉徴収なし)を選び、外国税額控除を活用する方が最終手取りを高めやすいでしょう。
税負担を減らす2025年時点の有効制度
まず押さえておきたいのは、2025年度も継続する新NISAのメリットです。非課税枠は生涯で1,800万円と大きく、使い切るまで何度でも売却と再投資を繰り返しても枠が減らない「枠の再利用」が可能です。REITのように分配金が多い資産を非課税で保有すると、複利効果がより強く働きます。
加えて、つみたて投資枠を用いてREITインデックスファンドを毎月自動購入すれば、価格変動リスクを時間分散できます。金融庁の試算によると、過去20年間の分散投資では年間平均リターンが5%前後に落ち着いており、税金を抑えた長期保有がパフォーマンス向上に直結することが示されています。
iDeCo(個人型確定拠出年金)は掛金が全額所得控除となり、運用益も非課税です。証券各社の2025年商品ラインナップを見ると、J-REIT指数に連動する投資信託が組み込まれています。60歳まで引き出せないという流動性の低さはありますが、所得税率が高い人ほど節税効果が大きくなります。
最後に、小規模企業共済や不動産所得との損益通算も検討余地があります。たとえば個人事業主がREITで損失を出した場合、事業所得と相殺することで総合課税所得を圧縮できるケースがあります。ただし、制度の適用可否は年ごとに更新されるため、利用前に税理士へ確認するのが安全です。
確定申告で失敗しない手順と注意点
ポイントは、年間取引報告書と分配金計算書を早めに整理し、申告ソフトで試算を行うことです。特定口座(源泉徴収あり)の人でも、医療費控除やふるさと納税で還付を受けたい場合は確定申告が必要になります。
まず、証券会社のサイトからPDFで取得できる年間取引報告書を確認します。売却損益、分配金、外国税額が一覧になっているので、数字を転記すれば大半の入力は完了します。次に、他社口座や投資信託の分配金がある場合は合算し、損益通算できるかをチェックします。国税庁「確定申告書等作成コーナー」は2025年1月からスマホ対応が強化され、AIによる入力補助も導入されています。
また、3年間の繰越控除制度を活用すれば、今年計上したREITの損失を翌年以降の利益から差し引けます。たとえば2025年に20万円の損失を出し、2026年に30万円の利益が出た場合、課税対象は差し引き10万円となります。損失の申告を忘れると繰越が無効になるため、赤字の年こそ申告が重要です。
最後に、海外REITの外国税額控除を使う場合は、外国所得税の計算明細書を別途提出します。入力を誤ると控除額が減るだけでなく、書類の再提出が必要になることもあります。申告期限間際は税務署が混雑するので、2月上旬までに下書きを終えると安心です。
まとめ
本記事では、分配金と売却益にかかる基本税率、証券口座別の課税方法、海外REITでの外国税額控除、そして新NISAやiDeCoなど2025年時点で活用できる節税制度を取り上げました。要するに「どこで REIT 税金 が引かれるか」は口座の選び方次第であり、非課税口座を上手に組み合わせることで手取りを大幅に増やせます。これからREIT投資を始める人は、まず特定口座と新NISAを開設し、小額でも実際に取引して税金の流れを体感しましょう。行動を起こすことでしか、最適な税戦略は見えてこないからです。
参考文献・出典
- 国税庁 – https://www.nta.go.jp
- 金融庁「NISA特設ページ」 – https://www.fsa.go.jp/policy/nisa/
- 総務省統計局「家計調査年報2024」 – https://www.stat.go.jp
- 東京証券取引所「J-REIT市場統計データ」 – https://www.jpx.co.jp
- 財務省「外国税額控除に関する手引き2024」 – https://www.mof.go.jp

