不動産投資に興味はあるものの、「REITなら少額で始められると聞くけれど、実物物件をゼロから買ったほうが利益は大きいのでは」と悩む人は多いです。投資経験が浅いほど、情報の広さと深さのギャップに戸惑いがちなものです。本記事では、REITと現物投資を並べて徹底的に比較し、それぞれのメリット・デメリットを具体的に示します。読後には、自分に合った入口を判断する軸がはっきりし、最初の一歩を踏み出す自信が得られるでしょう。
REITとゼロからの現物投資の基本構造
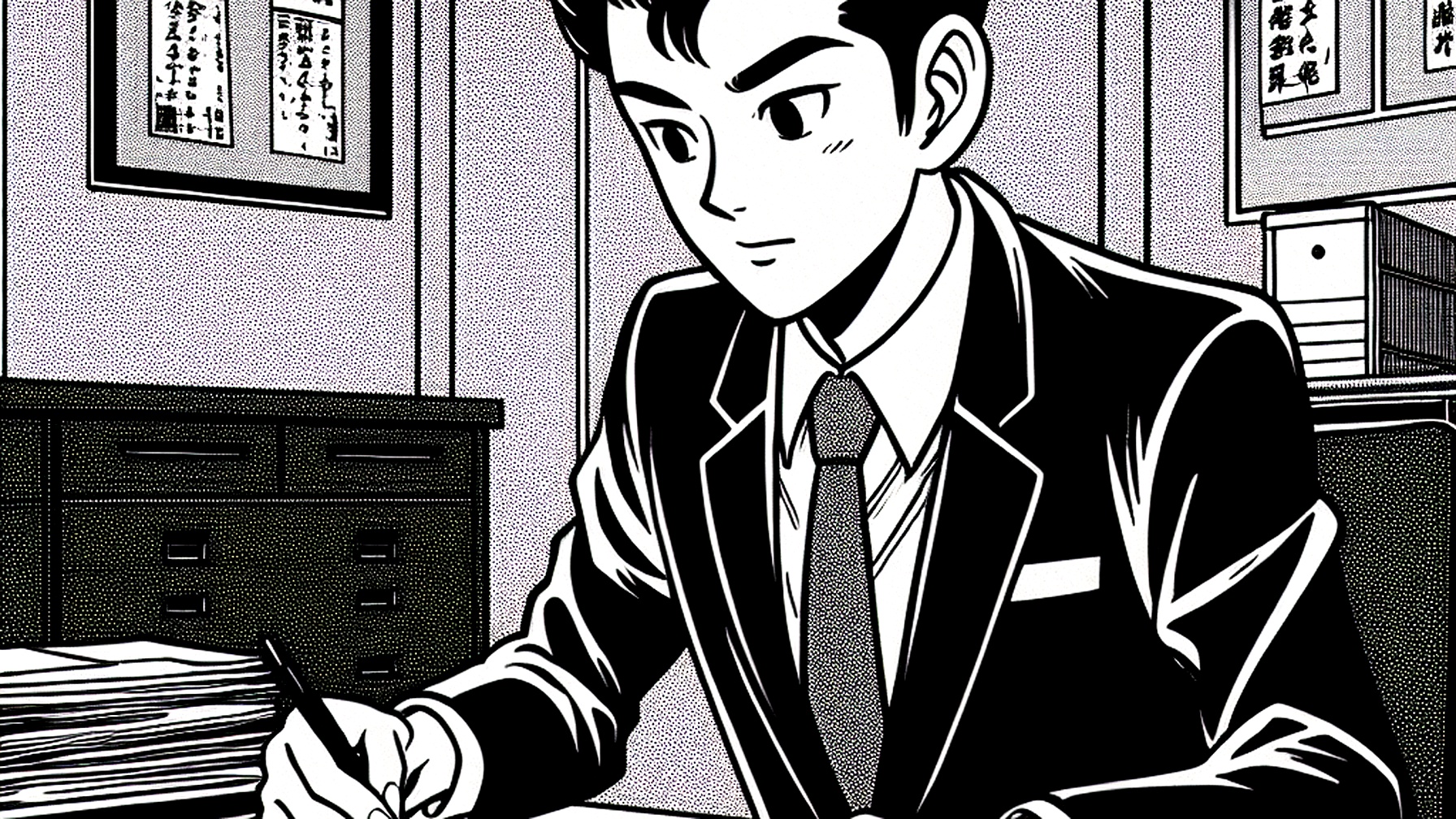
まず押さえておきたいのは、両者の仕組みの違いです。REIT(不動産投資信託)は投資家から集めた資金でプロが複数物件を運用し、その賃料や売却益を分配金として支払います。一方、ゼロからの現物投資は、個人が物件を直接所有し、自ら管理または管理会社を通じて運営します。
REITは東京証券取引所で株式と同じように売買できるため、数万円から投資が可能です。また、複数物件に分散投資されているので、空室リスクが平準化されやすい点が特徴です。対して現物投資は、頭金や諸費用を含め数百万円の自己資金が必要になるものの、レバレッジ(借入)を活用すれば自己資金以上の資産を運用できる魅力があります。
日本証券取引所のデータによると、2024年度の東証REIT指数の平均分配利回りは4.1%でした。これに対し、国土交通省の家賃実態調査ではワンルーム区分マンションの実質利回りが平均5.0%前後となっています。数字だけ見ると現物優位に映りますが、後述する手間や追加費用を踏まえて総合評価することが重要です。
収益性とリスクを数値で読み解く
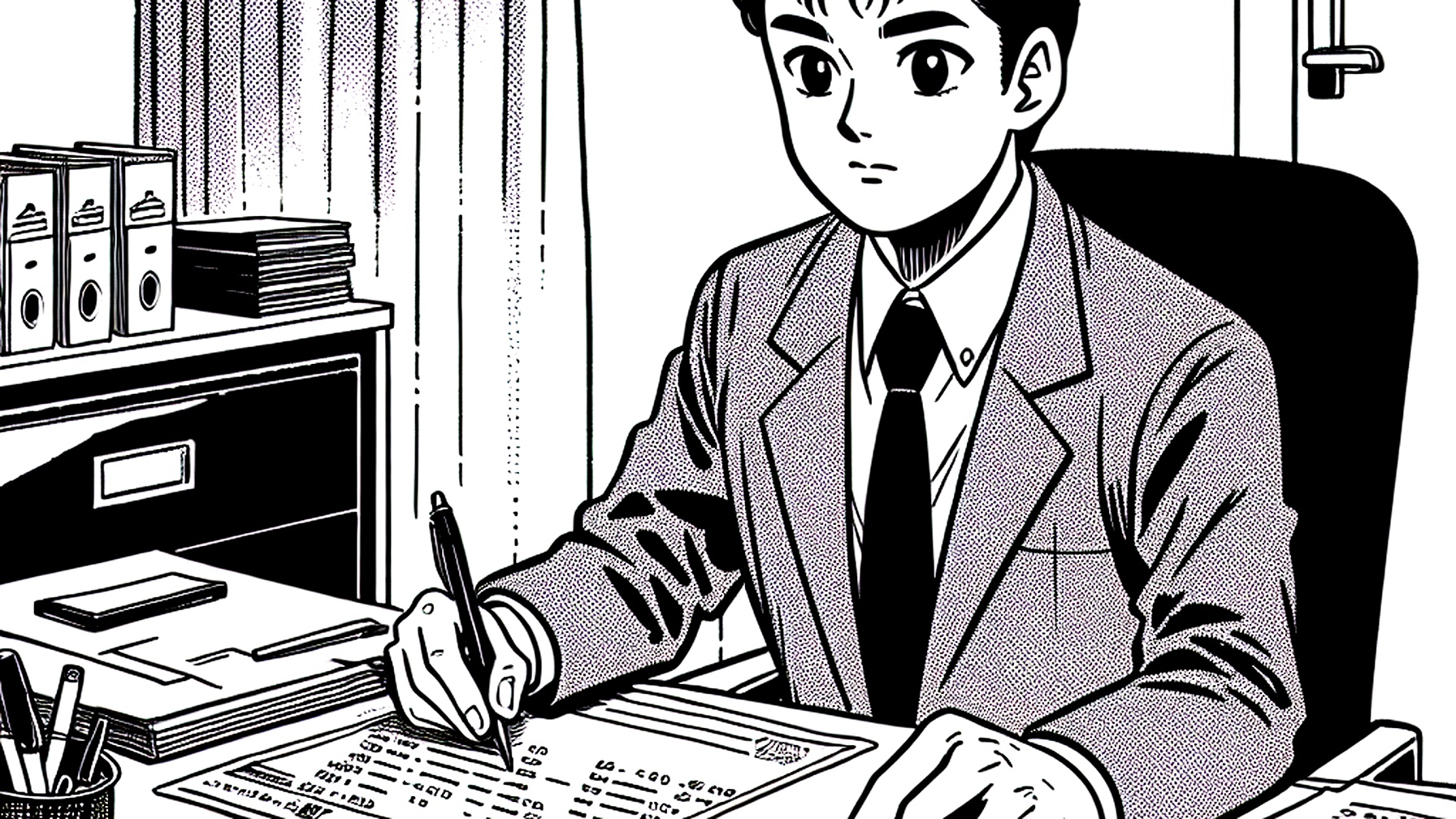
ポイントは、単純利回りではなく「リスク調整後リターン」を比較する姿勢です。REITの場合、価格変動の標準偏差は過去10年平均で年率14%前後です。つまり、株式市場に近いボラティリティがある一方で、値上がり益も期待できます。
現物投資は、物件価格の年平均変動率が3%程度と比較的穏やかです。しかし、空室や大規模修繕が発生すると年間キャッシュフローがマイナスになることもあります。例えば築20年の区分マンションで配管更新が必要になった場合、100万円超の一時負担が現実的です。
金融庁の「家計の金融行動に関する調査」では、投資初心者の約65%が「損失が出ても原因が把握できない」と回答しています。REITはインターネットで開示情報が充実しており、分配金の変動要因を比較的追いやすいのが利点です。一方、現物ではエリア特性、物件管理、入居者対応など多層的な要素が絡むため、知識のアップデートを怠るとリスクが拡大します。
資金計画とレバレッジの使い方
重要なのは、自己資金と借入のバランスです。REITは現金一括投資が原則で、証券口座にある範囲内でしか買えません。信用取引を用いたレバレッジも可能ですが、金利負担と追証リスクを考えると初心者には推奨しにくいです。
一方で現物投資は、2025年度も続くフルローンやオーバーローンの審査が厳格化しているものの、物件価格の70〜80%を金融機関が貸し付ける事例が多いです。金利は地方銀行で年1.8〜3.0%、期間は30年が主流です。月々の返済額を賃料収入で賄える設計なら、自己資金を温存しつつ資産拡大を狙えるのが魅力です。
ただし、日本銀行の統計によれば、2025年4月時点の住宅ローン平均残高は過去最高を更新しています。金利が上昇局面に転じた場合、レバレッジを大きくかけた投資家が返済負担増でキャッシュフローを圧迫されるリスクがあるため、中長期の金利シナリオを複数想定することが欠かせません。
税制と手間 2025年度制度面から見る優劣
実は、税制面でのメリットは投資形態によって色合いが異なります。REITの分配金は配当所得として扱われ、2025年度も上場株と同じく20.315%の申告分離課税が適用されます。一方、現物投資の家賃収入は不動産所得となり、所得税と住民税の総合課税です。
所得が高い人ほど税率が上がるため、現物投資では減価償却を活用した節税がポイントになります。木造アパートなら最短4年で大きく経費計上できるケースもあり、課税所得の圧縮効果が高まります。ただし、2025年度税制改正大綱では、過度な損益通算を防ぐ観点から耐用年数の見直し議論が継続しており、将来変更される可能性には注意が必要です。
手間という観点では、REITは証券会社が管理事務を代行するため、確定申告しない特定口座を選べば運用はほぼ放置できます。対して現物投資は、賃貸契約や修繕手配、確定申告など時間的コストが避けられません。管理会社に業務委託すれば手間は減りますが、管理料として家賃の3〜5%が差し引かれる点を計算に入れる必要があります。
投資家タイプ別に考える最適解
まず時間と知識の制約が大きい会社員や子育て世代には、少額から分散投資できるREITが向いています。手間が少ない分だけ継続しやすく、投資マインドを育てる入口として最適です。また、市場価格が毎日確認できるため、資産形成の進捗を可視化しやすいメリットがあります。
一方で、長期にわたり安定した家賃収入を得たい人や、相続対策を兼ねたい人には現物投資が候補となります。不動産を直接所有すると、固定資産として評価額が下がりやすく、相続税の圧縮効果が期待できるからです。さらに、入居者とのコミュニケーションを楽しめる性格の人は、物件価値を自ら高める余地があります。
結論として、REIT 比較 VS ゼロから の選択は、資金力・リスク許容度・ライフスタイルの組み合わせで変わります。両方を少額ずつ試し、自分の適性を確認してから拡大するステップが、2025年現在の不確実な市場では最も合理的といえるでしょう。
まとめ
ここまで、REITとゼロから始める現物投資を資金、リスク、税制、手間の側面から比べました。REITは流動性と分散性に優れ、忙しい人でも継続しやすい選択肢です。対して現物投資は、レバレッジと節税により高い収益性を狙えますが、知識と時間が不可欠です。まずは自己資金と目標期間を明確にし、小規模に試すことで経験値を積み重ねてください。行動することでしか得られない学びが、次の投資判断を確かなものにしてくれます。
参考文献・出典
- 日本証券取引所グループ – https://www.jpx.co.jp
- 国土交通省 住宅市場動向調査 – https://www.mlit.go.jp
- 金融庁 家計の金融行動に関する調査 – https://www.fsa.go.jp
- 日本銀行 金融統計月報 – https://www.boj.or.jp
- 総務省 統計局 家計調査 – https://www.stat.go.jp

