アパート経営を始めたいものの、円安が進み、コロナ後の生活様式も定着してきた今、どこに物件を買えば良いのか悩む人は多いでしょう。実は立地選定を間違えると、家賃下落や空室が続き、想定した収益を得られません。しかし需要の変化を捉え、資金計画を固めれば、初心者でも安定したキャッシュフローを築けます。本記事ではアフターコロナで変化した入居者ニーズ、円安時代の地域選び、そして失敗を避ける具体的な視点をわかりやすく解説します。読み終えるころには、自分に合ったエリアを見極めるヒントが得られるはずです。
アフターコロナで変わる賃貸需要の潮流

まず押さえておきたいのは、コロナ禍を経て賃貸需要の質が大きく変わった点です。国土交通省の住宅統計によると、2025年8月の全国アパート空室率は21.2%で前年より0.3ポイント低下しました。テレワークが定着し、自宅で快適に過ごせる広さと通信環境を重視する人が増えたため、設備が充実した物件ほど空室改善がみられます。
一方で、ワンルーム中心のビジネス街近接エリアは、出社回帰の遅れから以前の需要が戻り切っていません。つまり物件タイプと立地のミスマッチが顕在化しており、供給過多の地域では家賃下落が続くリスクがあります。これを裏返せば、在宅勤務に適した間取りや高速インターネットを備えた郊外駅近物件は、今後も堅調な賃貸需要が期待できるということです。
また、インバウンド再開で観光地近郊の賃貸住宅に短期滞在需要が流入し始めています。住宅宿泊事業法に沿った運用は手間がかかりますが、複数年賃貸とのハイブリッド運営が可能なエリアでは利回り向上の余地があります。アフターコロナのニーズを読み取り、ターゲットを絞った物件選びが欠かせません。
円安時代に強いエリアとは
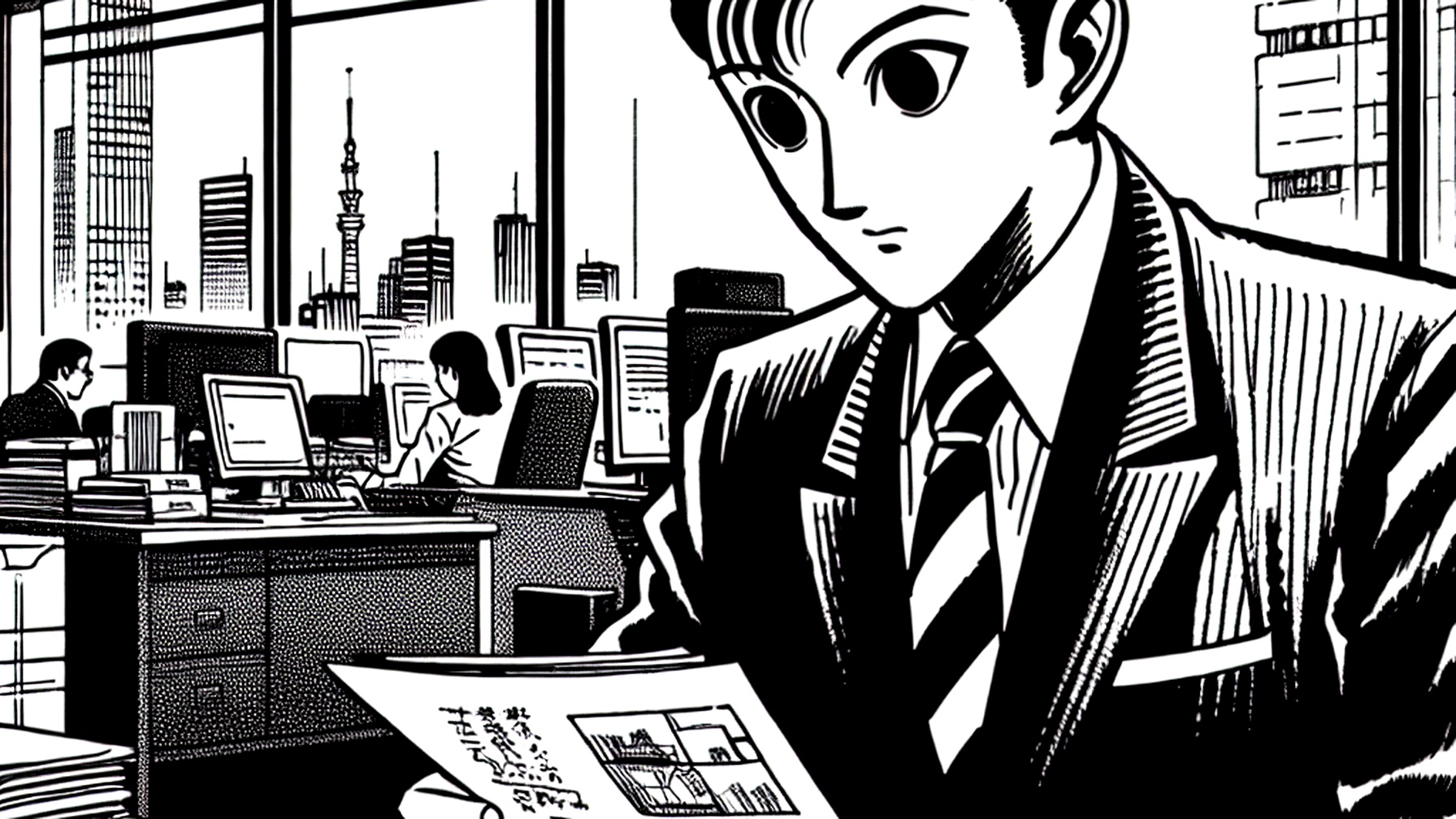
重要なのは、円安が地域経済に与える影響を理解し、外貨収入が増えるエリアを選ぶことです。2025年9月の平均為替レートは1ドル=154円台で推移し、輸出企業の集積地や観光地は雇用が拡大しています。具体的には港湾と臨空を備える関西圏や九州北部、さらに外国人観光客が戻った北海道の主要都市が代表例です。
円安で訪日客が増えると、飲食・小売・宿泊関連の求人が増加します。これらの従業員は職場近くに住む傾向があるため、駅から徒歩10分圏内の1LDK〜2LDKが堅調です。言い換えると、実需が外貨に支えられる地域は家賃相場が下がりにくく、ローン返済の安全余裕が広がります。
一方で、輸入原材料に依存する工場地帯ではコスト高が長期化し、企業の賃上げ余力が限られる可能性があります。その結果、家賃に回せる可処分所得が伸び悩み、賃料引き上げが難しくなるでしょう。円安時代こそ地域産業の構造を調べ、外貨を稼ぐ産業が多いか確認する姿勢が求められます。
立地選定で失敗しない五つの視点
ポイントは、人口動態・雇用・競合供給・交通網・行政施策の五つを順に検証することです。最初に総務省統計局の将来人口推計を見て、今後10年で若年人口が増えるまたは横ばいの市区町村を抽出します。人口が減らなければ長期の賃貸需要を確保しやすく、空室リスクを抑えられます。
次にハローワーク求人統計や地元経済紙で雇用の質を確認します。IT企業や医療・教育関連が増えていれば、賃貸物件でも設備に対する支払い意欲が高く、家賃水準を維持しやすい傾向があります。また、競合となるアパートの完成予定戸数を不動産経済研究所のデータで把握し、供給過多のサインがないかチェックしましょう。
交通アクセスも欠かせません。鉄道の複線化や新駅計画があるエリアは、完成前に物件を取得するとキャピタルゲインを狙えます。一方、路線バス頼みの地域はガソリン価格高騰の影響を受け、利便性が下がる恐れがあります。
最後に行政施策です。2025年度も継続している固定資産税の新築住宅軽減措置は、床面積50〜120平方メートルで3年間税額が半減します。対象条件を満たす木造アパートなら、取得直後のキャッシュフローを大きく改善できる点は見逃せません。
想定外リスクを減らすキャッシュフロー管理
まず押さえておきたいのは、立地が良くても資金繰りが苦しくなると投資は継続できないことです。自己資金は物件価格の25%を目安にし、融資は返済比率が家賃収入の50%以内に収まるよう設計します。日本政策金融公庫の推奨でも、家賃の半分を返済に充てれば、空室率が20%に悪化しても赤字を回避しやすいとされています。
さらに、空室率や修繕費を保守的に見積もったシミュレーションが不可欠です。例えば空室率25%、金利上昇2%を想定し、それでも毎月のキャッシュフローがプラス1万円残るかを確認しましょう。ここでプラスが確保できれば、実際の運営で多少の変動があっても黒字を維持しやすくなります。
実はエネルギーコストの上昇も見逃せません。電気代が上がると共用部の照明や給湯費が増え、管理費が圧迫されます。LED照明への交換や太陽光発電の自家消費など、運営段階でのコスト削減策を早めに組み込むと長期収益が安定します。
最後に、家賃保証や火災保険の内容を定期的に見直すこともリスク低減に直結します。2025年は保険金支払い増に伴い、火災保険料が平均7%上昇しました。複数社を比較し、補償範囲と保険料のバランスを最適化する姿勢が求められます。
まとめ
この記事では、アフターコロナと円安時代という二つの大きな環境変化を踏まえ、アパート経営における立地選定の考え方を解説しました。需要の質の変化を読み、外貨に強い地域を選び、人口動態や雇用動向まで確認することが成功の鍵です。さらに保守的なキャッシュフロー管理と運営コストの削減策を併用すれば、長期にわたり安定収益を期待できます。まずは気になるエリアの統計データを集め、五つの視点で候補地を絞り込む行動から始めてみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅着工統計 – https://www.mlit.go.jp/statistics/
- 総務省統計局 将来人口推計 – https://www.stat.go.jp
- 不動産経済研究所 新築分譲マンション・アパート供給動向 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 日本政策金融公庫 創業・事業計画書モデル – https://www.jfc.go.jp
- 日本銀行 為替相場統計 – https://www.boj.or.jp
- 消防庁 火災保険料動向調査 – https://www.fdma.go.jp

