不動産投資を続けていると「節税になる」「融資が有利だ」といった理由で法人化を勧められる場面が増えます。しかし、実際に会社を設立してから後悔する投資家も少なくありません。本記事では、2025年10月時点の制度と実務を踏まえ、法人化のデメリットを具体的に整理します。個人と法人の違いを理解し、自分に最適な選択肢を見極める手助けとなるはずです。
法人化が急増する背景を正しく捉える
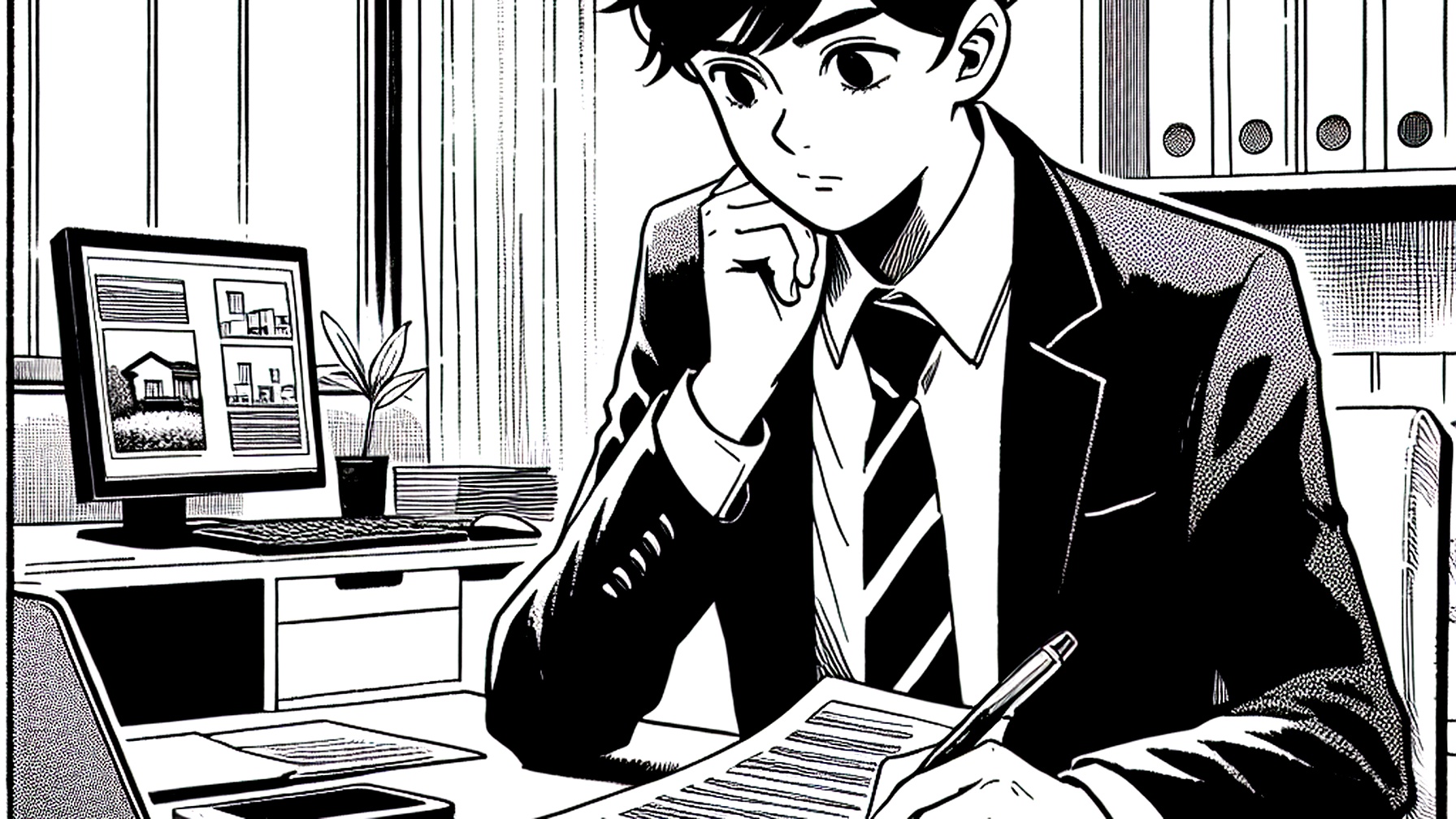
まず押さえておきたいのは、近年の低金利環境と税制改正で法人スキームが広まりやすくなった事情です。個人より低い実効税率や消費税還付が紹介され、インターネット上にはメリットを強調する情報が溢れています。一方で、その影響で法人設立数は総務省統計によると2024年度に過去最高を更新し、競争環境が変化した点を無視できません。
実は、法人化で本当に効果が出るのは課税所得が年間900万円程度を超える層に集中しています。国税庁「令和6年度民間給与実態統計」によれば、個人でここまでの家賃所得に到達する投資家は全体の数パーセントに過ぎません。したがって、法人化を前提に資金計画を組むと、収益規模が追い付かず逆に資金繰りを圧迫するケースが増えています。
さらに、2023年導入のインボイス制度に対応できていない零細法人が相当数存在し、適格請求書発行事業者にならなければ仕入税額控除が受けられません。2025年時点で免税事業者の法人が消費税還付だけを目的に設立しても、税務調査で否認リスクが高い点が見逃されています。
こうした背景を理解しないまま「法人化=得」という単純な図式に飛びつくことが、最大の落とし穴と言えるでしょう。
初期コストとランニングコストが重くのしかかる
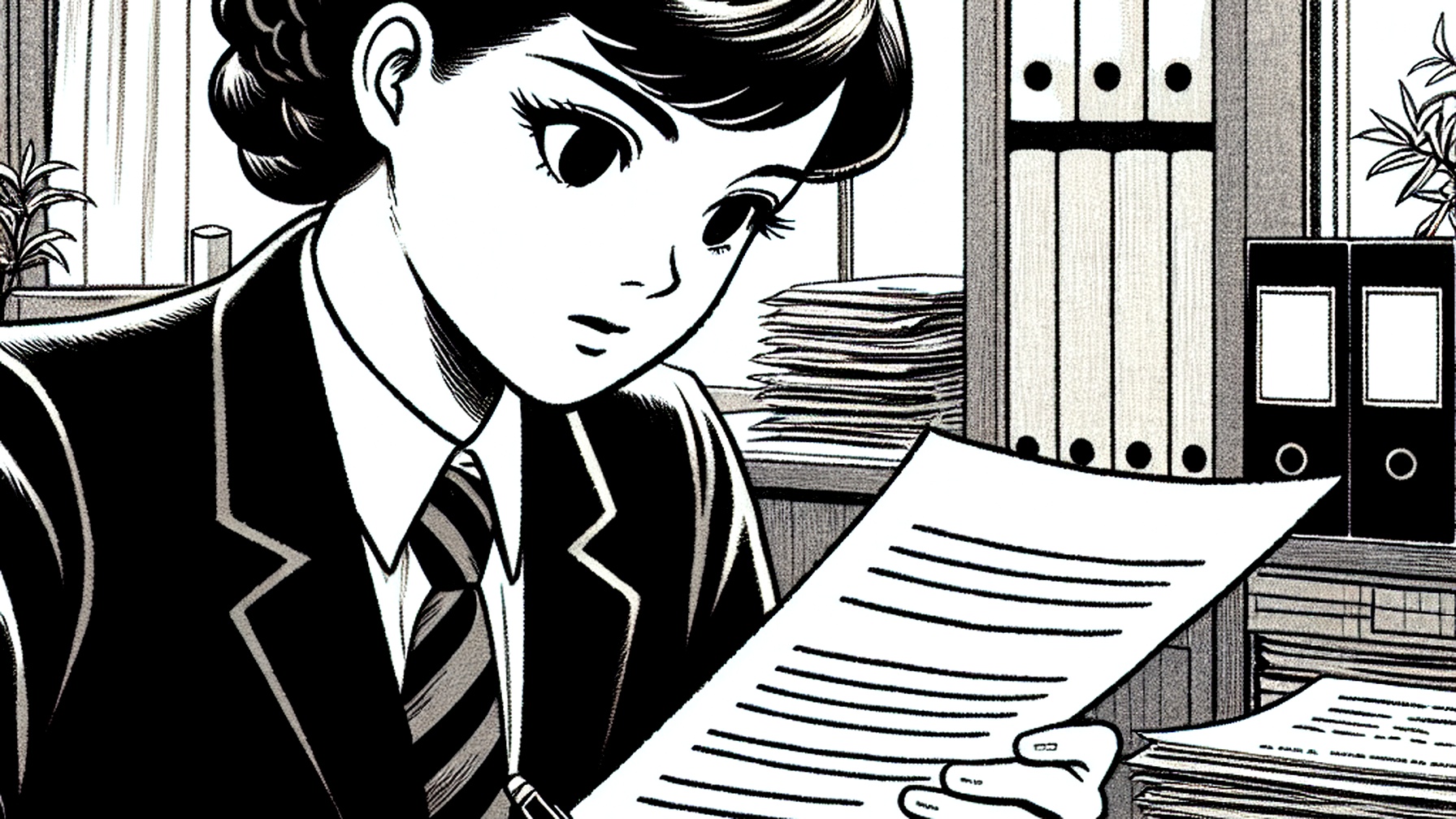
ポイントは、会社を維持するだけで毎年固定費が発生する事実です。設立時には定款認証や登録免許税などで約25万円、司法書士へ依頼するとさらに10万円前後が必要になります。また、資本金を1円で設立可能とはいえ、実務上は金融機関からの信用を得るために300万円以上を入れる例が多く、自己資金を圧迫します。
維持費も軽視できません。税理士報酬は年間30万〜50万円が相場で、事業規模が拡大すれば60万円を超えます。社会保険も代表取締役が加入義務を負うため、年齢や報酬額によっては年間80万円近い負担になる場合があります。この額は空室が続いても発生し、キャッシュフローを直撃します。
さらに、黒字でも赤字でも法人住民税の均等割(2025年度は7万円〜)が毎年課税されます。個人なら実質ゼロで済む赤字期間にも固定費が発生する点が、特に築古物件で減価償却を狙う投資家にとって痛手です。
つまり、「経費計上できるから問題ない」と楽観視していると、手元資金が不足し追加融資の審査も厳しくなる悪循環に陥りやすいのです。
融資と税制で立ちはだかる想定外の壁
重要なのは、法人化したからといって必ずしも融資枠が広がるわけではない点です。2025年現在、多くの地方銀行や信用金庫は代表者個人の連帯保証を前提としており、決算3期分の黒字実績を求めるケースが一般的です。設立直後の法人が提出できるのは資本金と事業計画だけであり、個人より審査が厳しくなることさえあります。
税制面でも落とし穴があります。中小企業向けの軽減税率は所得800万円以下部分が15%(2026年3月期まで延長予定)ですが、それを超えた部分は23.2%になります。一方、個人の所得税は累進課税で最高45%まで上がるものの、青色申告特別控除や損益通算で税負担を圧縮できる余地があります。法人化しても赤字を個人の給与所得と通算できなくなるため、初期の赤字が節税に生かせない点は見逃されがちです。
加えて、法人が保有する不動産の売却益は法人税・住民税の課税対象です。個人なら長期譲渡所得に区分されれば約20%で済むところ、法人税率が適用されることで税負担が高くなる可能性があります。出口戦略まで含めた総合的な試算が欠かせません。
管理とガバナンスの手間が増える現実
まず押さえておきたいのは、法人には法定調書や各種議事録作成など、個人より多い事務義務が課せられる事実です。株主総会議事録を毎年作成し、決算公告を怠ると過料を科せられる恐れがあります。不動産投資に集中したいと考えていたはずが、書類作成に追われることになるのです。
また、登記情報は誰でも閲覧できるため、代表者の住所や氏名が半永久的に公開されます。賃借人や取引先とトラブルが起きた際、個人情報が悪用されるリスクがある点も見逃せません。個人名義なら公開範囲が限定的で精神的な負担が小さく済みます。
取締役会設置会社にすると社内ガバナンスが複雑化し、親族間の意見対立が表面化することもあります。議事録の不備が税務調査で指摘されると、形式的な問題でも追徴課税に発展する場合があるため、専門家のサポートが欠かせません。結果として、外部専門家費用が再び膨らむ悪循環に繋がります。
このように、「法人=自由度が高い」というイメージとは裏腹に、実務上は管理コストとリスクが確実に上昇します。
相続・出口戦略で生じる盲点
実は、法人化すると相続対策が難しくなるケースがあります。不動産が法人名義になると、相続時に株式評価で承継する形になりますが、評価の算定に純資産価額方式が用いられると含み益まで課税対象になるため、相続税負担が増えることがあります。個人所有なら小規模宅地特例や貸家建付地の評価減が使える場合でも、法人所有では適用されません。
加えて、将来物件を売却し法人を清算したい場合、清算所得にも法人税が課税されます。個人なら譲渡益課税のみで済むところ、法人では二重課税に近い状態になり、手取額が大幅に減少する点が見逃せません。特に築古アパートを減価償却で早期に簿価ゼロにし、その後高値売却を想定している投資家は要注意です。
出口戦略が未定のまま法人を設立すると、株式売却や事業承継の選択肢も限られます。家族に不動産投資の意思やスキルがなければ、株式を引き継いでも運営が立ち行かず、最終的には物件を叩き売るリスクが高まります。法人化は長期的なビジョンと後継者育成がセットでなければ、逆効果になりかねません。
まとめ
結論として、法人化には確かなメリットがある一方、初期費用・固定費・事務負担・税務リスクなど見過ごされがちなデメリットが数多く存在します。まずは個人名義で十分なキャッシュフローと融資実績を積み、課税所得が安定して高くなった段階で法人化を検討する方が安全です。具体的なシミュレーションを税理士と行い、出口戦略まで含めた長期計画を立ててから決断しましょう。目先の節税効果だけに惑わされず、総合的な視点で不動産投資を進めることが、将来の後悔を防ぐ最善策になります。
参考文献・出典
- 国税庁「法人税率等」 – https://www.nta.go.jp
- 財務省「令和6年度税制改正のポイント」 – https://www.mof.go.jp
- 総務省「経済センサス-活動調査 2024年速報」 – https://www.stat.go.jp
- 厚生労働省「協会けんぽ 保険料率一覧(2025年度)」 – https://www.kyoukaikenpo.or.jp
- 中小企業庁「小規模企業白書2025」 – https://www.chusho.meti.go.jp

