投資用マンションの広告で「利回り10%」という文字を見ると、思わず心が躍るものです。しかし実際に手元に残るお金は、数字ほど単純ではありません。管理費や修繕費、さらに税金まで差し引くと、想像していた利益と現実にギャップが生じるケースが少なくないからです。本記事では「不動産投資 どれくらい儲かる」という疑問に向き合い、収益構造や費用、2025年時点の制度まで丁寧に解説します。読み終えるころには、自分の資金計画に合わせたリターンの目安をつかめるでしょう。
投資収益の仕組みをまず押さえよう
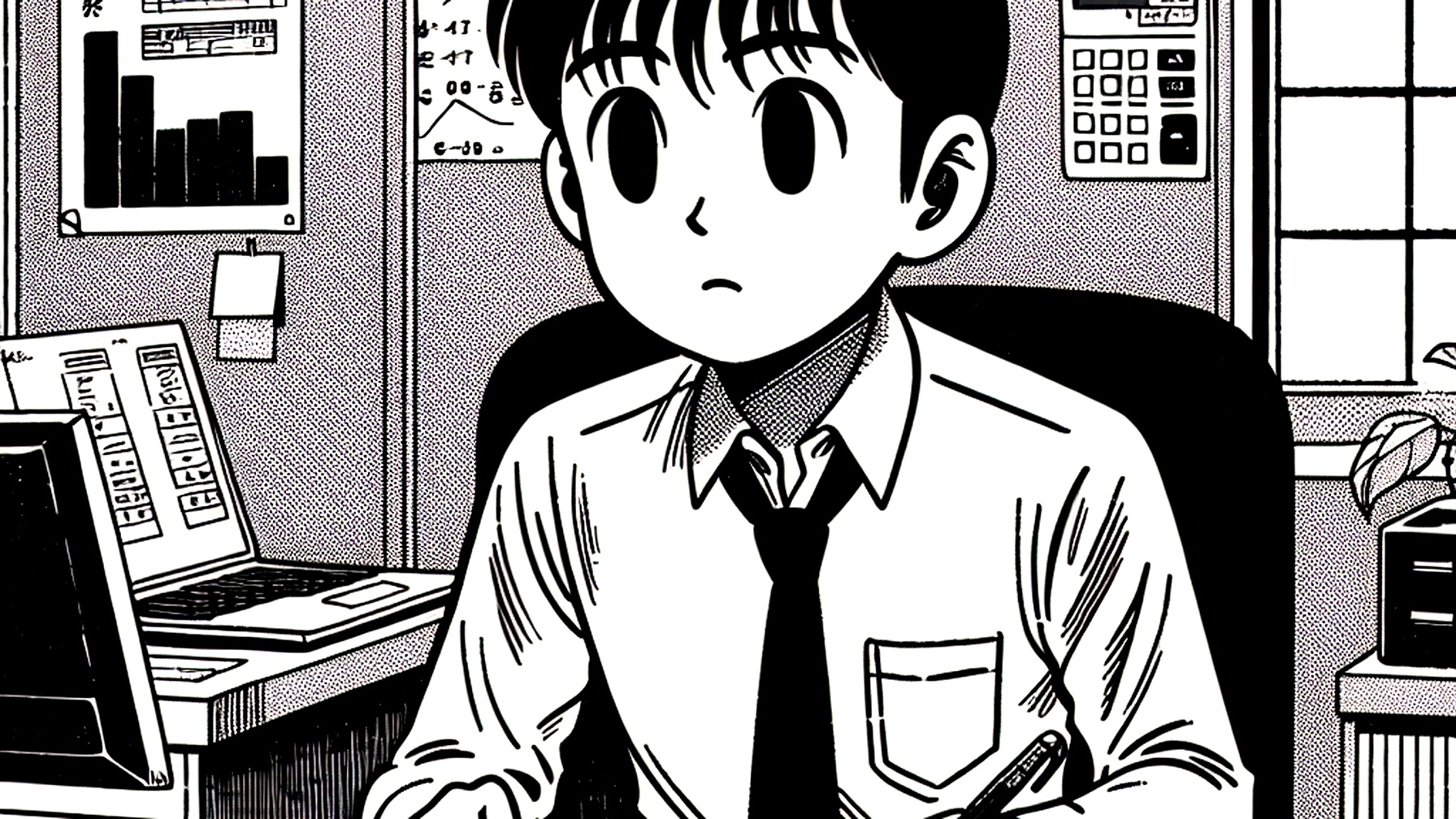
重要なのは、家賃収入がそのまま利益になるわけではない点を理解することです。不動産投資の実際の儲けは「キャッシュフロー」と呼ばれ、家賃から諸費用を引いた残りこそが本当の収益です。また、長期保有中の資産価値の変動が、最終的な売却益に影響を与えます。つまりインカムゲイン(賃料収入)とキャピタルゲイン(売却益)の両面をバランス良く見る必要があります。
まず家賃から差し引かれるのは、管理委託料や共用部の修繕積立金が代表例です。国土交通省の「賃貸住宅市場調査」によると、都心ワンルームの平均管理費は月額5千円前後です。さらに固定資産税が年額10〜15万円発生し、火災保険も2年で2万円程度かかります。加えて、築10年を超えるとエアコン交換など小修繕が年数万円単位で発生するため、家賃の約25〜30%は維持費に消える計算です。
一方で、物件価格にはローン金利が上乗せされます。2025年10月時点の主要銀行の投資用ローン固定金利は年1.9〜3.2%が中心です。3千万円を2.5%固定・30年で借りた場合、月々の返済は約12万円になり、返済比率が家賃収入の60%を超えるとキャッシュフローが圧迫されます。このように、家賃単価とローン条件の組み合わせが利益を大きく左右します。
キャッシュフローと利回りのリアル
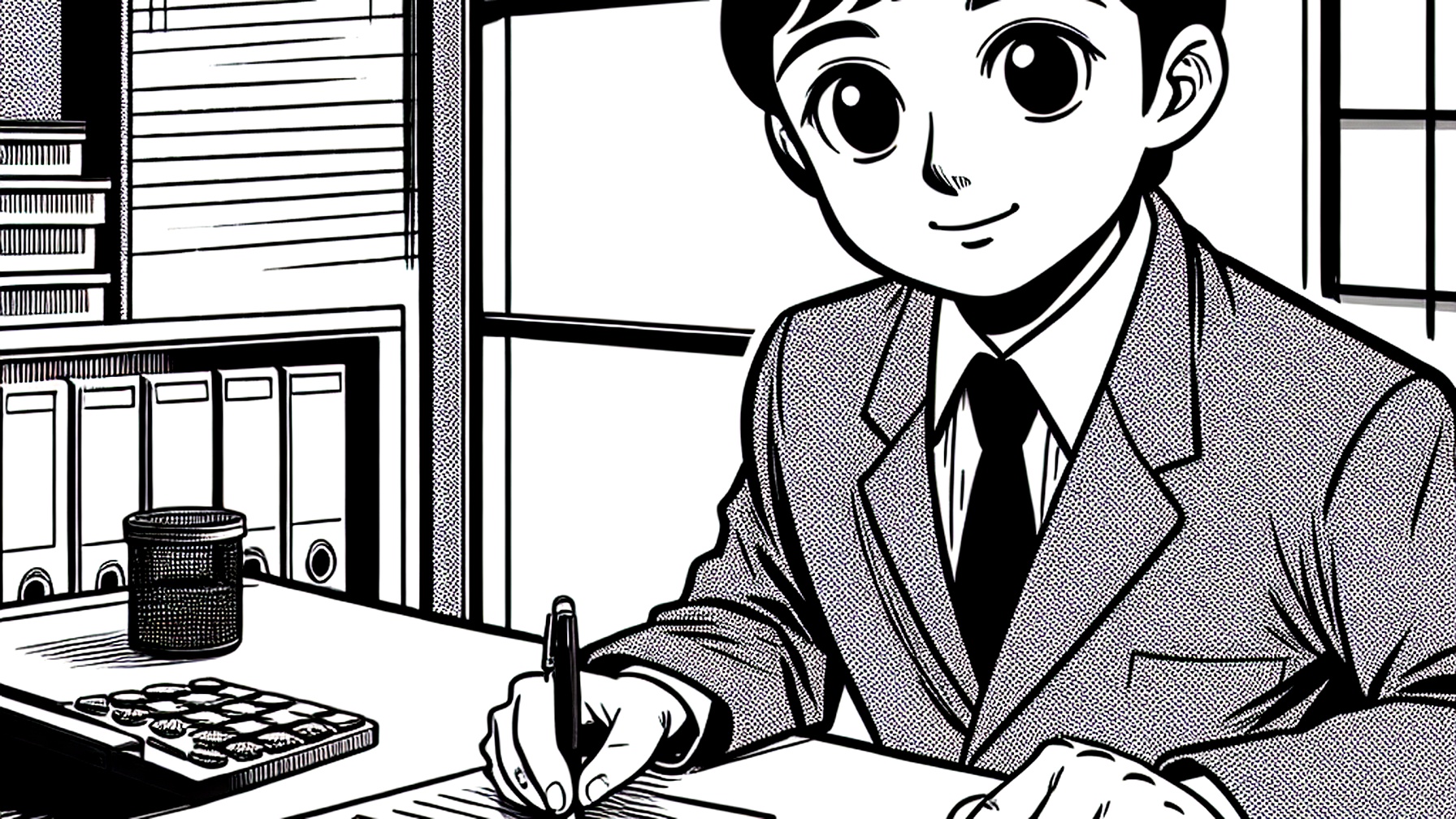
ポイントは、表面利回りと実質利回りを区別することです。表面利回りは家賃総額を購入価格で割るだけなので、手残りを正確に示しません。実質利回りは諸費用を控除した後の純家賃で計算するため、キャッシュフローに近い指標となります。
実は東京都心の区分マンションで、平均表面利回りは4〜5%にとどまります。家賃10万円の物件を3千万円で購入すると、表面利回りは4%です。ここから管理費1万円、修繕積立金5千円、空室率5%、固定資産税月割り1万円を差し引くと、実質利回りは約2%まで低下します。手残りは月5千円強に過ぎず、年間6万円しか残りません。
一方、札幌や福岡の築浅アパートでは表面利回り7〜8%が狙えます。仮に総戸数4戸、家賃合計28万円、物件価格4千万円なら表面7%です。地方は管理費率が低く、固定資産税も抑えられるため、実質利回り4%台を実現するケースがあります。ただし人口減少リスクや将来の賃料下落を見込む必要があり、収益の安定性は都心より劣る点に注意が必要です。
総務省「住宅・土地統計調査」2023年速報によれば、全国平均空室率は13.6%です。都心ワンルームでは9%前後、地方郊外では20%を超える地域もあります。空室が1カ月でも発生すると、利回りは簡単に1ポイント以上下がるため、保守的なシミュレーションを欠かせません。
初心者が押さえるべきコストとリスク
まず押さえておきたいのは購入時点の初期費用です。仲介手数料、登記費用、ローン事務手数料、火災保険などを合計すると、物件価格の7〜9%が目安になります。3千万円の物件では諸費用が200万円を超えることも珍しくなく、自己資金を準備しておかないと融資実行が遅れる可能性があります。
さらに、築後15年を過ぎると外壁塗装や屋上防水といった大規模修繕の負担が増します。国交省の「マンション大規模修繕実態調査」2024年版では、専有面積30㎡あたりの平均負担額が約90万円と示されています。この費用を積み立てていないと、臨時徴収でキャッシュフローが一気にマイナスになる恐れがあります。
リスク面では、地震や水害による資産価値の毀損が挙げられます。2025年に改訂されたハザードマップは、従来よりも詳細に洪水・土砂災害リスクを表示しています。購入前に役所でリスクを確認し、保険でカバーできない部分は投資対象から外す判断が賢明です。こうしたリスクを洗い出し、管理計画に組み込むことで、収益のブレを最小限に抑えられます。
2025年時点の税制優遇と融資環境
実は、税制を味方につけることでキャッシュフローは大きく改善します。2025年度の所得税法では、不動産所得の赤字を給与所得と通算する損益通算制度が続いています。減価償却費を適切に計上すれば、課税所得を圧縮できるため、実質的な税引き後利回りが向上します。ただし赤字が過大だと税務調査の対象になりやすく、耐用年数を無視した計上は禁物です。
また、危険負担軽減を目的とした「住宅ローン減税」は自宅向け制度であり、投資用は対象外です。一方、2025年度の登録免許税軽減措置は、一定の中古住宅取得時に適用されるため、所有権移転登記の税率が0.3%から0.2%に下がります。適用期限は2027年3月末までと定められているため、スケジュール管理が重要になります。
融資環境を見ると、日本政策金融公庫の創業融資枠を活用したアパートローンが注目されています。自己資金1割でも融資が受けられるケースがあり、金利は1.0〜1.5%と民間より低めです。ただし、賃貸経営計画書や3年分の収支予測が必須となり、空室率や修繕計画が甘いと審査に通りません。民間金融機関では、自己資金2割以上を条件に金利1.9%で30年固定という商品が主流で、借入期間は築年数と合わせて法定耐用年数以内に制限される点も押さえましょう。
成功事例に学ぶ収益最大化の戦略
ポイントは、データに基づいたエリア選定とシナリオ別シミュレーションです。たとえば30代会社員Aさんは、東京23区内で築8年・駅徒歩6分のワンルームを3千万円で購入しました。家賃は10.5万円、実質利回り2.2%と低めでしたが、融資金利1.8%固定でキャッシュフローは月7千円を確保できました。将来の値上がりを見込み、5年後に3,300万円で売却したため、キャピタルゲインも併せて年平均利回り6%を達成しました。
一方、地方政令市で築浅アパートを一棟購入した40代Bさんは、表面利回り7.5%、実質利回り4.5%を狙える計画を立てました。購入後に近隣に新築アパートが急増し、家賃が想定より1割下落しましたが、サブリース契約ではなく自主管理を選択していたため、入居者ニーズに合わせたリフォームで空室を最小限に抑えられました。結果としてキャッシュフローは月8万円を維持し、年間キャッシュリターンは自己資金500万円に対して18%に到達しています。
共通しているのは、購入前に最低3通りのシナリオを試算していた点です。金利上昇、空室率上昇、家賃下落を組み合わせ、最も厳しい条件でも赤字にならないことを確認しています。また、出口戦略として売却価格を複数の不動産会社に査定依頼し、想定キャピタルゲインを保守的に見積もることで、リスクを限定しました。こうした準備こそが、実際の儲けを最大化する鍵と言えるでしょう。
まとめ
本記事では、「不動産投資 どれくらい儲かる」という疑問に対し、キャッシュフローの基本から税制、具体的な成功事例まで幅広く解説しました。家賃収入だけに目を奪われると、管理費や空室リスクで手残りが減る現実を見落としがちです。重要なのは、表面利回りと実質利回りを正確に計算し、税制や融資条件を踏まえたキャッシュフローを把握することです。さらに、複数のシナリオで収支を検証し、出口戦略まで組み込めば、長期的に安定した利益が期待できます。まずは自身の資金力とリスク許容度を整理し、数字と向き合うところから一歩を踏み出してみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産価格指数(2025年7月公表) – https://www.mlit.go.jp
- 国土交通省 賃貸住宅市場調査(2024年度版) – https://www.mlit.go.jp
- 国土交通省 マンション大規模修繕実態調査(2024年) – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 住宅・土地統計調査 2023速報 – https://www.stat.go.jp
- 日本政策金融公庫 融資資料(2025年4月更新) – https://www.jfc.go.jp

