不動産市場に興味はあるものの、まとまった資金や管理の手間が不安で一歩を踏み出せない人は多いものです。そんな悩みを解決する選択肢としてREIT(不動産投資信託)が注目されていますが、実はメリットばかりではありません。本記事では「REIT デメリット 投資家」という視点から、仕組みやリスク、2025年度の最新税制までをやさしく整理します。初心者でも読み終えた瞬間に、自分に向いているか判断できる内容になっていますので、最後までお付き合いください。
REITの基本構造と魅力を押さえる
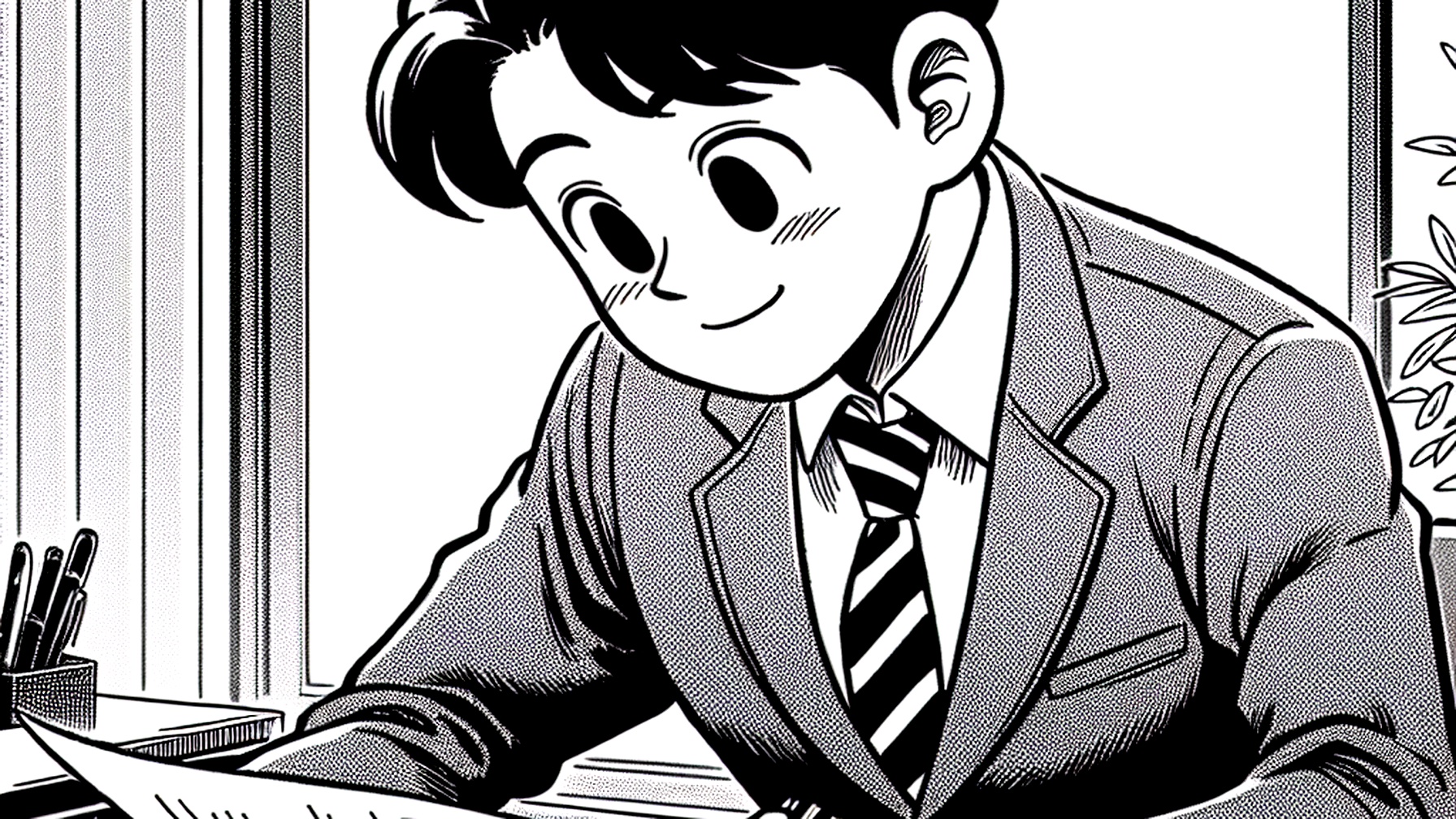
まず押さえておきたいのは、REITが大勢の投資家から集めた資金で複数の不動産を保有し、その賃料や売却益を分配する仕組みです。株式のように証券取引所で売買できるため、現物不動産と比べて流動性が高く、少額から参加できる点が魅力です。
国内REITの平均投資単位は10万円前後で、個人投資家でも手軽に分散投資が可能です。また、2025年10月時点での東証REIT指数は前年同月比で約7%上昇しており、長期的に安定した配当利回りを示しています。つまり、年4〜6%の分配金を狙いつつ値上がり益も期待できるのが一般的なイメージです。
しかし、流動性が高いからといってリスクが消えるわけではありません。価格は日々変動し、分配金も業績しだいで減る可能性があります。次のセクションでは、代表的なデメリットを具体的に見ていきます。
覚えておきたい三つの主要デメリット
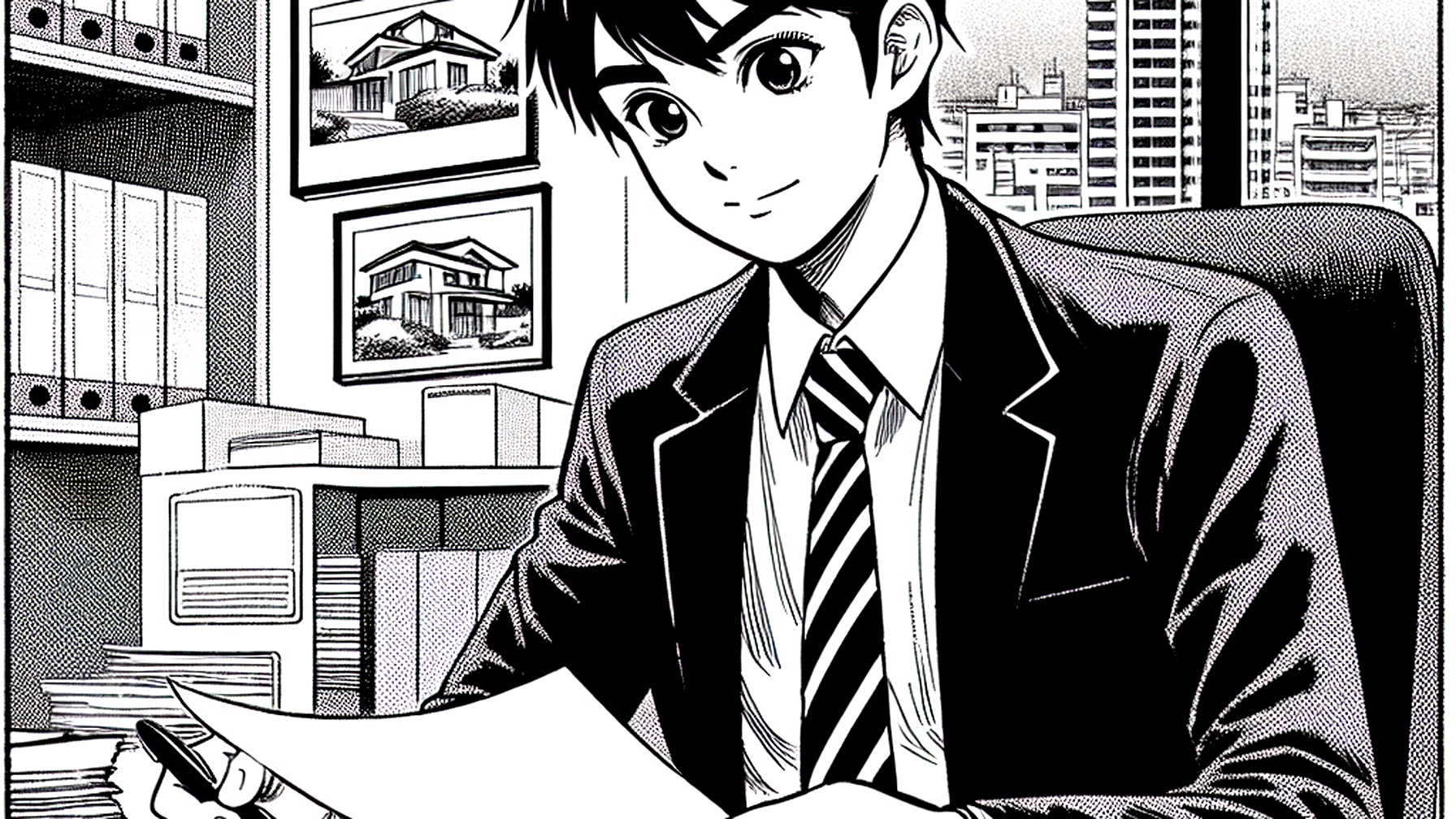
重要なのは、REIT特有の市場リスクを正しく理解することです。第一に、市場価格の変動リスクがあります。REITは上場株と同様に投資家心理や金利動向で値動きし、短期的に10%以上の下落も珍しくありません。特に2023年の金利上昇局面では、一部銘柄が半年で15%超値下がりしました。
次に、金利リスクです。REITの運用会社は物件取得に借入金を使うため、政策金利が上がると支払利息も増えます。日本銀行が2025年6月に長期金利上限を1.5%へ引き上げた際、借入比率が高い物流系REITの分配金予想が平均5%減少しました。言い換えると、金利上昇は配当に直接響く要素です。
最後に、物件集中リスクがあります。特定エリアや用途に偏ったポートフォリオのREITは、災害や需要変化で収益が急落する可能性があります。2024年の能登半島地震では、北陸地方にホテルを多く持つ銘柄の稼働率が一時20%台に落ち込みました。つまり、分散されているとはいえ銘柄選定を誤ると想定外の打撃を受けるのです。
リスク管理の実践ポイント
ポイントは、投資前に個別銘柄の財務と物件構成を細かく確認することです。借入比率(LTV)が50%を超える銘柄は金利上昇に弱くなります。2025年10月時点で東証に上場する64銘柄の平均LTVは42%ですが、差が大きいので要注意です。
また、用途別・地域別の分散状況も重要です。例えば、オフィス比率が70%を超えるREITはテナントの賃料交渉力が強まる景気後退局面で分配金が落ち込みやすくなります。物流、住宅、ヘルスケアなど複数用途に広がる銘柄を組み合わせると、一つのセクター不況の影響を和らげられます。
配当利回りが高すぎる銘柄にも注意が必要です。利回り8%超は一見魅力的ですが、修繕積立不足や含み損の先送りが原因の場合があります。運用報告書のキャッシュフローステートメントを確認し、設備投資(CapEx)が安定して行われているかをチェックしましょう。こうした地道な分析が、REIT デメリット 投資家のリスクを小さくする近道です。
REITと現物不動産投資の比較で見える真価
実は、REITの弱点は現物投資の強みでもあります。現物不動産は自分で賃料設定や修繕計画を決められるため、コントロール性が高い一方、流動性が低く初期費用も大きいです。国土交通省の2024年不動産投資実態調査によると、都心ワンルームの平均取得価格は約2,800万円で、諸費用を含めた自己資金は600万円前後必要でした。
一方でREITは数万円単位から購入できますが、価格決定権はなく、市況が悪化しても保有中にテコ入れできません。また、個別不動産なら借入金利を固定化するなど対策が可能ですが、REITでは運用会社の判断に委ねるしかない点が制約となります。つまり、資金や時間をどこまで投入できるかで適切な手法が変わるというわけです。
投資効率を比較する場合、REITの分配利回りが4%、現物のネット利回りが6%なら単純な差は2ポイントですが、管理コストや空室リスクを加味すると実質的な差は縮まります。さらに、REITは配当控除の対象外のため税負担が高くなる場合があることも見逃せません。
2025年度税制と手数料の最新注意点
まず押さえておきたいのは、分配金が20.315%の申告分離課税で源泉徴収される点です。2025年度もこの税率は維持される見込みで、NISA口座を使えば年240万円まで非課税投資が可能です。ただし、NISAでは損益通算ができないため、値下がりリスクとのバランスが課題になります。
さらに、売買手数料は証券会社によって差があります。ネット証券大手の平均は取引額10万円で99円程度ですが、REITは売買単価が高くなるため手数料率を事前に確認しましょう。特に分配金再投資を頻繁に行う場合、手数料がリターンを圧迫します。
2025年度に新設された「高齢者住宅REIT控除」は、一定の介護施設を組み込んだREITへの投資額のうち5%が所得控除対象となります。ただし、適用期限は2027年末までで、対象銘柄は国交省と財務省が認可したファンドに限られます。制度利用の前に、対象銘柄が限定的である点を理解しておくことが大切です。
まとめ
REITは少額から不動産に分散投資できる便利な商品ですが、市場価格の変動、金利上昇、物件集中など独自のリスクを抱えています。運用報告書を読み込み、LTVや用途分散を確認する習慣が身を守る鍵となります。また、現物不動産との違いを理解し、自己資金や時間の制約に合わせて手法を選ぶ視点も欠かせません。この記事を参考に、自分の投資目的に沿ったREIT戦略を練り、実践的な資産形成へ一歩踏み出してみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産投資実態調査報告書2024 – https://www.mlit.go.jp/
- 日本取引所グループ 東証REIT指数月報2025年9月 – https://www.jpx.co.jp/
- 財務省 2025年度税制改正大綱 – https://www.mof.go.jp/
- 日本銀行 金融政策決定会合議事要旨2025年6月 – https://www.boj.or.jp/
- 一般社団法人投資信託協会 REITデータブック2025 – https://www.toushin.or.jp/

