多額の相続税をどう減らすか、家族に迷惑を掛けず資産を次世代へ渡せるか――こうした悩みは年々深刻さを増しています。現金のままでは評価額がそのまま課税対象になりますが、形を変えることで税負担を軽くできる場合があります。実は、少額から参加できる「不動産クラウドファンディング」を活用すると、従来の賃貸経営よりも手間を抑えつつ相続対策を図れる可能性があります。本記事では、その魅力と注意点を具体的に解説し、「相続対策 不動産クラウドファンディング 始め方」の全体像をわかりやすくお伝えします。
なぜ相続対策にクラウドファンディングを活用するのか
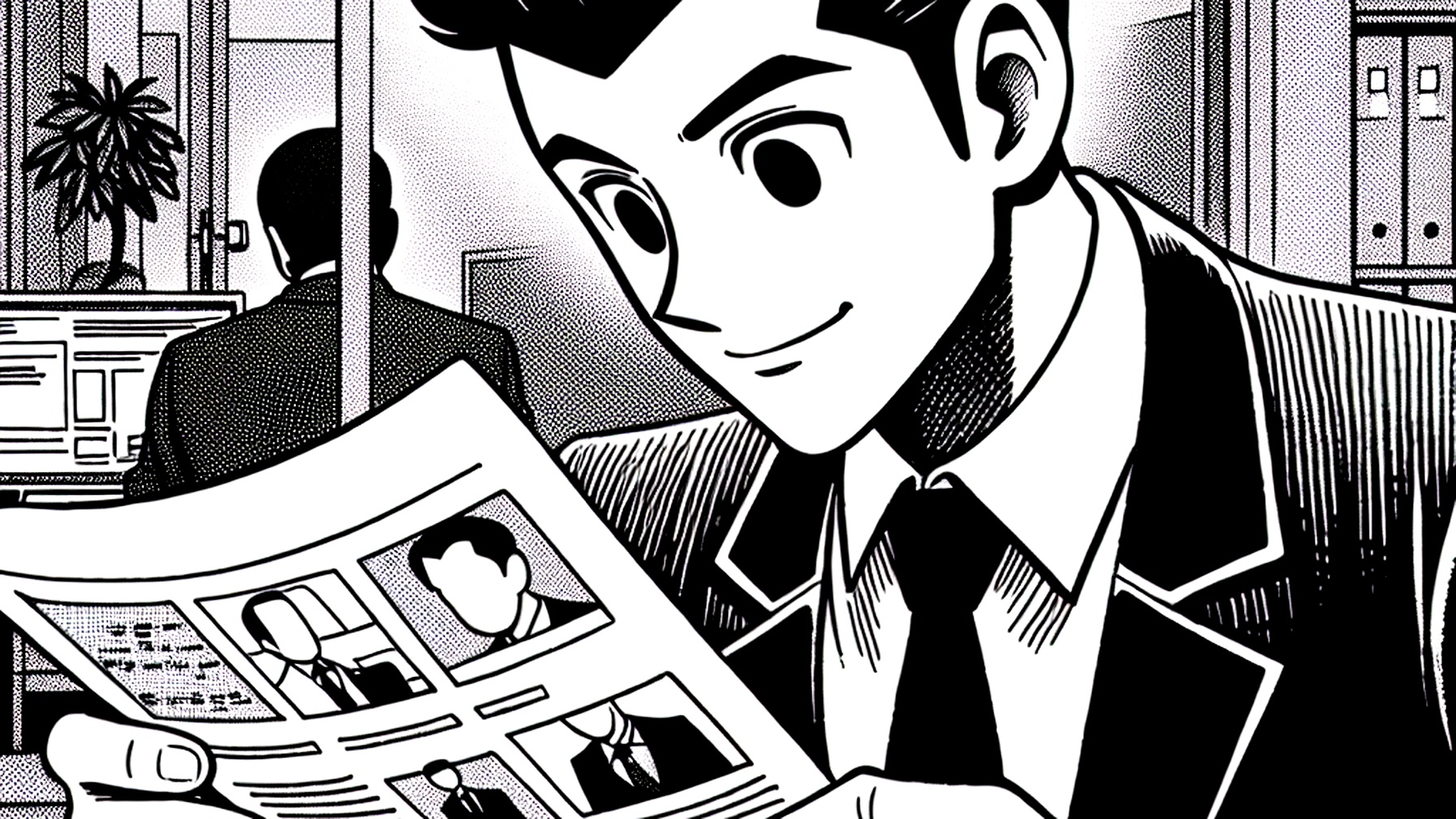
重要なのは、不動産に換えることで相続評価額を圧縮し、現金よりも税負担を抑えやすくする仕組みです。不動産クラウドファンディングでは、一口1万円程度から物件の所有権に準じる持分を取得できるため、大規模な借入を抱えなくても評価減の恩恵を受ける余地があります。
国税庁の「相続税の申告事績」(2024事務年度)によると、現金・預金の課税割合は依然として全体資産の34%を占めています。現金をそのまま保有すると額面が評価額になる一方、不動産は路線価や固定資産税評価額を基準とするため、時価より2〜3割低く見積もられるケースが一般的です。クラウドファンディングを通じて取得した持分も同様の評価方法が適用されるため、結果的に直接物件を購入した場合と近い効果が期待できます。
さらに、運用期間中の配当が「雑所得」に区分され、相続開始前に所得分散が行える点も見逃せません。所得税率が高い世代から低い世代へ資金を移す形になれば、トータルの税負担を下げられる可能性があります。ただし、この戦略が有効かどうかは個別の所得状況に左右されるため、後述する専門家への相談が欠かせません。
不動産クラウドファンディングの基本仕組み
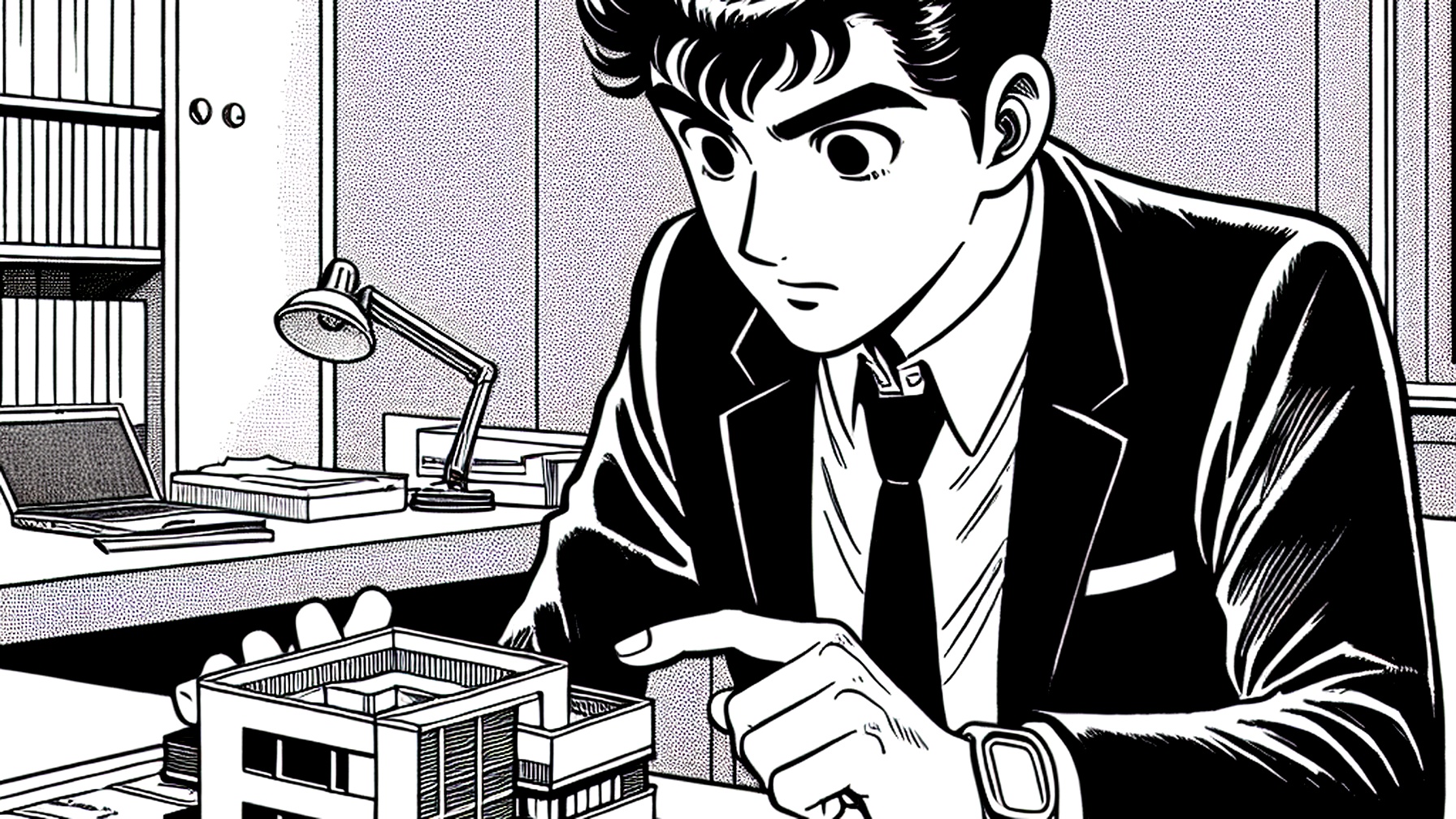
まず押さえておきたいのは、クラウドファンディング事業者が不動産特定共同事業法にもとづき物件を取得・運営し、投資家は匿名組合または任意組合契約を通じて出資する構造です。物件の管理は事業者が行うため、オーナーとしての煩雑な業務やテナント対応は発生しません。
投資家が得るリターンは、大きく分けて運用期間中の分配金と売却益の二つです。分配金は賃料収入から諸経費を差し引いたキャッシュフローが原資となり、年2〜4%程度の利回りを設定するファンドが多い傾向にあります。また、運用終了時に物件を売却して利益が出た場合、その一部が成果配当として加算される仕組みです。J-REITに似ていますが、個別物件を限定的に扱うため、物件特性を自分で選びやすい点が特徴と言えます。
一方で、途中解約が原則としてできない点は注意が必要です。流動性リスクを補うため、運用期間は3年以内に設定されるファンドが増えており、NRIの調査(2025年3月)では全体の62%が「2〜3年」で募集されています。運用期間と資金需要のタイミングを見極めた上で参加することが、安全運用の前提になります。
始める前に押さえる税務と法的ポイント
ポイントは、相続税評価と所得区分の二つを理解し、想定外の課税を防ぐことです。相続時には、保有中のクラウドファンディング持分が「不動産の共有持分」とみなされる場合と、「営業権類似の権利」とみなされる場合に分かれます。前者なら路線価に基づく評価、後者なら出資額評価が基本となり、事業者の契約形態によって取り扱いが変わります。
2025年度税制では、小規模宅地等の特例や相続時精算課税制度が引き続き適用可能ですが、クラウドファンディングの持分は「貸付事業用宅地」に該当しないことが一般的です。そのため、特例で80%評価減が受けられる賃貸アパートと比べると、評価減率は控えめになる点を理解しておきましょう。しかし、300万円前後の少額投資で評価額を抑えられるという手軽さが強みです。
贈与を活用するときは、2024年に導入された「相続時精算課税の150万円基礎控除」が2025年も継続しているため、年間150万円まで非課税で移転し、超過部分を一律20%で納税する方法が有効です。この枠内でクラウドファンディング持分を贈与し、子や孫へ資産をスライドさせる手順が、年間計画として組み込みやすいでしょう。
また、不動産特定共同事業法では、第二号事業(契約金総額1億円超ファンド)の場合、適格特例投資家限定型に該当することがあります。適格特例投資家は、総資産3億円以上など厳しい条件を満たす必要があるため、一般投資家向けファンドを選ぶのが現実的です。事業者の登録番号と業務管理体制を必ずチェックし、金融庁の「クラウドファンディングモニタリングリスト」で確認する習慣を付けましょう。
口座開設から投資までのステップ
まず、事業者の会員登録を行い、オンラインで本人確認を済ませます。マイナンバーカードと顔写真付きIDによるeKYC(オンライン本人確認)が主流で、最短翌営業日に口座が開設されます。登録完了後、募集案件の詳細情報(所在地、鑑定評価書、賃料想定、リスク要因)を読み込み、想定利回りだけでなく出口戦略を見極めることが欠かせません。
実際の入金は、ファンドごとに指定された期日までに振り込む形です。投資金額は1口1万円が平均的ですが、最低募集金額に達しなければ不成立となり、全額返金されます。成立後は運用開始日から分配基準日までの期間に応じて分配金が計算され、四半期または半年ごとに指定口座へ振り込まれる流れです。
途中で資金が必要になった場合、セカンダリーマーケットを提供する事業者なら売却の機会があります。日本クラウド不動産協会のレポート(2025年4月)では、セカンダリー対応ファンドが全体の28%に増えたと公表されており、流動性は徐々に改善しています。ただし、買い手が付かないリスクや手数料が3〜5%かかる点を考慮し、余裕資金で投資する姿勢が基本です。
ファンド償還後は、元本と売却利益が戻り、確定申告で雑所得として計上します。所得税と住民税が合わせて最大55%になる高所得者は、分配金に対する源泉徴収(20.42%)で足りない場合があるため、税理士と相談し不足分を納税しましょう。逆に、給与所得控除後の課税所得が330万円以下なら、追加納税が発生しないケースが多く、相続対策と同時に所得分散の効果も実現できます。
2025年度の優遇制度と注意点
実は、2025年度は不動産クラウドファンディングそのものに直接適用される補助金や税額控除制度はありません。しかし、投資対象物件が「長期優良住宅」や「ZEB Ready」(ゼロエネルギービル)に該当する場合、事業者サイドで固定資産税の減額や登録免許税の軽減を受けられるため、結果として投資家利回りが底上げされる可能性があります。募集要項に記載があれば、その恩恵が分配金にどう反映されるかを確認しましょう。
一方で、2024年に続き「金融サービス仲介業法」による届出制が強化され、無登録業者の排除が進んでいます。金融庁の警告事例では、実在しない海外物件を名目に高利回りを謳うケースが散見されるため、公式サイトの登録番号と「第二種金融商品取引業」または「不動産特定共同事業」の表示を必ず確認してください。
海外居住者が日本国内のクラウドファンディングに出資する場合、租税条約に基づき利子配当課税が10%に軽減される国もあります。ただし、相続税については「全世界課税」が原則であり、日本国籍を持つ被相続人の場合、海外在住のままでも課税対象になる点は変わりません。国境を越える資産移転を想定する際は、国際税務に詳しい専門家が必要です。
まとめ
相続対策として不動産クラウドファンディングを活用する最大のメリットは、少額から不動産評価減の効果を得られ、運用の手間を事業者に任せられる点です。評価方法や税区分を正しく理解し、2025年度の制度枠内で贈与や所得分散を組み合わせれば、家族全体で税負担を抑えつつ資産の世代交代をスムーズに進められます。まずは信頼できる事業者を選び、余裕資金でテスト投資を行いながら経験値を積むことが、長期的な資産防衛への第一歩となるでしょう。
参考文献・出典
- 国税庁「令和5事務年度 相続税の申告事績」 – https://www.nta.go.jp
- 日本総合研究所「不動産クラウドファンディング市場動向調査 2025年版」 – https://www.jri.co.jp
- 金融庁「クラウドファンディングモニタリングリスト」 – https://www.fsa.go.jp
- 日本クラウド不動産協会「セカンダリー市場レポート2025」 – https://www.jcria.or.jp
- 国土交通省「不動産特定共同事業ガイドライン(2025年度版)」 – https://www.mlit.go.jp

