不動産投資を始めたいけれど「築古物件は本当に稼げるのか」「金融機関はどこまで融資してくれるのか」と悩む人は多いはずです。さらに2024年に大改正された新NISAの活用法も気になるところでしょう。本記事では、築古の収益物件に焦点を当て、融資条件をクリアする具体策から新NISAを絡めた資金戦略まで、初心者でも理解できるよう順を追って解説します。読み終えるころには、物件選びから資金調達、ポートフォリオの組み立て方まで、今日から行動に移せるヒントが得られるはずです。
築古収益物件の基本とメリット
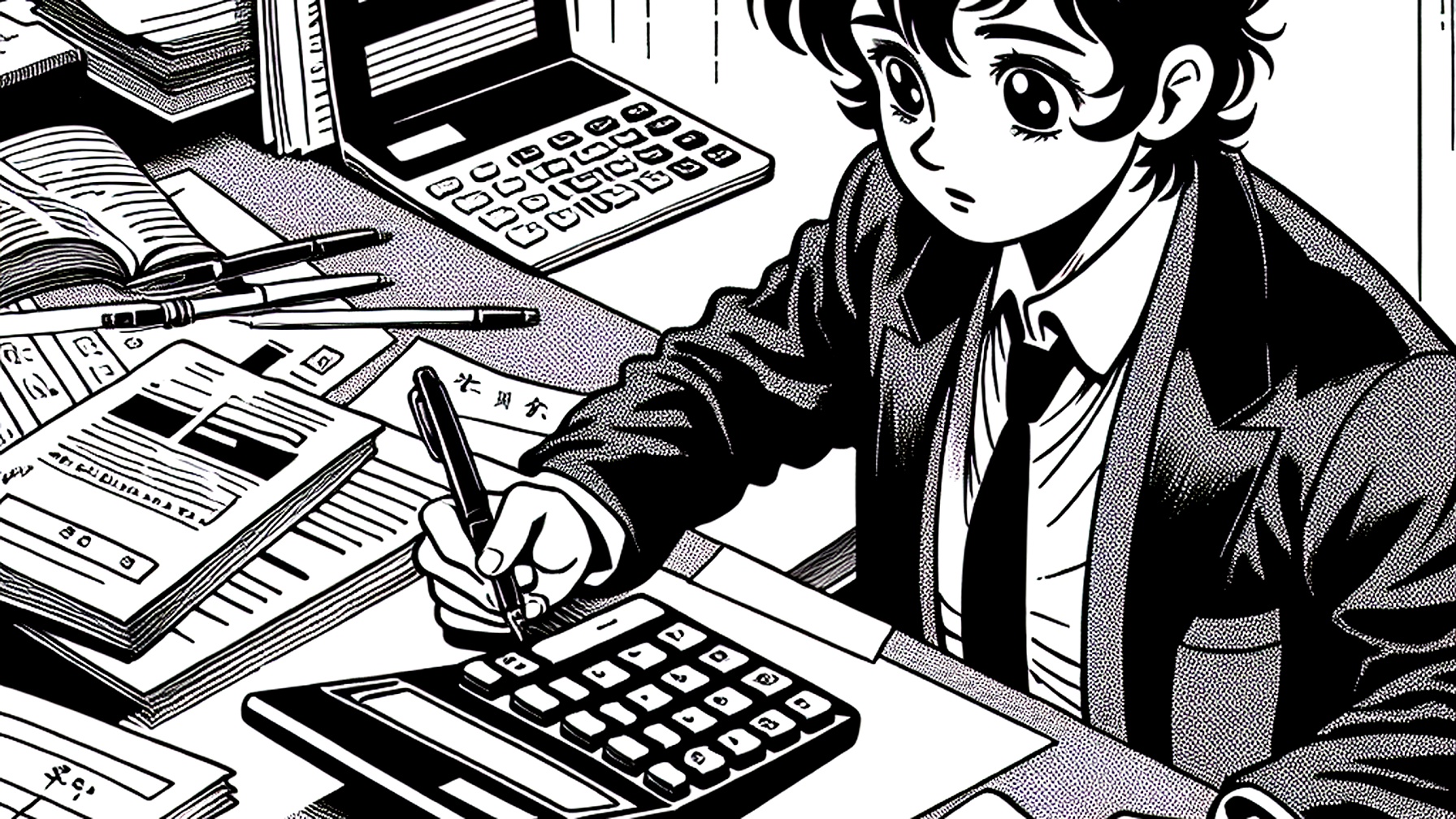
重要なのは、築古物件と聞いて即座に「リスクが高い」と決めつけないことです。確かに設備は古く修繕費がかかりますが、取得価格が抑えられるため利回りが高いケースが多く、運営次第ではキャッシュフローを厚くできます。また、国土交通省の不動産価格指数(2025年8月速報)によると、築後30年以上の木造アパート価格は横ばいで推移しており、価格変動リスクが比較的小さい点も魅力です。
次に、人口動態が安定しているエリアを選べば空室リスクを減らせます。例えば総務省の2025年住民基本台帳統計では、地方でも大学や工業団地を抱える市区は微増傾向が確認されています。築古でも立地さえ押さえれば、新築より高い入居ニーズを得ることも珍しくありません。
一方で、設備更新や外壁改修などの突発費用は避けて通れません。だからこそ購入前に長期修繕計画を作り、家賃収入の一部を毎月積み立てる体制が欠かせません。つまり築古物件は「安く買って計画的に直す」ことで、少額からでも高収益を狙える選択肢になるのです。
融資条件を左右する三つの視点
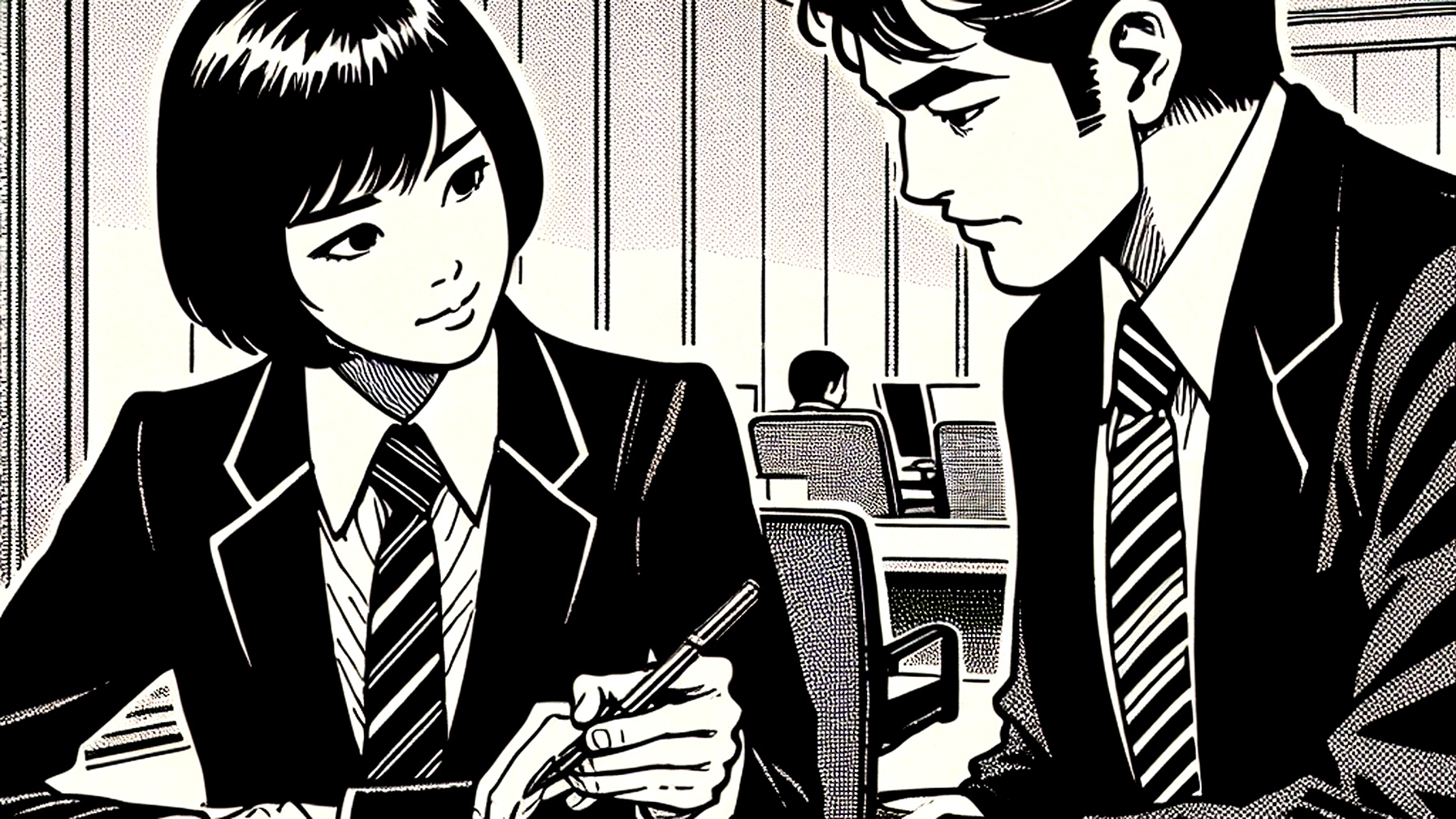
まず押さえておきたいのは、金融機関が重視するのは「物件力」「投資家の属性」「事業計画」の三点です。物件力とは収益性と担保評価を指し、築年数が古いほど評価は下がる傾向があります。しかし、実勢利回りが10%を超え、空室率が低いデータを提示できれば、評価不足を補うことが可能です。
次に投資家の属性ですが、年収だけでなく勤続年数や自己資金の比率も審査対象です。日本銀行の2025年4月貸出動向調査では、自己資金10〜20%を入れると貸出承認率が約15%上がると報告されています。また、副業としての不動産投資を歓迎する金融機関が増え、会社員でも挑戦しやすい環境が整っています。
最後に事業計画の質が結果を左右します。具体的な修繕スケジュールや出口戦略を盛り込めば、築古でも運営リスクを低減できると示せます。つまり「数字と計画で不安を打ち消す」ことが、融資の可否を決める最大のポイントと言えるでしょう。
築古で融資を通すための実践テクニック
実は、築年数の壁を乗り越えるための方法はいくつもあります。まず耐用年数超過物件でも、金融機関が独自に設定する「経済的残存年数」を提示できれば融資期間を延ばせます。リフォーム後の建物診断書を添付し、残存年数を延長できた事例は珍しくありません。
さらに、共同担保の活用も有効です。自宅や別の区分所有物件に抵当権を設定し、担保余力を確保すれば融資枠が広がります。日本政策金融公庫の2025年度不動産担保融資ガイドにも、共同担保で融資期間を10年から20年に伸ばしたケースが掲載されています。
加えて、家賃保証会社とサブリース契約を併用し、安定収入を証明する方法もあります。ただし保証料が利回りを圧迫するため、契約期間や解除条件を細かく確認し、シミュレーションに反映させることが不可欠です。
新NISAと不動産投資の組み合わせ方
ポイントは、非課税運用枠を不動産運営の安全装置として使うことです。2024年にスタートした新NISAは年間投資上限360万円、非課税期間は恒久化されました。毎月3万円の積立なら12年で約600万円の原資を作れ、修繕費や返済準備金として活用できます。
さらに、不動産のキャッシュフローをそのまま新NISA口座へ自動積立する仕組みを作れば、複利効果とリスク分散を同時に実現できます。金融庁のNISA利用状況(2025年6月公表)によると、20代でも累計平均残高が150万円を超えており、小口でも長期で増やせる実績が見えてきました。
ただし、不動産所得は総合課税、新NISAの運用益は非課税と税区分が異なるため、確定申告時に損益通算はできません。そのため「不動産はインカムゲイン、新NISAはキャピタルゲイン」という役割を明確に分け、資金繰り表を二本立てで管理することが大切です。
リスク管理と出口戦略を描く
まず、築古物件では修繕リスクが最大の敵です。屋根や配管など大規模修繕が重なると一時的に赤字化するため、修繕積立金を家賃収入の10%以上確保することを推奨します。また、火災保険と地震保険は保証範囲を広げ、災害リスクをカバーしましょう。
一方で空室リスクにも備える必要があります。不動産テック企業の調査(2025年7月)では、オンライン内見を導入した築古アパートは平均空室期間を25%短縮できたと報告されています。デジタル施策を組み込むことで、築古でも入居付けは十分可能です。
出口戦略としては、物件価値がピークを迎える時期に売却益を狙うか、簿価が減価償却でゼロに近づいた後も保有し続け、キャッシュフローを最大化するかの二択が基本です。いずれの場合も、購入時からシナリオを描き、融資返済完了タイミングと合わせて計画することが成功の鍵となります。
まとめ
築古の収益物件は、取得価格の低さと高利回りで魅力的ですが、融資条件のハードルが高い点が最大の課題です。物件力の根拠をデータで示し、自己資金と事業計画を緻密に整えれば、金融機関の目線をクリアできます。さらに、キャッシュフローの一部を新NISAに振り向けることで、非課税で資金を増やし修繕費や返済準備金に充当できる点も強みです。これらを組み合わせ、リスク管理と出口を明確にすることで、初心者でも築古物件を安定収益の柱に育てることが可能になります。今日紹介したステップを参考に、まずは自分の資金計画とターゲットエリアの市場調査からスタートしてみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産価格指数 2025年8月速報 – https://www.mlit.go.jp/
- 日本銀行 貸出動向調査 2025年4月 – https://www.boj.or.jp/
- 総務省 住民基本台帳人口移動報告 2025年版 – https://www.soumu.go.jp/
- 金融庁 新NISA利用状況 2025年6月公表資料 – https://www.fsa.go.jp/
- 日本政策金融公庫 2025年度不動産担保融資ガイド – https://www.jfc.go.jp/

