家賃収入で資産形成をしたいものの、「区分所有マンションならいくらで買えるのか」「自己資金はどれだけ必要か」と悩む人は少なくありません。高額な買い物だけに、費用の全体像を把握しないと不安は消えないでしょう。本記事ではマンション投資の中でも比較的参入しやすい区分所有に焦点を当て、購入価格の目安から融資の組み立て方、運用コスト、出口戦略までを順序立てて解説します。読み終えるころには、投資資金を具体的な数字でイメージでき、次の行動に自信を持てるはずです。
区分所有マンション投資の基礎知識
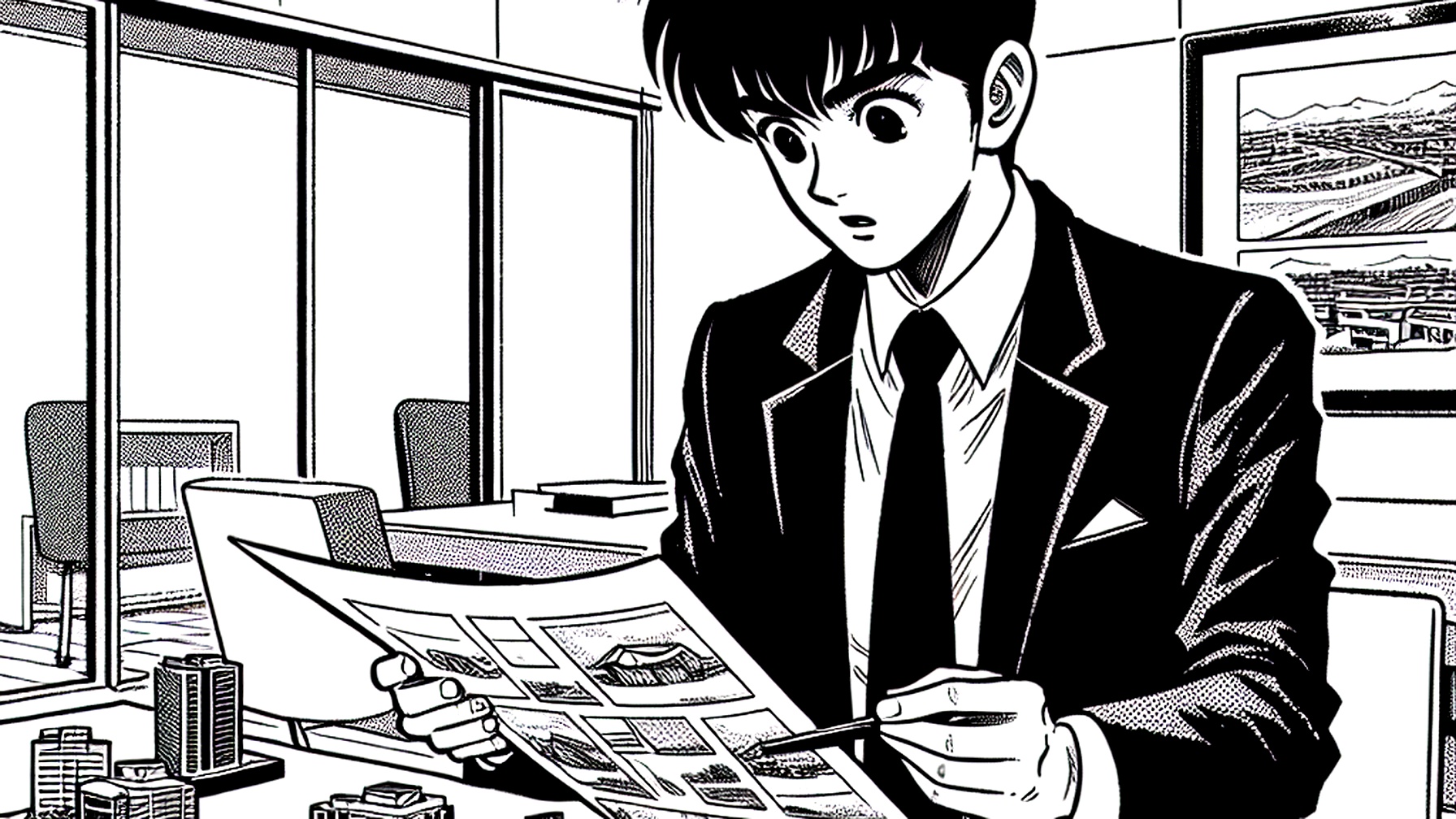
まず押さえておきたいのは、区分所有とは一棟ではなく部屋単位で物件を保有する形態を指すことです。そのため一棟投資よりも購入価格が抑えられ、管理組合が共用部を維持してくれる点が魅力になります。
投資対象は主に新築と中古に分かれます。新築は設備故障のリスクが低く入居者募集でも有利ですが、価格が高いため利回りは控えめです。一方、中古は購入費を抑えられる半面、修繕積立金の上昇や設備更新費が先行して発生する可能性があるので、購入時に建物の長期修繕計画を確認することが欠かせません。
また、賃貸需要の見極めも重要です。総務省の住民基本台帳によれば、2024年度の東京23区の人口は約1万2千人増と微増で推移しました。人口が増えるエリアでは空室期間が短くなるため、区分所有でも安定収益が見込みやすくなります。
物件価格はいくらが目安になるか
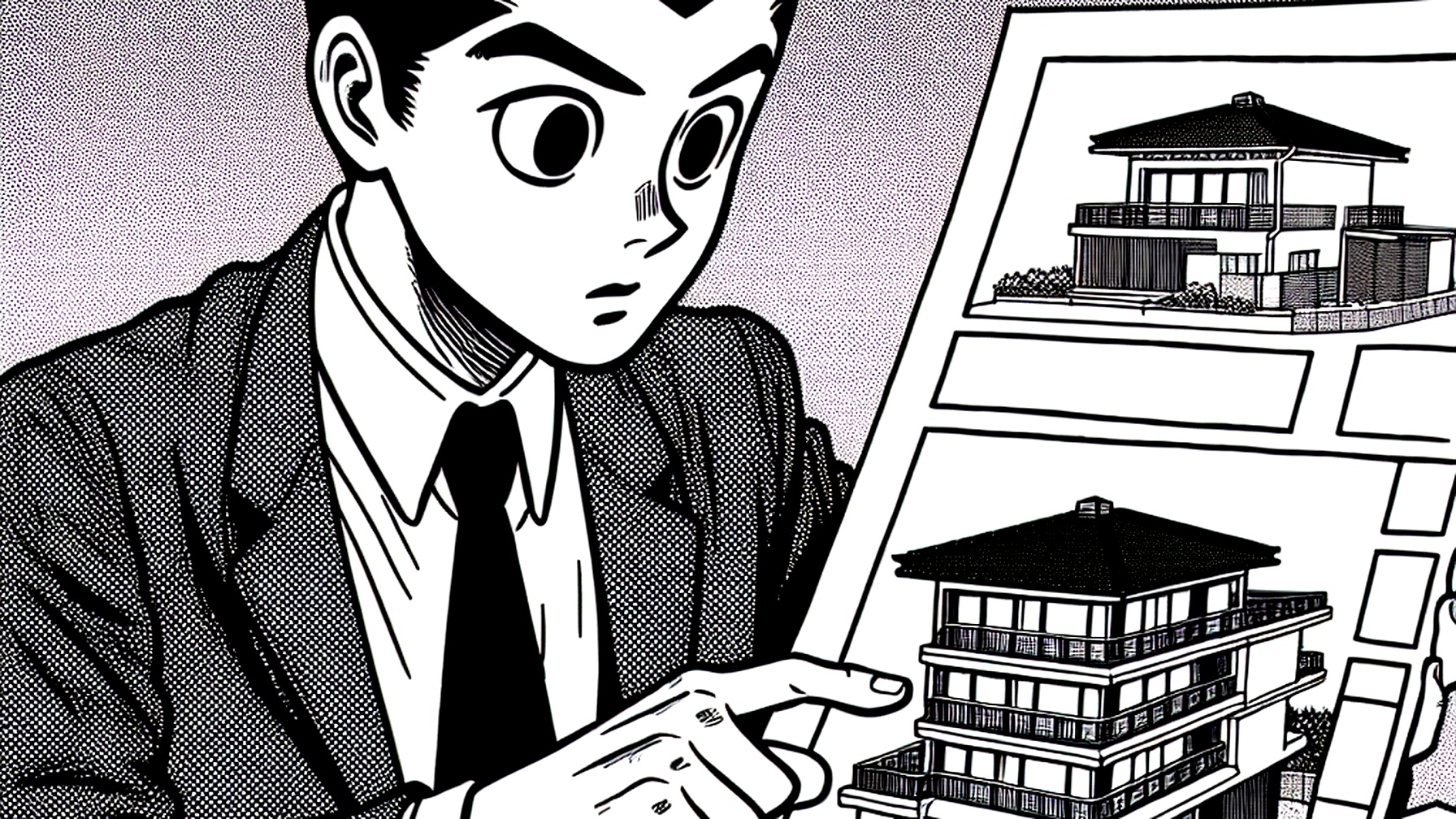
重要なのは、エリアと築年数で価格帯が大きく変わる点です。2025年10月時点での新築マンション平均価格は東京23区で7,580万円と不動産経済研究所が発表しています。ただし、この数字はファミリー向けを含む総平均です。単身者向けワンルームの場合、都心5区では3,500万〜4,500万円、城東・城北エリアでは2,500万〜3,500万円が目安となります。
中古市場を見れば、築15年前後で都心3区のワンルームが2,800万〜3,600万円、郊外なら1,500万〜2,400万円で成約する事例が多く見られます。つまり「マンション投資 いくら 区分所有」という問いの答えは、立地と築年数、部屋の広さによって2,000万〜4,500万円の範囲に収まるのが一般的ということです。
価格だけでなく管理費と修繕積立金も比較する必要があります。例えば、月額管理費6,000円、修繕積立金8,000円の物件と、合計で2万円かかる物件では年間で14万円以上の差が生じ、利回りに直結します。購入前に3年先までの積立金改定予定を確認しておくと、想定外のコスト増を防げます。
資金計画と融資の組み立て方
ポイントは、自己資金と借入のバランスを最初に決めることです。一般的に投資用ローンでは物件価格の80〜90%まで融資を受けられ、自己資金は10〜20%が一つの目安となります。3,000万円の中古区分なら、頭金300万〜600万円を準備するイメージです。
金利は変動型で年1.8〜2.9%が主流ですが、2025年度でも金融機関によって幅があります。例えば金利2.1%、融資期間35年、借入額2,700万円の場合、毎月返済額は約9.0万円です。これに管理費・積立金1.5万円、固定資産税月割り0.8万円を加えると、毎月の支出は11.3万円となります。一方、都心ワンルームの平均賃料は14万円前後なので、表面利回りは約5.6%、手取りキャッシュフローは月2.7万円が目安です。
実は、借入期間を短くすると返済負担は増えますが、金利負担総額は軽減されます。返済シミュレーションで返済比率(家賃収入に対する返済額の割合)を40%以下に抑えると、空室時のリスクを低減できます。また、2025年度も投資用物件には住宅ローン控除が適用されません。したがって、節税効果を狙う場合は減価償却費を活用し、所得税・住民税の圧縮を図る方法を検討すると良いでしょう。
ランニングコストとキャッシュフローの考え方
まず押さえておきたいのは、家賃収入がそのまま利益ではないという事実です。区分所有では管理費・修繕積立金・ローン返済・固定資産税・火災保険料・募集手数料など、多様な支出が発生します。
例えば年間家賃168万円(14万円×12カ月)の物件で、ローン返済108万円、管理費と積立金18万円、固定資産税10万円、募集手数料と原状回復12万円とすると、手取りは約20万円です。ただし、空室が1カ月発生すれば手取りは一気にマイナスになります。そのため家賃保証(サブリース)に頼るより、入居率の高いエリアと適切な賃料設定で空室期間を短縮する方が長期的には有利です。
加えて、修繕積立金は築年とともに上昇する傾向があります。国土交通省の「マンション総合調査」では、築20年超で平均9,800円、築30年超で1万5,000円と段階的に増えるデータがあります。将来のコスト増をキャッシュフロー計算に組み込んでおくことが、資金繰り悪化を防ぐ鍵となります。
収益を左右する出口戦略
実は、買う時よりも売る時の計画が収益を大きく左右します。区分所有の場合、個人投資家が中古として売り出すケースが多く、流動性は比較的高いものの、築年数と立地が価格に直結します。
築10年以内で売却する「短期転売」は価格下落が緩やかなため、自己資金回収を早める戦略として有効です。この際、購入時に販売会社の買取保証がつく新築物件を選ぶと、出口の想定が立てやすくなります。一方、長期運用で家賃収入を得続ける場合は、築25年以降にリノベーションを行い、家賃を維持または向上させる方法が有効です。
税制面では、所有期間が5年を超えると譲渡所得税率が約半分になります。2025年度も長期譲渡の税率は20.315%で据え置きですので、売却のタイミングを6年目以降に設定すると手取りが増える計算になります。出口戦略を事前に定め、複数の不動産仲介会社に査定依頼をかけ、適正価格を把握することが成功への近道です。
まとめ
マンション投資を区分所有で始める際、「いくら必要か」は立地・築年数・自己資金比率で大きく変わります。都心ワンルームなら2,000万〜4,500万円が相場で、頭金は10〜20%が目安です。ローン返済比率を40%以下に抑え、将来の修繕積立金増額を織り込んだキャッシュフロー表を作ることが、安定運用の第一歩になります。最後に、売却時期と税率を踏まえた出口戦略を事前に計画し、購入から運用、売却まで一貫したシナリオを描いて行動することが、資産を守り育てる鍵となるでしょう。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 総務省 住民基本台帳人口移動報告 – https://www.soumu.go.jp
- 国土交通省 マンション総合調査 – https://www.mlit.go.jp
- 国税庁 譲渡所得の税率 – https://www.nta.go.jp
- 日本銀行 金融機関貸出金利レポート – https://www.boj.or.jp

