会社勤めをしながら「いつかは大型物件を所有して安定収入を得たい」と考える人は少なくありません。しかし、2億円規模の収益物件となると、自己資金や融資審査、運営リスクなど不安要素が山積みです。そこで本記事では、会社員が実際に2億円の物件を取得し、リフォームを通じて価値を高めるまでのプロセスを徹底解説します。金融機関の最新動向や2025年度のリフォーム支援制度も盛り込み、初心者でも具体的な行動に移せる内容にまとめました。
会社員でも狙える2億円規模の収益物件とは
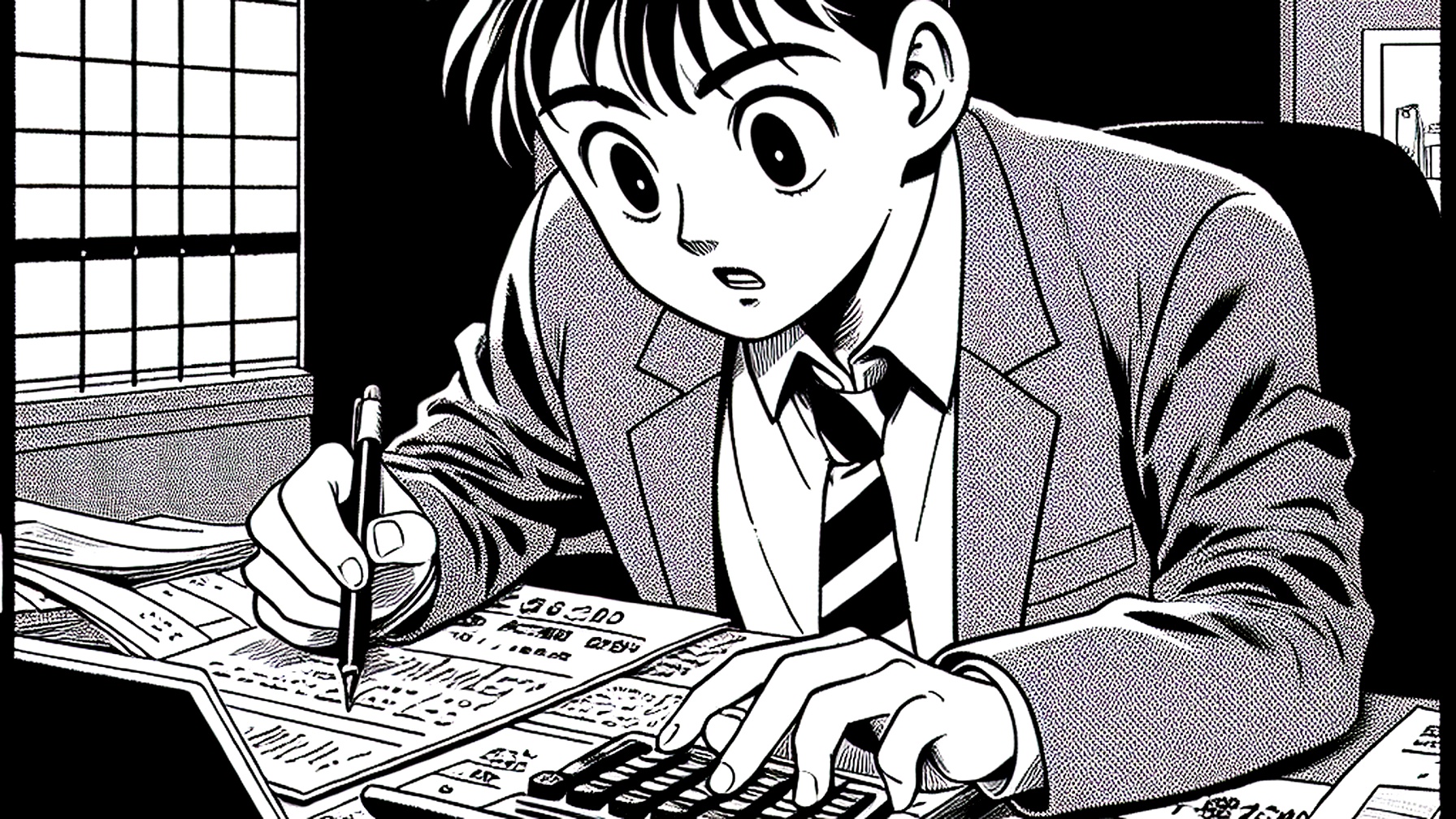
まず押さえておきたいのは、2億円の物件が必ずしも高級タワーマンションとは限らない点です。実は、首都圏の築25年前後の一棟アパートや地方中核市のRC造マンションでも、延床800㎡程度なら2億円前後で流通しています。国土交通省「不動産価格指数」によると、築古一棟物件の価格はコロナ禍以降も横ばいで推移し、利回りは都心で5%、地方で8%前後が目安とされています。つまり、適切なリフォームで空室率を抑えれば、年間1,000万〜1,600万円の家賃収入が期待できる計算です。
次に、会社員が2億円を調達する現実的な方法として、金融機関のノンリコースローンや法人スキームの活用があります。金融庁の2025年4月版「地域金融機関向けガイドライン」では、賃貸需要の裏付けがある案件への長期融資を推奨しており、自己資金2割(4,000万円)を目安に相談すれば審査通過率が高まる傾向です。さらに、家族を役員にした合同会社での購入も、所得分散や相続対策で評価されています。
最後に、立地の見極めが成功の鍵です。総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」では、2024年の転入超過上位は東京23区・名古屋市・福岡市で、これらの駅徒歩10分以内物件は空室率が低水準です。一方で、人口減少が進むエリアでも、大学や工業団地に隣接する物件なら安定需要が見込めます。購入前に用途地域や将来の開発計画を役所で確認し、想定家賃が甘くないか必ずチェックしましょう。
融資戦略と資金計画の立て方
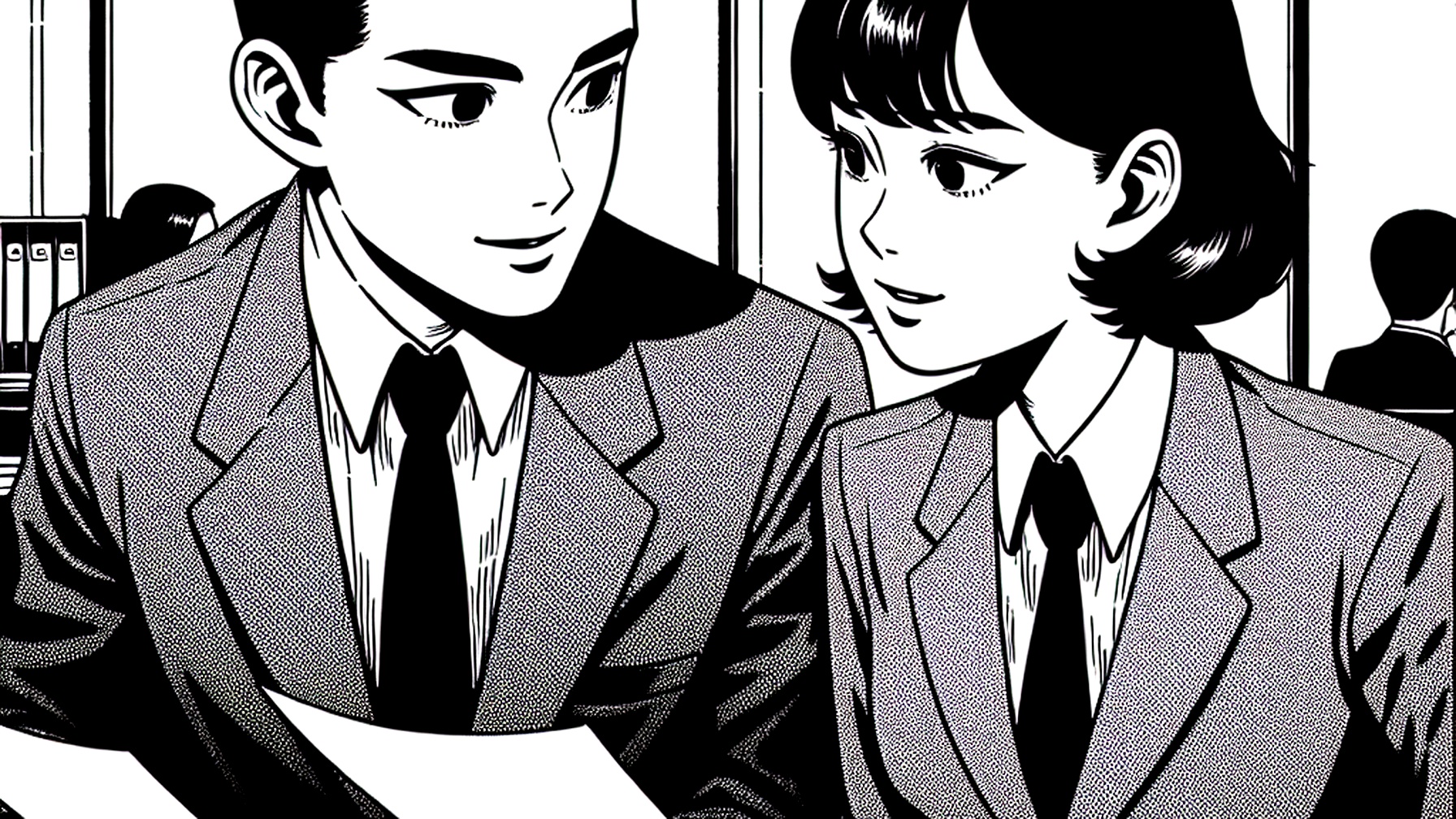
ポイントは、個人属性と物件収支を両輪で評価してもらうことです。年収700万円の会社員でも、自己資金と担保力を示せば2億円融資は十分射程内に入ります。ただし、金融機関は「長期安定雇用」を重視するため、転職直後や業績連動型報酬の割合が高い人は注意が必要です。日本銀行「貸出態度判断DI」でも、2025年は中立水準ながら不動産向け融資は慎重姿勢が続くと報告されています。
また、返済比率は家賃収入の50%以下に抑えると安全域が広がります。例えば表面利回り7%、年間家賃1,400万円の物件なら、元利金返済は700万円以内が目安です。変動金利が1.5%から2.5%に上昇するストレスシナリオも試算し、その場合でもキャッシュフローが黒字か確認しましょう。さらに、修繕積立として年間家賃の5%を別口座に確保しておくと突発的な出費にも対応できます。
自己資金は頭金のほか、購入時諸費用(物件価格の7%前後)とリフォーム費用を想定します。2億円物件の場合、仲介手数料や登録免許税などで約1,300万円、共用部の大規模修繕に2,000万円前後がかかるケースが多いです。これらを加味すると、合計5,300万円程度の現金を用意できれば、金融機関からの信頼度が大幅に向上し、金利優遇も受けやすくなります。
リフォームで価値を高める実践ポイント
重要なのは、投資対効果を定量的に評価する姿勢です。賃貸需要の高いエリアでは、室内をフルリノベーションしなくても、共用部のLED化や宅配ボックス設置で家賃3,000円アップが見込める場合があります。国土交通省「賃貸住宅市場の調査結果」(2024年度)によると、希望設備トップ3は高速インターネット、防犯カメラ、浴室乾燥機で、導入後の成約スピードが平均1.5倍に向上しています。
一方で、築30年超のRC造では給排水管の更新が必須となるケースも多く、ここを後回しにすると漏水事故のリスクが跳ね上がります。長期的な資産価値を守るには、外壁塗装や屋上防水と同時に配管まで一体で更新し、施工保証が付く業者を選ぶと安心です。見積もりは必ず3社以上取り、工事項目ごとに単価を比較することで、コストを10%以上抑えられた事例も多数あります。
2025年度は「長期優良住宅化リフォーム推進事業」が継続予定で、全体工事費の3分の1、上限250万円の補助が受けられます。適用条件は、耐震性や省エネ性能の向上をセットで行うこと、そして工事後に住宅性能評価を取得することです。期限は2026年3月交付申請分までと発表されていますので、スケジュールに余裕を持って申請しましょう。
キャッシュフローを守る管理と出口戦略
まず押さえておきたいのは、運営コストを固定化し、収入変動に備える体制づくりです。管理会社との委託契約は、家賃回収率、原状回復費の上限、広告料の負担割合を明確にし、毎年見直す姿勢がポイントになります。例えば広告料1ヶ月分を0.5ヶ月に抑えるだけで、年間40万円以上の支出削減につながるケースもあります。
また、入居者ターゲットを明確にすると、リフォームや募集広告の方向性がブレません。駅近ワンルームなら社会人単身者、郊外ファミリー向けなら子育て世帯を想定し、学区や保育施設の情報を広告に盛り込むと成約率が上がります。公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の調査では、入居者が物件を選ぶ決め手の42%が「周辺生活環境」と回答しており、立地情報の訴求は欠かせません。
さらに、出口戦略として5年後以降の売却益を狙うか、長期保有でインカムゲインを積み上げるかを早い段階で決めておくと、リフォーム仕様や繰上返済計画に一貫性が生まれます。税務面では、法人保有なら譲渡益課税が20.42%に抑えられ、個人の場合の短期譲渡39.63%と比べて有利です。これらを踏まえ、将来の金利動向や人口推移を定期的に確認しながらシナリオを更新しましょう。
2025年度の支援制度と税制メリット
一方で、国の支援策を活用すると初期費用を圧縮できます。2025年度は、省エネ改修を行うと固定資産税が3年間1/2になる「既存住宅省エネ化特例」が継続見込みです。対象要件は、外皮性能の向上または高効率給湯器の導入などで、工事完了後3か月以内の申告が必須となります。
また、住宅金融支援機構の「賃貸住宅融資」は、会社員でも法人を組成すれば利用可能で、金利は1.3%台から2.0%台と民間銀行よりやや高いものの、最長35年固定で安定性が魅力です。資金使途の3割までをリフォームに充当できるため、物件取得と同時に大規模修繕を行いたい場合に有効です。
加えて、国土交通省「住宅設備省エネリフォーム税制」は、断熱改修や太陽光発電の設置費用の10%(上限45万円)が所得控除される仕組みで、2026年12月まで延長予定と発表されています。これらの制度を組み合わせると、実質的な自己資金を数百万円単位で減らせるため、融資審査での自己資本比率も引き上げられます。
まとめ
最も伝えたいのは、会社員でも緻密な計画と制度活用によって、2億円規模の収益物件を安全に運営できるという事実です。立地選定と融資戦略を両立させ、リフォームで競争力を高めることで、キャッシュフローは安定し、将来の売却益も視野に入ります。まずは自己資金と与信力を棚卸しし、信頼できる仲介会社や工事業者とチームを組むことから始めましょう。行動を一歩踏み出せば、大型物件は決して遠い夢ではありません。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省統計局 住民基本台帳人口移動報告 – https://www.stat.go.jp
- 日本銀行 貸出態度判断DI – https://www.boj.or.jp
- 金融庁 地域金融機関向けガイドライン(2025年版) – https://www.fsa.go.jp
- 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 市場動向調査 – https://www.jpm.jp

