不動産価格が高止まりする一方で、相続税の負担は年々増しています。そんな状況で「アパート経営に興味はあるけれど本当にうまくいくのか」と不安を抱く方は多いでしょう。この記事では、安定収益を狙いながら相続対策も実現する方法を、最新データと具体例を交えて解説します。読み終えるころには、どのような物件を選び、どのように運営すればよいかがイメージでき、自分に合った次の一歩を踏み出せるはずです。
なぜ今アパート経営が注目されるのか
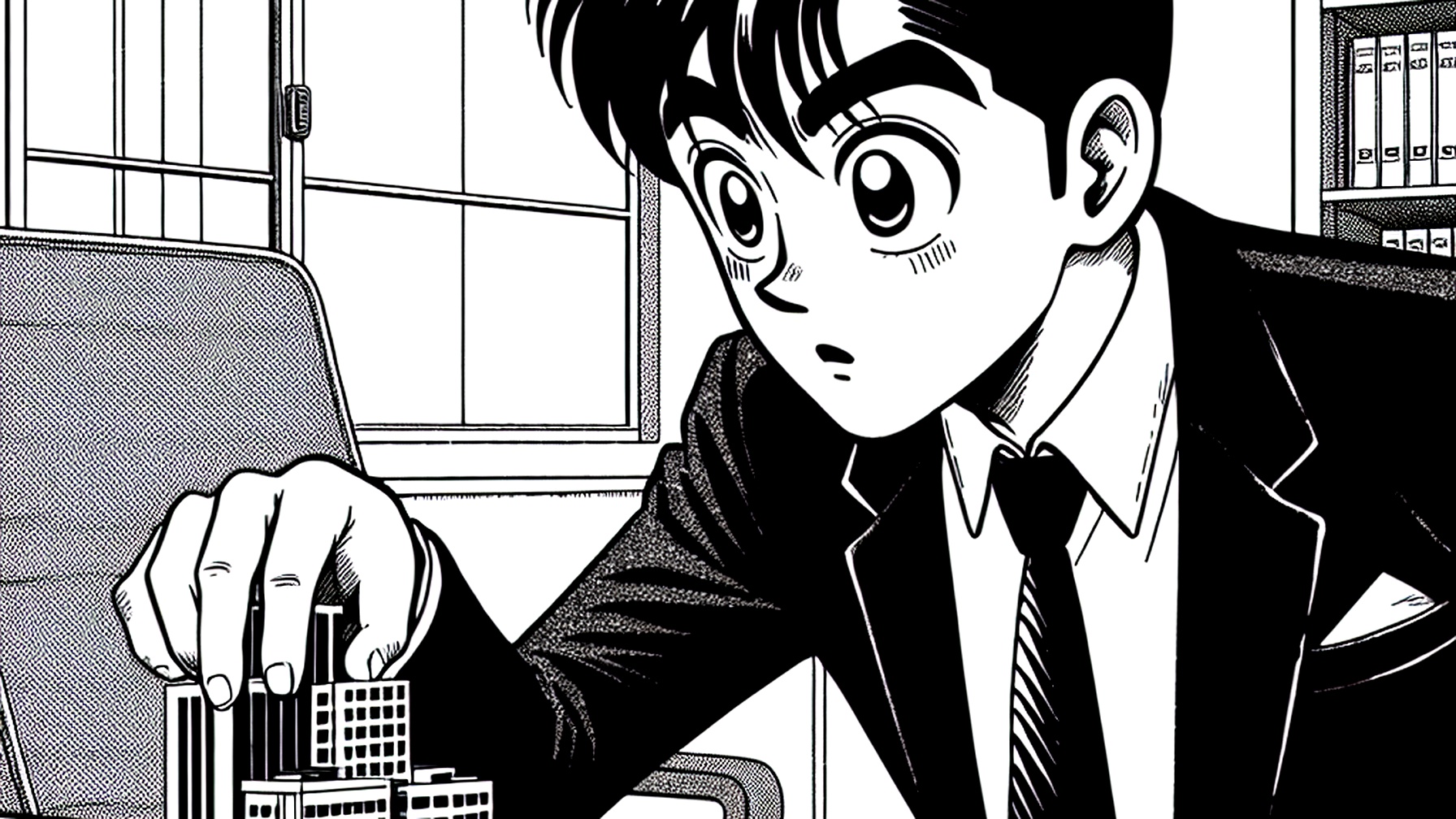
まず押さえておきたいのは、投資環境の変化です。国土交通省の住宅統計によると、2025年8月の全国アパート空室率は21.2%で前年比0.3ポイント改善しました。つまり、賃貸市場にはまだ余裕がありつつも、需給バランスはわずかに締まりつつある状況です。
一方で、預金金利は0.1%台にとどまり、株式市場も値動きが激しいため、資産を長期で安定させたい層から不動産への資金流入が続いています。また、相続税評価額を建物分で抑えられるメリットがあるため、相続対策としてアパートを選ぶ動きが加速しています。さらに、2025年度税制改正で登録免許税の軽減措置が延長されたことも追い風です。
しかし、注目度が高いというだけで成功が保証されるわけではありません。立地や運営方法を間違えれば空室率の波に飲み込まれ、手残りが赤字になるリスクもあります。重要なのは、需給バランスを読み解き、長期で収益を積み上げる仕組みを作ることです。
キャッシュフローを安定させる三つの視点
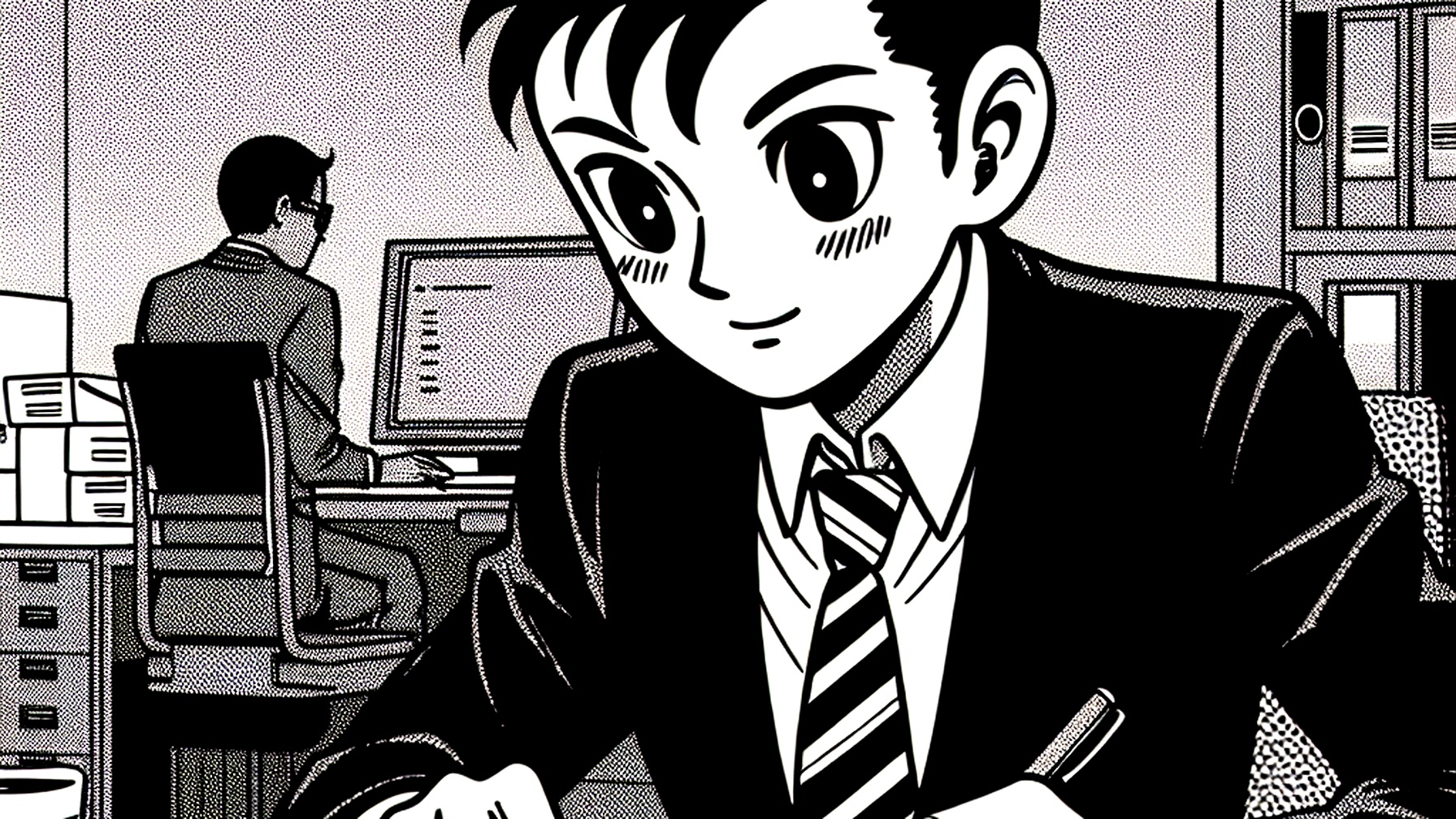
ポイントは「収入の確保」「支出の抑制」「税負担の最適化」です。まず家賃収入を最大化するには、駅徒歩10分圏内や大学病院の近くなど、転勤・通学需要が見込める立地を選びます。都心部は物件価格が高いものの、空室リスクが低く家賃も下がりにくいため、長期保有には向いています。
次に支出の抑制ですが、管理会社との業務委託契約を定期的に見直すことが効果的です。管理料が月額家賃の5%から3%に下がるだけで、年間で数十万円のキャッシュが残ります。また、共用部のLED化や太陽光パネル設置による電気代削減も、中長期で見れば無視できません。
最後に税負担の最適化として、不動産取得税や固定資産税の軽減措置を把握し、確定申告で減価償却費を漏れなく計上することが欠かせません。たとえば、木造アパートなら22年、鉄骨造なら34年の法定耐用年数を活用し、初期数年間の所得を圧縮できます。この三つの視点をバランス良く組み立てることで、キャッシュフローは想定以上に安定します。
相続対策としてのアパート経営の仕組み
実は、相続税評価額が下がる仕組みを理解すると、アパート経営の魅力がより鮮明になります。土地は路線価で評価され、貸家建付地として約20%の減額が見込めます。建物も固定資産税評価額で計算されるため、市場価格の70%程度まで圧縮されるのが一般的です。
これにより、現金で3億円を持っているよりも、1億円の自己資金と2億円のローンでアパートを建てたほうが、課税対象額を大幅に下げられるケースがあります。さらに、賃料収入でローンを返済しつつ元本を減らせるため、次世代へ非課税で財産を移せる効果も期待できます。
ただし、相続人が複数いる場合は、分割方法まで考慮しておく必要があります。賃貸物件を共有するとトラブルの火種になるため、生前に法人化して持株割合で調整する方法や、一棟を売却し現金で分割できる出口戦略を決めておくことが肝心です。相続発生後に慌てないよう、遺言書や家族信託なども併用して備えましょう。
2025年度の税制と補助金をどう活用するか
まず、2025年度も適用される住宅取得資金贈与の非課税枠(上限1,000万円)は、親子間で活用しやすい制度です。贈与された資金で土地を取得し、建物はローンで組むことで、自己資金不足を補えます。また、登録免許税の軽減措置は、建物表題登記が2026年3月末までに完了すれば税率が0.3%から0.2%に下がります。
環境性能を高めた新築アパートについては、2025年度も引き続き「長期優良住宅化リフォーム推進事業」の補助金が活用できます。たとえば、断熱改修や劣化対策を行うことで、最大250万円の補助を受けられます。省エネ性能が上がると、賃料にプレミアムを付けやすくなるため、長期的な家賃下落を抑える効果も期待できます。
なお、補助金や軽減措置は申請期限を過ぎると受け取れないため、着工スケジュールを逆算して計画することが重要です。また、同じ制度でも自治体ごとに加算額が異なるケースがあります。事前に市区町村の窓口で最新情報を確認し、見込みキャッシュフローに反映させましょう。
失敗を防ぐプロのチェックポイント
重要なのは、購入前に想定外の出費リスクを洗い出すことです。築年数が浅くても、外壁や屋上防水の保証期間を確認し、更新時期と費用を見積もっておきます。修繕積立を月々1万円先取りするだけで、大規模工事時の資金繰りに慌てずにすみます。
また、金融機関の選定では金利だけでなく、融資期間と元金据置期間の有無を比較します。例えば、金利が0.2%高くても5年長く借りられれば、月々の返済額は下がり、キャッシュフローはむしろ改善するケースがあります。つまり、総返済額と年間手残りを同時に見る視点が大切です。
さらに、管理会社任せにせず、半年ごとに物件を巡回し、設備の劣化や入居者の属性変化を確認しましょう。入居者アンケートでネット使用状況を聞き取り、無料Wi-Fi導入を検討するだけでも満室期間を延ばせます。小さな施策を積み重ねることが、最終的な投資成績を大きく左右します。
まとめ
ここまで、空室率の動向から税制、相続対策まで幅広く見てきました。アパート経営で成功をつかむ鍵は、収入・支出・税金の三つをバランスさせ、長期視点で計画を練ることに尽きます。特に「アパート経営 成功法 相続対策」を同時に叶えるには、制度を正しく活用しつつ、家族との合意形成を早めに進める姿勢が欠かせません。まずは気になるエリアの賃貸需要を確認し、信頼できる専門家に収支シミュレーションを依頼するところから始めてみてください。行動を一つ積み重ねるたびに、将来の安心が形になっていくはずです。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計調査 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省統計局 家計調査 – https://www.stat.go.jp
- 財務省 税制改正資料 2025年度版 – https://www.mof.go.jp
- 国税庁 相続税・贈与税のあらまし 2025 – https://www.nta.go.jp
- 中小企業庁 長期優良住宅化リフォーム推進事業 – https://www.chusho.meti.go.jp

