不動産投資に興味はあるものの、「税金が高そう」「結局どれだけ手元に残るのか」と不安を抱える方は多いものです。実は投資用物件を活用すると、家賃収入を得ながら節税効果も期待できます。本記事では2025年10月時点の税制に基づき、初心者でも理解しやすい形で仕組みと実践策を解説します。読み終えれば、余計な税負担を抑えつつキャッシュフローを安定させる道筋が見えてくるでしょう。
なぜ投資用物件で節税が可能なのか
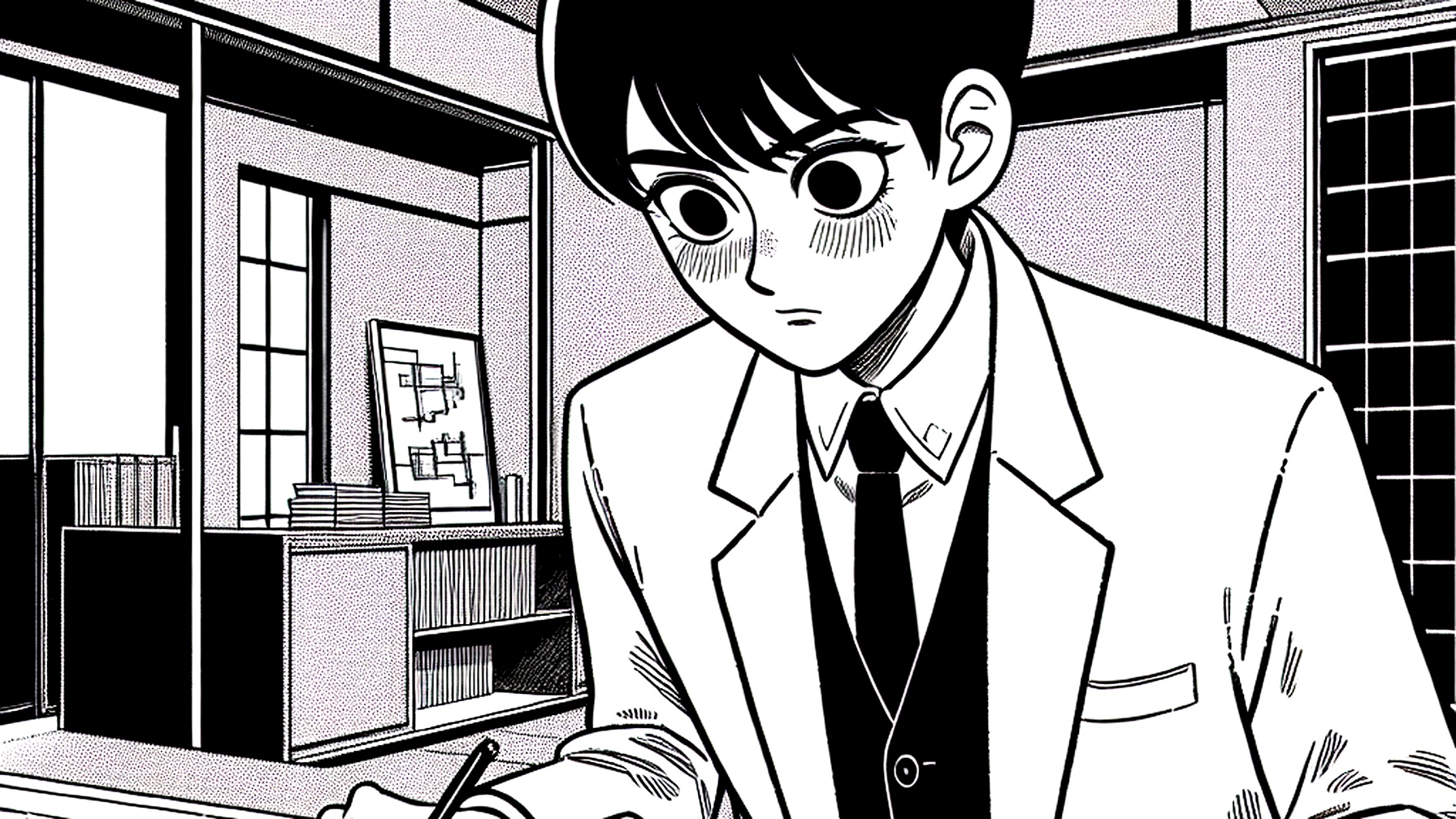
まず押さえておきたいのは、賃貸経営の収入が「事業所得」や「不動産所得」として扱われる点です。この区分になると、家賃収入から必要経費を差し引いた後の金額に対して課税されます。つまり経費を適切に計上すれば課税所得を小さくでき、その分だけ節税効果が生まれます。国税庁の統計によると、2024年度の不動産所得者の平均経費率は35%前後でした。個々の状況で差はありますが、給与所得と比べて控除項目の幅が広い点が強みです。
一方で経費計上のルールに誤りがあると、税務調査で否認されるリスクが高まります。青色申告特別控除65万円を受けるには複式簿記での記帳と期限内申告が前提です。この申告形式は手間がかかるものの、融資審査で有利になるケースも多く、一石二鳥と言えます。投資用物件で節税を狙うなら、適正な経費管理と帳簿作成が第一歩となるのです。
経費計上で失敗しない基本
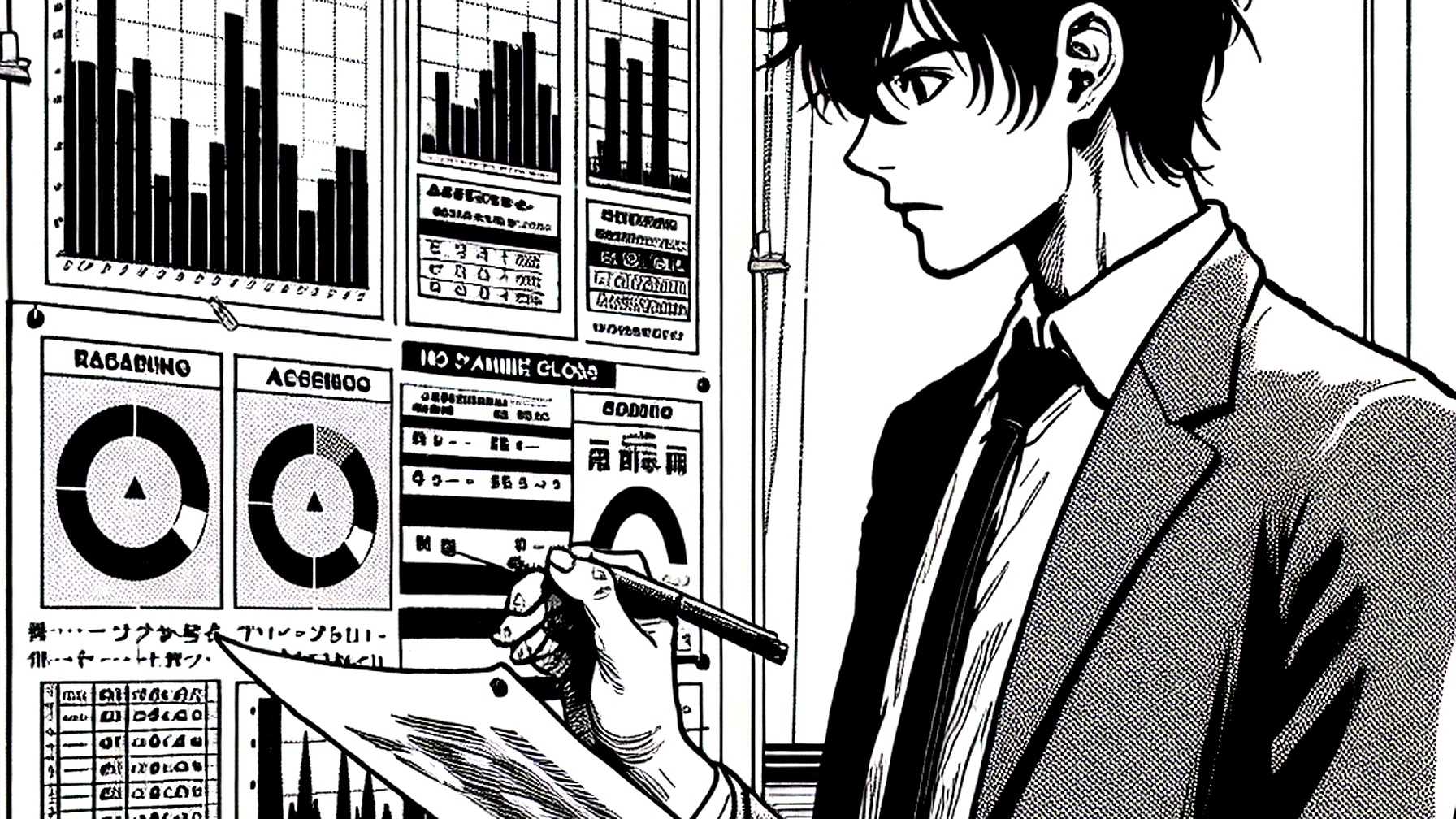
重要なのは「実際に支出し、賃貸経営と直接関係する」費用だけを経費とすることです。管理会社へ支払う委託手数料や火災・地震保険料は典型的な経費であり、国税庁のタックスアンサーでも例示されています。また、物件を視察するための交通費やセミナー参加費も業務関連性が明確なら認められます。ただし家族旅行を兼ねた視察の旅費などは私的要素が強く否認されやすい点に注意しましょう。
さらに、修繕費と資本的支出の区別も押さえておくべきポイントです。10万円未満、あるいは取得価額の10%以下の軽微な工事は原則として修繕費に該当し、その年度で全額損金算入できます。対して外壁全面改修といった大規模工事は資本的支出となり、減価償却で複数年にわたり費用化することになります。資本的支出を誤って修繕費に計上すると後日修正申告を求められる恐れがあるため、工事内容と金額の明細を保存しておくと安心です。
減価償却を最大限に生かす方法
ポイントは、建物価格と耐用年数の設定で減価償却費をコントロールできる点にあります。建物と土地が一体で売買される場合でも、土地は減価償却の対象外です。したがって売買契約書に建物割合を適正に記載し、土地値が過大にならないよう留意しましょう。国土交通省が発表する建築費指数や不動産鑑定評価基準を活用すると、客観的な建物割合を示しやすくなります。
中古物件の場合、法定耐用年数を経過していても「経過年数×0.2+残存年数」で再計算でき、結果的に償却期間を短く設定できるケースがあります。例えば鉄骨造耐火建物(法定耐用年数34年)を築25年で取得した場合、新たな耐用年数は9年となり、減価償却費を厚く計上できます。減価償却費はキャッシュアウトを伴わない経費なので、税負担を軽くしつつ手元資金を守る効果が大きいのが魅力です。
ただし短期間で償却が終わると、将来の控除額が減ることも考慮する必要があります。長期保有が前提なら、中古区分マンションと新築木造アパートを組み合わせてバランスを取るなど、ポートフォリオ全体で償却スケジュールを設計すると安定性が増します。
2025年度の税制優遇と注意点
まず、2025年度も引き続き「住宅ローン控除」は居住用が対象であり、投資用物件 節税には使えません。しかし、賃貸住宅の省エネ性能を高める投資に対しては、固定資産税が3年間半減される地方自治体の制度が残っています。対象となるのは断熱性能等級5相当以上の新築または改修を行った場合で、各自治体により申請期限が異なるため、事前確認が不可欠です。
また、賃貸併用住宅を自己居住部分50%以上で設計すれば、住宅取得資金贈与の非課税枠(2025年度は最大1000万円)を利用できる可能性があります。国税庁は「併用住宅であっても自己居住割合が基準を満たせば適用可能」と明確に示しており、親から資金援助を受ける計画がある方には有効な手段となります。ただし将来的に居住割合が変わると税務上の取り扱いが複雑になるため、長期的な生活設計と合わせて検討しましょう。
一方で、短期譲渡所得の税率は高いまま維持されています。取得から5年以内に売却すると約39%の税率が適用されるため、節税目的で購入した物件を短期で転売するとメリットが消える恐れがあります。投資用物件 節税を狙うときは、保有期間と出口戦略を必ず一本化しておくことが欠かせません。
キャッシュフローを守る節税戦略
実は節税効果が大きくても、手元資金が枯渇すれば投資は続きません。家賃収入からローン返済、管理費、税金を差し引いた後に残るキャッシュフローを常に意識しましょう。日本銀行の金融システムレポートによると、2025年上期の不動産向け貸出金利は平均1.9%で横ばいです。低金利環境を活用し、長期固定ローンで返済額を安定させれば、減価償却が進む数年間にキャッシュを積み増せます。
さらに、赤字を意図的に作る「損益通算」を行う場合でも、金融機関は黒字経営を重視する点を忘れてはいけません。帳簿上の赤字が続くと追加融資が難しくなるため、減価償却以外での赤字は極力避ける戦略が安全です。具体的には、管理費や修繕費の発生タイミングを分散させる、家賃を段階的に引き上げるなど、キャッシュフローを調整しながら節税効果を維持する方法が有効です。
最後に、税理士との連携は費用以上のリターンを生むことが珍しくありません。不動産に強い税理士は、最新の法改正情報や地方独自の減税措置を熟知しており、節税プランの精度を高めてくれます。顧問料を経費にできる点も踏まえ、専門家活用を前向きに検討してみてください。
まとめ
投資用物件 節税の鍵は、正しい経費計上と減価償却の活用、そして2025年度税制の優遇措置を積極的に取り込むことです。家賃収入を増やすだけでなく、手元に残るキャッシュを守る視点が欠かせません。まずは青色申告の準備と修繕計画の見直しから着手し、信頼できる税理士や管理会社と連携しながら一歩ずつ改善を進めましょう。適切な知識と計画があれば、税負担を抑えながら長期的に資産を拡大できるはずです。
参考文献・出典
- 国税庁 – https://www.nta.go.jp
- 国土交通省 建築費指数調査 – https://www.mlit.go.jp
- 日本銀行 金融システムレポート – https://www.boj.or.jp
- 総務省 統計局 住宅・土地統計調査 – https://www.stat.go.jp
- 全国賃貸住宅新聞社 家賃動向調査 – https://www.chintainews.co.jp

