不動産投資を始めたいものの、自己資金や借入を合わせて2億円規模となると「本当に回収できるのか」「何を基準に選べば良いのか」と不安になる方は多いでしょう。特に2025年現在は金利上昇リスクや人口動態の変化が取りざたされ、正しい判断軸を持たないまま動くと損失が拡大しかねません。この記事では「比較 2億円」をキーワードに、一棟アパート、区分マンション、都心オフィス、さらにはREIT(不動産投資信託)まで、投資シナリオ別の収益性とリスクを徹底的に検証します。読み終えたとき、あなたは自分に合った戦略を見極め、具体的な次の一歩を踏み出せるはずです。
2億円という投資規模をどう捉えるか
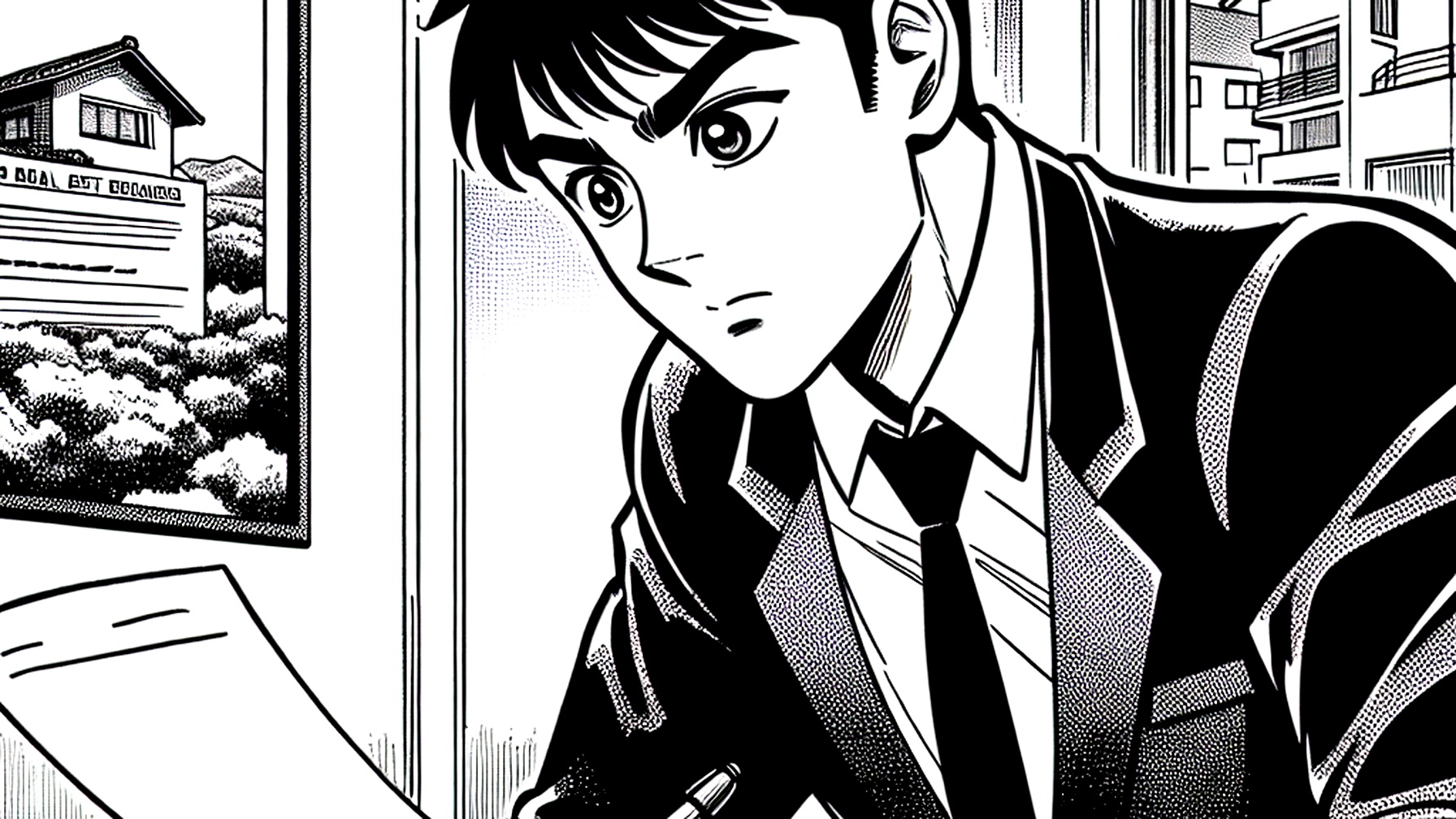
まず押さえておきたいのは、2億円という額が個人投資家にとって決して途方もない数字ではなくなりつつある点です。国土交通省の住宅市場動向調査によると、2025年における投資用一棟アパートの平均成約価格は約1億6,000万円で、2億円は中規模クラスに位置します。つまり自己資金3,000万円、残りを融資でまかなう現実的な計画が可能です。また、同じ2億円でもREITなら10万円単位で分散購入できるように、資金の割り振り方でリスクプロファイルは大きく変わります。このように金額の大きさより「どう配分し、どの程度レバレッジ(借入)を使うか」が成否を分けるポイントになります。
次に、投資期間と出口戦略を決めることが欠かせません。たとえば木造アパートを新築で購入する場合、法定耐用年数22年を意識し、15年後の売却益もしくは建替え原資の確保が焦点になります。一方、築古RC(鉄筋コンクリート)マンションを取得する選択肢では、短期での減価償却メリットを最大化する戦術があり、キャッシュフローの厚みは大きく異なります。つまり同じ2億円でも運用年数と物件種別の掛け合わせで、期待利回りも税負担もまったく別の姿を示すのです。
売買と融資のシミュレーションを比較
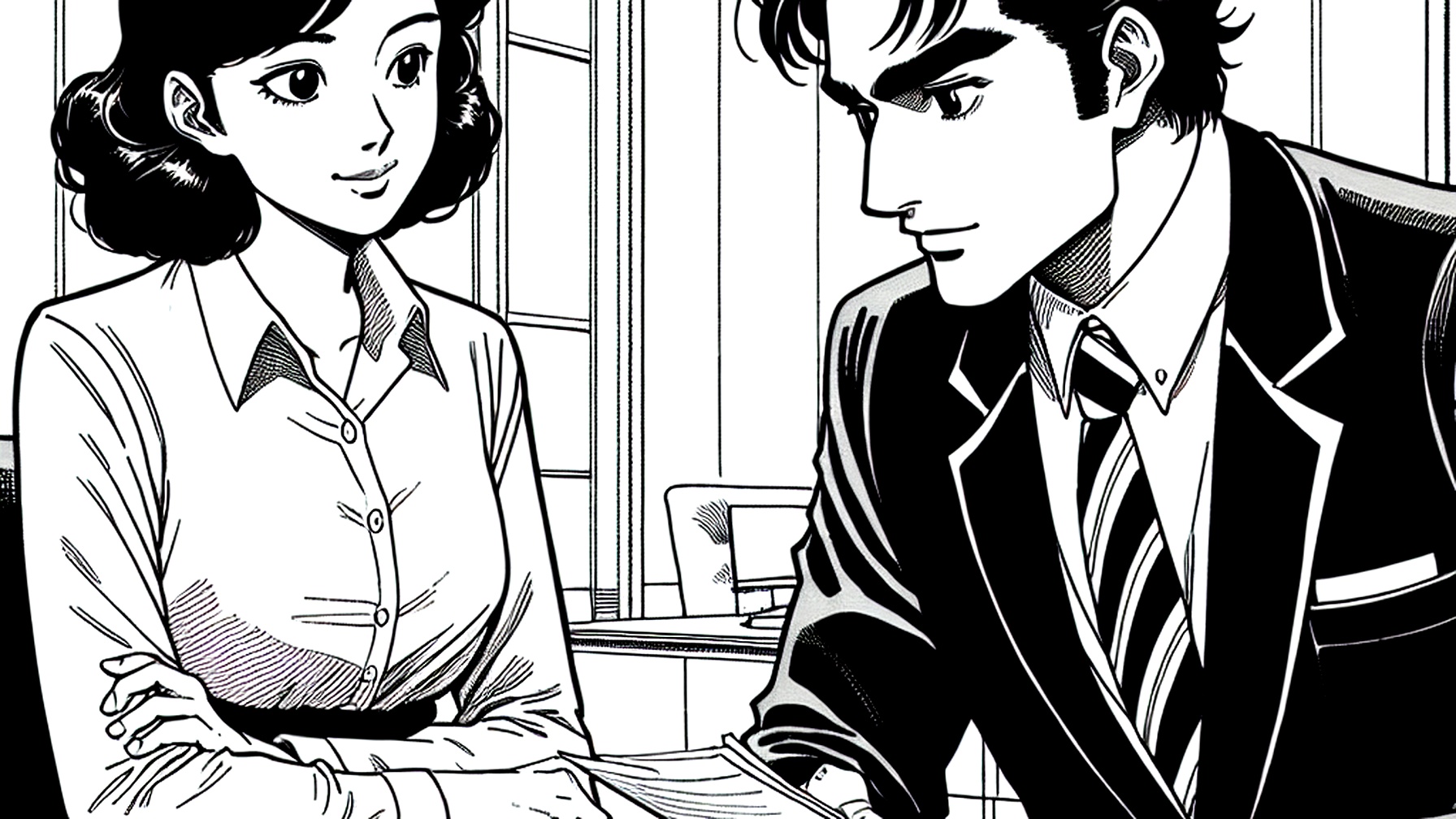
重要なのは、物件価格の比較だけでなく融資条件を含めた総コストを把握することです。2025年度の主要地銀ではアパートローン金利が2.0%前後、最長融資期間は30年が一般的で、元利均等返済の場合、2億円全額借入なら年間返済額は約9,000万円になります。自己資金を2割入れて借入を1億6,000万円に抑えると、年間返済は約7,200万円へ圧縮でき、表面利回り7%の物件ならキャッシュフローは月次で約70万円改善します。つまり自己資金比率と金利のわずかな差が、収益性を大きく左右します。
さらに、借入時に発生する各種手数料や火災保険料、登録免許税を含めると諸費用は物件価格の6〜8%かかるのが通例です。具体的には2億円の取引で最大1,600万円が別途必要となります。シミュレーションを行う際は、購入諸費用を借入に組み込めるかどうか、金融機関に確認することが欠かせません。また金利タイプにも注意が必要です。変動金利は低水準ですが、将来的に1%上昇するだけで30年間の総返済額は約2,500万円増加します。一方、全期間固定にすると初期金利は高くなるものの返済総額は安定し、長期保有に向いた設計になります。
物件タイプ別リスクとリターン
ポイントは、2億円を「一棟で集中」か「複数で分散」かでリスク構造が変わることです。一棟アパートなら意思決定が早く修繕も一括管理できますが、空室が出たときの収益インパクトが大きく、立地選定を誤ると即座にキャッシュフローが悪化します。対照的に区分マンションを複数戸買い進める方法は、エリア分散や賃借人属性の分散が図れますが、管理会社との折衝コストが累積し、共用部修繕の意思決定に時間がかかる点がデメリットです。
都心オフィスへの投資は、賃料単価が高く収益性が魅力ですが、景気変動による空室率上昇リスクが顕著です。特にリモートワーク浸透で需要が読みにくくなっており、公益財団法人日本生産性本部の調査でも、中規模オフィスの空室率は2023年の5.1%から2025年に7%へ上昇しました。つまり安定重視の個人投資家には、オフィス単体よりも住宅系への配分が依然として適しています。
REITを加えたハイブリッド戦略も選択肢になります。例えば2億円のうち1億5,000万円で現物不動産を購入し、残り5,000万円をREITに投じれば、即時換金性を確保しながら流動的な分配金を得られます。日本取引所グループによると、2025年の東証REIT指数分配金利回りは4%前後で推移しており、安定分配を補完する役割が期待できます。こうした組み合わせで、突発的な資金需要にも柔軟に対応できる体制を整えられます。
税務とキャッシュフローの最適化
実は、手取りベースでリターンを高めるには税金の扱いが鍵を握ります。不動産所得は総合課税となり、給与所得と合算されるため、高所得者ほど税率が上がります。対策として、減価償却費を用いて課税所得を圧縮する方法が一般的です。特に築20年以上の木造や築30年以上のRCは、残存耐用年数が短く、償却費を多く計上できるため、初期のキャッシュフローを押し上げる効果があります。
加えて、法人化による実効税率のコントロールも検討する価値があります。資本金1億円以下の中小法人なら2025年度の法人税率は19%、住民税と事業税を合わせても約30%に抑えられ、最高45%の個人所得税と比べて優位です。ただし法人設立費用や社会保険料負担が増えるため、年間所得が800万円を超えたあたりを分岐点に検討するのが現実的です。売却益課税についても、保有5年超で長期譲渡となり税率が下がるため、出口時点の保有期間を意識するだけで納税額を数百万円単位で軽減できるケースがあります。
2025年度の制度と金融環境
まず、2025年度も継続される「エネルギー性能向上計画認定住宅に対する登録免許税の軽減」は、賃貸住宅も対象になりうるため、長期保有を前提とする新築物件では検討価値があります。登録免許税が通常の0.4%から0.2%へ半減するため、2億円の場合で40万円のコスト削減です。さらに、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅認定(セーフティネット制度)を受けると、固定資産税の減額措置が受けられ、自治体によっては3年間半額となる地域もあります。このように、税制優遇を組み合わせれば、実質利回りを0.2〜0.3ポイント引き上げることも難しくありません。
一方で、金融環境は慎重に見極める必要があります。日本銀行は2024年にマイナス金利を解除し、2025年10月時点の長期金利は1.3%前後で推移しています。これに伴い地方銀行の基準金利は引き上げ傾向にあり、変動型ローンの下限は1%台後半に到達しました。つまり今後の追加利上げを想定し、返済比率35%以内の保守的な計画を立てておくことが重要になります。また、物価上昇に伴い建築費も高止まりしているため、リノベーション費用の見積もりは早めに取得し、予算超過を未然に防ぎましょう。
まとめ
本記事では「比較 2億円」を軸に、投資規模の捉え方、融資条件、物件タイプ、税務戦略、そして2025年度制度まで多角的に見てきました。要するに、同じ2億円でも自己資金比率や物件配分、法人化の有無で手取りキャッシュフローは数千万円規模で開きます。今後の金利上昇や人口動向を踏まえ、立地選定と出口戦略を具体化しながら、公的優遇を活用することが成功の近道です。この記事を参考に、まずはシミュレーションを精緻化し、信頼できる金融機関や税理士と連携して、自分だけの最適ポートフォリオを構築してください。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅市場動向調査 2025年版 – https://www.mlit.go.jp
- 日本銀行 長期金利推移データベース – https://www.boj.or.jp
- 日本取引所グループ REIT市場情報 2025年10月 – https://www.jpx.co.jp
- 公益財団法人日本生産性本部「オフィスマーケット調査2025」 – https://www.jpc-net.jp
- 総務省 統計局 人口推計 2025年9月確定値 – https://www.stat.go.jp

