不動産価格が高止まりするなか、「築古物件 収益物件 台東区」というキーワードに興味を持つ人が増えています。都心へのアクセスと観光需要の両方を狙える台東区は、築年数が古くても高い利回りを確保しやすいエリアです。しかし、耐震性や修繕費など不安も多いでしょう。本記事では、築古物件を選ぶ理由から資金計画、リノベーションの勘所まで、初心者でも具体的に行動できるポイントを解説します。読み終えるころには、台東区の築古物件を収益化するための全体像がつかめるはずです。
台東区で築古物件が注目される背景
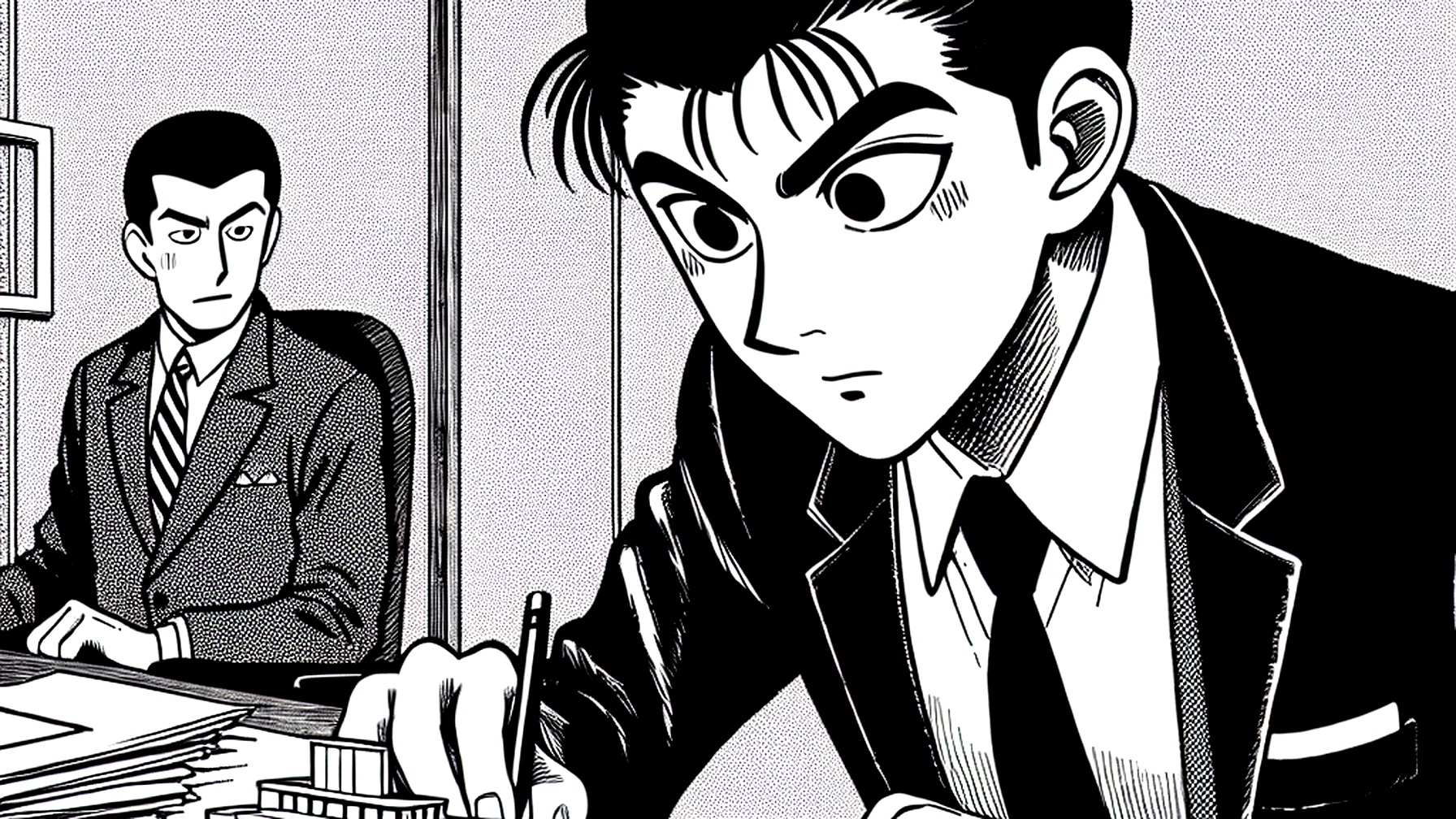
まず押さえておきたいのは、台東区の需要構造です。観光地の浅草や上野を抱える同区は、国内外の旅行者だけでなく、周辺企業に勤めるシングル層の賃貸需要も旺盛です。国土交通省の住宅市場動向調査(2025年版)によると、台東区の中古マンション平均成約価格は23区平均より約12%低い一方、平均賃料は約5%しか下がりません。つまり、表面利回りが出やすい環境が整っているのです。
一方で、同区の分譲マンション築年数中央値は29年と古く、1970年代後半から90年代前半に建てられたストックが多いことも特徴です。築古物件は購入価格が抑えられるため、自己資金が限られる初心者でも参入しやすい利点があります。ただし魅力的な利回りに目を奪われ、修繕計画を軽視すると収支が崩れる点には注意が必要です。
さらに、2025年度の東京都「観光まちづくり戦略」によると、浅草駅周辺の外国人宿泊者数はコロナ禍前比で116%まで回復しています。インバウンド需要が戻ったことで、民泊や中期賃貸といった新しい運用手法も選択肢に入り、築古物件の出口戦略が広がっています。
築古物件に潜むリスクとその対策
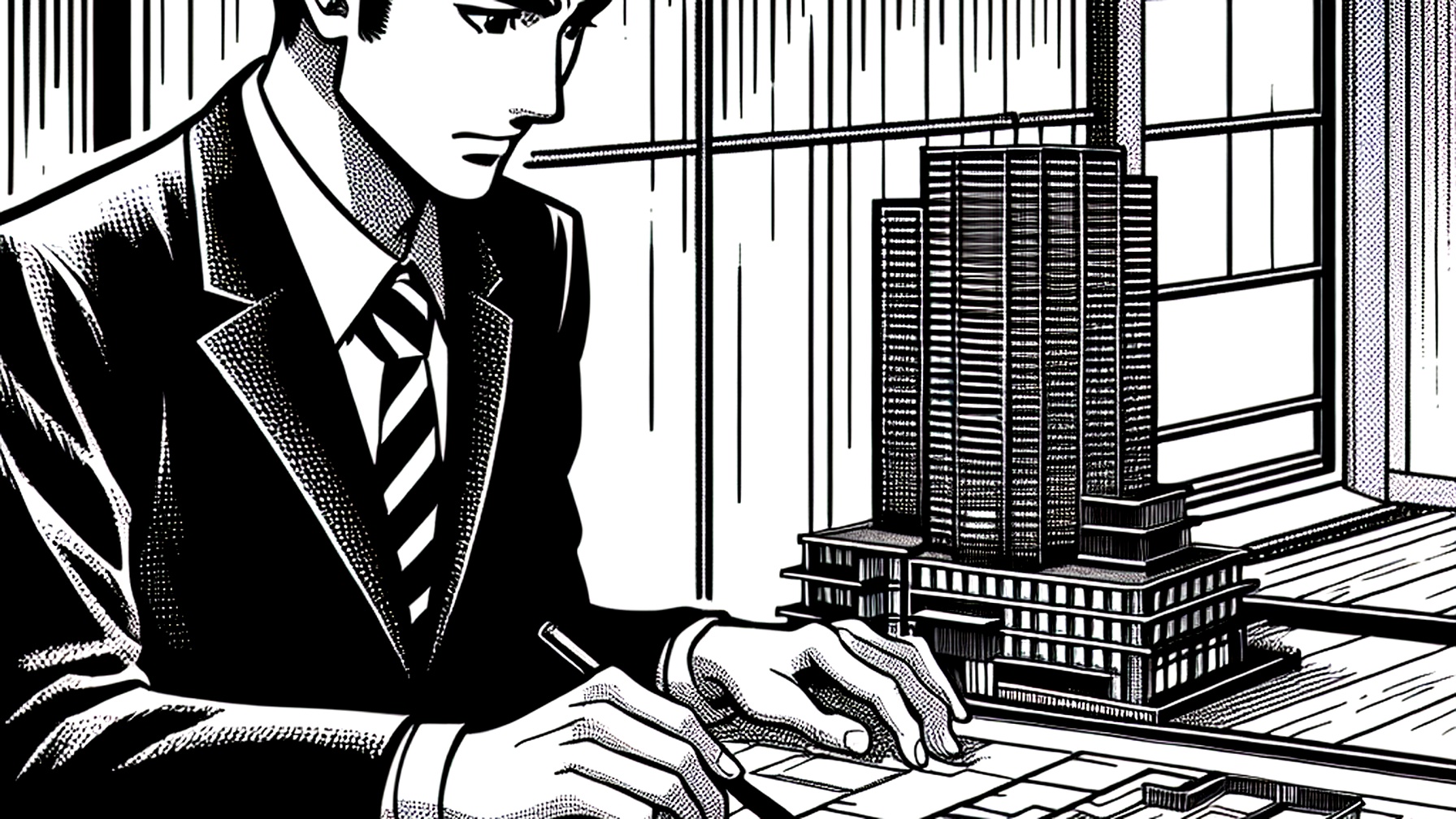
重要なのは、築古物件特有のリスクを正しく認識し、対策コストを事前に計上することです。耐震性、設備の老朽化、共用部の修繕積立不足は代表的な懸念材料ですが、調査と交渉でかなりの部分をコントロールできます。
まず耐震性については、1981年6月の新耐震基準を満たしているかが分岐点です。台東区役所の「建築物耐震診断助成制度」(2025年度)では、旧耐震基準のマンションに対し診断費用の2/3を補助する仕組みがあります。診断結果で補強が必要になった場合、長期修繕計画に組み込むことで、区分所有者全体の合意形成を得やすくなるでしょう。
次に、設備の老朽化は見過ごしがちなコスト要因です。特に配管やガス給湯器は故障すれば即日対応が求められます。購入前に管理組合の総会議事録を確認し、直近の修繕履歴と今後の予定をチェックしておくと、思わぬ出費を回避できます。また、設備更新を前もって実施すると、賃料アップの交渉材料にもなります。
最後に、修繕積立不足への対応策としては、購入時に管理費と積立金を含めた実質利回りを計算することが欠かせません。金融機関によっては、修繕積立不足を理由に融資額を減額するケースもあります。物件選びの段階で長期修繕計画が健全かどうかを確認し、必要なら管理組合に改善提案を行う姿勢が長期の安定運用につながります。
収益力を高めるリノベーション戦略
ポイントは、投資額と家賃上昇幅のバランスを見極めることです。築古物件ではフルリノベーションを想像しがちですが、台東区の賃貸需要を考慮すると部分改修でも十分な競争力を得られるケースが少なくありません。
例えば、2025年上半期の賃貸動向(不動産情報サービス LIFULL HOME’S)では、上野・浅草エリアの単身向け平均賃料は6.9万円ですが、室内洗濯機置場とWi-Fi無料を追加した物件の平均賃料は7.5万円に上昇しています。この差額は年間7.2万円です。低コストで導入できる設備投資なら、3年以内の回収も十分に可能でしょう。
一方、フローリング全面張り替えや水回り総交換を伴う大型リノベは、施工単価が平米あたり10万円を超えることもあります。実は、外国人観光客の短期滞在ニーズをターゲットにする場合、内装よりも家具とインターネット環境の充実が優先される傾向があります。ターゲットを明確にし、費用対効果をシミュレーションしたうえで工事内容を決定することが肝要です。
さらに、東京都の「既存住宅省エネ改修促進事業」(2025年度)は、断熱性能の向上や高効率給湯器の導入で最大80万円の補助を受けられます。省エネ性能を高めると光熱費の削減を前面に出した募集が行え、長期入居につながる点も見逃せません。
購入前に押さえたい資金計画と制度
まず押さえておきたいのは、収支シミュレーションの充実です。築古物件は価格が低めでも、修繕費や金融機関の金利条件によってキャッシュフローが大きく変動します。日本政策金融公庫の「生活衛生貸付」を利用すれば、宿泊業用途のリフォーム資金を年利1.4%程度で調達できる場合があります。融資期間が10年と短いものの、リフォーム後の増収効果と相殺すれば十分に採算が合うケースが多いです。
また、住宅金融支援機構の「フラット35リノベ」は、一定の省エネ基準を満たすことで金利が0.5%引き下げられる制度が2025年度も継続しています。ただし、借入対象が居住用に限定されるため、自身が一定期間居住する「セカンドハウス投資」という形で活用するのが一般的です。自己居住と賃貸併用は管理面で手間が増えますが、初期費用を抑えたい初心者には検討に値します。
さらに、固定資産税の軽減措置にも触れておきましょう。築古マンションは評価額が低いため固定資産税が抑えられることが多いものの、2025年度から東京都は耐震性が不足する物件の税率を段階的に引き上げる方針を示しています。耐震補強工事を行うことで、引き上げを回避できるだけでなく、所得税の投資型減税(10%控除)も受けられるため、長期的にはむしろ得になるケースが見込めます。
運用開始後の管理と出口戦略
実は、築古物件の運用成否は購入後の管理体制で大きく分かれます。台東区は短期滞在者と長期居住者が混在するため、入居者ターゲットに応じた契約形態と管理方法を柔軟に選ぶ必要があります。例えば、マンスリーマンションとして運営する場合、掃除や鍵管理を外部委託すると月額2万円前後のコストがかかる半面、家賃は通常賃貸の1.3〜1.5倍まで上げられるケースが多いです。
さらに、文化財保護条例や景観条例に抵触しないよう、看板やサインの設置位置まで確認しておくと、行政指導による運営停止リスクを下げられます。自治体とのコミュニケーションは手間に感じるかもしれませんが、観光地ならではの規制をクリアすることで、競合が参入しにくいブルーオーシャンを確保できます。
出口戦略としては、複数年の運営実績を示し、表面利回りよりも実質収益率を強調した売却資料を作ると、次の投資家に高値で引き継ぎやすくなります。台東区では築30年以上でも適切に運営された実績付き物件が人気で、国土交通省「不動産価格指数」によれば2022〜2024年の同エリア中古マンション取引価格は年平均3.8%上昇しています。実績を示せれば、市場平均を上回るキャピタルゲインも狙えるでしょう。
まとめ
築古物件 収益物件 台東区という組み合わせは、観光需要と賃貸需要が共存する独自の市場環境に支えられています。耐震診断や修繕積立の確認など手間はかかりますが、その分だけ高い利回りと多様な出口戦略が期待できます。この記事で紹介したように、リスクを洗い出して対策費用を見積もり、補助制度や低利融資を活用すれば初心者でも十分にチャレンジ可能です。まずは対象物件の長期修繕計画と周辺賃料の実態を調べ、具体的なシミュレーションから一歩を踏み出してみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅市場動向調査2025年版 – https://www.mlit.go.jp
- 東京都 観光まちづくり戦略2025 – https://www.metro.tokyo.lg.jp
- 台東区 建築物耐震診断助成制度 – https://www.city.taito.lg.jp
- LIFULL HOME’S 賃貸住宅市場レポート2025上半期 – https://www.homes.co.jp
- 住宅金融支援機構 フラット35リノベ – https://www.flat35.com

