ローンの返済に追われず、家族へ資産を残しながら早期リタイアを目指せたら――そんな理想を抱く読者は少なくありません。実は、アパート経営は相続対策とFIRE(Financial Independence, Retire Early)の双方に効く手段として2025年も注目度が高まっています。本記事では、相続税を抑える仕組みから安定収益を生む運営ノウハウ、さらに最新の補助制度までを体系的に解説します。初めての方でも具体的な行動がイメージできるよう、データと実例を交えてご案内しますので、最後までお付き合いください。
アパート経営がFIRE志向者に支持される理由
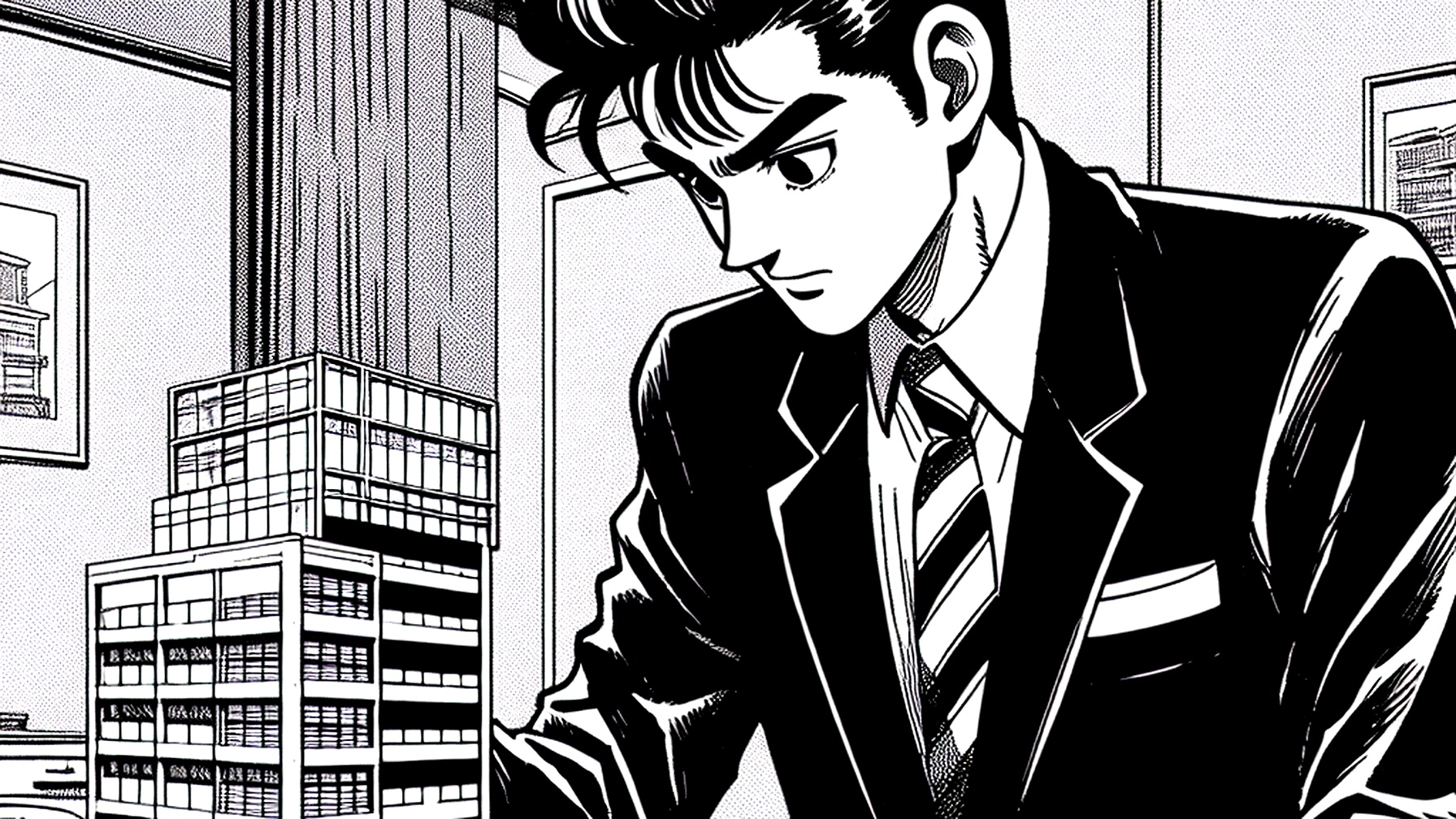
重要なのは、家賃収入が生活費を上回る状態を早期に作れるかどうかです。給与だけに頼ると多額の金融資産を築くまでに時間がかかりますが、アパート経営ならレバレッジ効果で資産形成のスピードを高められます。自己資金の2倍、3倍の物件を購入し、家賃からローン返済と経費を差し引いた残りがプラスになれば、その分だけ退職時期を早められるからです。
一方で、株式配当と比べたときの強みは減価償却費という非資金支出を経費計上できる点にあります。帳簿上の利益を抑えられるため所得税・住民税を圧縮でき、可処分所得が増える仕組みです。国税庁の「租税特別措置統計」によると、年間家賃収入600万円規模の個人オーナーでも、適切な減価償却により課税所得を200万円前後まで下げられるケースが報告されています。
また、国土交通省住宅統計が示す2025年8月の全国アパート空室率は21.2%で前年より0.3ポイント改善しました。空室リスクは依然として無視できませんが、物件選定と運営次第で安定収益を確保できる余地は十分あると言えます。つまり、リスクを可視化しコントロールできれば、アパート経営はFIREを目指す人にとって実用性の高い手段になるのです。
相続対策として有効な仕組みと税制
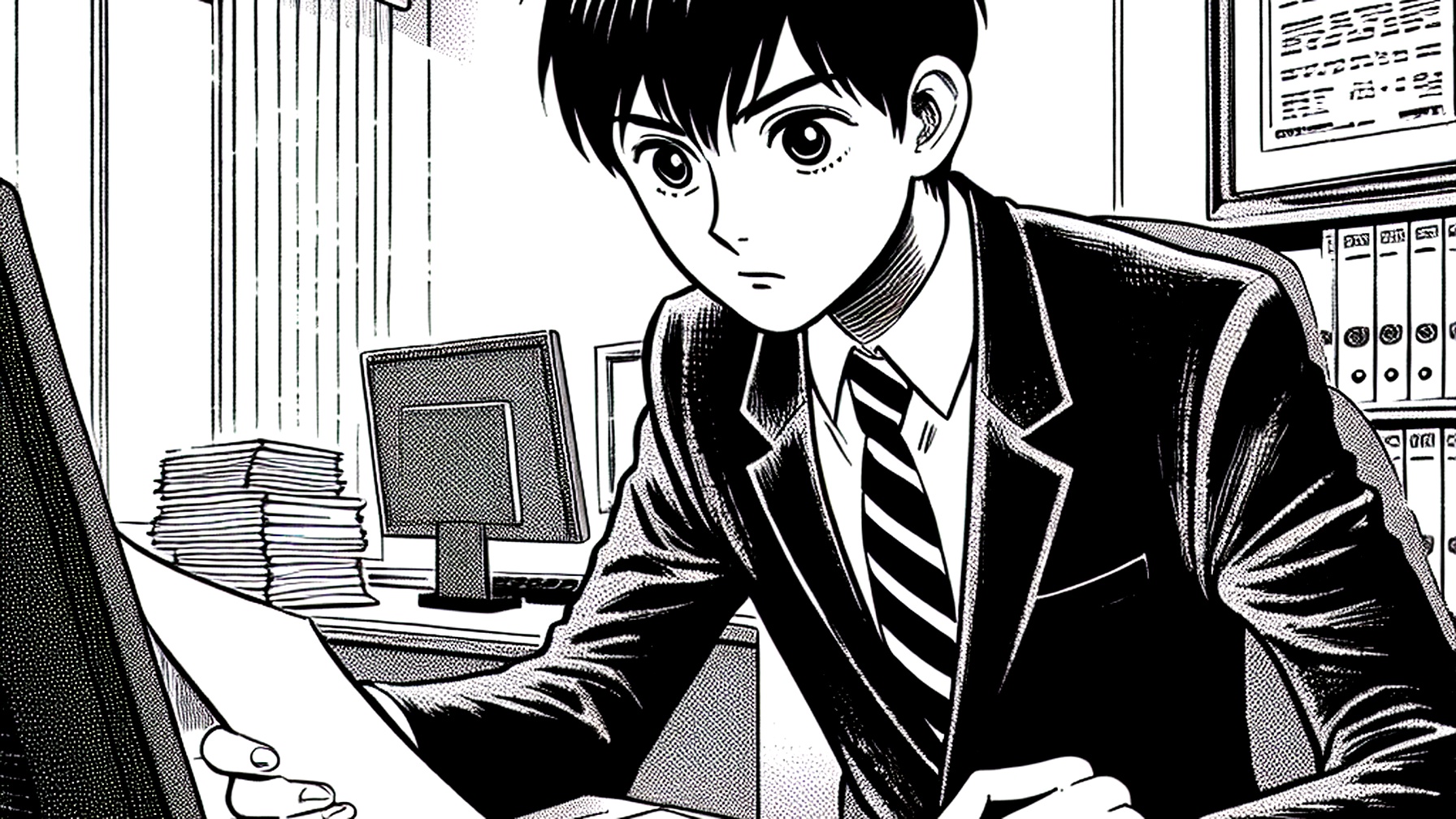
まず押さえておきたいのは「貸家建付地(かしやたてつけち)」という評価方法です。土地と建物を賃貸用として保有すると、相続税評価額が更地より約20〜30%低く計算されるため、納税額を大幅に下げられます。さらに建物自体も固定資産税評価額で算定されるため、市場価格の60〜70%程度まで圧縮される点がメリットです。
加えて、2025年度も利用できる「小規模宅地等の特例」は、一定要件を満たせば貸付事業用宅地として最大200平方メートルまで50%評価減が適用されます。期限の定めがない恒久措置ですが、適用には3年以上の事業継続が原則となるため、早めの計画が欠かせません。
一方で、相続開始前3年以内に取得した土地は評価減の対象外になる場合があります。つまり、節税を急ぐあまり直前に駆け込み購入すると逆効果になりかねません。税理士と連携しながら、贈与・生命保険・法人化など他の対策と組み合わせることで、より効果的なプランを設計できます。
立地選びと空室率データの読み方
ポイントは「将来の人口流入が見込めるか」という視点で統計を確認することです。国立社会保障・人口問題研究所の推計では、2025〜2035年に20〜34歳人口が微増する政令市の中心区が複数存在します。こうしたエリアはワンルームアパートの賃貸需要が底堅く、家賃下落リスクを抑えやすいと言えます。
しかし、同じ市内でも駅徒歩15分を超える地区では空室率が10ポイント以上高くなる例も珍しくありません。総務省「住宅・土地統計調査」の地域別データを照らし合わせると、地方中心部よりも郊外住宅地のほうが空室率が高い傾向が続いています。つまり、エリア選定では市区町村単位ではなく、最寄り駅と周辺施設まで踏み込んだ比較が欠かせません。
具体例として、仙台市青葉区では2019年〜2024年にかけて学生数が1割増えた影響で単身者向け住宅需要が拡大しました。この結果、同区の空室率は全国平均を約5ポイント下回っています。データを裏付けにした立地判断が、家賃の下落を防ぎキャッシュフローを安定させるカギとなるのです。
キャッシュフロー管理で失敗を防ぐ
実は、家賃収入が同程度でもCF(キャッシュフロー)が赤字に転落する物件と黒字を維持できる物件の差は、経費構造にあります。最も変動が大きいのは修繕費で、築20年を超えると年間家賃収入の15%前後に達するケースがあります。したがって、修繕積立金を早期に積み上げることがリスク緩和の第一歩です。
一方で、金融機関の融資条件もCFに直結します。金利が1.2%と1.7%では、1億円を35年返済した場合の総支払額が約1000万円差となります。日本銀行が2025年4月に示した短期金利指針では「緩やかな利上げ局面」が示唆されています。固定と変動のどちらを選ぶかは、返済期間や自己資金比率に応じて検討すべきです。
さらに、家賃下落を前提にしたシミュレーションを作ることが重要です。例えば、家賃月額が2%下がり空室率が5%悪化しても返済比率が70%以下なら、自己資金で十分に吸収できます。収支計画を悲観的に見積もることで、想定外の出費に耐えられるポートフォリオが完成します。
2025年度の補助制度と金融環境のポイント
まず、賃貸住宅の省エネ性能向上を支援する「2025年度 先進的省エネ賃貸改修補助金」は、内窓設置や断熱材追加工事費の3分の1(上限300万円)が補助されます。家賃競争力を高めつつ修繕費を圧縮できるため、築古アパートを再生して利回りを向上させたい投資家に好相性です。
また、住宅金融支援機構の「賃貸住宅エコリノベ融資」は2025年度も継続予定で、金利優遇が年0.3%引き下げられます。省エネ改修と同時に耐震性を高める計画を提出すれば、さらに0.1%の追加優遇が受けられます。金融機関の一般融資よりも金利が低く、長期固定が組みやすい点が強みです。
一方で、地銀や信金が取り扱うアパートローンは、物件所在地が営業圏外だと融資が難しい傾向が続いています。オンライン審査で全国対応するノンバンクも選択肢に入りますが、金利が高めになるため総返済額をシビアに比較する必要があります。つまり、補助金と融資優遇を組み合わせ、投資効率を高める戦略が2025年の王道と言えるでしょう。
まとめ
ここまで、アパート経営が相続対策とFIREを両立できる理由から、立地選定、キャッシュフロー管理、2025年度の補助制度までを解説しました。空室率や税制のデータを丁寧に読み解き、修繕積立や金利交渉を早めに進めれば、安定した家賃収入を得ながら資産評価額を引き下げられます。次の一歩として、候補エリアの人口動態を調べ、税理士と資金計画を共有することをおすすめします。行動を積み重ねることで、相続対策とFIREの実現は着実に近づきます。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計調査(2025年8月速報値) – https://www.mlit.go.jp
- 国立社会保障・人口問題研究所 人口推計 – https://www.ipss.go.jp
- 国税庁 租税特別措置統計(令和6年度) – https://www.nta.go.jp
- 日本銀行 金融政策決定会合議事要旨(2025年4月) – https://www.boj.or.jp
- 住宅金融支援機構 賃貸住宅エコリノベ融資制度概要(2025年度) – https://www.jhf.go.jp
- 国土交通省 先進的省エネ賃貸改修補助金 事業概要(2025年度) – https://www.mlit.go.jp/housing

