不動産投資に興味はあるものの、現物のマンション購入には手間もリスクも大きいと感じていませんか。実は、株式と同じ感覚で購入できる「REIT(不動産投資信託)」なら、5000万円というまとまった資金を効率的に分散投資へ振り向けられます。本記事では、初心者がつまずきやすいポイントに寄り添いながら、REITの魅力とリスク、具体的な始め方、さらには運用中の進め方までを丁寧に解説します。読み終えたとき、あなたは5000万円をREITでどう運用するかのロードマップを描けるはずです。
REITの基礎を押さえる
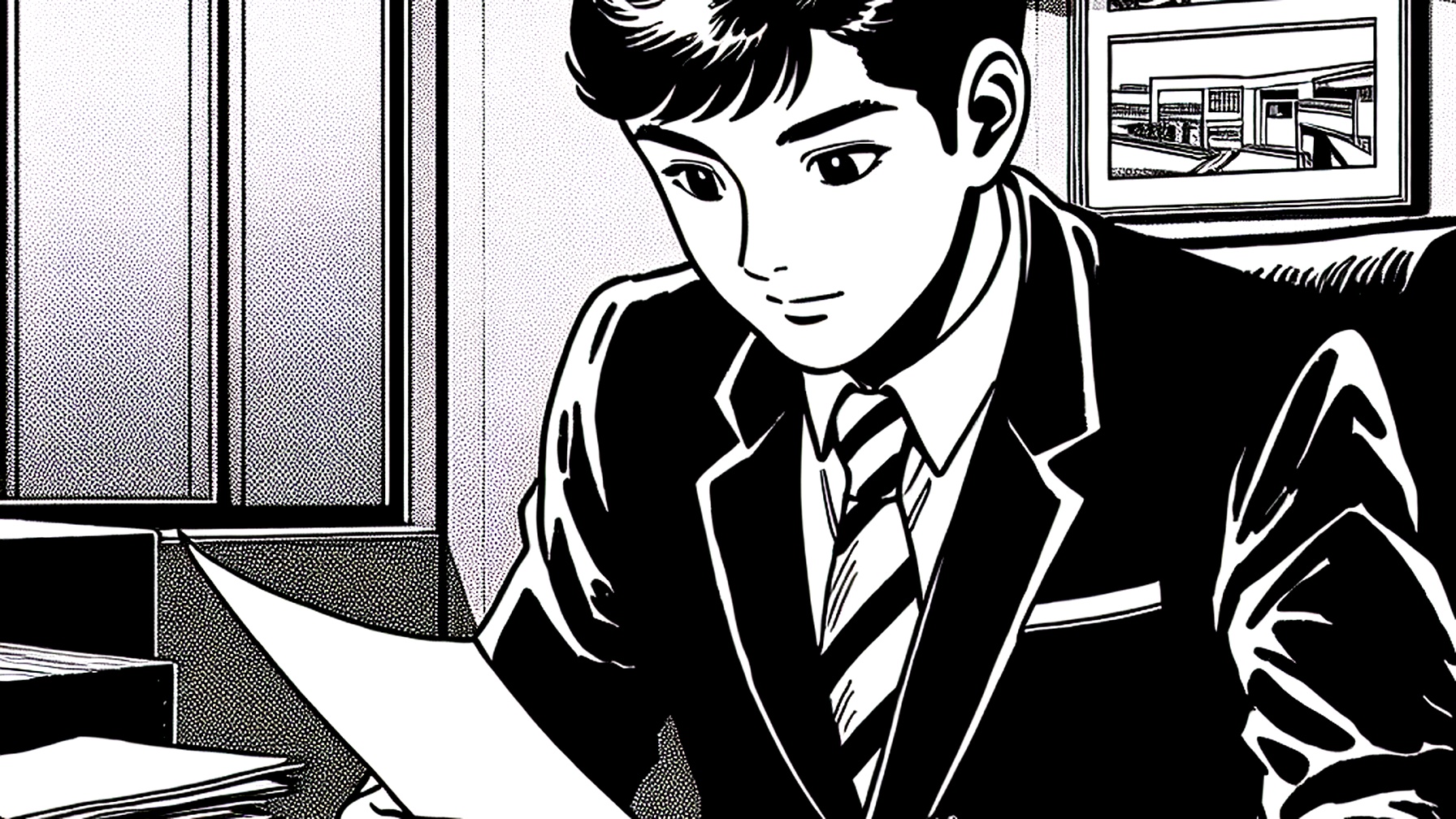
まず押さえておきたいのは、REITが株式市場に上場している投資信託だという点です。投資家から集めた資金でオフィスビルや商業施設、物流倉庫などを取得し、賃料収入や物件売却益を配当として還元します。金融庁の2025年9月時点のデータによると、東証REIT指数の平均分配利回りはおよそ3.9%で、日本株全体の配当利回りをやや上回る水準です。
次に、REITの価格変動要因を理解しましょう。賃料市況や金利、物件評価額が代表的ですが、上場銘柄数が60を超える現在、用途や地域による差も無視できません。例えば、物流特化型はEC需要の拡大を背景に安定的な分配金を維持してきました。一方、ホテル特化型は新型感染症の影響を受けた後、インバウンド回復局面で値動きが大きくなる傾向があります。
最後に、税制面の特徴です。分配金には20.315%の源泉分離課税が適用され、配当控除の対象外となります。しかしNISA口座を活用すれば、年間360万円(成長投資枠240万円+つみたて投資枠120万円)の範囲で非課税投資が可能です。5000万円を全額非課税枠に収めるのは現実的ではありませんが、長期で見れば節税インパクトは無視できません。
5000万円をどう配分するか
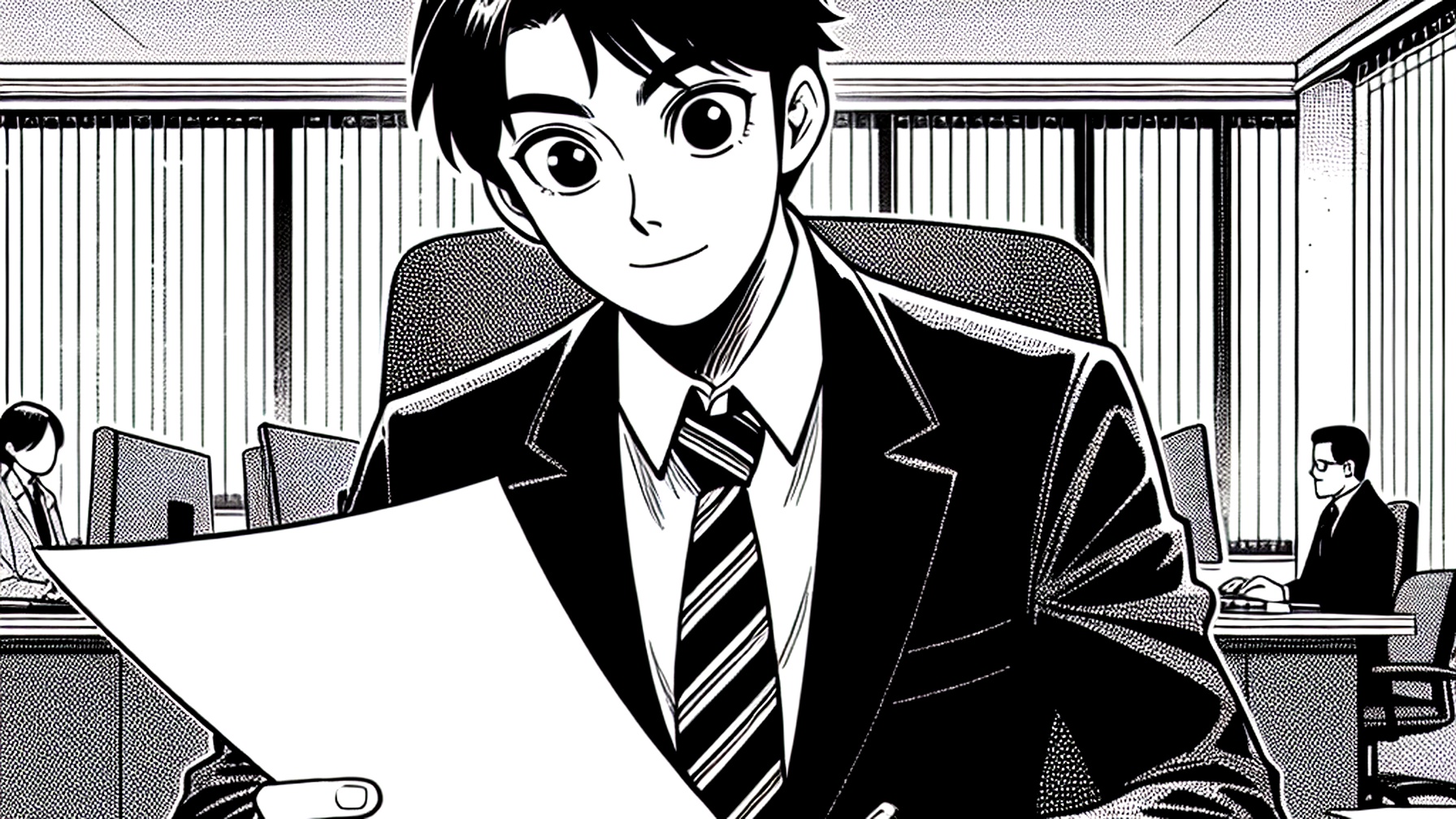
重要なのは、5000万円を一度に投入するのではなく、時間と用途で分散させる戦略です。目安として、まず2000万円を3〜5銘柄に分けて買付し、残りは相場変動に備えた待機資金として残しておくと安心です。東京証券取引所の統計では、東証REIT指数は過去10年間で年率約12%の値幅を経験しており、一括投資は短期の価格変動リスクを高めます。
具体例として、オフィス系30%、物流系30%、住宅系20%、インフラ投資法人10%、残り10%をホテルや商業施設といった景気敏感型に配分すると、収益源と地域をバランス良く組み合わせられます。こうしたモデルポートフォリオはあくまで出発点ですが、賃料市況や金利動向を見ながら、毎年リバランスすることで中長期のリスクを抑えられます。
また、ドルコスト平均法を応用し、半年ごとに1000万円ずつ追加投資する方法も考えられます。これにより、急激な金利上昇や地政学リスクがREIT市場を揺らした際にも、取得価格を平準化できるメリットがあります。つまり、資金量が大きいほど“投下タイミングの分散”は効果を発揮するのです。
口座開設から購入までのステップ
ポイントは、証券会社選びと取引コストの最適化です。ネット証券の多くはREITの売買手数料が無料ないし定額制になっており、対面証券よりもコスト面で有利になるケースが目立ちます。加えて、取引ツールで賃料成長率やLTV(借入比率)を簡単に比較できる機能が付帯しているかを確認しましょう。
口座開設後は、以下の流れで注文を出します。
- TSEコードを入力し、指値もしくは成行を選択
- 購入単位は1口からだが、1口価格は10万〜25万円が中心
- 約定後、分配金の受取口座を確認し、NISA枠を使用する場合は注文前に設定
このステップに要する時間は最短で3営業日ほどです。まずは試しに100万円程度から発注し、約定・受渡・分配金受領の流れを体感すると良いでしょう。経験しておくことで、5000万円の本格投資時に心理的負担が大きく下がります。
運用中に注意すべきリスクと対処法
実は、REITの価格変動リスクだけでなく、金利上昇リスクも見落とされがちです。REITは不動産購入のために借入を行うため、市中金利の上昇は分配金の圧迫要因になります。日本銀行が2025年4月にマイナス金利政策を解除した後、長期金利は1%台前半で推移していますが、米欧の金融政策次第ではさらなる上昇も想定されます。
また、物件の含み損失にも注意が必要です。鑑定評価額が下落するとNAV(純資産価値)が縮小し、市場価格がそれを先取りして下落する場合があります。2023〜2024年にかけて都心オフィスの空室率は7%前後で横ばいですが、2025年7月の国交省データでは地方中核都市のオフィス空室率が10%を超える地点もあると報告されています。したがって、物件立地や用途の偏りが大きい銘柄は慎重に見極める必要があります。
対処法としては、LTVが50%未満かつ平均借入期間が5年以上の銘柄を優先することが有効です。借入比率が低く返済スケジュールに余裕があれば、金利上昇時の影響を抑えられます。具体的な指標を四半期決算短信で確認し、数値の推移に異変があればポートフォリオの組み替えを検討しましょう。
5000万円を守り育てる進め方
まず押さえておきたいのは、分配金を再投資する「複利効果」です。年間利回り3.9%で得た分配金を再投資すると、10年後の資産規模は約1.47倍に膨らみます。加えて、NISA枠に収まる分配金部分を非課税化すれば、実効利回りを押し上げることができます。
一方で、所得税の課税所得が900万円を超える投資家は、損益通算にも目を向けましょう。REITの売却損は株式と通算可能なため、価格調整局面で一部を損切りし、他の株式の配当や売却益と相殺することで税負担を軽減できます。つまり、ポートフォリオ全体での最適化が鍵になります。
さらに、ファンダメンタルズの変化を定点観測する体制が欠かせません。東証や日本不動産研究所が公表する賃料指数、内閣府の景気動向指数などを月次でチェックし、物件用途ごとのトレンドを把握しましょう。数字を追う習慣が、感情に左右されない投資判断につながります。
まとめ
結論として、5000万円という資金規模だからこそ、時間・用途・銘柄を分散させるREIT投資が有効だといえます。REITの基礎知識を押さえ、手数料の低い証券口座で少額から試運転し、金利や賃料市況の変化に応じてポートフォリオを調整する仕組みを整えれば、安定したキャッシュフローを確保しながら資産成長を狙えます。今日からできる行動として、まずは口座開設とモデルポートフォリオの作成に着手し、資産運用の第一歩を踏み出してみてください。
参考文献・出典
- 金融庁「金融レポート2025」 – https://www.fsa.go.jp
- 東京証券取引所「上場REITデータブック2025年9月版」 – https://www.jpx.co.jp
- 日本銀行「短観 2025年9月調査」 – https://www.boj.or.jp
- 国土交通省「不動産市場動向2025年7月号」 – https://www.mlit.go.jp
- 日本不動産研究所「不動産投資家調査 2025年上期」 – https://www.reinet.or.jp

