家賃収入を得られる不動産投資に興味はあるものの、「物件を選んで管理するのは大変そう」と感じている人は多いはずです。そこで手軽な選択肢として注目されるのが上場不動産投資信託、いわゆるREITです。しかし、投資家がメリットばかりに目を向けると後悔につながるケースも珍しくありません。本記事ではREIT特有のデメリットを中心に、2025年10月時点の市場環境を交えて分かりやすく解説します。読み終えたころにはリスクを冷静に見極め、自分に合った投資判断ができるようになるでしょう。
REITとは何か簡潔に理解する
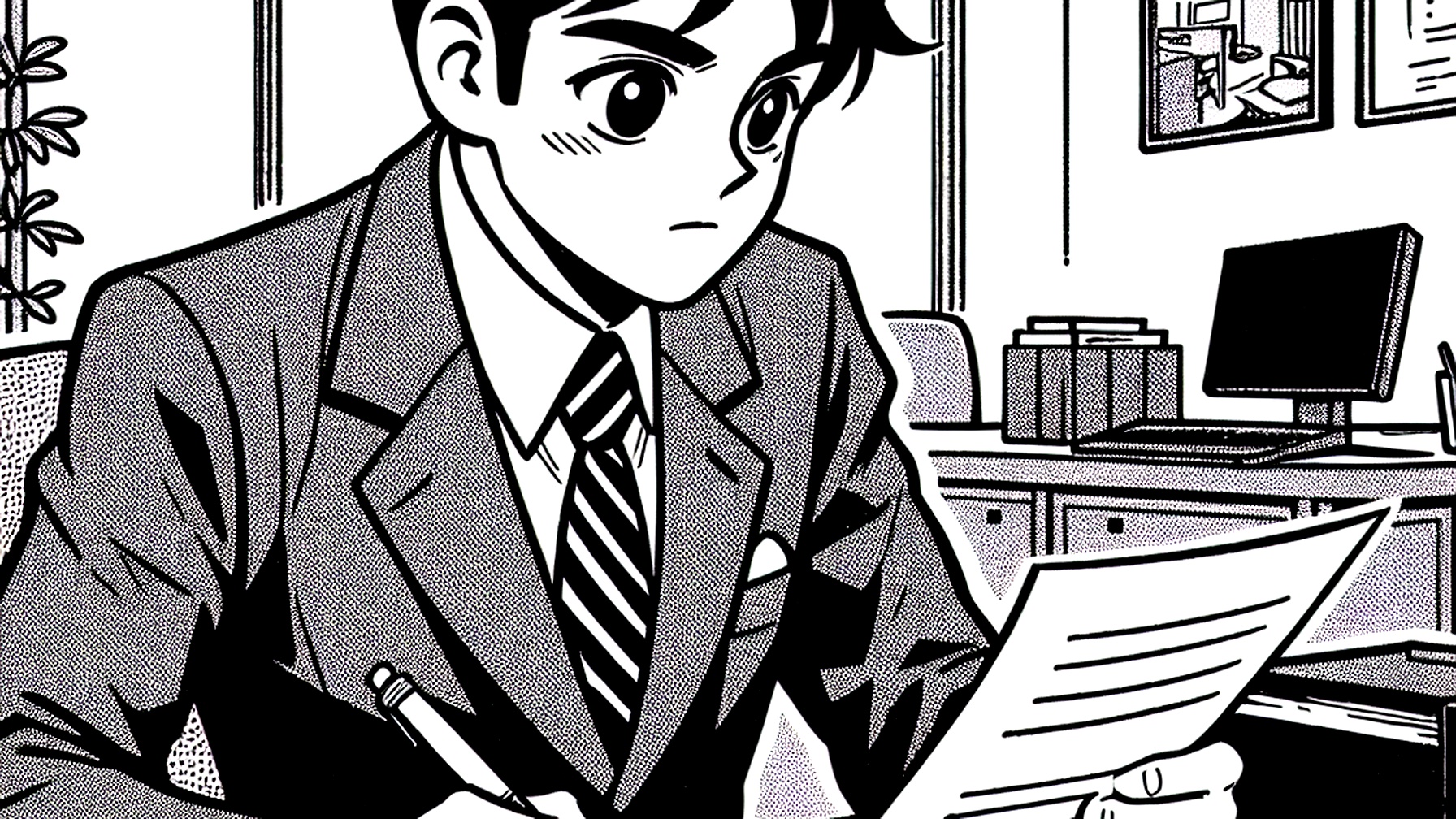
まず押さえておきたいのは、REIT(Real Estate Investment Trust)が多数の投資家から集めた資金で複数の不動産を保有し、賃料収入や売却益を分配する仕組みだという点です。東京証券取引所に上場しているため株式と同様に売買でき、最低投資額が10万円前後と手軽です。
REITは単一物件への直接投資と違い、オフィス、住宅、物流施設など複数用途に分散投資できる利点があります。また、投資法人は法律上、利益の90%超を分配すると法人税が実質免除されるため、配当利回り(分配金利回り)が概ね3〜4%で推移しています。日本取引所グループの統計によると、2025年9月末時点でJ-REITの時価総額は約18兆円に達し、個人投資家の保有比率は21%です。
一方で「小口化」「分散」「高利回り」という魅力の裏には見落とされやすいリスクが潜んでいます。次章以降で具体的なデメリットを確認し、対応策を考えていきましょう。
分配金の変動リスク
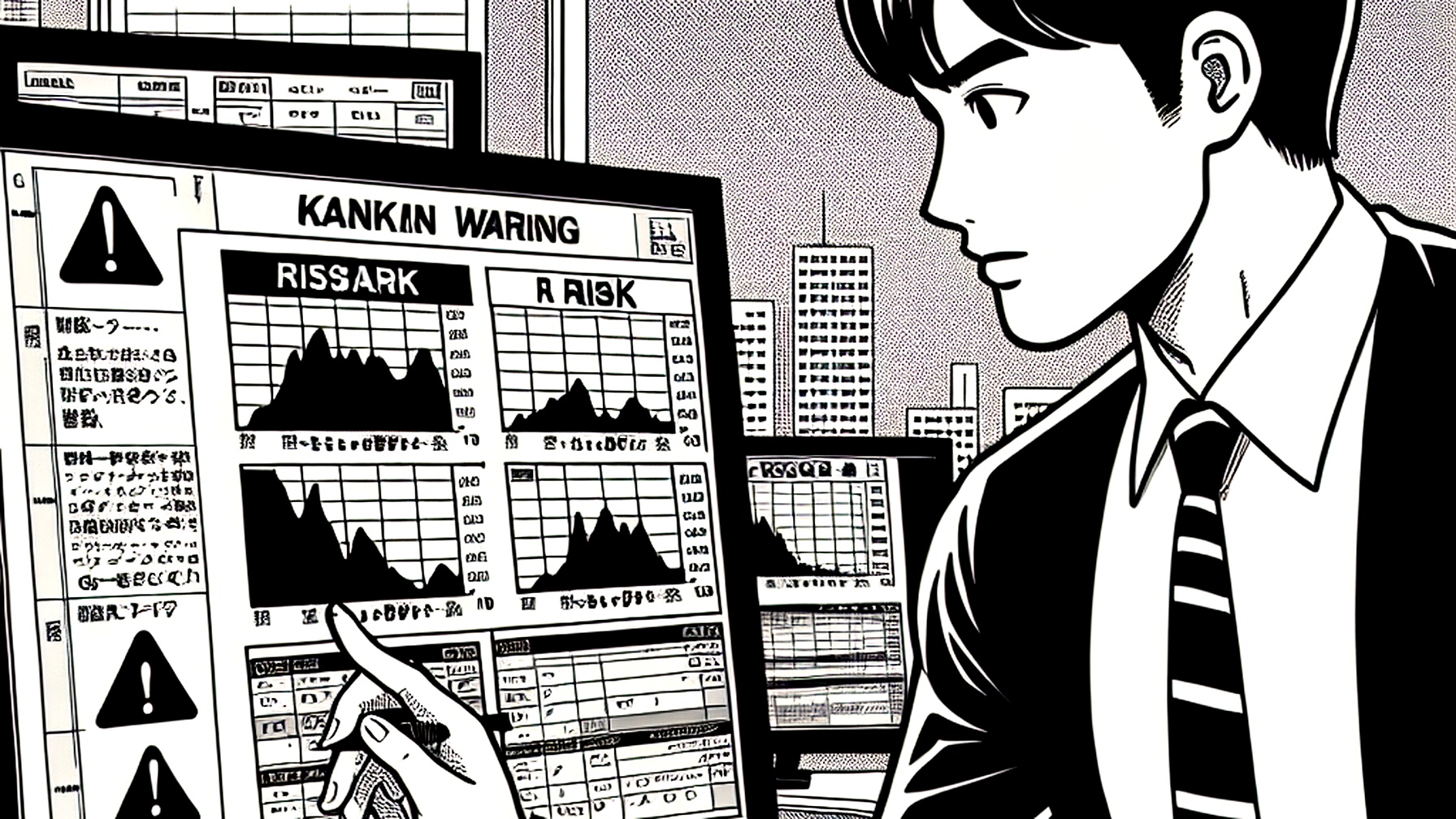
重要なのは、REITの分配金が確定利息ではなく事業収益に連動する点です。したがって、市況によって上下し、配当性向が法律で保証されているわけではありません。
たとえばオフィス系REITでは空室率の変動が直接影響します。東京都心5区の平均空室率は、2023年には5%台まで改善しましたが、2025年上期には新規供給増加の影響で再び7%台に跳ね上がりました。この2%の差が年間1口あたり分配金を数百円押し下げる要因となり、投資家の想定利回りを狂わせます。
さらに、景気後退局面では賃料の引き下げ交渉が増えます。物流施設や住宅を主体とするREITは比較的安定すると言われますが、総務省「住宅・土地統計調査」によると地方部の世帯数は2025年も減少傾向が続き、地方住宅主体のREITには逆風が吹きやすい状況です。
この変動を緩和する方法として、異なる用途に投資する複数のREITを組み合わせるポートフォリオ戦略が有効です。また、上場企業の決算短信と同様に、REITの運用報告書や物件一覧を定期的に確認し、賃料改定状況を把握する習慣を持つことが大切です。
物件選定を自分でコントロールできない点
ポイントは、投資家が物件を選ぶ自由度を失うことにあります。直接投資なら「再開発が進む駅前の築浅マンションを買う」といった戦略を練れますが、REITでは運用会社がすべてを決定します。
具体例として、ホテル主体のREITがアジアからのインバウンド需要を見込んで多額の追加投資を行った直後、想定外の感染症再拡大で稼働率が急落したケースがあります。投資家はその時点で売却するしか選択肢がなく、長期保有を貫くと分配金低下の影響を受けました。
また、REITは投資法人傘下での物件入替えを活発に行いますが、売却益が継続的に得られるかは相場次第です。国土交通省の「不動産価格指数」によれば、2024年末の商業地指数は前年同月比で1.1%下落に転じました。下落局面での物件売却は分配金の減少と資産規模の縮小を同時に招くため、投資家のリスクが高まります。
この制約に対処するには、REIT選定時に「運用方針の明確さ」や「スポンサー企業の資金力」を重視するとともに、月次レポートで取得予定・売却予定のパイプラインをチェックし、想定外の方針転換が起きた際は速やかにポジションを見直すことが欠かせません。
借入金比率と金利上昇の影響
実は、REITの魅力的な利回りの裏にはレバレッジ効果があります。借入金(有利子負債)を利用して自己資本利益率を高めているためです。
J-REIT全体の平均LTV(Loan to Value:総資産に対する借入金比率)は2025年6月時点で約47%です。日銀がマイナス金利政策を段階的に解除し、長期金利が1%台で推移する現在、借入コストは過去最低水準を脱しつつあります。仮に平均調達金利が0.3%から0.8%に上昇すると、金融費用は単純計算で2.6倍に増えます。分配金が同程度増加しない限り、利回りが圧迫されるのは避けられません。
さらに注意したいのが「借換えリスク」です。REITの借入期間は5年前後のローンが多く、2026〜2028年に大型返済が集中します。その時点で金利が高止まりしていれば、想定以上に分配金が目減りする可能性があります。
対策としては、各REITのIR資料に記載されている「借入期間の平均残存年数」「固定金利比率」を確認し、短期比率が高すぎる銘柄への集中投資を避けることが重要です。また、分配金利回りだけで選ぶのではなく、「金利1%上昇時のEPS感応度」を公表しているREITを優先的に検討すると、リスクを数値で把握しやすくなります。
税制と手数料が収益を削る仕組み
まず、投資家が見落としがちなのは税引き後利回りです。REITの分配金は「配当所得」として課税され、2025年度の税率は所得税15.315%、住民税5%、合計20.315%が源泉徴収されます。NISAでの非課税投資枠は拡充されたものの、年間360万円の成長投資枠では高額投資家ほどカバーしきれません。
加えて売買時のコストとして証券会社の委託手数料が発生します。近年はゼロ円のネット証券も増えましたが、信託報酬(資産運用報酬)は年率0.3〜0.8%程度かかり、基準価格に日々反映されるため気づきにくいコストになります。
分配金再投資を繰り返す長期戦略では、複利効果よりもコスト累積が上回るケースがあります。金融庁の「資産形成シミュレーション」によると、年率4%のリターンでも信託報酬0.8%を差し引くと、20年後の運用成果は約15%目減りします。つまり、コスト管理がリターンの鍵を握るわけです。
この課題への対応策として、NISA枠を最大限活用しつつ、同一セクターであれば信託報酬の低い銘柄を優先することが基本です。また、3年以上分配金利回りが4%を下回る場合は高コスト体質でないか確認し、別の資産クラスとの比較を怠らない姿勢が求められます。
まとめ
REITは小口で分散された不動産投資を可能にする一方、分配金の変動、物件選定権の欠如、金利上昇の影響、そして税制・手数料といった複数のデメリットを内包しています。これらは単独で作用するのではなく、市況次第で複合的に投資家のリターンを揺さぶる点が厄介です。
それでも、情報開示が進んでいるREITはリスクを「見える化」しやすい資産クラスでもあります。IR資料を丹念に読み、用途や金利構成が異なる複数銘柄を組み合わせれば、リスクはある程度コントロール可能です。本記事で紹介したポイントを参考に、自分の投資目的と許容リスクを照らし合わせ、納得のいくポートフォリオを構築していきましょう。
参考文献・出典
- 日本取引所グループ(JPX) – https://www.jpx.co.jp
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 統計局 住宅・土地統計調査 – https://www.stat.go.jp
- 金融庁 資産形成シミュレーション – https://www.fsa.go.jp
- 不動産証券化協会(ARES) – https://www.ares.or.jp

