相続した空き家やマンションをどうすれば良いのか、管理費や固定資産税だけが重なり頭を抱えている方は少なくありません。売却には時間と手数料がかかり、自己運用では賃貸管理の手間がのしかかります。そこで近年注目されているのが「不動産クラウドファンディング」です。専門事業者に運用を委ねつつ、少額から分散投資できるため、相続物件の新しい活用手段として急速に広がっています。本記事では仕組みの基本から、2025年度の税制や制度を踏まえた具体的なポイントまで網羅的に解説します。読み終える頃には、自分に合ったサービス選びと実行手順がイメージできるようになるはずです。
不動産クラウドファンディングの仕組みを押さえる
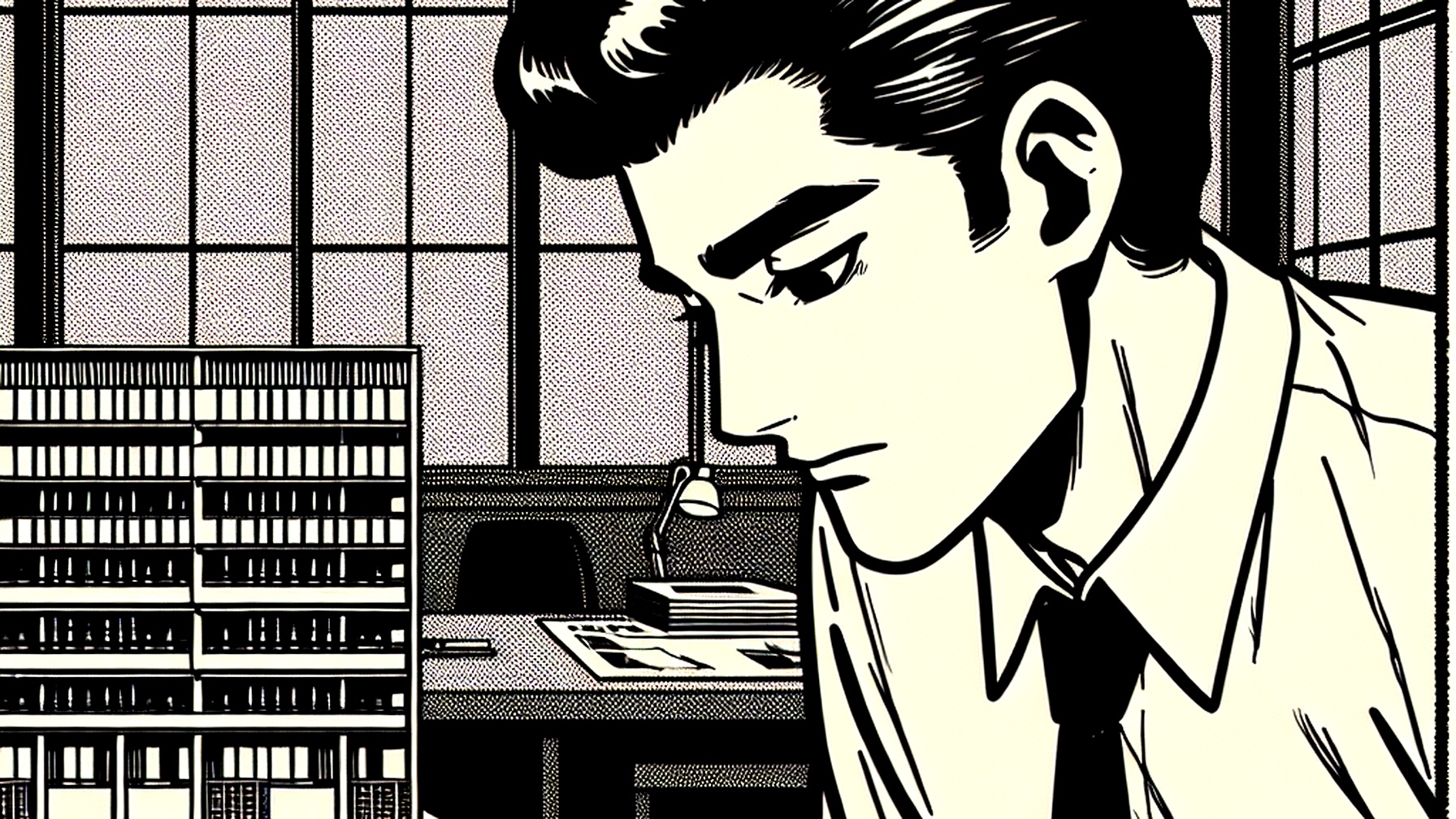
まず押さえておきたいのは、クラウドファンディングが「多数の投資家から小口資金を集め、不動産事業を共同で行う仕組み」だという点です。投資家は一口1万円程度から参加でき、運用益や賃料収入が分配金として戻ってきます。金融商品取引法上は「匿名組合契約」または「任意組合契約」に分類され、元本保証はありませんが、運用会社が物件の選定・運営・売却まで担うため、オーナー業務は不要です。
実は、この仕組みは相続人が保有する物件にも応用できます。物件を運用会社へ現物出資する「アセット型」や、物件を売却して得た資金を再投資する「キャピタル型」が代表例です。国土交通省の2025年版宅地建物市場動向調査によると、クラウドファンディングを利用した不動産取引額は前年比26%増と右肩上がりで、特に空き家再生案件が全体の16%を占めています。これは相続物件の活用ニーズと合致しており、需要の高さがうかがえます。
一方で、元本割れや運用会社の倒産リスクがゼロではない点は見逃せません。金融庁のガイドラインに従い、各社は分別管理や信託保全を整備していますが、契約書で保全スキームを確認することが欠かせません。つまり、仕組みを理解し、リスクを見極めたうえで利用することが最初の関門となります。
相続物件をクラウドファンディングに組み込むメリット
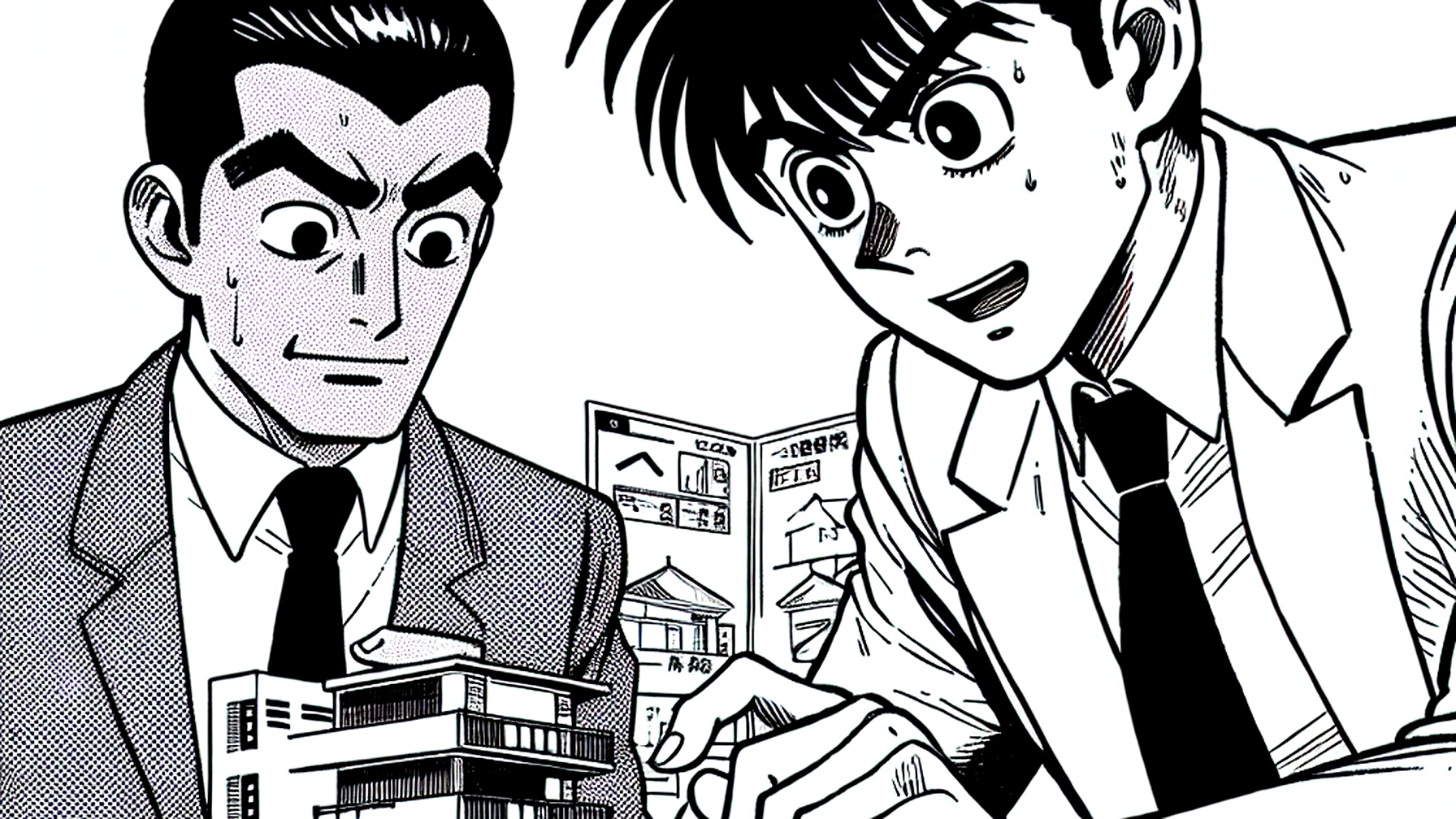
ポイントは、相続特有のコストと手間を大幅に減らせることです。例えば管理委託や原状回復費用を自ら負担せずに済み、毎月の収支が予測しやすい利点があります。総務省「住宅・土地統計調査2024」によると、空き家を所有する世帯の維持費は年平均19万円に上り、固定資産税・都市計画税が約40%、修繕費が約30%を占めます。クラウドファンディングで運用を委託すれば、これら維持費の多くがファンド側負担となるため、キャッシュフローが大きく改善します。
さらに、複数物件へ分散投資できるため、単一の相続物件に起因する空室リスクを薄められます。相続人が複数いるケースでは、共有名義の解消手段としても有効です。物件をファンドに現物出資して持ち分を投資口に換えることで、相続人ごとに口数を分配でき、いわゆる“争族”を回避しやすくなります。
加えて、2025年度の税制では「小規模宅地等の特例」が継続適用されており、貸付事業用宅地の評価減(50%)を受けられれば、相続税負担を抑えながら現金化が図れます。評価減後に売却代金をクラウドファンディングへ回すという二段階のスキームも実務上増えています。このように節税とキャッシュフロー改善を両立できる点が最大の魅力です。
リスクを減らす案件選びと運用のコツ
重要なのは、利回りの数字だけでなく、事業計画の前提を読み解く力です。予定利回り8%前後の案件でも、空室率や想定売却価格が楽観的なら実現性は低くなります。国土交通省「不動産価格指数(2025年8月公表)」では、地方中核都市の中古マンション価格が前年同月比▲2.1%でした。にもかかわらず売却益を主な収益源とする案件は慎重に見る必要があります。
また、分配スケジュールと税引後の手取りにも注目しましょう。分配が半年ごとの場合、キャッシュを手にできない期間が長く、突発的な支出に対応しにくくなります。さらに、雑所得扱いで総合課税になるため、高所得者は実効利回りが下がる点も忘れがちです。
リスク対策としては、①信託保全が整っているか、②運用会社が直近3期連続黒字か、③募集前に物件デューデリジェンス(調査)が行われているか、の三つを最低限確認してください。これらは金融庁の登録業者情報や決算公告で閲覧できます。加えて、ファンド総額の3〜5%を自己資金として残す「余裕資金ルール」を設けることで、最悪期でも家計を守れます。
2025年度制度を踏まえたおすすめ運用スタイル
まず押さえておきたいのは、2025年4月施行の相続登記義務化により、相続開始から3年以内に登記を済ませないと10万円以下の過料が科される点です。この手続きをクラウドファンディングへの現物出資と同時進行で行えば、書類作成を1回に集約でき、司法書士報酬の節約につながります。
また、環境性能に優れたリノベーション物件へ投資すると「2025年度 省エネ改修促進税制」により、一部設備費が30%税額控除の対象になります(法人出資の場合、上限200万円・2026年3月契約まで)。個人投資家でも分配金の源泉税を軽減する効果が期待でき、ESG投資の流れに乗った案件は将来の売却キャピタルも狙えます。
さらに、同年度の「NISA成長投資枠」は年間360万円まで投資益非課税です。上場不動産投資信託(J-REIT)に比べ、非上場クラファンは対象外ですが、相続物件を売却して得た資金の一部をNISA、残りをクラファンへ振り分けると課税最適化が図れます。つまり、制度を組み合わせたポートフォリオ設計が2025年のカギとなります。
初心者でも始めやすいプラットフォーム比較
実は、国内の主要クラウドファンディング業者は約40社ありますが、相続物件の受け入れ実績を公表しているのはごくわずかです。ここでは実務経験から、次の三つを紹介します。
・F社:最低投資額1万円で都心区分マンションに特化。信託保全を導入し、運用会社自己投資比率が10%以上と高い。 ・S社:相続空き家の再生に強み。地場工務店と提携し、改修後にファンド組成するため工期遅延リスクが低い。 ・C社:CRE(企業不動産)を転用する大型案件が中心。運用期間は長いが、賃料保証付きで年6%前後の安定配当が魅力。
いずれも口座開設から投資までオンラインで完結しますが、本人確認やマイナンバー提出に数日かかる点には注意が必要です。まずは無料で資料請求し、過去案件の運用レポートを比較してみると違いが見えてきます。
まとめ
相続物件は維持コストと手間がかかる半面、適切に活用すれば安定収益の源泉になります。不動産クラウドファンディングは少額かつ分散で始められ、相続税対策や共有解消にも有効です。ただし利回りだけで判断するとリスクを見落としがちなので、信託保全や事業計画の妥当性を丁寧に確認しましょう。相続登記義務化や省エネ改修促進税制など、2025年度の制度を組み合わせれば手取りをさらに高められます。まずは信頼できるプラットフォームの資料を取り寄せ、自分の資金計画に沿った試算を行うことから始めてみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産市場動向調査2025年版 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 住宅・土地統計調査2024 – https://www.stat.go.jp
- 国税庁 相続税・贈与税に関する情報2025 – https://www.nta.go.jp
- 金融庁 クラウドファンディング業者等登録状況 – https://www.fsa.go.jp
- 経済産業省 省エネ改修促進税制の概要(2025年度) – https://www.meti.go.jp

