退職金の運用先を探しつつも、大きな値動きは避けたい――。そんな思いを抱く60代の方は少なくありません。銀行預金の金利はわずかで、物価はじわりと上がり続けています。実物不動産を購入するには手間もリスクも大きい。その中で少額から始められ、堅実な分配金を期待できるREITが注目されています。本記事ではREITの仕組みから60代ならではのメリット、そして2025年度の制度をふまえた運用のコツまで、経験15年の筆者がわかりやすく解説します。
60代がREITを選ぶ背景と市場動向
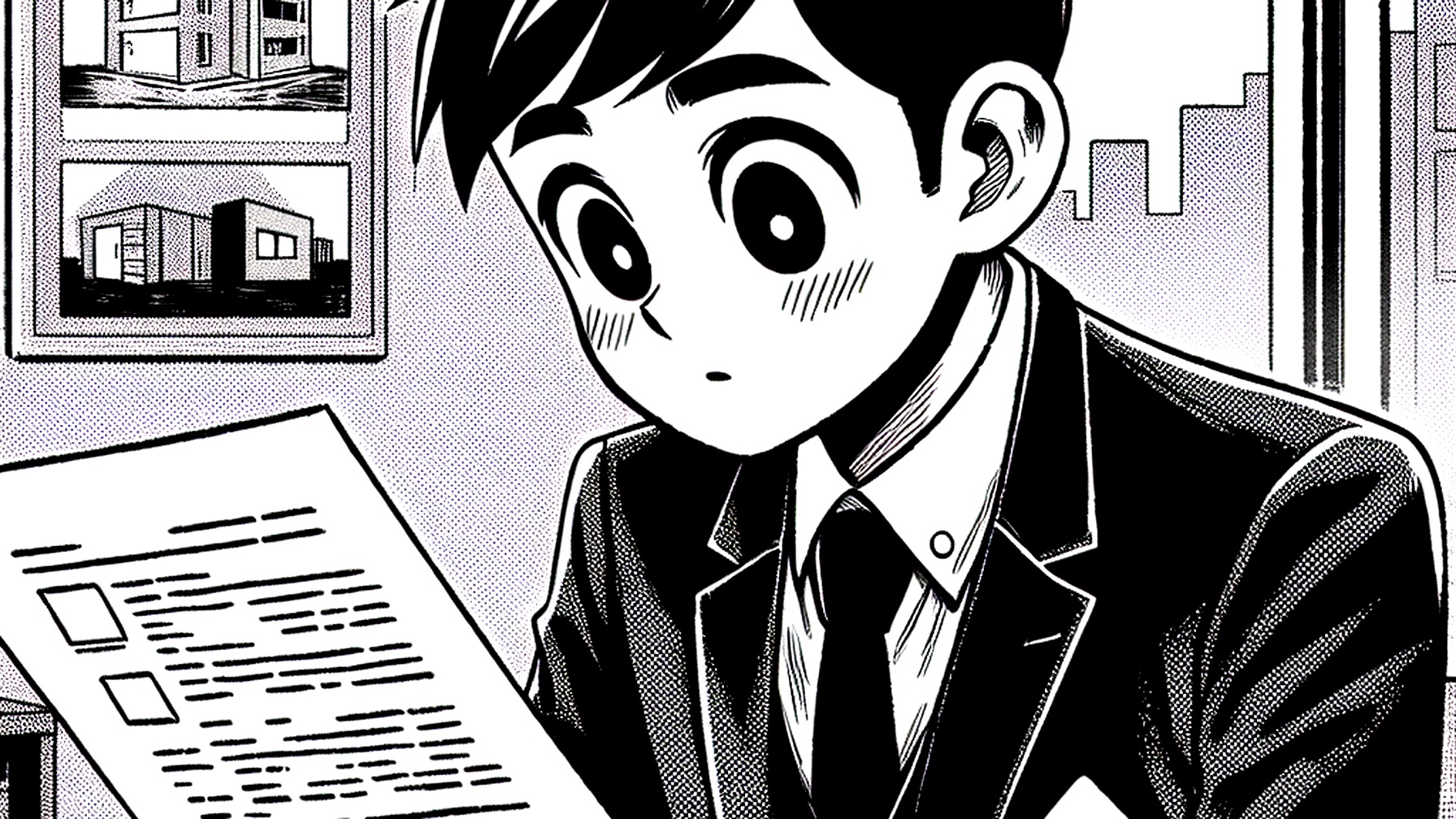
重要なのは、資産寿命が人生寿命を上回るよう備えることです。平均寿命は女性87歳、男性81歳と長期化し、定年後20年以上の生活費が必要になります。低金利が続くなか、預貯金だけではインフレに追いつけない恐れがあります。
日銀が2025年7月に公表した資金循環統計によると、家計金融資産の約53%が現預金にとどまっています。一方、投資信託は6%台にすぎません。つまり、多くの高齢者が運用機会を逃しているのが現状です。
また、東証REIT指数は過去10年間で年平均リターン4%前後を維持してきました。価格変動は株式ほど大きくないものの、配当利回りは3〜4%台と魅力的です。少額で複数物件に分散できる点も、実物不動産とは異なる特徴です。
こうした背景から、60代でも管理や修繕の手間をかけずに不動産収益を得られる手段としてREITが選ばれています。まずは仕組みを理解したうえで、自身の目標と照らし合わせることが大切です。
REITの基本と仕組みを押さえる
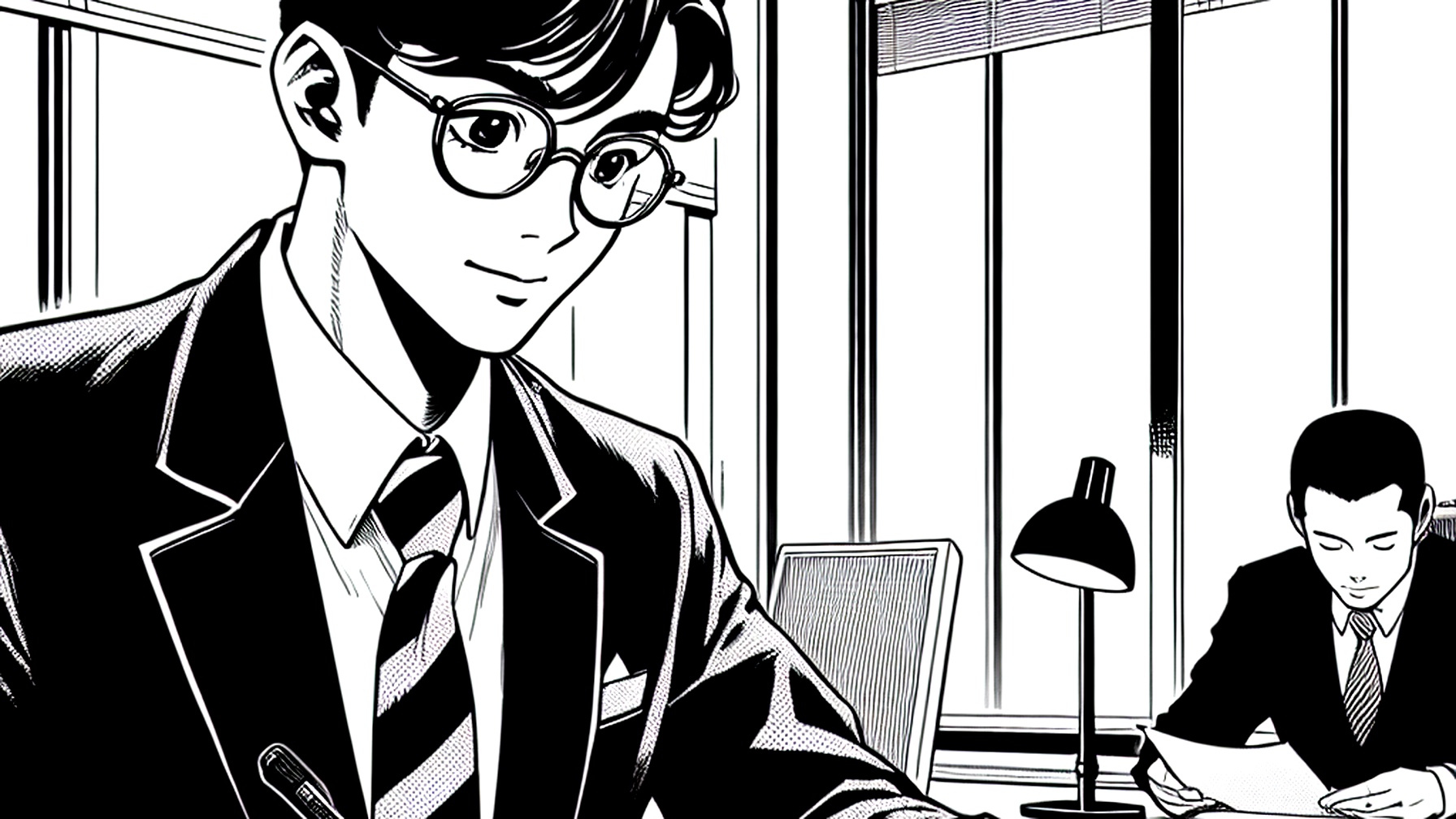
まず押さえておきたいのは、REITが「不動産投資信託」の英語表記Real Estate Investment Trustの頭文字であるという点です。投資家から集めた資金でビルや商業施設、物流センターなどを購入し、賃料収入や売却益を分配します。仕組みそのものは投資信託に近く、個人が間接的に不動産を保有する形になります。
運用会社はプロのアセットマネジャーで構成され、物件選定やテナント交渉、修繕計画まで一括して管理します。投資家が現場に足を運ぶ必要はなく、管理ストレスが大幅に軽減されます。また、資産は信託銀行に分別保管されるため、運用会社が破綻しても資産は守られます。
上場REITは東京証券取引所に上場しており、株式と同じように平日の取引時間ならいつでも売買が可能です。1口数万円から購入できるため、数千万円単位が必要な実物不動産に比べ初期コストが抑えられます。流動性と透明性の高さは、リタイア世代にとって大きな安心材料です。
配当は年2回の分配が主流で、REITは税法上、利益の90%以上を分配すると法人税が実質非課税となる優遇があります。そのため運用会社は積極的に分配を行い、投資家は安定したインカムゲインを得やすいのです。
60代投資家にとっての5つのメリット
ポイントは、REITが60代のライフプランに合致する具体的な利点を複数持つことです。以下では代表的な五つのメリットを順に見ていきます。
まず、分配金利回りの高さです。2025年10月時点のJ-REIT平均利回りは3.7%前後で、メガバンクの定期預金(0.01%程度)を大きく上回ります。公的年金に上乗せする形で毎年の生活費を補填しやすく、計画的なキャッシュフローを組めます。
第二に、分散効果です。J-REITは住宅、オフィス、物流、ホテルなどセクターが多岐にわたります。複数銘柄を組み合わせれば、一棟マンションを単独所有するよりテナント退去のリスクを抑えられます。言い換えると、一つの物件トラブルが資産全体に直結しにくいのです。
第三に、換金性の高さが挙げられます。株式のように市場価格で即日売却できるため、医療費や子どもの支援など急な出費にも対応できます。高齢期の流動性リスクを軽減できる点は見逃せません。
第四に、管理負担の軽さがあります。固定資産税や修繕工事の手配、入居者対応といった実務を自分で行う必要がありません。体力や時間が限られる60代でも安心して保有を続けられます。
最後に、相続対策としての活用です。REITは口数単位で分割しやすく、評価額は市場価格が基準になります。そのため実物不動産より相続税評価額が高くなるケースはあるものの、均等分割の調整がしやすく、不要な兄弟間トラブルを避けやすいのです。
リスク管理と堅実運用のポイント
重要なのは、メリットだけでなくリスクを正確に把握し、堅実に運用することです。REITも市場価格が変動する以上、元本保証ではありません。そこで押さえておきたい管理術を紹介します。
価格変動リスクに備える基本は分散と長期保有です。たとえばオフィス主体の銘柄が景気後退で下落しても、住宅系や物流系が下支えする場合があります。持ち口数を定期的に積み増すことで平均取得価格を平準化でき、配当も再投資すれば複利効果が働きます。
次に、金利上昇への注意が必要です。REITは物件取得資金の多くを借入で賄っています。日本銀行の政策修正で長期金利が1%増えると分配金が数%減る銘柄もあります。運用報告書で借入比率(LTV)が50%以下か、固定金利比率が高いかを確認する習慣が大切です。
さらに、自然災害リスクにも目を向けましょう。地震や風水害で賃料が減る恐れがありますが、複数地域に物件を持つREITを選べば影響を分散できます。運用会社が地震保険に加入しているかもチェックポイントです。これらを踏まえれば、60代でも堅実な収益源としてREITを活用しやすくなります。
2025年度の税制優遇と口座活用術
実は、2025年度はREIT投資を後押しする制度がそろっています。なかでも非課税制度の活用は見逃せません。
まず、新しいNISA制度は2024年から恒久化され、2025年度も年間積立枠120万円、成長投資枠240万円が利用できます。REITは成長投資枠の対象で、分配金と売却益が非課税となるのが大きな魅力です。非課税期間が無期限化されたことで、60代が70代、80代になっても税負担なく運用を続けられます。
一方で、特定口座で保有する場合は分配金に20.315%の源泉徴収税がかかります。課税口座とNISA口座の損益通算はできないため、長期保有分は優先的にNISAへ振り分けると効率的です。退職金で一括購入する場合でも、年ごとに枠内で段階的に買い進めれば、価格変動リスクを分散しながら非課税メリットを最大化できます。
加えて、2025年度のジュニアNISA終了後には未成年者も新NISAへ移行できます。孫への生前贈与を考える60代なら、REITを組み入れたポートフォリオを贈ることで、教育資金と資産形成を同時に支援できます。このように、税制の追い風を受けて堅実なリターンを伸ばせる環境が整っています。
まとめ
REITは少額・分散・高流動性という特性により、60代が求める「堅実なインカム」と「管理の手軽さ」を両立します。分配利回り3%台は年金の補完に役立ち、NISAを活用すれば税引き後の収益をさらに高められます。一方で、市場変動や金利動向への注意も欠かせません。銘柄選びと分散投資を徹底し、毎年の運用報告を確認する習慣をつけることで、長いセカンドライフを豊かに彩る安定収入源となるでしょう。まずは少額でも市場に触れ、自分の許容度を測る一歩から始めてみてください。
参考文献・出典
- 日本銀行 資金循環統計 2025年7月速報 – https://www.boj.or.jp/statistics/sj/
- 金融庁 新しいNISAの概要 – https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/
- 東京証券取引所 J-REIT市場データ 2025年9月 – https://www.jpx.co.jp/markets/j-reits/
- 総務省 家計調査報告 2025年版 – https://www.stat.go.jp/data/kakei/
- 国土交通省 不動産価格指数 2025年6月 – https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_fr_tk1_000043.html

