資産の目減りを防ぎたいものの、銀行預金や国債ではインフレに追いつけないのでは、と不安を抱えていませんか。実物不動産は魅力でも、物件選びや管理のハードルが高いと感じる方は多いでしょう。そこで注目されるのが不動産投資信託、いわゆるREIT(リート)です。本記事では「インフレ対策 REIT メリット」を軸に、2025年10月時点の最新データを用いて仕組みから運用のポイントまで丁寧に解説します。読了後には、なぜREITがインフレ局面で有効な選択肢になり得るのかを理解し、自分に合った投資判断ができるようになります。
REITとインフレの関係を押さえよう
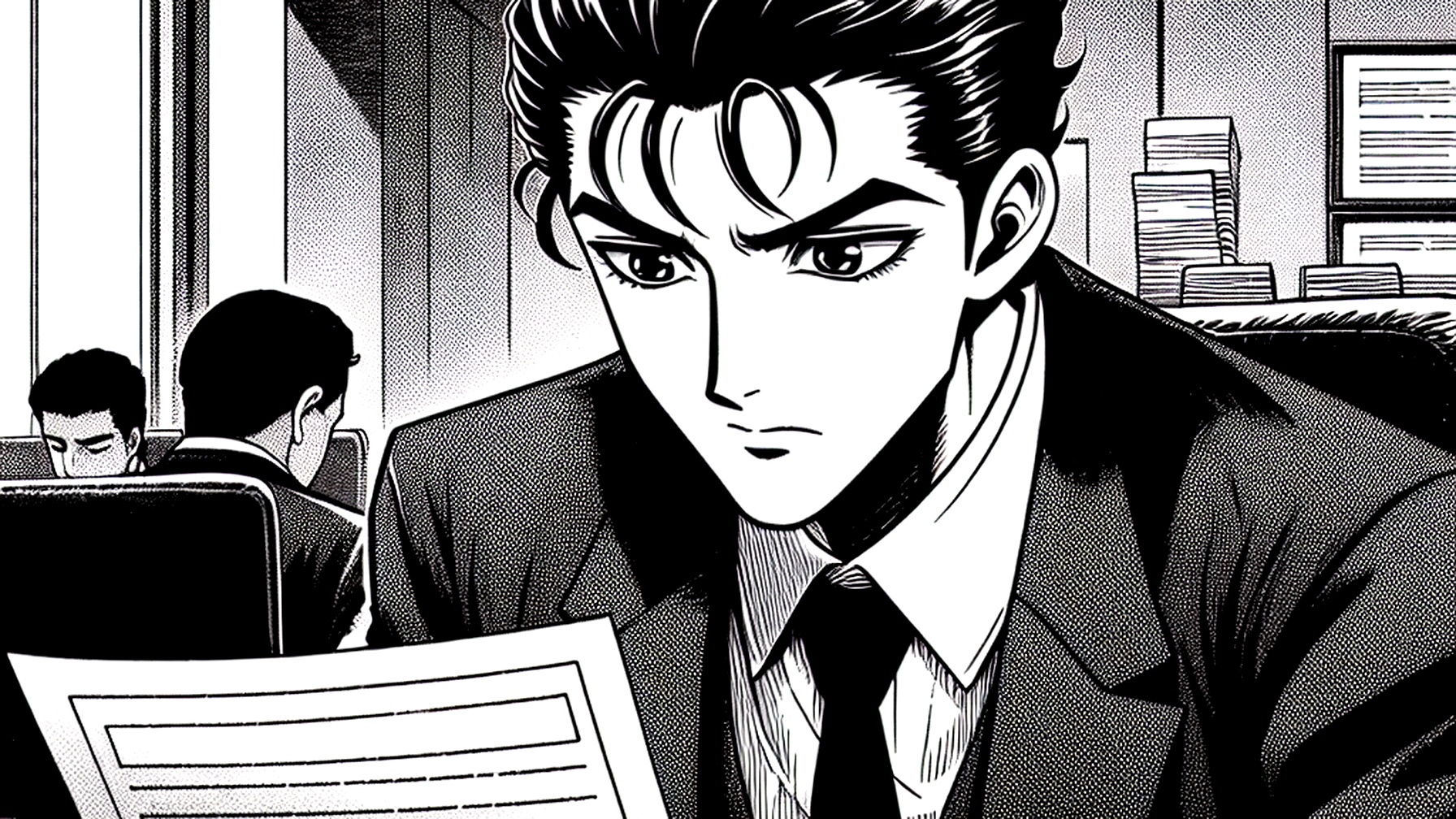
まず押さえておきたいのは、REITがインフレに連動しやすい構造を持つ点です。不動産賃料は一般的に物価上昇に合わせて時間差で上がる傾向があるため、REITの分配金も成長しやすいといえます。
REITは複数の不動産をパッケージ化し、投資家が少額から参加できる仕組みです。株式と同様に東京証券取引所で売買できるため、価格は日々変動します。また、J-REITの平均分配利回りは2025年9月時点で約3.5%(東証REIT指数ベース)と、10年国債利回り約1.1%を上回っています。さらに、内部留保を持たないため収益の90%以上を分配する設計が、インフレ下での実質利回りを支える要因になります。
一方で、賃料改定には契約期間やテナント交渉が伴い、上昇が遅れるケースもあります。そのため、インフレ初期には株式より出遅れることも珍しくありません。しかし賃料が反映されると、安定したキャッシュフローが継続しやすい点が強みとなります。つまり、物価上昇が長期化すると見込む局面でこそ、REITは真価を発揮しやすいのです。
インフレ期に際立つREITのメリット
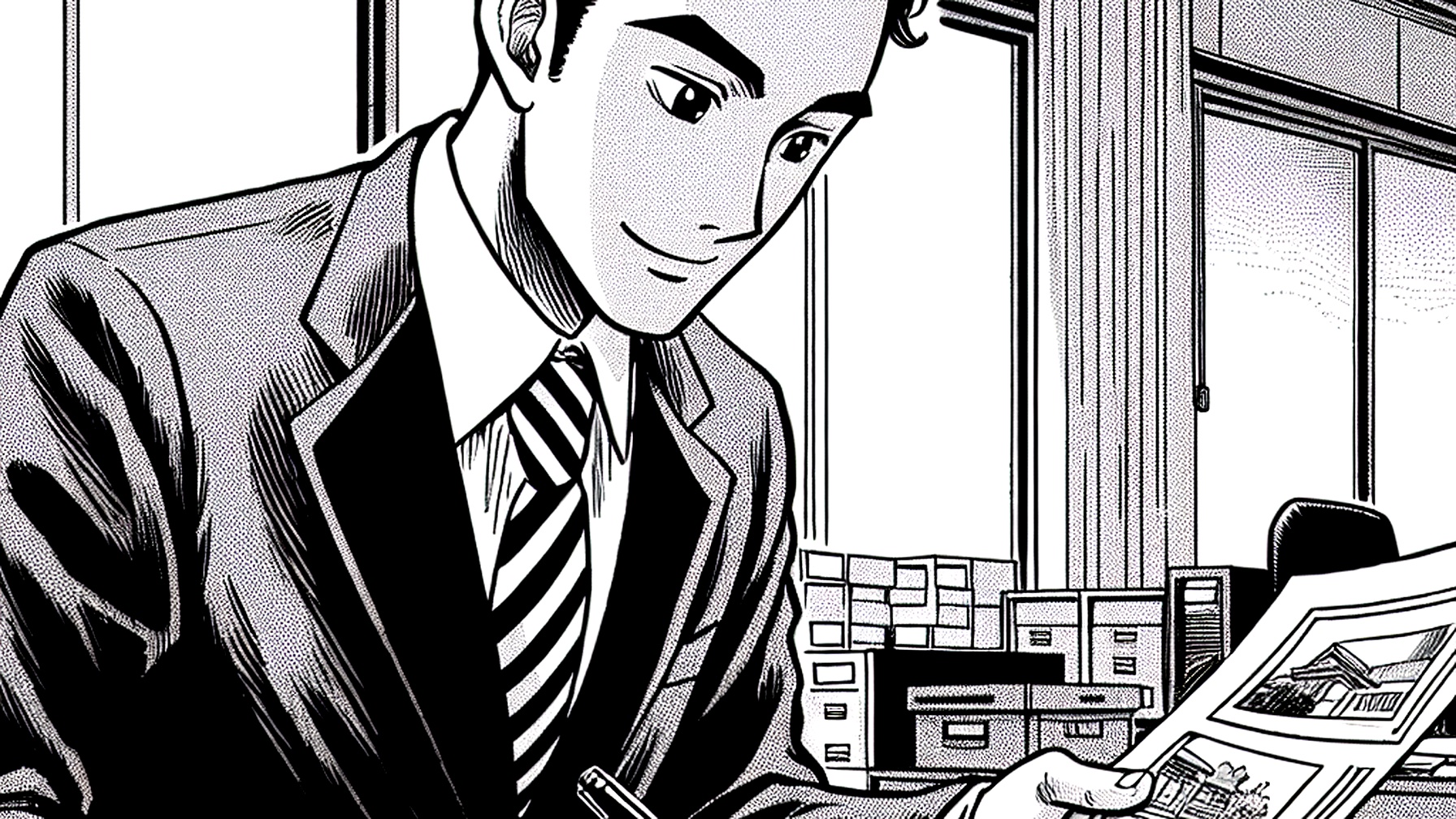
ポイントは、キャッシュフローのインフレ耐性と流動性、そして分散効果の3つです。ここではそれぞれを詳しく掘り下げ、実例を交えて説明します。
まずキャッシュフローの面では、都心オフィスや物流施設に強みを持つREITが賃料指数の上昇を取り込みやすい傾向にあります。国土交通省「不動産価格指数」によると、2022年から2024年にかけて商業用不動産価格は年平均4%超で上昇し、賃料もおおむね同程度で推移しました。この動きが継続すれば、分配金増加へとつながります。
次に流動性です。REITは上場株式と同様にリアルタイムで売買でき、指値注文や信用取引も可能です。現物不動産を売却する場合に数カ月から半年かかるのと比べ、資金の回収スピードが圧倒的に速く、インフレ局面で別の資産へ素早く乗り換えたいときに有利です。
最後に分散効果ですが、一般の個人投資家が複数の大型物件を直接所有するのは現実的ではありません。REITであれば、例えば住宅、オフィス、ホテル、物流施設といった異なるアセットタイプをまとめて保有できます。東証に上場する約60銘柄の時価総額は合計で18兆円超(2025年9月末)と、多彩な選択肢がある点も魅力です。
メリットを最大化する投資戦略
重要なのは、自分のリスク許容度に合った銘柄選びと購入タイミングです。分配利回りだけで飛びつくのではなく、資産規模やLTV(負債比率)、保有物件の立地を総合評価しましょう。
インフレ加速局面では、テナントが短期契約で賃料改定が頻繁に行われる物流施設や住宅系REITが恩恵を受けやすいとされています。また、財務健全性を見る指標としてLTVは50%以下が一つの目安です。低金利環境が長期化する中、借入金利は平均0.4%台(投資法人財務データより)ですが、将来金利上昇の局面でもゆとりのある資本構成が望まれます。
購入タイミングについて、東証REIT指数と長期金利の逆相関に注目する手法があります。日銀データでは、10年国債利回りが0.5%を超えるとREIT価格が短期的に調整する傾向が出ています。その局面でウォッチリストの銘柄を段階的に買い増すことで、平均購入単価を下げつつ分配利回りを高められます。
また、NISA(少額投資非課税制度)の2024年拡充により、投資上限が無期限・1800万円となりました。2025年度も制度は継続し、REIT配当に対しても非課税メリットが享受できます。非課税枠を最大限活用し、税引後利回りを押し上げる工夫が有効です。
リスク管理で押さえるべきポイント
実は、インフレ耐性があるとはいえ、REITにも価格変動リスクや金利上昇リスクがあります。そのため、複数銘柄へ分散投資するだけでなく、定期的なポートフォリオ点検が欠かせません。
金利リスクについては、借入期間の長期化と固定金利化の進捗を確認しましょう。投資法人の平均借入期間は7年程度ですが、一部銘柄では5年未満も散見されます。金利が急上昇した場合、借換えコストが分配金を圧迫する恐れがあるため、IR資料で詳細を確認する姿勢が大切です。
また、空室率の上昇はインフレ期でも発生し得ます。特にオフィス系REITはテレワーク定着により需給バランスの変動が続いています。物件入替えや用途変更で稼働率を維持する戦略が明示されているかチェックすると、将来のキャッシュフロー安定度を見極めやすくなります。
さらに、市場価格が割高なときは追加投資を控え、分配金を再投資用のキャッシュとして待機させる選択肢も有効です。REITの魅力は流動性にあるため、必ずしも長期ホールド一択ではありません。状況に応じて売却益と分配金のバランスを調整する柔軟性が求められます。
2025年度の制度・税制が追い風に
まず押さえておきたいのは、2025年度もREITを取り巻く税制優遇が維持されている点です。投資法人課税の実質免除要件(90%以上の利益分配)は継続し、法人段階での課税を回避できる仕組みが温存されています。
個人投資家向けには、前述の新NISAに加え、iDeCo(個人型確定拠出年金)でREIT投信を選択できる環境が整っています。iDeCoの掛金は全額所得控除になるため、分配金非課税と合わせ二重の節税効果が期待できます。ただしiDeCoは60歳まで引き出せない点に注意が必要です。
さらに、東証は2024年に「インフラ投資法人」市場とREIT市場を統合し、外国人投資家の参加が拡大しました。その結果、売買代金が約1.3倍に増加し、価格の透明性と流動性が向上しています。投資家層の厚みが増したことで、大口売買による価格歪みが減り、インフレ期でも適正価格に近い水準で取引されやすくなりました。
結論として、制度面の追い風が続く2025年度は、インフレ対策としてREITのメリットを享受しやすい環境が整っているといえます。ただし制度は将来変更される可能性があるため、毎年の税制改正大綱を確認する習慣をつけると安心です。
まとめ
ここまで、REITがなぜインフレ期に強いのか、そのメリットを最大化する投資戦略、そしてリスク管理のポイントまで解説してきました。賃料の物価連動性に支えられたキャッシュフロー、上場による高い流動性、多様なアセットによる分散効果がREITの三本柱です。さらに、2025年度のNISAや税制優遇が追い風となり、税引後利回りを高めやすい状況が続いています。まずは分配利回りやLTVに着目し、自分のリスク許容度に合った銘柄を少額から試してみることをおすすめします。インフレに負けない資産形成へ、一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_fr5_000041.html
- 日本銀行 統計データベース – https://www.boj.or.jp/statistics/index.htm
- 東京証券取引所 REIT・インフラファンド一覧 – https://www.jpx.co.jp/equities/products/reits/issues/
- 内閣府 経済財政白書2025 – https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je24/index.html
- 投資信託協会 J-REITデータブック – https://www.toushin.or.jp/research/reit/

