家賃収入で老後資金や学費をまかなえたら安心ですが、物価が上がる今の日本でどの物件を選ぶべきか迷う人は多いはずです。特に築古物件は価格が手ごろな一方、修繕費や空室リスクが気になります。本記事では、築古の収益物件を活用してインフレ対策を行い、失敗しないための判断軸を整理します。読み進めることで、物件選定から融資、運用、出口戦略まで、2025年10月時点の最新環境に即した実践的なヒントが得られるでしょう。
なぜ今、築古の収益物件に注目するのか
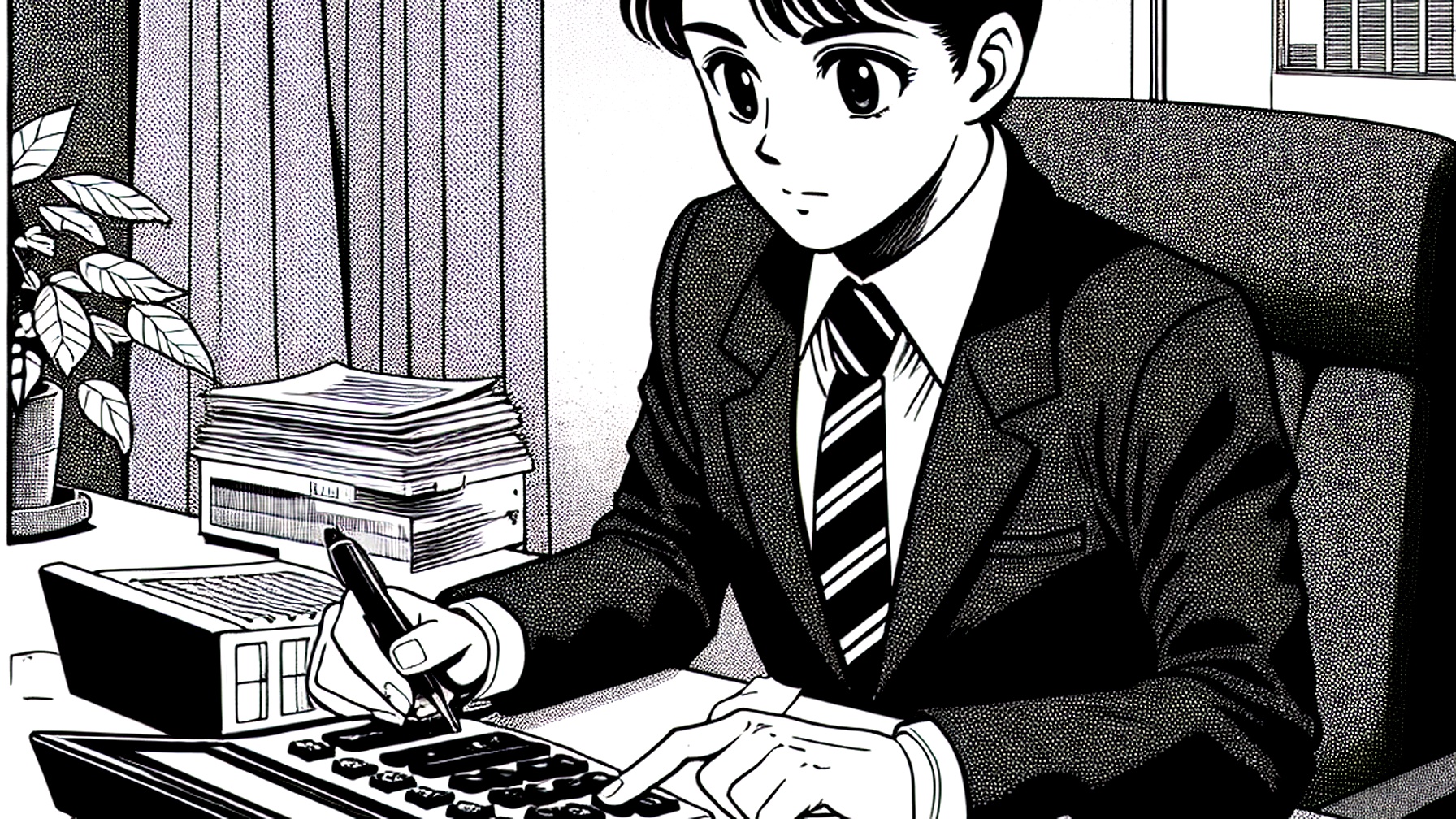
重要なのは、インフレ局面で「買える価格帯」と「高い利回り」の両立を図れる点に築古物件の強みがあることです。新築が高値圏にあるため、相対的に中古市場へ資金が流れています。
まず、総務省の消費者物価指数によると、2022年以降のCPIは年2%前後で推移しており、家賃はゆるやかに上昇しています。一方、国土交通省の住宅市場動向調査では中古マンションの成約価格が横ばい気味で、利回り格差が拡大しています。つまり、築古物件はインフレに対して価格の上昇が緩慢な分、実質利回りが高まりやすいのです。
さらに、築20年以上の区分マンションでも、駅徒歩10分圏であれば平均空室期間は2か月弱というデータがあります。都心プレミアムエリアを除けば取得価格を抑えやすく、賃料は周辺相場に連動するため、キャッシュフローが読みやすい傾向です。
ただし、修繕費がかさむと収益性を押し下げます。築年数が古いほど大規模修繕の履歴と積立金の水準が鍵になります。次章ではキャッシュフローを守る具体策を確認しましょう。
インフレ時代のキャッシュフロー戦略
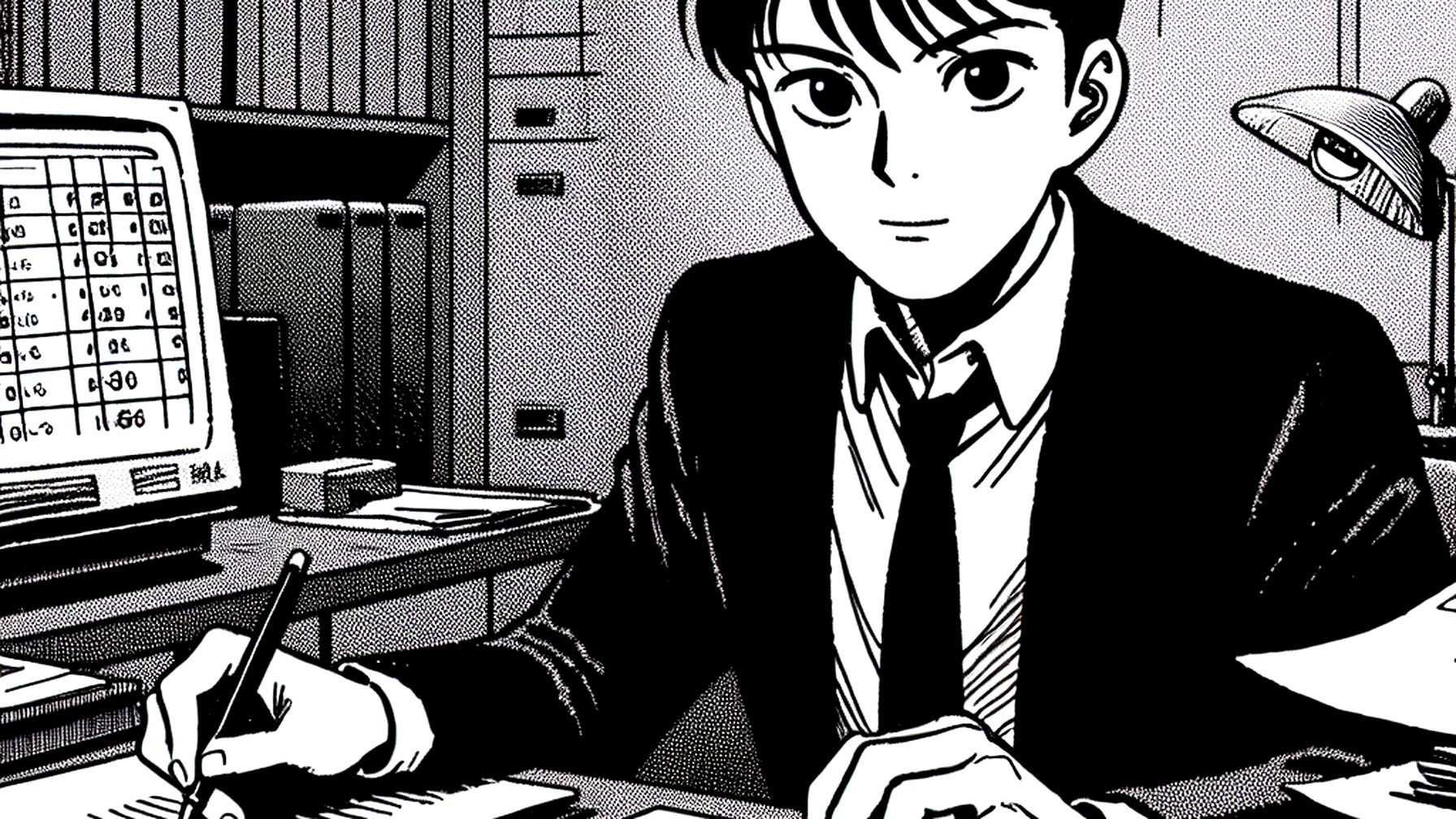
ポイントは、固定金利で借りて、変動する家賃収入で返済する「金利と賃料のミスマッチ」を味方に付けることです。インフレ下では物価とともに賃料も上がりやすい一方、固定金利の返済額は変わりません。
まず、収支を組む際は家賃上昇を期待しすぎず、手残りを年間家賃収入の20%以上確保する保守的なシミュレーションを作ると安全です。家賃が上昇すれば利益が伸び、上がらなくても破綻しにくい構造になります。
次に、金利水準を注視します。日本銀行の金融システムレポートでは、2025年春時点で住宅ローン固定金利は平均1.35%前後と報告されています。変動金利との差は0.4%程度ですが、30年でみると固定の方が将来の金利上昇リスクを回避できます。
最後に、賃料アップの施策として小規模リフォームを活用します。壁紙のアクセント張りやLED照明の導入は、1室あたり10万円以内で家賃を月3000円上げられるケースも珍しくありません。インフレで材料費が高騰しても、ターンオーバー時に限定すれば費用対効果を維持しやすいのです。
失敗しない築古物件の見極めポイント
実は、築古物件で最も差がつくのは購入前の調査精度です。表面利回りだけで決めると、修繕費や退去コストで失敗しやすくなります。
まず押さえておきたいのは立地評価です。人口動態を調べ、5年後に賃貸需要が維持できるか確認しましょう。駅距離だけでなく、再開発計画や大学の移転動向なども賃料水準に響きます。
次に、建物の構造と管理状態をチェックします。耐震基準を満たしている1981年以降の新耐震物件は金融機関の評価が通りやすく、修繕積立金も適正に設定されやすい傾向です。築40年超の場合は、長期修繕計画が現実的かどうか議事録で確認すると、想定外の負担を避けられます。
調査項目を整理すると下記のようになります。
- 管理組合の積立金残高と直近の徴収額
- 給排水管・屋上防水の更新年
- 入居者属性と直近3年の退去率
これらを網羅すれば、購入後のキャッシュフローが大きくブレるリスクを最小化できます。
2025年度の融資環境と活用できる制度
まず、2025年度の融資環境ですが、地銀や信金はインフレ対応で長期固定の融資姿勢を強めています。自己資金が物件価格の20%以上あれば、固定1.4〜1.6%で25年融資が引ける事例が増えています。
さらに、国土交通省が所管する「長期優良住宅化リフォーム推進事業(2025年度)」は、賃貸住宅でも耐震・省エネ改修を行う場合に最大300万円の補助を受けられます。上限額は工事内容により異なり、申請は工事着手前に行う必要があります。
固定資産税についても、国税庁がまとめる「耐震改修促進税制」を活用すると、築25年以上の木造アパートを耐震基準に適合させた場合、翌年度の固定資産税が半額になります(2025年度適用)。減税期間は1年ですが、投下資本の早期回収に寄与します。
融資と補助金を組み合わせると、実質の自己資金回収期間を2〜3年短縮できるケースがあります。ただし、制度には予算枠と申請期間があるため、購入前に施工業者とスケジュールを共有しておくことが肝心です。
長期で勝つための運用と出口戦略
まず押さえておきたいのは、運用期間中の「計画修繕」です。屋上防水や配管更新など大規模修繕を先延ばしにすると、賃料下落を招き利回りが低下します。購入時点で10年分の修繕計画を資金繰りに組み込むと、突発的なキャッシュアウトを避けられます。
次に、賃貸管理会社との連携を強化します。退去時のリフォーム見積もりを複数取得し、原状回復と付加価値工事を分けて発注するとコストが抑えられます。家賃を5000円維持できれば、年間6万円、10年で60万円の増収になり、修繕費の原資にもなります。
出口戦略としては、インフレで不動産価格が上昇する局面を見極め、簿価が低いうちに譲渡する方法があります。もしくは、頭金をほぼ回収した後も保有し続け、賃料と売却益のダブルインカムを狙うモデルも有効です。どちらを取るかは、金利動向と物件の築年数の兼ね合いで柔軟に判断しましょう。
結論として、築古の収益物件でも計画的な運用とデータに基づく意思決定を行えば、インフレ時代に強い資産となり得ます。出口を意識した長期プランが、失敗しない最大のポイントです。
まとめ
ここまで、インフレ下で築古の収益物件を選ぶ意義、キャッシュフローの組み立て方、物件調査の要点、2025年度の制度活用、そして出口戦略までを見てきました。要するに、価格が伸びにくい築古物件でも、利回りと修繕計画をコントロールすればインフレ対策として機能します。行動するときは、立地と建物状態を数値で検証し、固定金利と補助金を併用しながらリスクを小さく始めることが大切です。今日得た視点を使い、まずは気になるエリアの家賃相場と管理状況を調べるところから踏み出してみてください。
参考文献・出典
- 総務省統計局 – https://www.stat.go.jp
- 国土交通省 住宅市場動向調査 – https://www.mlit.go.jp
- 日本銀行 金融システムレポート – https://www.boj.or.jp
- 全国賃貸住宅新聞 賃料データ – https://www.zenchin.com
- 国税庁 固定資産税の特例措置 – https://www.nta.go.jp

