不動産投資で毎年の税負担を減らしたいが、複雑な制度に戸惑う人は多いでしょう。とくにREITを使った節税対策は手軽と聞くものの、仕組みや落とし穴を把握せずに始めるのは危険です。この記事では2025年10月時点の最新税制を踏まえ、初心者でも実践しやすいおすすめ手法とデメリットを丁寧に解説します。読み終えるころには、自分に適した戦略を選べる判断材料がそろうはずです。
REITが節税に使われる理由
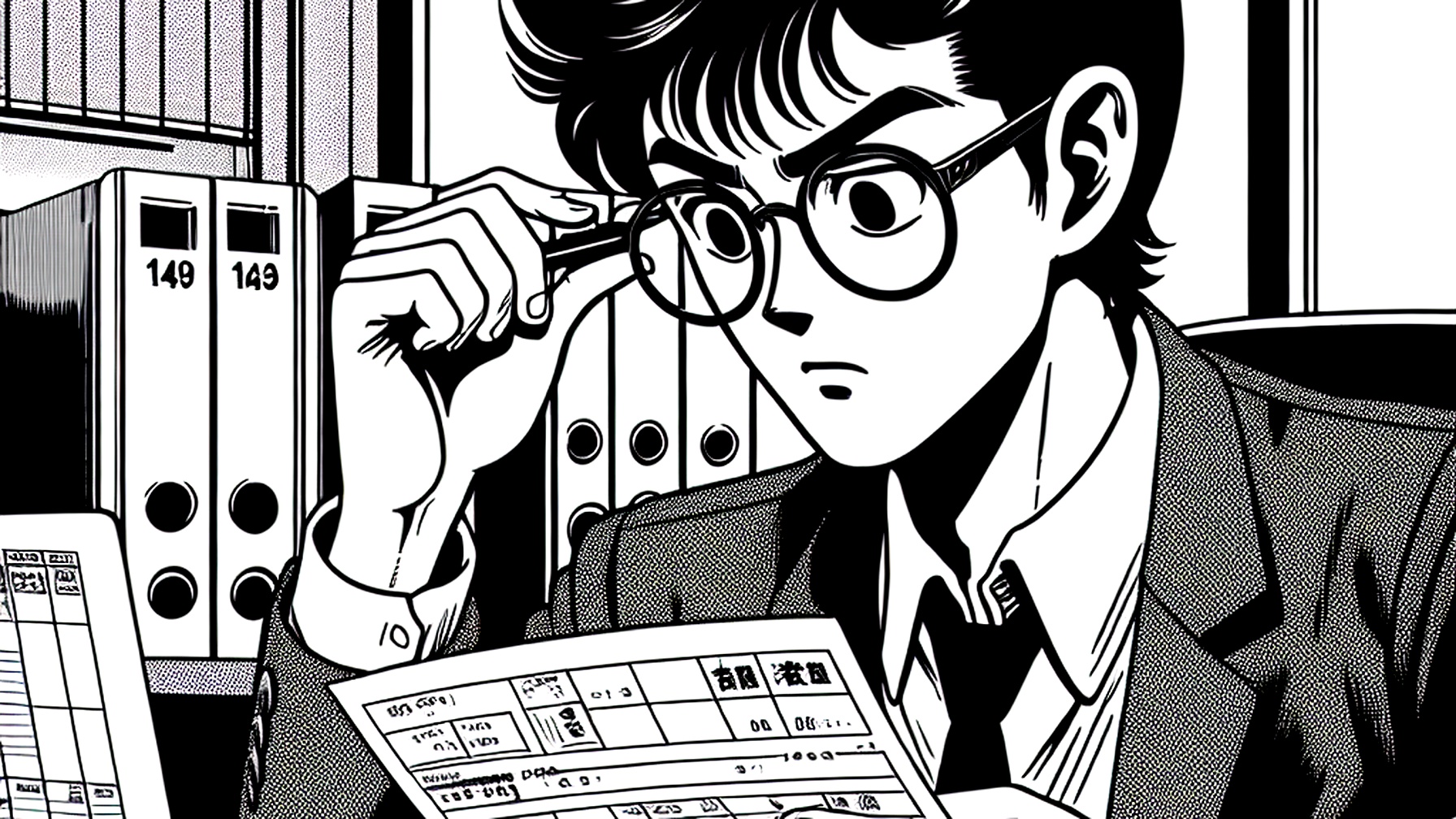
まず押さえておきたいのは、REITが税制上ほかの金融商品より優遇されている点です。REITは投資信託に分類され、利益の90%以上を分配すると法人税が実質的にゼロになります。結果として投資家が受け取る分配金は、配当所得として源泉徴収15.315%+住民税5%の申告分離課税にまとめられ、累進課税の高い給与所得より軽くなる場合が多いのです。
次に、REITは上場株式と同じように証券口座で取引でき、NISA口座を併用すれば分配金も売却益も非課税になります。金融庁の2025年上期統計によると、新NISA成長投資枠で購入された商品中、REITの割合は12%を超えました。非課税枠を活用するだけで実効税率を20%弱下げられるため、給与所得者にとって手続きが少なく効果が大きい方法といえます。
さらに、REITは物件管理をプロが担うため、個別物件の減価償却や修繕計画を自分で作る必要がありません。管理負担が小さいことは本業を持つ投資家にとって大きな魅力です。つまり、REITは「時間の節税」にもつながるわけです。
2025年度税制で確認すべきポイント

ポイントは、2025年度税制改正でREIT関連の控除規定に大きな変更がなかったことです。これにより、投資信託の分配金課税は前年と同様に20.315%が維持され、新NISAの非課税期間は無期限で継続されています。一方で、高所得者の給与控除が段階的に縮小されたため、課税所得900万円超の層はREITの分配金が節税に与えるインパクトが相対的に高まりました。
国税庁のモデル試算によれば、課税所得1,000万円の会社員が年間50万円のREIT分配金を受け取った場合、総合課税なら約23万円の税金がかかります。これを申告分離にするとおよそ10万円に下がり、差額は13万円です。新NISA内で受け取れば税額はゼロになり、さらに13万円の削減が可能です。
ただし、2025年度から「特定口座年間取引報告書」の電子交付が義務化されました。確定申告を行わずに源泉徴収で完結させる人も、取引履歴の確認がオンラインのみとなるため、データ保存の手間が増える点に注意してください。
おすすめの具体的節税スキーム
実は、REIT単体よりも他の金融商品や保険と組み合わせることで、節税効果とキャッシュフローを最大化できます。まず基本形として、新NISA成長投資枠に国内REITを毎月自動積立し、同時に特定口座で海外REIT ETFを長期保有する方法があります。海外REITの分配金にかかる外国税額控除を確定申告で取り戻せば、実効税率はさらに2〜3%下がります。
次に、損益通算を意識した戦略です。REITの価格が大きく下落した年に一部を損切りし、株式の配当益と相殺することで課税所得を減らせます。東京証券取引所のデータでは、2020年のコロナショック時に東証REIT指数が年間▲18%下落しましたが、翌年にほぼ回復しています。こうしたボラティリティを逆手に取ると、資本損失を利用した節税が可能です。
さらに、給与収入が多い人は小規模企業共済やiDeCoと併用することで、所得控除と分離課税の二重のメリットを得られます。たとえば年収1,200万円の医師がiDeCo満額(81.6万円)とREIT分配金50万円を組み合わせると、所得税・住民税合わせて年間約35万円の節税効果が見込めます。
REIT投資の主なデメリットと対策
一方で、REITは万能ではありません。まず価格変動リスクです。オフィス空室率の上昇や金利上昇が重なると、分配金が減り価格も下がります。日本不動産研究所が公表した2025年4月の想定CAPレートは、東京都心オフィスで3.8%と前年より0.3ポイント上昇しました。金利が上がる局面では、REITの利回り確保が難しくなる点を頭に入れておきましょう。
流動性リスクも見逃せません。震災や金融危機など非常時には売買が急減し、思い通りの価格で売れないことがあります。実際、2024年1月の能登半島地震直後、東証REIT指数は3営業日で6%下落しましたが、出来高は通常の半分以下でした。緊急時に資金を必要とする可能性がある人は、運用額の3〜6カ月分を現金で確保しておくと安心です。
もうひとつのデメリットはレバレッジがかけにくい点です。現物不動産なら金融機関融資で投資額の4〜5倍まで拡大できますが、REITでは証券会社の信用取引枠しか使えず金利も高めです。過度な借入で利回りを高める戦略は取りにくいため、高利回りを求めすぎて海外高リスクREITに偏らないようポートフォリオを組む必要があります。
個人と法人、どちらで持つべきか
まず、個人名義でREITを保有する場合は分配金が申告分離課税で完結し、確定申告も任意です。給与所得が高く速やかにキャッシュフローを得たい人にはこの方法が最も簡単でしょう。一方、法人名義で保有すると分配金は法人税の課税対象ですが、他の事業損失と相殺できるため利益調整の自由度が上がります。
国税庁の統計によると、資本金1億円以下の中小企業に適用される15%の軽減税率は2025年度も存続しています。年間分配金800万円以下にこの税率を当てはめると、個人よりも税負担が小さくなるケースが出てきます。また、法人で経費計上できる出張費や会議費を活用すれば、実効税率をさらに下げることも可能です。
ただし、法人設立には登録免許税や年間の決算費用が発生します。分配金が年300万円未満の場合は、設立コストが節税効果を上回ることが多いため慎重な試算が欠かせません。つまり、法人保有は事業拡大を視野に入れる投資家向けの選択肢と言えます。
まとめ
本記事では、REITを活用した節税の仕組みと2025年度税制のポイント、おすすめスキーム、そして見落とされがちなデメリットを解説しました。重要なのは、税率だけでなく流動性や価格変動リスクも踏まえ、NISAや損益通算など複数の制度を組み合わせて最適化することです。初めての方は、まず新NISAで少額から始め、電子交付された取引報告書を定期的にチェックする習慣を身につけてください。そうすることで、税金も時間も無駄にしない堅実なREIT投資が実現できます。
参考文献・出典
- 金融庁 令和6事務年度金融レポート 2025年版 – https://www.fsa.go.jp/
- 国税庁 所得税に関する統計 2025年 – https://www.nta.go.jp/
- 東証REIT指数 月次レポート 2025年9月 – https://www.jpx.co.jp/
- 日本不動産研究所 不動産投資家調査 2025年4月 – https://www.reinet.or.jp/
- 国土交通省 不動産証券化白書 2025年版 – https://www.mlit.go.jp/

