不動産投資に興味はあるものの「いきなり数千万円の物件を買うのはこわい」と感じる方は多いでしょう。そこで候補にあがるのがREIT(不動産投資信託)ですが、ネット上にはメリットの紹介ばかりが目立ち、リスクや欠点が見えにくいのが実情です。本記事では「REIT デメリット 1000万円」というキーワードを軸に、初心者でも理解できるよう注意点を整理し、手元に1000万円の資金がある場合の現実的な運用プランまで解説します。読み終えるころには、自分に合った投資スタイルを見極めるヒントが得られるはずです。
REITとは何か
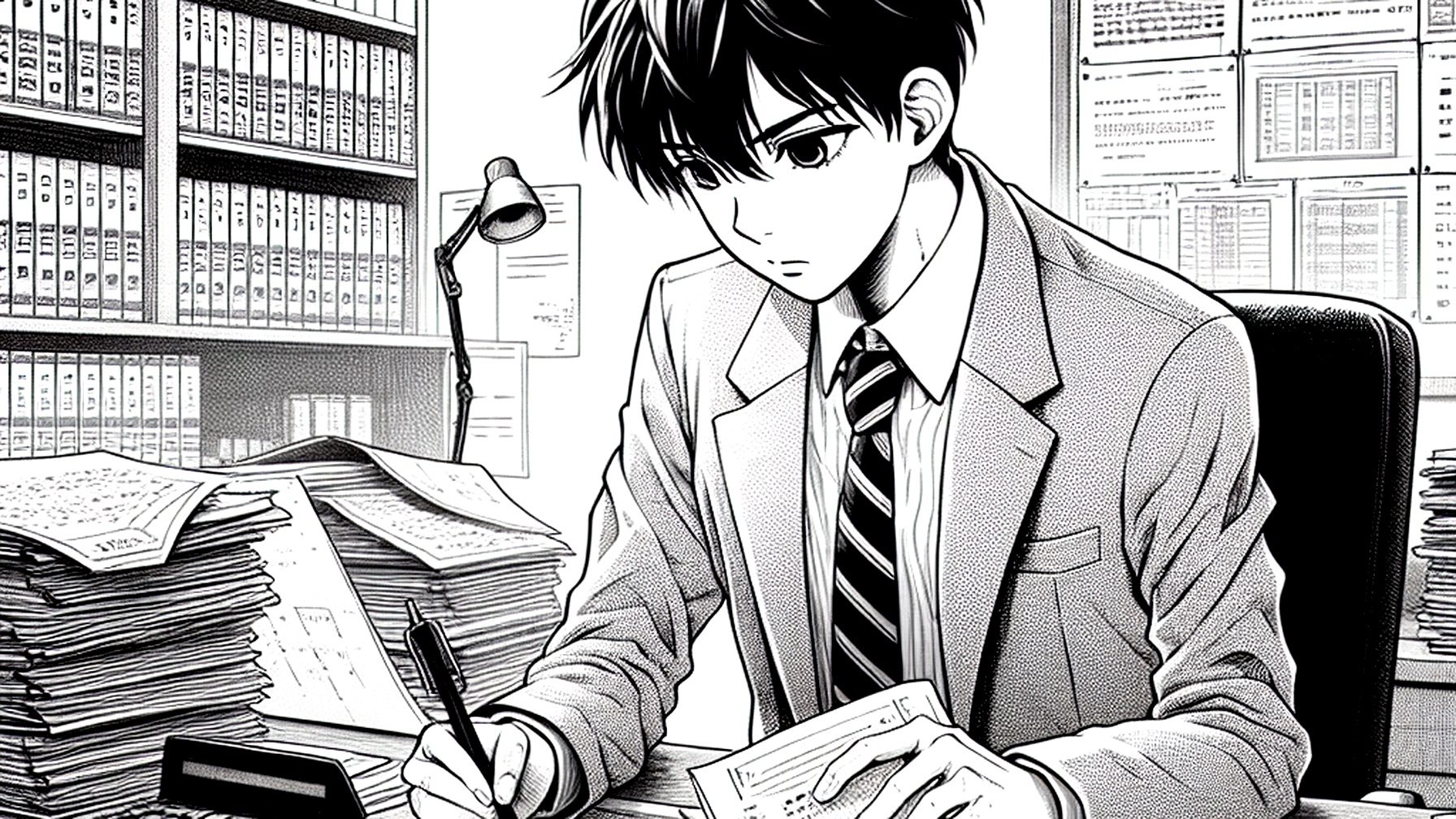
まず押さえておきたいのは、REITが株式と同じように証券取引所に上場している点です。つまり価格は日々変動し、売買は株と同様に証券口座から行えます。一口数万円という少額から分散投資ができ、複数のオフィスビルや商業施設に間接的に投資できるため、物件を直接保有するのとは異なる手軽さがあります。
一方で、REITは実物不動産と金融市場の両方の影響を受ける複合商品です。例えば日本銀行が金利を引き上げれば、借入コストが増すことでREIT価格が下落しやすくなります。また、入居率の低下など不動産固有のリスクも同時に抱えます。つまり、特徴を理解せずに「不動産だから安定」と考えるのは早計です。
2025年10月時点で東京証券取引所には約60銘柄のJ-REITが上場しており、オフィス特化型や物流施設特化型など、セクターごとにパフォーマンスも異なります。四半期ごとに公表される運用報告書を読めば、物件ごとの入居率や賃料改定率を確認できるため、株式分析と同様に定量データを追いかける姿勢が欠かせません。
覚えておきたいREITのデメリット
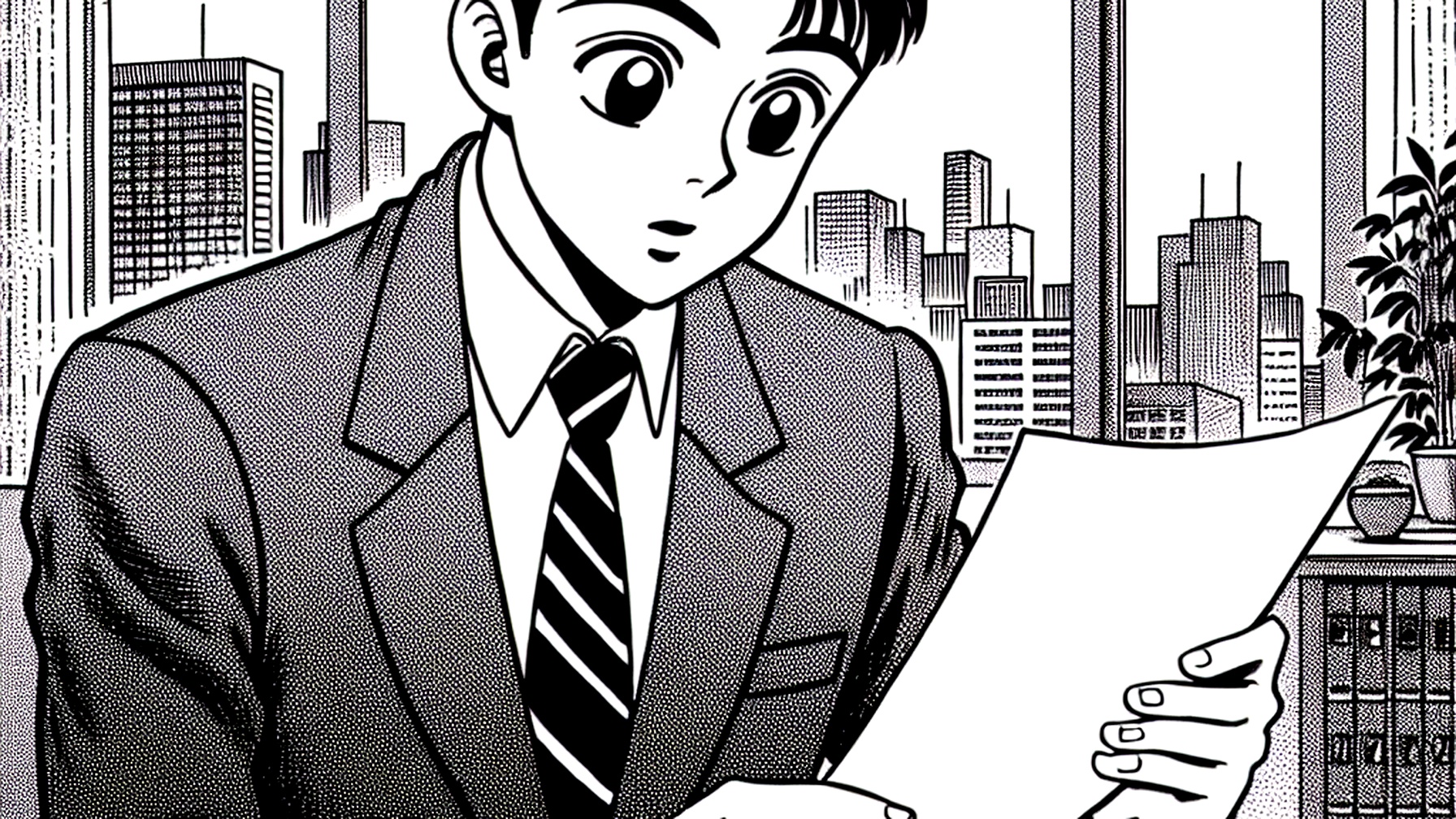
重要なのは、メリット以上にデメリットを具体的に把握することです。第一に、上場商品である以上、株式と同様の価格変動リスクがあります。2020年のコロナショック時には東証REIT指数がわずか1か月で4割近く下落しました。実物不動産と比べて流動性が高い反面、短期的な値動きにさらされる点は覚悟が必要です。
次に、内部コストの存在です。REITには運用報酬や物件の管理費、借入金利などが組み込まれており、投資家はそれらを間接的に負担します。運用報酬は純資産の0.3〜0.5%程度が一般的ですが、物件売買時のフィーや成功報酬が加算されるケースもあるため、実質コストは1%前後になることも珍しくありません。
三つ目は物件集中リスクです。分散投資といっても、個別銘柄が10棟前後のビルで構成されている場合、単一施設のトラブルが分配金に影響する可能性があります。特にオフィス主体の銘柄では、テレワーク定着により空室率が徐々に上昇しているデータもあり、セクター偏在には注意が必要です。
さらに、税制面でも知っておくべきポイントがあります。分配金は配当所得として総合課税または申告分離課税(20.315%)の対象となり、実物不動産のように減価償却による大幅な節税メリットは得られません。したがって、高額所得者が課税所得を圧縮したい場合には向かない選択肢となります。
1000万円をどう分散するか
ポイントは、1000万円を一括で投入せず、時間と銘柄の両面で分散することです。まず300万円を市場全体に連動するETF「東証REIT指数連動型上場投信」に配分し、基盤となる値動きを把握します。次に400万円を物流施設や住宅系など景気連動性が比較的低い個別銘柄へ段階的に投資します。残りの300万円は半年から1年かけて追加購入する「ドルコスト平均法」を意識すると、急落局面でも心理的余裕が生まれます。
実は、REITの平均分配利回りは2025年10月時点で約3.5%です。1000万円を平均利回りで運用すると年間35万円のインカムが期待できますが、管理費用や税金を差し引くと手取りは約28万円に下がります。この数字を生活費補填か再投資に回すかで将来の資産形成スピードが変わってきます。
もう一歩踏み込むなら、海外REITを組み込む方法があります。米国の優良REIT ETFは利回り3%台ながら、人口増加と賃料上昇が続く構造的な強みがあります。ただし為替リスクが付随するため、外貨預金や海外株をすでに保有している投資家に限定する形が賢明です。為替ヘッジ型ETFを併用すれば、円安局面での評価損をある程度抑えられます。
2025年度の制度と税制を活用する
まず押さえておきたいのは、2025年度の新しいNISA制度です。つみたて投資枠と成長投資枠を合わせて年間360万円まで非課税で運用できます。REIT ETFは成長投資枠の対象商品であり、非課税期間が無期限化されたことで、分配金への課税を回避できるメリットが際立ちます。1000万円のうち120万円ずつNISA枠に振り分ければ、税引き後利回りを実質0.7ポイントほど押し上げられます。
一方、iDeCo(個人型確定拠出年金)は2025年度も掛金所得控除と運用益非課税が続きますが、60歳まで引き出せない点がネックです。流動性を確保したい場合、REIT投資との相性は必ずしも高くありません。それでも長期で資産を積み上げたい人は、NISAとiDeCoを併用し、課税口座とのバランスをとることで、全体のキャッシュフローを滑らかにできます。
また、法人を設立している場合は、REITの配当控除が適用されないため、個人名義で保有したほうが税負担は軽くなるケースが多いです。逆に、実物不動産を法人で所有し、REITを個人で保有するといった役割分担を行うことで、節税と資産分散の効果を両取りできます。
デメリットを越えるための実践ポイント
実は、REITの欠点は管理の手間を省いた代償として発生するものが大半です。そこで、手数料や借入金利に敏感な銘柄を避け、「LTV(負債比率)が50%以下」「運用報酬率が0.5%未満」など、財務の健全性に注目するだけでもリスクを下げられます。四半期報告の注記に目を通し、修繕計画の積立率が2%を下回っていないか確認する習慣をつけましょう。
さらに、景気循環に応じたポートフォリオの入れ替えも有効です。景気後退が見込まれる局面では、賃料改定が比較的固定されている住宅系へ比重を移し、ウォール街が利上げ停止を示唆すれば、金利敏感なオフィスや商業系を拾う戦略が考えられます。これは株式投資のセクターローテーションと同じ発想で、REITでも有効に機能します。
最後に、情報源の質を高めることが欠かせません。運用会社のIR資料はもちろん、国土交通省が公表する「不動産価格指数」や総務省の「家計調査」を横断的に読むことで、分配金の源泉となる賃料動向をより深く理解できます。SNSの短文情報に頼らず、一次データを自ら確認する姿勢が、デメリットをチャンスに変える最大の武器になります。
まとめ
本記事では、REITのデメリットを四つに整理し、1000万円というまとまった資金を安全に配分する方法を解説しました。価格変動や内部コストといった弱点はあるものの、NISAの非課税効果やセクター分散を組み合わせれば、安定したインカムを得ながら資産を増やす道は十分に開けます。まずは少額で値動きを体感し、資料を自分の目で読んで判断する習慣をつけることが、長期で勝ち抜くための第一歩です。今日できる行動として、証券口座の銘柄スクリーニング機能を使い、LTVや利回りを比較してみましょう。継続的な学びが、REIT投資を味方につける最大のコツです。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp/
- 総務省 家計調査 – https://www.stat.go.jp/
- 東京証券取引所 REIT市場情報 – https://www.jpx.co.jp/
- 金融庁 NISA特設ページ(2025年度版) – https://www.fsa.go.jp/
- 一般社団法人投資信託協会 REITデータ集 – https://www.toushin.or.jp/

