相続で突然物件を引き継いだけれど、売却か賃貸か決めきれず管理コストだけが重い──そんな悩みを抱える人は年々増えています。実は、近年急速に広がる「不動産クラウドファンディング」が相続物件の負担をチャンスへ変える手段として注目されています。本記事では、不動産投資歴15年の筆者が仕組みとメリット、2025年度の制度面、リスク管理まで順を追って解説します。読み終えたとき、相続物件の眠れる価値を手間なく引き出す具体的な行動イメージが得られるはずです。
相続物件とクラウドファンディングが出会う背景
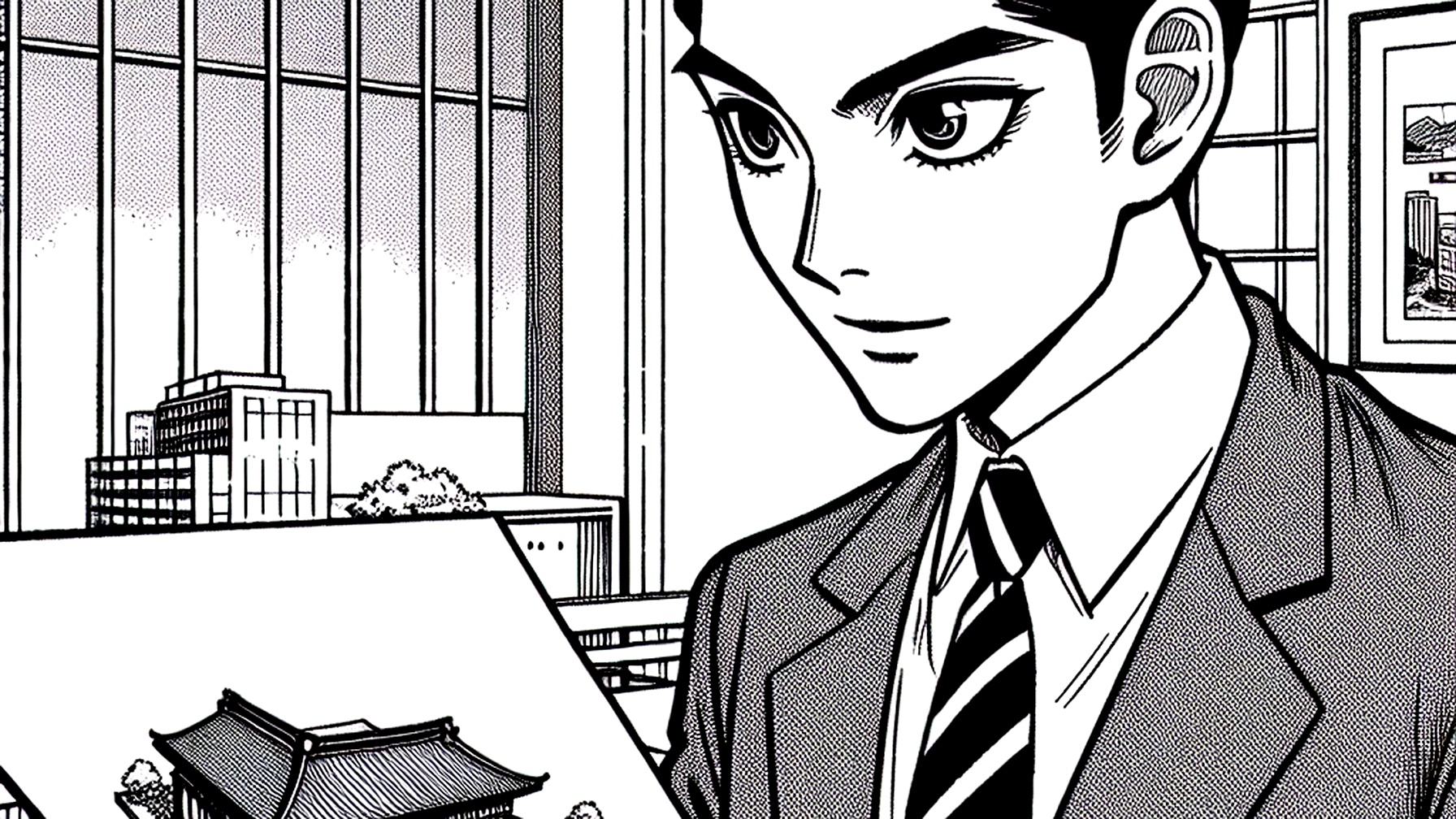
まず押さえておきたいのは、相続物件が抱える社会的課題です。2025年施行の相続登記義務化により、放置物件の名義変更が加速するといわれますが、国土交通省の令和7年版土地白書では「空き家率14.5%」が示され、問題の根深さが浮き彫りになりました。一方、多くの個人投資家が高額な現物不動産に手を出しにくい状況は続いています。
そこで登場したのが小口化で参加しやすい不動産クラウドファンディングです。金融庁が2024年に更新したガイドラインでは、1口1万円から参加できるサービスが増加し、累計募集額は対前年比38%の伸びを記録しました。言い換えると、相続で持て余した物件と投資ニーズのマッチングプラットフォームが整ったわけです。
この流れは所有者にも投資家にも好循環をもたらします。所有者は運用ノウハウや管理業務を事業者に任せながら収益分配を受けられ、投資家は少額で分散投資が可能になります。つまり、相続物件の流動化と資産形成の両立が、テクノロジーを介して現実味を帯びてきたのです。
仕組みとメリットを押さえる
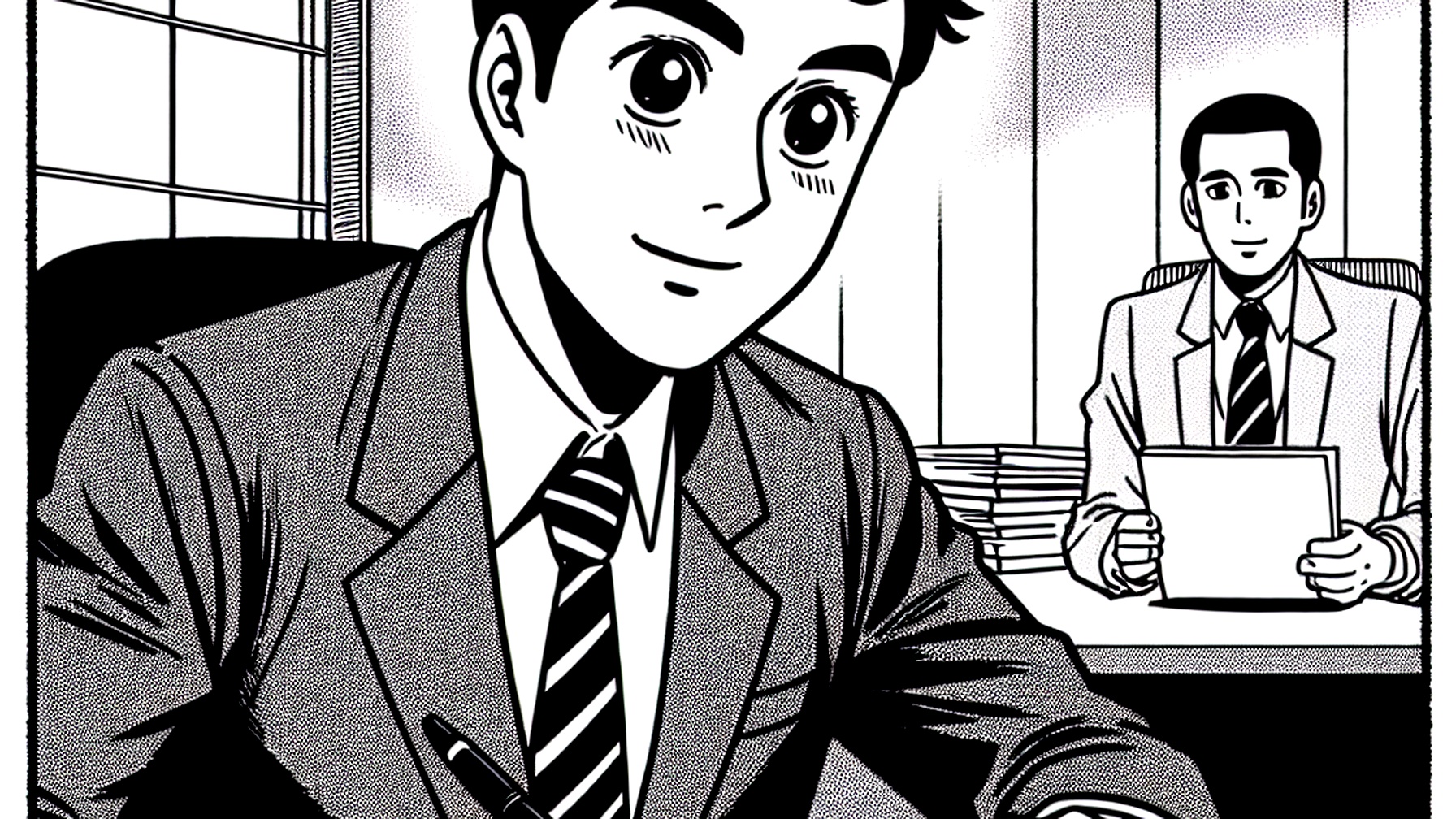
ポイントは、事業者が相続物件を匿名組合スキームなどで小口化し、インターネットで出資を募る仕組みです。投資家は利回りや運用期間を確認して出資し、家賃収入や売却益が分配されます。出資額が小さいためリスクを限定しつつ、市場調査や管理の手間を省ける点が最大の魅力です。
また、2025年10月時点で有効な「不動産特定共同事業法」改正により、オンライン完結での契約と本人確認が正式に認められ、手続きが大幅に簡素化されました。総務省の2025年版通信利用動向調査でも、成人の74%がスマホで金融取引を行うと報告されており、スマホ一台で完結する利便性が浸透しています。
さらに、相続物件の所有者が自ら運営側に回るケースも増えています。専門事業者と共同でファンドを立ち上げ、出資金の一部を自己負担しながら運用益を受け取る形です。これは売却よりも長期的な収益を得たい人にとって有効な選択肢となります。
投資前に確認すべきリスク
重要なのは、リターンだけでなく潜在的なリスクを理解することです。最も基本的なリスクは元本毀損で、入居率の低下や修繕費の増加が原因になります。国交省の「賃貸住宅市場動向調査」によると、築25年超の平均入居率は80%前後に下落するため、物件の築年数を必ず確認しましょう。
一方で流動性リスクも見逃せません。クラウドファンディングの持分は上場株のように自由に売却できず、運用期間中は資金が拘束される場合が多いです。加えて、事業者の倒産リスクも存在します。金融庁のモニタリングでは、一部事業者で内部統制の不備が指摘されており、監査報告書や運用実績の開示姿勢が判断材料になります。
こうしたリスクに対処するには、利回りが高い案件だけでなく、物件のエリア分析や事業者の財務健全性をチェックする姿勢が欠かせません。つまり、クラウドファンディングでも投資の基本原則である「分散」と「情報開示の確認」が有効なのです。
2025年度の制度と税制ポイント
まず、2025年度税制改正ではクラウドファンディングによる分配金が「雑所得」に区分される点が維持されました。総合課税になるため、給与所得と合算した税率が適用されます。給与年収が高い人ほど税負担が増すため、確定申告時に必要経費を整理しておくと節税効果が高まります。
また、相続物件をファンド化する際、所有者側が得る分配金は「不動産所得」か「事業所得」に該当するケースがあります。国税庁の2025年度通達では、管理委託の程度と独立性で判定すると示されており、税理士へ事前相談するのが安全です。
さらに、2025年度に有効な補助制度として「空き家再生等推進事業」があります。耐震改修や省エネ改修を行う場合、上限120万円の補助が受けられ、ファンド組成前のリノベーション費用を圧縮できます。ただし申請は自治体経由で、交付決定前の着工は対象外になるのでスケジュール管理が必須になります。
失敗しない案件の見極め方
実は、優良案件かどうかは「開示情報の深さ」に表れます。具体的には、運用物件のレントロール(賃料一覧)、修繕履歴、募集額に対する自己資金比率などが詳細に記載されているファンドほど実績が安定しています。逆に、利回りだけを強調し情報が薄い案件は要注意です。
次に、エリア分析では人口動態を確認しましょう。総務省の「住民基本台帳2025年版」では、三大都市圏の一部サテライト市で人口微増が続く一方、人口5万人未満の自治体は平均1.9%の減少が報告されています。地方案件でも大学や工業団地の近隣なら需要が底堅い場合があるため、賃貸ターゲットの属性を具体的にイメージすることが欠かせません。
最後に、資金管理の観点で「案件ごとの投資額を年収の10%以内に抑える」ルールを設けると、複数案件へ分散しやすくなります。この自己ルールが心理的な余裕を生み、クラウドファンディング本来のスマートな資産形成を実現します。
まとめ
ここまで、不動産クラウドファンディング 相続物件の活用法を基礎から解説しました。相続登記義務化で動き始めた物件をオンラインで小口化し、管理の手間を減らしながら収益化できる点が大きな魅力です。一方で入居率や事業者の健全性など基本的なリスクチェックを怠ると、思わぬ損失につながります。ファンド情報を精査し、税制や補助制度を活用すれば、相続物件は手間のかかる遺産から安定したキャッシュフロー源へ変わります。まずは少額から試し、データに基づく判断力を鍛えてみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 令和7年版土地白書 https://www.mlit.go.jp
- 国税庁 2025年度税制改正大綱 https://www.nta.go.jp
- 金融庁 クラウドファンディングモニタリングレポート2024 https://www.fsa.go.jp
- 総務省 2025年通信利用動向調査 https://www.soumu.go.jp
- 総務省 住民基本台帳人口移動報告2025 https://www.soumu.go.jp

