円安が進むと海外旅行や輸入品の価格が上がり、現金を持つだけでは資産が目減りするのではと不安になる人が増えます。加えて、相続時の税負担をどう抑えるかという悩みも重なり、資産防衛と承継を両立できる方法を探す声が高まっています。そこで注目されるのが不動産投資信託、いわゆるREIT(リート)です。本記事ではREITの仕組みから円安局面で得られる具体的なメリット、さらに2025年度の制度を踏まえた相続対策までを丁寧に解説します。
REITとは何かと円安の関係
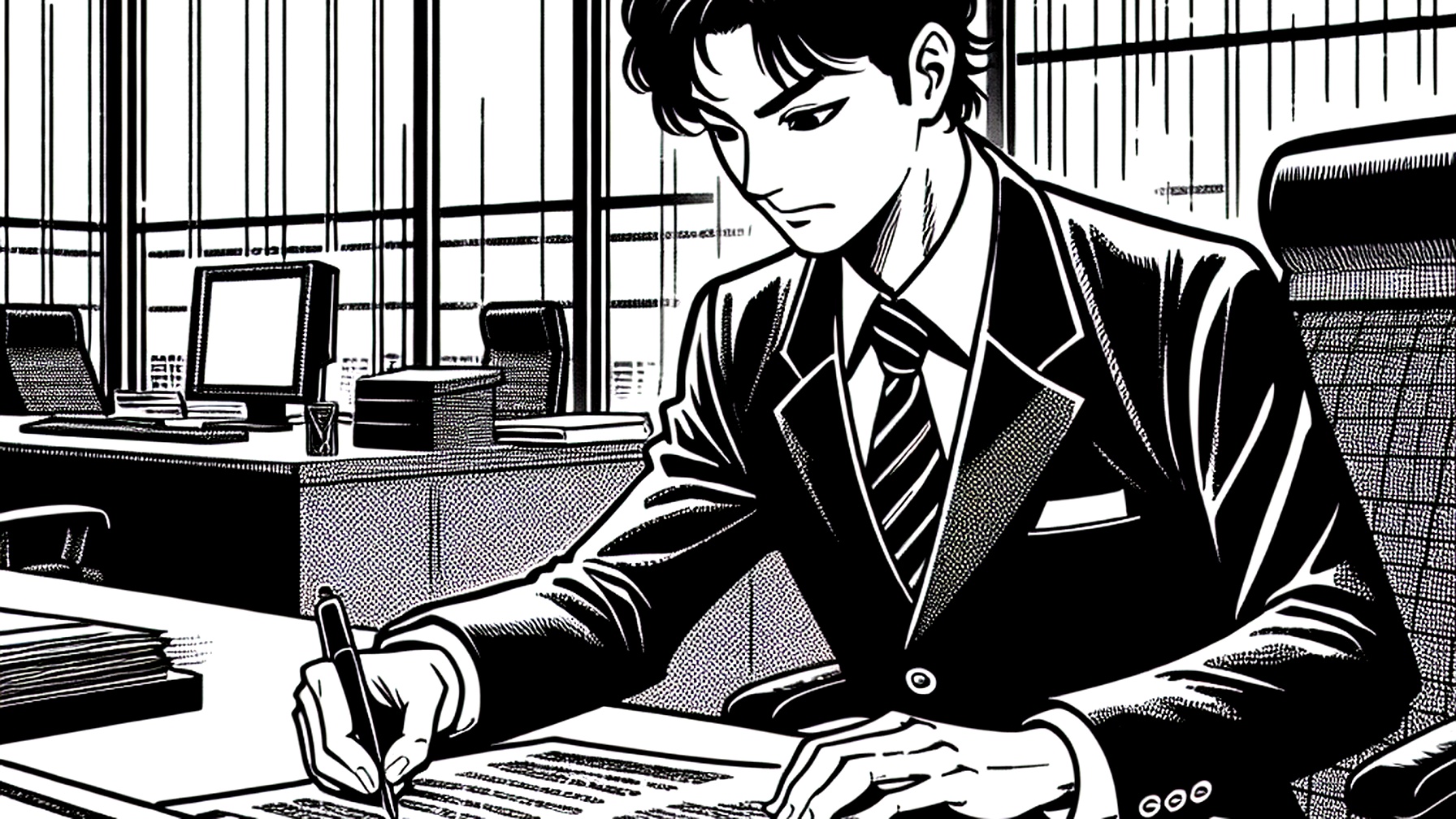
まず押さえておきたいのは、REITが多数の不動産をまとめて運用し、株式と同じように証券取引所で売買できる仕組みだという点です。投資家は一口数万円から大規模オフィスや物流施設などに間接的に出資でき、賃料収入と売却益が分配金として還元されます。つまり、個人でも手軽に分散された不動産ポートフォリオを持てるわけです。
円安はREIT市場に二つの影響を与えます。第一に、海外投資家から見ると円建て資産が割安になるため、J-REITへの資金流入が増えやすくなります。日本取引所グループの統計では、2025年上期の海外投資家によるJ-REIT買越額は前年同期比で28%増となりました。第二に、円安が国内インフレを押し上げると、賃料の上昇や不動産価格の底堅さが期待できるため、分配金水準も維持されやすくなります。
一方で為替変動による直接的なリスクは限定的です。J-REITの大半は国内不動産を保有し、収益は円で計上されるからです。したがって、円安時代においては「為替に強い国内資産を手軽に保有する手段」としてREITが選ばれる背景があります。
円安で高まるREIT投資のメリット
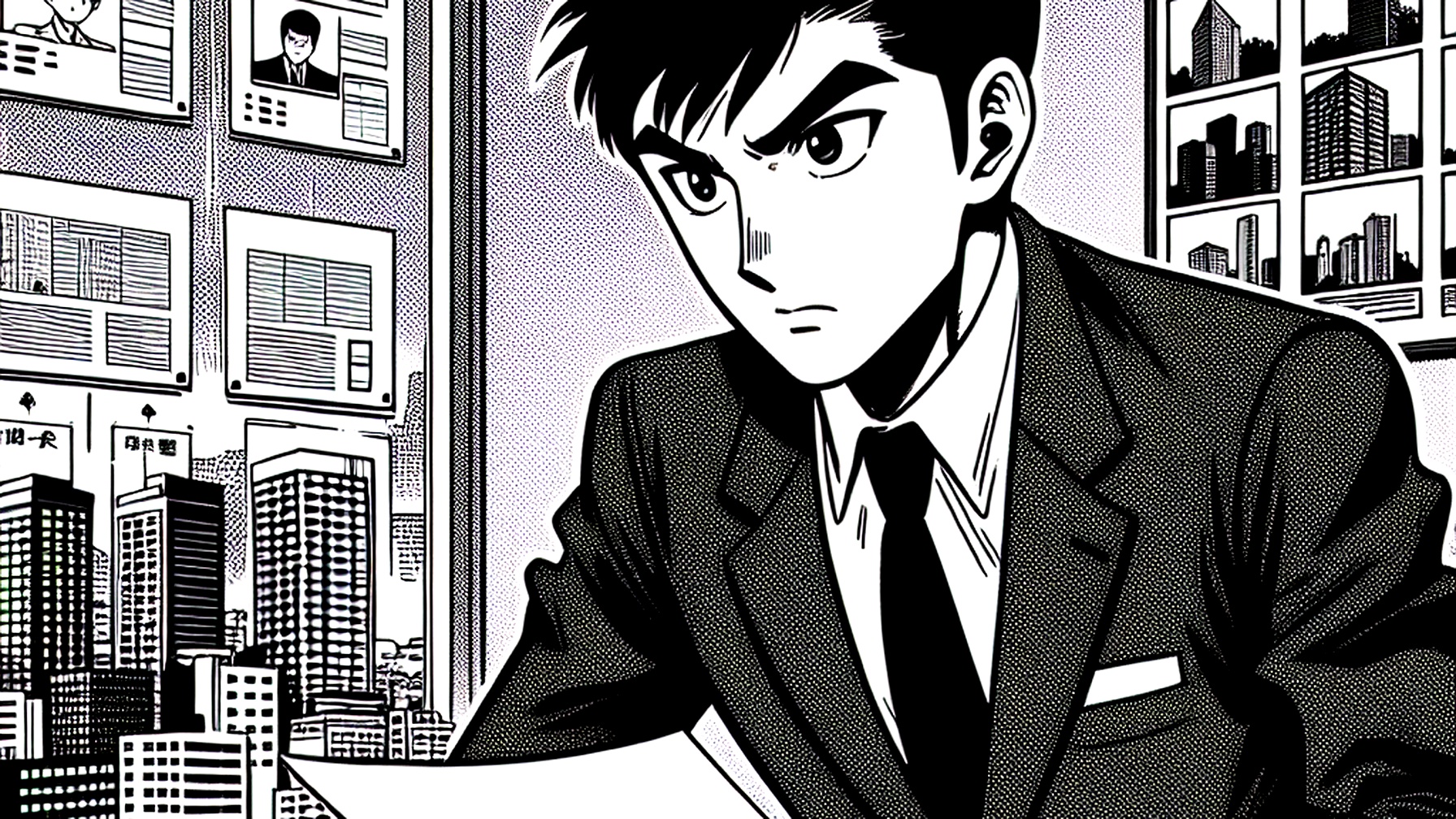
ポイントは、円安とインフレが同時に進む局面でREITが「インフレヘッジ」と「安定配当」の両方を提供する可能性が高いことです。ここでは三つの側面から具体的に見ていきます。
最初の側面は分配金利回りです。2025年9月時点の東証REIT指数に連動する平均分配金利回りは3.9%前後で、長期国債利回り(1.2%前後)を大きく上回っています。物価上昇で実質金利が低下する環境では、相対的に魅力が増すわけです。また、賃料改定が反映されるまでタイムラグはあるものの、オフィスや物流施設の一部では2〜3年ごとに賃料を見直す契約が主流で、継続的なインフレ局面なら分配金の底上げが見込めます。
次の側面は資産分散効果です。日本銀行の資金循環統計によると、家計金融資産のうち現預金は50%以上を占めています。円安で通貨価値が揺らぐとき、現預金の割合が高いポートフォリオはリスクが偏ります。REITに一部を振り向ければ、不動産という実物資産の値動きを取り込めるため、通貨下落リスクを緩和できるのです。
最後の側面は流動性の高さです。現物不動産の売却には数カ月を要しますが、REITなら株式と同じく市場で即時売買できます。急な資金需要が生じても売却しやすく、保有コストも管理費や固定資産税を直接負担しない点で明確に有利です。円安局面で機動的に利益を確定したい場合、この流動性が大きな武器になります。
相続対策としてのREIT活用法
実はREITは相続対策でも効果を発揮します。相続税の課税対象は評価額で決まりますが、上場株式に該当するREITの評価額は「相続開始日の終値の月末平均」などで算出されるため、市場価格が基準となります。これにより、元本を上回る評価減メリットは得にくいものの、流動性と分散効果という別の強みがあります。
まず、共有名義問題を避けられる点が重要です。現物不動産を複数の相続人で共有すると、売却や修繕の意思決定が難航することが多々あります。その点、REITなら保有口数を分けて遺贈でき、現金化も容易なため、相続後のトラブルを避けやすいのです。
さらに、2025年度の税制では「配偶者居住権」や「小規模宅地等の特例」など不動産評価を圧縮する措置が維持されていますが、これらは自宅や事業用宅地が対象です。投資用マンションなどには適用されません。REITであれば当初から市場価格が基準となり、評価圧縮策を無理に狙う必要がない分、相続計画をシンプルにできます。
加えて、生前贈与と組み合わせる方法も考えられます。暦年贈与の基礎控除(年110万円)を利用し、毎年少しずつREIT口数を移転すれば、大きな贈与税を回避しつつ資産承継が可能です。贈与資金が再投資される間も分配金が得られるため、家族全体で資産を増やすサイクルを作りやすい点も見逃せません。
2025年度の税制と制度上のポイント
基本的に、REIT投資に対する税制は上場株式と同じ分離課税で、譲渡益と分配金に対して20.315%(所得税・住民税・復興特別所得税を合算)が課されます。2025年度税制改正ではこの税率に変更はなく、配当控除も適用外という点が従来通りです。
一方、少額投資非課税制度(NISA)は2024年に恒久化され、2025年も年間投資枠は「成長投資枠240万円、つみたて投資枠120万円」のまま維持されています。REITは成長投資枠で購入でき、非課税保有限度額1,800万円の一部としてカウントされます。つまり、分配金も売却益も非課税で運用できるため、長期保有のインセンティブが大きいわけです。
また、個人型確定拠出年金(iDeCo)は2024年から拠出上限を月額68,000円(企業型加入者は同54,000円)に引き上げており、2025年度も同水準が継続します。iDeCo口座内で購入できるREITインデックスファンドも増え、掛金を全額所得控除しつつREITのリターンを積み立てる選択肢が広がりました。
制度利用には期限もあります。NISAは非課税期間が無期限化されたものの、年間投資枠の余りは翌年へ繰り越せません。iDeCoは60歳まで引き出せないため、流動性確保には通常口座や特定口座のREITを組み合わせる必要があります。制度の特徴を理解し、相続計画やライフイベントに合わせて資金配分することが大切です。
リスク管理と銘柄選びの基本
重要なのは、REITが万能ではない点を理解し、リスク管理を徹底することです。価格変動リスクは株式市場と連動する部分があり、短期的には10%前後の調整も珍しくありません。2020年のコロナ急落では東証REIT指数が1カ月で36%下落した事例があります。こうした過去データを踏まえ、投資比率を調整する姿勢が欠かせません。
次に、ポートフォリオの分散が鍵になります。J-REITにはオフィス、商業施設、物流、ホテル、住宅など多様なセクターがあり、景気や円安の影響が異なります。例えば、円安が訪日観光を押し上げればホテル系REITが恩恵を受ける一方、テレワーク定着でオフィス系は空室率が上がるかもしれません。セクターを横断して組み合わせることで、特定業種の不振を補い合えるのです。
最後に、スポンサー企業の財務健全性や物件取得戦略も重視しましょう。大手デベロッパーやインフラ企業が支援するREITは資金調達力に優れ、円安局面での国外物件の買収など成長オプションを持ちやすい傾向にあります。IR資料でLTV(負債比率)が50%以下に抑えられているか、平均借入金利が上昇局面でも固定化されているかを確認すると、安心感が高まります。
まとめ
本稿では円安時代におけるREITのメリットと相続対策を中心に解説しました。円安が続くとき、REITはインフレ耐性と高い流動性を同時に提供し、海外マネー流入も追い風になります。相続面では分けやすさと市場価格評価の明快さが魅力で、NISAやiDeCoを活用すれば税負担を抑えながら次世代へ資産を移せます。結論として、現預金に偏った資産構成を見直し、分散と承継を意識してREITを適切な比率で組み込むことが、2025年の円安環境を乗り切る現実的な一歩と言えるでしょう。
参考文献・出典
- 日本取引所グループ(JPX) – https://www.jpx.co.jp
- 日本銀行 資金循環統計 – https://www.boj.or.jp/statistics/sj/sjexp.pdf
- 国土交通省 国土交通白書2025 – https://www.mlit.go.jp
- 国税庁 相続税申告の手引(令和7年度版) – https://www.nta.go.jp
- 金融庁 NISA・iDeCo制度説明資料2025 – https://www.fsa.go.jp

