資産形成を始めたいけれど、現物不動産にするかREIT(不動産投資信託)にするか決めきれない──そんな悩みを抱える人は少なくありません。特に最近は築浅物件が注目され、情報もあふれていますが、選択肢が広がるほど判断は難しくなります。本記事では「比較 REIT 築浅」というキーワードを軸に、両者の特徴を分かりやすく解説します。読み終えるころには、自分に合った投資スタイルを見極める具体的な手がかりが得られるでしょう。
キャッシュフローで見る築浅物件とREITの違い
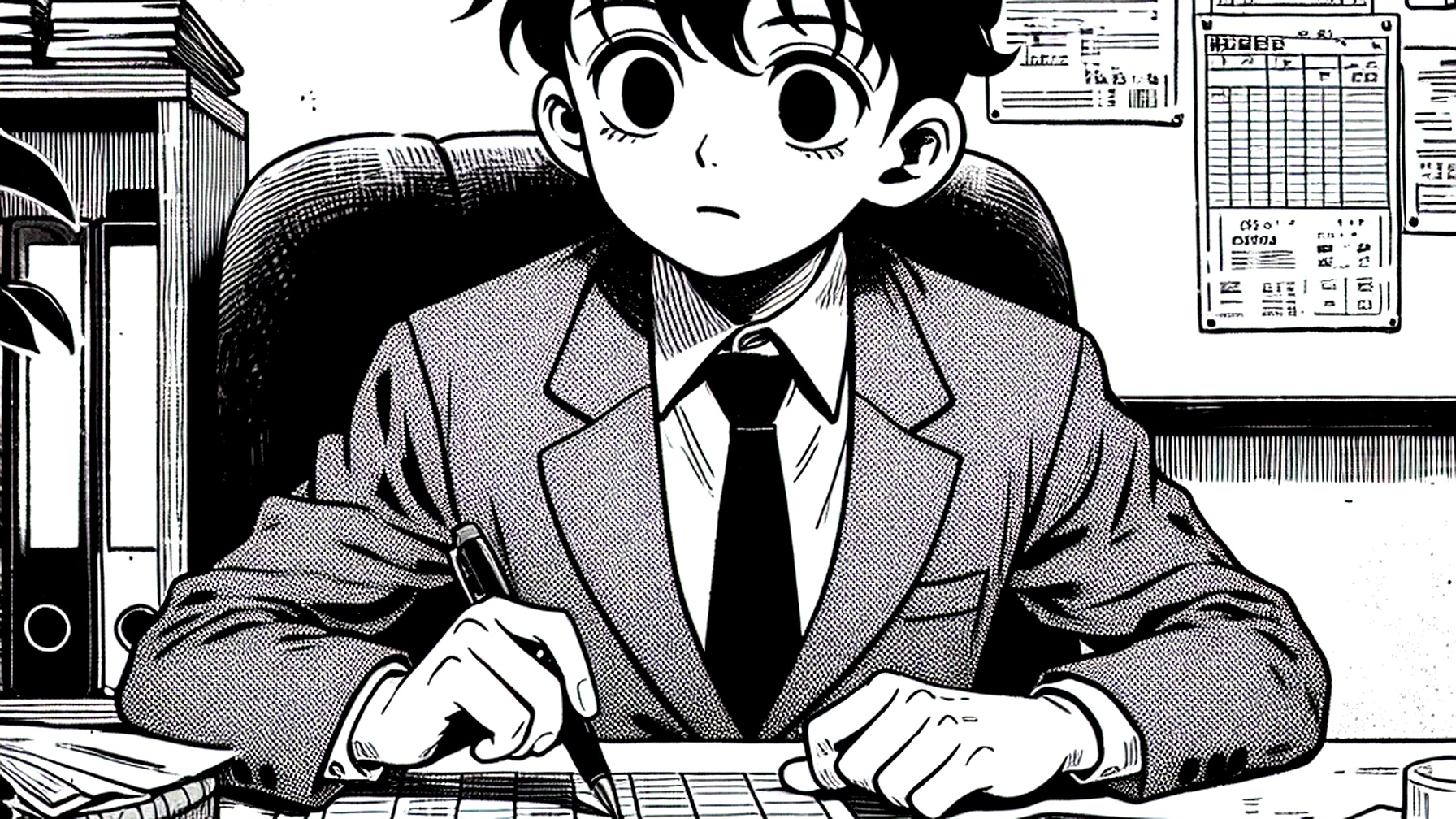
重要なのは、毎月手元に残るお金をどう管理できるかを理解することです。キャッシュフローとは家賃収入や分配金から諸費用を差し引いた残額を指し、投資の継続性を左右します。
まず築浅物件の場合、家賃下落が緩やかで修繕費も少ないため、購入後5年間は手取り率が高くなる傾向があります。国土交通省「賃貸住宅市場データブック2025」によると、築5年以内の首都圏平均家賃は築20年超より約28%高く、空室率も3ポイント低いと分析されています。一方でローン返済が重く、金利上昇局面ではキャッシュフローが急減するリスクが残ります。
これに対しREITは物件管理費や借入金の調整を運用会社が担い、投資家には分配金という形で利益が還元されます。2025年10月時点の東証REIT指数平均分配利回りは3.7%前後で推移し、日本銀行のマイナス金利解除後も安定が続いています。分配金は四半期ごとに支払われるため、キャッシュフローが読みやすいのが特徴です。
つまり、短期的な手取り率の高さを狙うなら築浅物件、収益の安定性と流動性を優先するならREITが有利となります。ただし後述するリスクと費用の全体像を踏まえ、「比較 REIT 築浅」で見た違いを総合的に判断することが欠かせません。
築浅物件投資のメリットと落とし穴
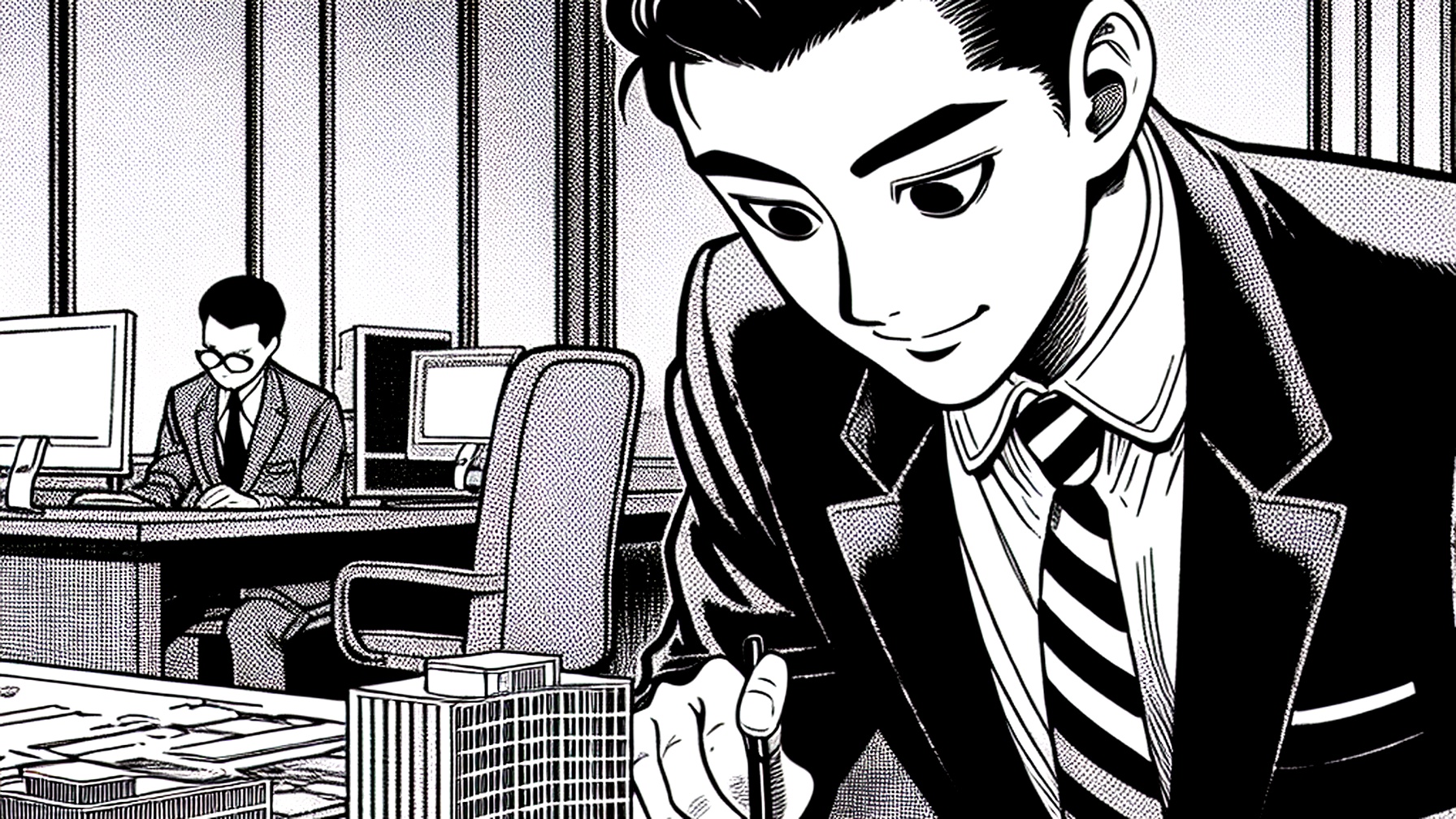
まず押さえておきたいのは、築浅物件が持つ資産価値の保ちやすさです。新耐震基準や最新の省エネ性能を満たす物件は、退去後の再募集でも高い募集賃料を維持しやすい傾向があります。さらに2025年度も継続中の固定資産税減額措置※により、最初の3年間は税負担が半額になる点が収益を押し上げます。
しかし、メリットの裏には落とし穴も存在します。最大の注意点は購入価格が高く、表面利回りが低くなりがちな点です。金融機関の融資姿勢は2023年以降引き締まり、自己資金20%以上を求めるケースが増えています。自己資金を押し上げると、投下資本利益率(ROI)が想定より下がる恐れがあります。
また、築浅物件は一見修繕費が少なく見えますが、10年目以降にエレベータや給湯設備の更新が重なることがあります。国交省「賃貸住宅修繕実態調査2024」では築10〜15年で平均90万円の大規模修繕を実施したデータが報告されており、長期保有なら修繕積立の準備が必須です。
さらに、借上げ保証(サブリース)を利用すると、初期の家賃が高く設定されがちですが、契約更新時に10%前後の減額要請を受けることもあります。契約内容を正しく理解し、シミュレーションを保守的に作成する姿勢が欠かせません。
REIT投資で得られる安定性と分散効果
ポイントは、小口化によるリスク分散と透明性の高さにあります。REITは複数の不動産をポートフォリオに組み込むため、単一物件の空室や災害リスクが分散されます。日本取引所グループの統計では、上位10銘柄でもオフィス・住宅・物流などセクターが分散されており、地震保険やテナント保険も運用会社が包括契約しています。
さらに、東証REIT指数は2020〜2025年で年率6.3%のトータルリターン(分配金込み)を記録し、株式市場の日経平均と同水準の成長を見せました。また、売買単位は1口で数万円から購入できるため、初心者でも段階的に投資額を増やせます。信託報酬(運用コスト)は年率0.3〜0.6%が中心で、現物不動産の管理料や固定資産税と比べてコスト構造が明瞭です。
一方でREITにも価格変動リスクがあります。金利上昇局面では借入コストが増え、分配金の減額や基準価額の下落を招く場合があります。ただ、J-REIT全体の平均LTV(借入比率)は2025年6月で約44%と、金融危機時の60%超から大幅に改善しています。運用会社が金利ヘッジを施していることも、キャッシュフローの安定に寄与しています。
言い換えると、REITは「小口・分散・透明」という三つの特徴で個人投資家をサポートしますが、長期的に市場と向き合う姿勢が必要です。配当利回りだけでなく、スポンサー企業の信頼性やポートフォリオの地域・用途分散を確認することで、リスクをコントロールできます。
収益シミュレーションで実力を測る方法
実は、築浅物件とREITの優劣を語るうえで欠かせないのが収益シミュレーションです。数字を並べるだけでなく、前提条件をそろえて比較することで真の違いが浮き彫りになります。
たとえば築浅区分マンション(価格3,500万円、家賃12万円、空室率5%)と、購入価格同額のREIT口数(平均利回り3.7%)を比較します。ローン金利1.3%、期間30年、管理費・修繕積立金月2万円で試算すると、初年度の手取りキャッシュフローは物件が約34万円、REITが約129万円となります。ただし物件は借入を活用しているため、元本返済で純資産が年60万円強増える点が魅力です。
さらに、空室率が15%へ悪化し、金利が2.5%に上昇したケースも見ておきましょう。築浅物件はキャッシュフローがマイナス66万円に転落しますが、REITは分配金減少を1割程度にとどめるという結果が得られました。これにより、レバレッジを利用する物件投資はシナリオに敏感であることが明確になります。
結論として、シミュレーションは楽観・悲観の両方を設定し、10年後の純資産とトータルリターンを比べることが重要です。ここで初めて「比較 REIT 築浅」のどちらが自分の目的に適合するかがわかります。数字が裏付けると、感情に流されない堅実な意思決定が可能になるでしょう。
まとめ
築浅物件は高めの家賃と税制優遇で短期の収益力が際立ちますが、金利や修繕費の影響を強く受けます。一方、REITは小口で分散が効き、運用コストが明瞭なため安定したキャッシュフローを得やすい反面、市場変動と金利動向に左右されます。まず自己資金やリスク許容度を整理し、同じ前提でシミュレーションを行うことが成功への近道です。本記事を参考に、自分自身の目的に合った投資戦略を選び、次の一歩を踏み出してみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 賃貸住宅市場データブック2025 – https://www.mlit.go.jp
- 国土交通省 賃貸住宅修繕実態調査2024 – https://www.mlit.go.jp
- 日本取引所グループ 東証REIT指数データ – https://www.jpx.co.jp
- 日本銀行 金融システムレポート2025年4月 – https://www.boj.or.jp
- 総務省 固定資産税に関する資料(2025年度) – https://www.soumu.go.jp

