不動産投資に興味はあるものの、高額な自己資金や空室リスクが心配で一歩踏み出せない人は少なくありません。特に堅牢で人気の高い鉄骨造(てっこつぞう)の物件は魅力的ですが、現物を購入するとなるとハードルが高いのが現実です。そこで注目されるのが不動産投資信託「REIT(リート)」を通じて鉄骨造物件に間接的に投資する方法です。本記事では、2025年10月時点の最新情報をもとに、初心者でも理解できる鉄骨造 REIT 始め方を丁寧に解説します。リスクを抑えながら安定したインカムゲインを得たい方は、ぜひ最後まで読み進めてください。
鉄骨造の特徴を押さえる
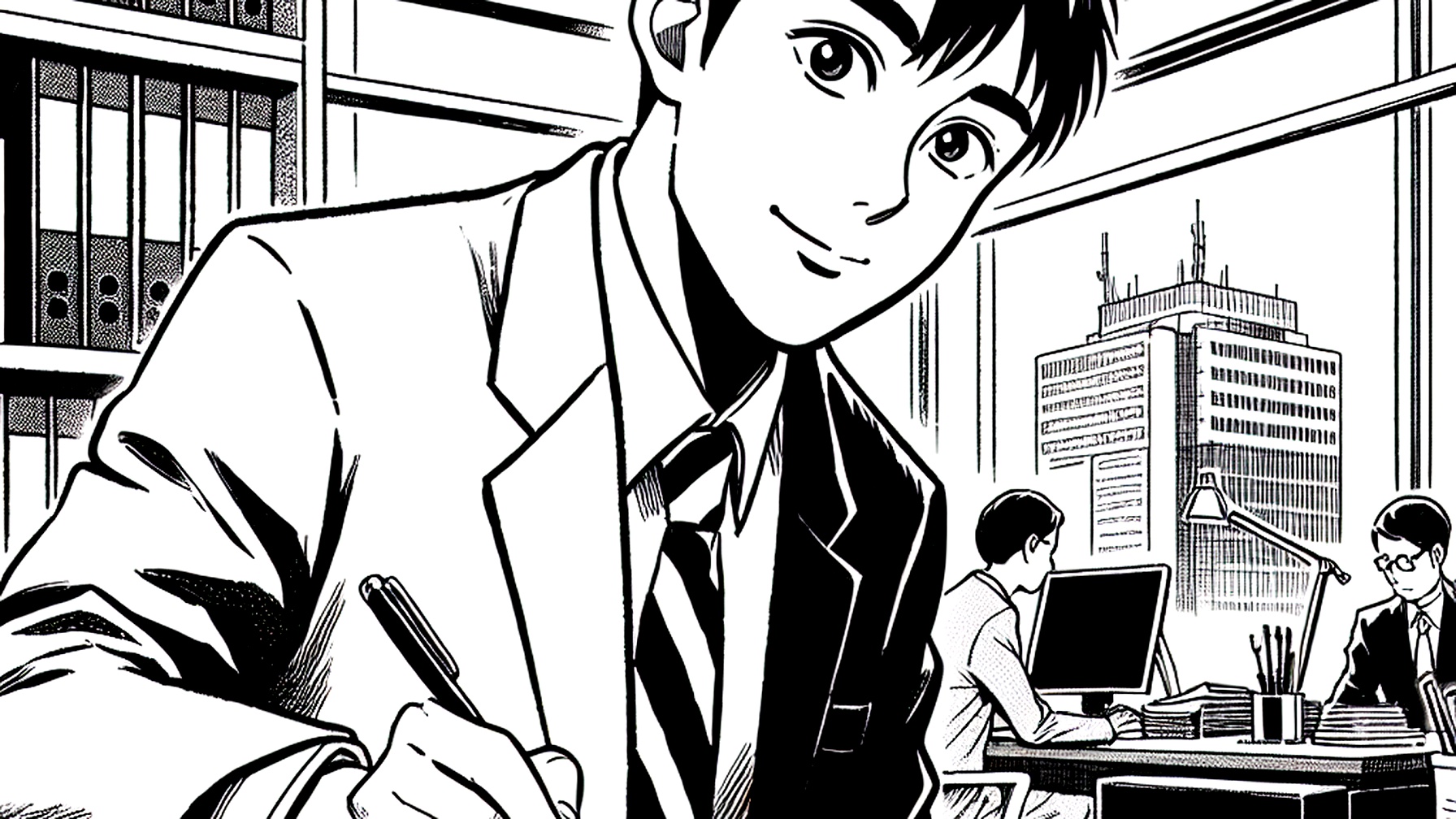
重要なのは、鉄骨造が木造や鉄筋コンクリート造(RC造)とどのように違うかを知ることです。耐震性や耐久性に優れ、修繕周期が長い点が鉄骨造の大きな魅力になります。
まず、国土交通省の建築着工統計によると、2024年度に新築された中層マンションの約47%が鉄骨造でした。これは軽量鉄骨を含めた割合で、耐震性能の向上とコストのバランスが評価されています。一方で、木造は初期費用が抑えられるものの、定期的な大規模修繕や火災保険料の上昇がネックになります。RC造は耐久性こそ最も高いものの、構造体が重く建設費が増大しやすい点が課題です。
鉄骨造は、これらの中間に位置する存在として、ランニングコストとリセールバリューの両面で優位性を持ちます。また、2025年度の賃貸住宅市場調査では、鉄骨造物件の平均空室率が6.1%で、木造の7.8%より低い水準でした。つまり、鉄骨造は投資家が求める安定収益を実現しやすい構造と言えるのです。
REITの仕組みを理解する
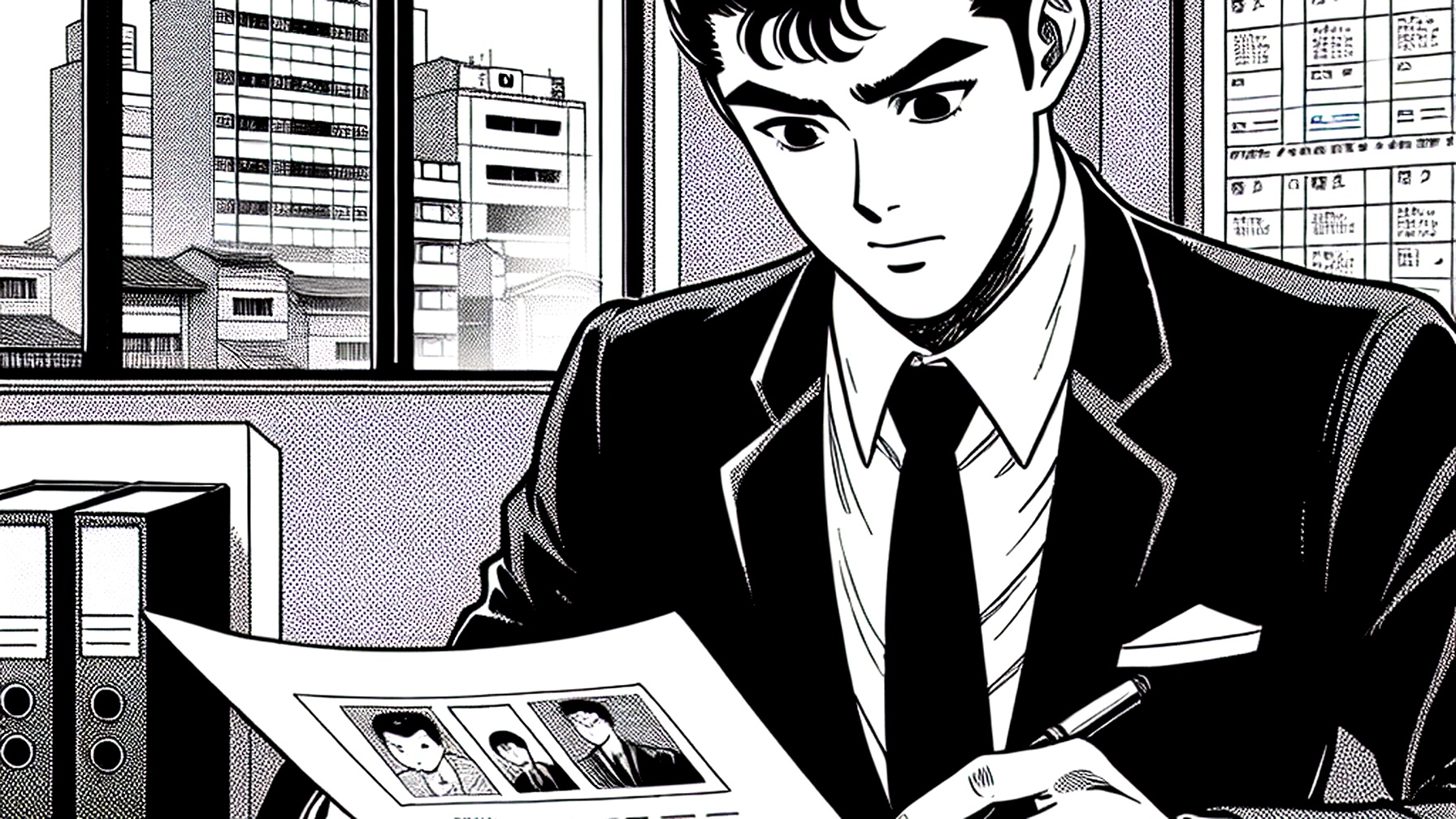
ポイントは、REITが多くの投資家から資金を集めて複数の不動産を運用し、その賃料収入や売却益を分配する仕組みであることを理解することです。株式と同じように証券取引所で売買できるため、少額からでも参加できます。
J-REIT(ジェイ・リート)は東証に上場する国内REITの総称で、2025年9月末時点で64銘柄が取引されています。平均分配利回りは3.8%前後で、低金利環境下でも相対的に魅力的です。加えて、REITが収益の90%以上を配当することで法人税が免除される「投資法人課税特例」が継続しているため、投資家は高い分配金を受け取りやすい仕組みになっています。
REITの保有資産にはオフィス、住宅、商業施設、物流施設など多様なカテゴリーがあります。鉄骨造の住宅や物流施設に特化した銘柄も複数存在し、用途別比率や地域分散の情報は各投資法人のアセットマネジメントレポートで公開されています。つまり、銘柄選びの段階で鉄骨造物件への投資比率を確認することが可能なのです。
鉄骨造が多いREITを選ぶ視点
実は、全てのREITが鉄骨造物件を多く持つわけではありません。そこで、ポートフォリオの構成比率と運用方針をチェックする必要があります。
まず押さえておきたいのは、住宅系REITと物流特化型REITの多くが鉄骨造物件を主力としている点です。住宅系では「アドバンス・レジデンス投資法人」が、2025年6月期時点で保有資産の約73%を鉄骨造が占めます。物流系では「日本ロジスティクスファンド投資法人」が、耐震性能と天井高を確保する目的で鉄骨造倉庫を多数組み入れています。
さらに、物件の築年数と改修履歴も要チェックです。一般に鉄骨造は築20年を超えると大規模修繕が必要になることが多く、修繕コストが一時的に分配金を圧迫する可能性があります。ただし、2025年度から適用されている「長寿命化改修費税額控除」により、一定の省エネ改修を行った場合に法人税の特別控除を受けられるため、修繕負担を抑えつつ競争力を高める事例が増えています。
繰り返しになりますが、銘柄を比較するときはIR資料に記載された「構造別割合」「築年数別割合」を確認し、自分のリスク許容度と照らし合わせることが欠かせません。
個人投資家が始める手順と注意点
まず押さえておきたいのは、証券口座を開設し、購入資金を準備するまでの流れを整理することです。投資初心者でも迷わないよう、手順は次の三つに集約できます。
- ネット証券で総合取引口座と2024年に刷新された新NISA口座を同時に開設
- 取扱銘柄検索で鉄骨造比率の高いREITをリストアップし、分配利回りやLTV(負債比率)を比較
- 成行または指値注文で少額購入し、四半期ごとにIR情報を確認して保有方針を見直す
ここで重要なのは、レバレッジを掛けすぎないことです。REIT自体が不動産担保のローンで資産を購入しているため、高いLTVの銘柄を選ぶとダブルでリスクが高まります。また、配当権利落ち日直後に価格が調整されることがあるため、購入タイミングにも注意しましょう。
さらに、2025年度の税制改正でNISAの年間投資上限は成長投資枠240万円、つみたて枠120万円の合計360万円になっています。REITは成長投資枠の対象となるため、非課税枠を活用することで分配金にかかる約20%の税金を回避できます。言い換えると、NISA枠を上手に使うことが、手取り利回りを最大化する鍵になるのです。
最後に、流動性リスクを見落とさないように注意してください。時価総額が小さい銘柄は、急な売買で価格変動が大きくなる傾向があり、想定通りに売却できない場合があります。平均売買代金が一日5億円以上の銘柄を選ぶと、ある程度の流動性は確保できるでしょう。
2025年度の制度を活用した投資戦略
ポイントは、最新の政策や補助策を把握し、投資効率を高めることです。国土交通省は2023年度から継続している「省エネルギー性能向上計画制度」を2025年度に拡充し、REITも改修計画を届け出ることで固定資産税の軽減措置を受けられる仕組みを維持しています。
REITがこうした制度を活用すると、改修後の稼働率向上と税コスト削減が分配金へ還元されやすくなります。また、環境配慮型の投資を支援する「グリーンボンドガイドライン2024」も引き続き有効で、グリーンREIT債を発行した場合、金融機関からの調達金利が0.1〜0.2%優遇されるケースが増えています。
これらを踏まえると、環境認証(CASBEEやBELS)の取得割合が高いREITや、ESGレポートを詳細に開示している投資法人を選ぶことで、中長期的に安定した利回りが期待できます。つまり、制度をうまく使っているREITほど、収益と資産価値の両面で優位に立つ可能性があるのです。
さらに、日本銀行が2025年4月に実施した政策点検で、長期金利の誘導目標を0.75%前後に据え置いたことから、当面の金利上昇幅は限定的と見る向きが多い状況です。REITの借入コストが急激に上がりにくい環境が続けば、分配金は一定程度守られると考えられます。ただし、物価上昇によるテナント退去リスクには目を配り、四半期決算ごとに運営状況を確認する姿勢が欠かせません。
まとめ
本記事では、鉄骨造 REIT 始め方をテーマに、構造の特徴、REITの仕組み、銘柄選び、実際の手続き、そして2025年度の政策活用までを解説しました。鉄骨造は耐震性とコストバランスに優れ、REITを通じて少額から投資できる点が大きな魅力です。まずはNISA枠を活用し、鉄骨造比率の高い銘柄を小口で購入しながら、IR情報で運用状況を確認する習慣を身につけましょう。制度や市場環境を味方につけて、安定したキャッシュフローを確保する一歩を踏み出してみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 建築着工統計調査報告 2024年度版 – https://www.mlit.go.jp
- 国土交通省 賃貸住宅市場の実態調査 2025年度 – https://www.mlit.go.jp
- 東証 REIT分配利回り月次データ 2025年9月 – https://www.jpx.co.jp
- 財務省 税制改正大綱 2025年度 – https://www.mof.go.jp
- 日本銀行 金融政策決定会合議事要旨 2025年4月 – https://www.boj.or.jp

