不動産投資を続けていると、節税や資金調達の壁にぶつかる方が少なくありません。個人名義で始めやすい一方、所得が増えるほど税率が上がり、次の一手に悩むケースが多いからです。本記事では「不動産投資 法人化 メリット」を軸に、2025年10月時点で有効な制度と数字を交えながら、初心者でも理解しやすい形で法人化の利点と注意点を解説します。読み終えるころには、自身の投資ステージに合わせた最適な選択肢が見えてくるはずです。
法人化で節税効果が高まる仕組み
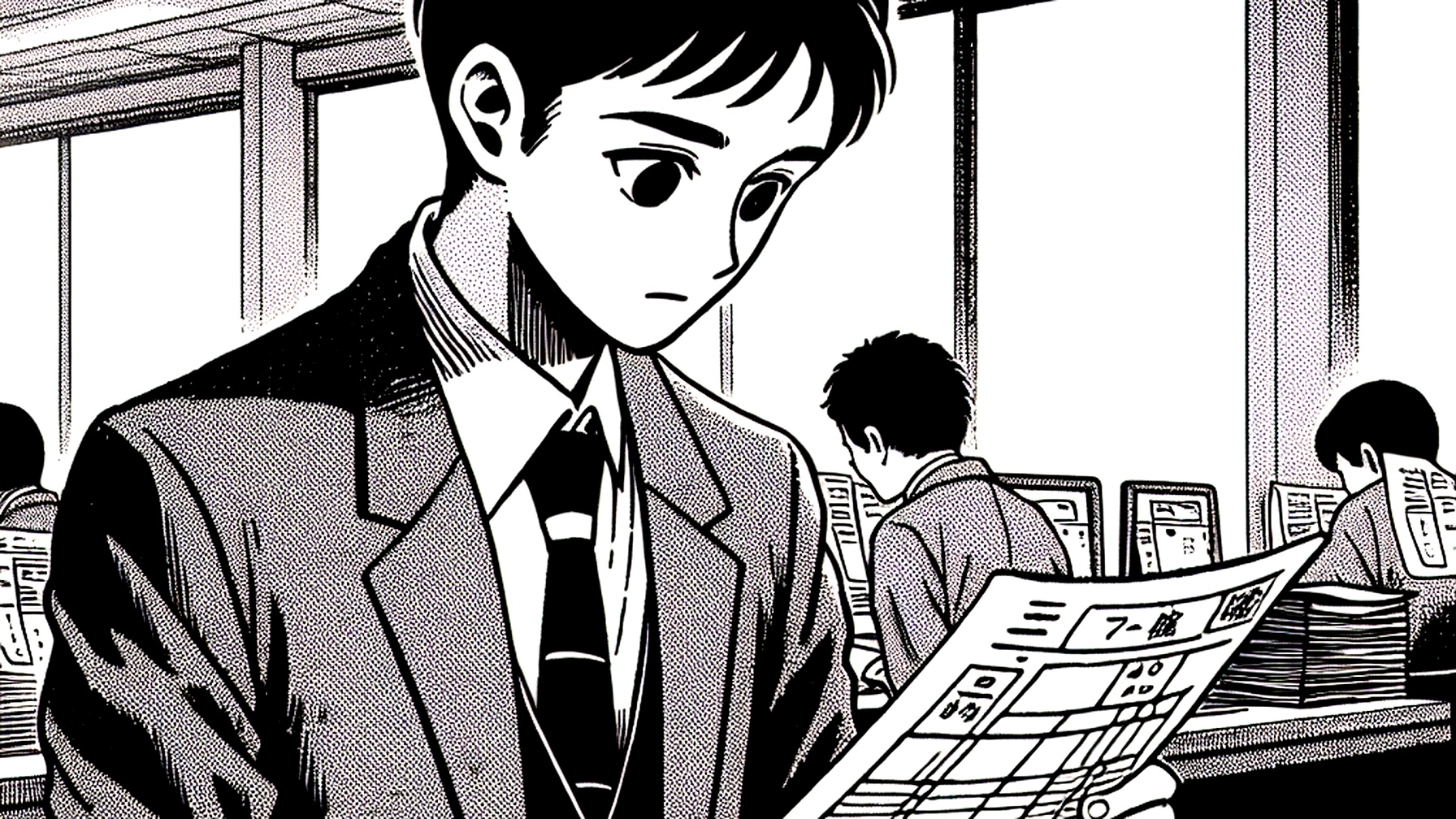
重要なのは、税率構造の違いを正しく把握することです。個人の不動産所得は累進課税で最大45%まで上がりますが、2025年度の中小法人の実効税率はおおむね23.2〜33%に収まります。この差が大きくなるのは、課税所得が900万円を超えるあたりからです。
まず、法人では役員報酬を経費計上できるため、所得を分散させつつ可処分所得を確保できます。つまり、同じ家賃収入でも手取りが増える可能性が高いのです。また、減価償却費を早めに計上しやすい点も見逃せません。土地付き中古アパートを個人で買うと耐用年数の残存期間が短くなる一方、法人では独自の償却計画を立てやすく、キャッシュフローを安定させる効果が期待できます。
さらに、2025年度時点で継続している「中小企業投資促進税制」を活用すれば、一定のエネルギー効率改善工事に対し即時償却が可能です。これは個人事業主では対象外となるため、法人化の優位性が際立ちます。一方で、住民税均等割(最低7万円/年)や事務コストが増える点は計算に入れておきましょう。
資金調達力が大きく広がる
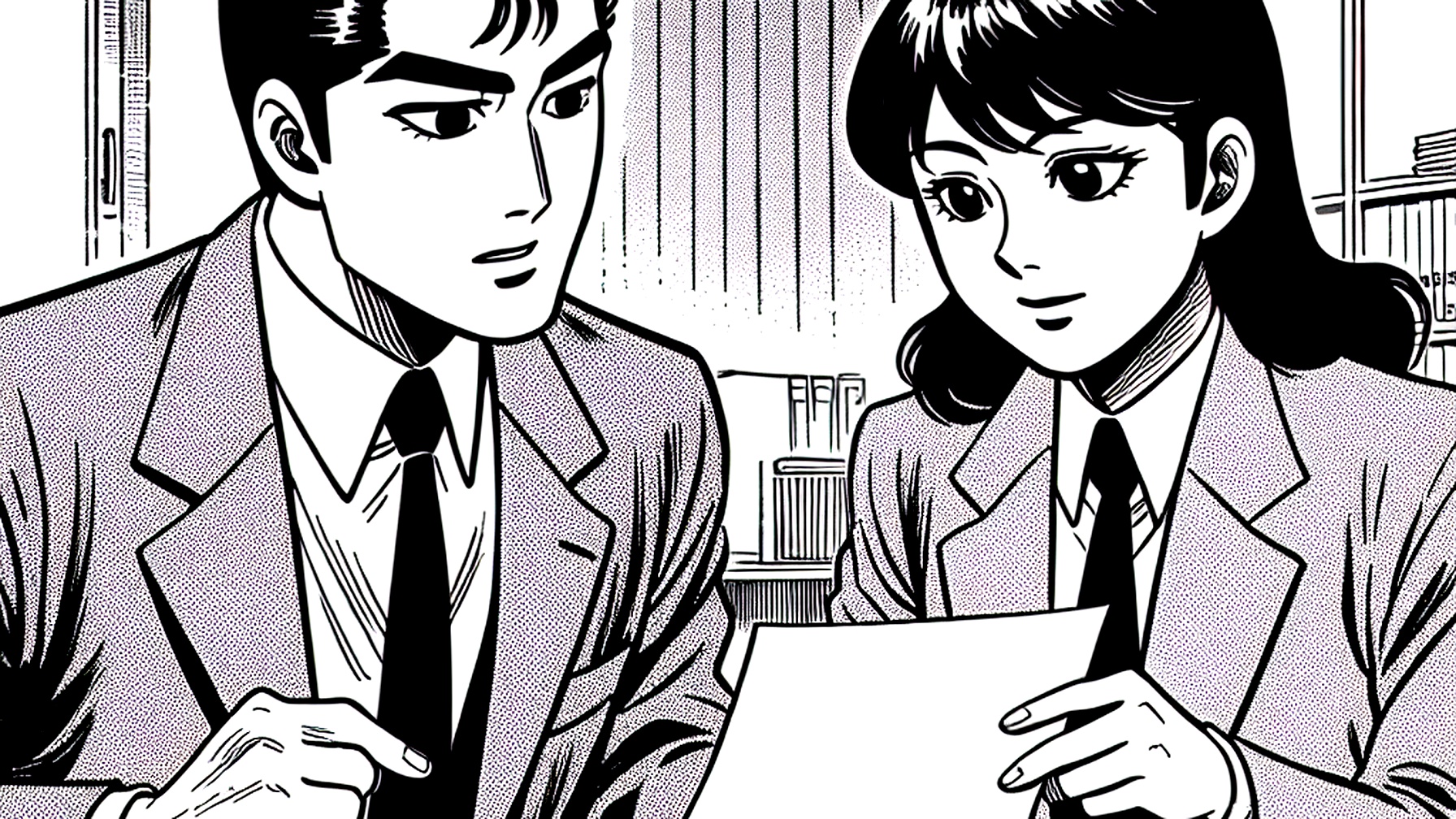
ポイントは、法人が金融機関から受ける評価軸が個人とは異なることです。個人では年収と返済負担率が最重視される一方、法人では事業計画と物件の収益性が評価対象となります。その結果、同じ物件でも法人名義のほうが長期・低金利で融資を得られるケースが増えています。
実は、日本政策金融公庫の2024年度実績では、不動産賃貸業向け融資の平均金利は2.0%前後でした。これに対し、地方銀行の個人向けアパートローン平均金利は2.8%と0.8ポイント高い水準です。長期で見れば総返済額の差は数百万円に達します。また、法人の決算書は複数年の実績を積み上げられるため、将来的にリファイナンス(借り換え)を狙う際の交渉材料になります。
ただし、設立初年度は決算実績が乏しいため、代表者の連帯保証を求められるのが一般的です。この期間を乗り切るには、自己資金比率をやや厚めにし、早期に黒字決算を作る戦略が現実的でしょう。
相続・事業承継をスムーズにできる
まず押さえておきたいのは、株式という形で資産を一括管理できる点です。個人保有だと物件ごとに相続登記が必要ですが、法人化すれば株式を後継者へ移転するだけで権利が引き継がれます。これにより相続コストと時間を大幅に削減できます。
さらに、2025年度の相続税評価は土地・建物ごとに行われるため、個人名義では評価額が高止まりしやすい一方、法人株式は取引相場のない株式として原則類似業種比準価額で算出されます。これが純資産の圧縮効果を生み、最終的に相続税額を抑えられる可能性が高まります。
一方で、オーナーが自己資金を法人に貸し付けた場合、その貸付金が相続財産に計上される点には注意が必要です。適切な資本金構成や贈与計画を税理士と相談し、二重課税を避ける設計が欠かせません。
損益通算と赤字繰越の柔軟性
実は、法人では赤字を最大10年間繰り越せます(2025年度現行法)。個人の不動産所得は赤字が生じても損益通算の範囲が限定的で、3年しか繰り越せません。この期間差は、築古物件の大規模修繕や一時的な空室リスクに直面した際、大きな安心材料になります。
また、法人化すれば本業が別にあるサラリーマン投資家でも、会社の給与所得と賃貸事業の赤字を合算する必要がなくなります。つまり、賃貸事業は賃貸事業として独立した損益管理が可能です。これにより節税の自由度が高まり、投資戦略を柔軟に描けます。
ただし、赤字を長期化させると金融機関の評価が下がる点は忘れてはいけません。計画的に黒字転換する目標を立て、決算期ごとに財務バランスを調整する運営が求められます。
法人化する際の実務コストとリスク
まず、株式会社か合同会社を選ぶ段階でコストと柔軟性が変わります。設立費用は株式会社で約25万円、合同会社で約10万円が相場です。加えて、毎年の決算申告に税理士報酬が20〜40万円かかる点も外せません。個人の確定申告より負担が大きいため、年間節税額がこれを上回るかシミュレーションが必要です。
役員報酬の設定を誤ると、社会保険料が想定以上に増えるリスクもあります。2025年度の健康保険・厚生年金合わせた負担率は約29%です。高めの報酬を取れば手取りが減り、法人側のキャッシュも圧迫されるため、配当や退職金を組み合わせた長期計画が重要です。
さらに、法人名義の融資には代表者個人の連帯保証が付く場合が多く、万が一の際に責任が限定されるわけではありません。物件管理が甘いと、法人でも個人でもダメージを受ける点は変わらないので、管理会社との連携や修繕計画を怠らない姿勢が欠かせません。
まとめ
法人化は節税・資金調達・相続対策など多角的なメリットをもたらしますが、設立コストや事務負担が増える点も避けて通れません。年間家賃収入が900万円を超え、所得税率が30%を上回るあたりが検討タイミングの目安です。具体的には、税理士にシミュレーションを依頼し、設立前後のキャッシュフローを比較すると判断材料が揃います。記事で紹介したポイントを踏まえ、収益拡大とリスク管理を両立する最適な投資スキームを描いてください。
参考文献・出典
- 国税庁「令和6年分 所得税の税率表」 – https://www.nta.go.jp
- 財務省「法人税関係法令」(2025年版) – https://www.mof.go.jp
- 日本政策金融公庫「小企業の経営指標 2024年度」 – https://www.jfc.go.jp
- 総務省統計局「家計調査年報 2024」 – https://www.stat.go.jp
- 中小企業庁「中小企業投資促進税制の概要(2025年度)」 – https://www.chusho.meti.go.jp

