子どもの進学費用はいずれ必ずやって来る大きな出費です。学資保険や積立投信では心もとないと感じ、「もっと効率的に増やせないか」と悩む親御さんは多いでしょう。本記事では、賃貸アパートやマンションなどの収益物件を活用して教育資金をつくる考え方を解説します。購入前に行う収支計算の基本から、学費の支払い時期に合わせた資金計画まで、初心者でも理解できるように丁寧に説明します。読むことで「なぜ収益物件が教育費に向くのか」が分かり、自分に合った投資判断ができるようになります。
教育資金が重くのしかかる理由と不動産投資という選択肢
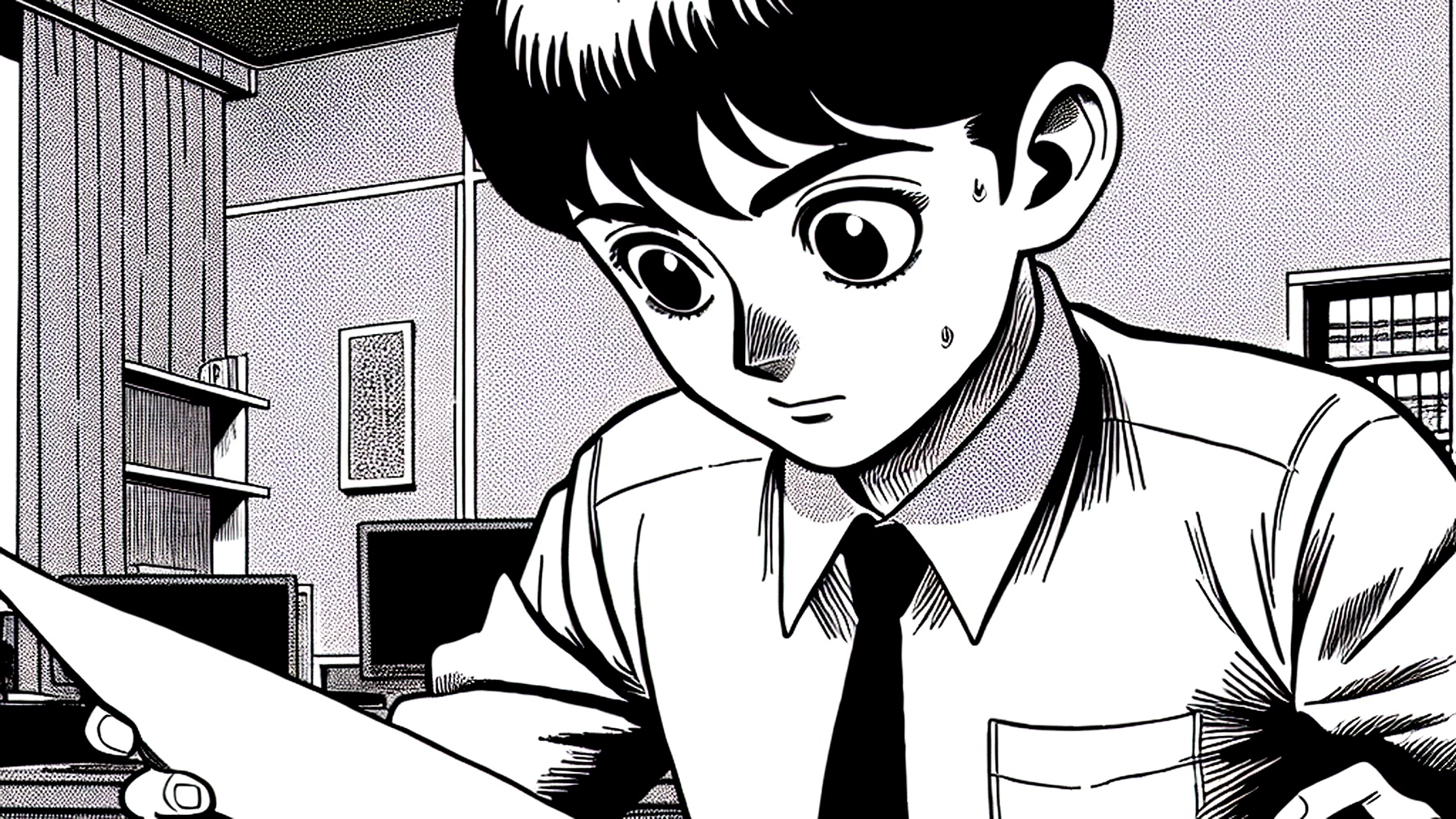
まず押さえておきたいのは、実際にどれくらいの教育費が必要かという現実です。文部科学省の令和6年度「子供の学習費調査」によると、高校から大学まで私立を選んだ場合、入学金や授業料、塾代を含めた総額は約1,200万円に達します。さらに大学進学率が過去最高の57.7%まで伸びるなど、進学はほぼ既定路線となりつつあります。これだけの資金を18年で準備するには、毎月5万円前後の積立が必要ですが、物価高と賃金の伸び悩みが家計を圧迫しています。
一方で、収益物件から得る家賃収入を教育費に充てる発想なら、元手を大きく動かさずにキャッシュフローで学費をまかなえます。住宅ローンより長い35年融資が組めるため、低金利を活かしながら運用を続けることも可能です。つまり、教育費という明確なゴールがあるからこそ、長期で安定収入を生む不動産は相性が良いのです。
収益物件のキャッシュフロー構造を理解する
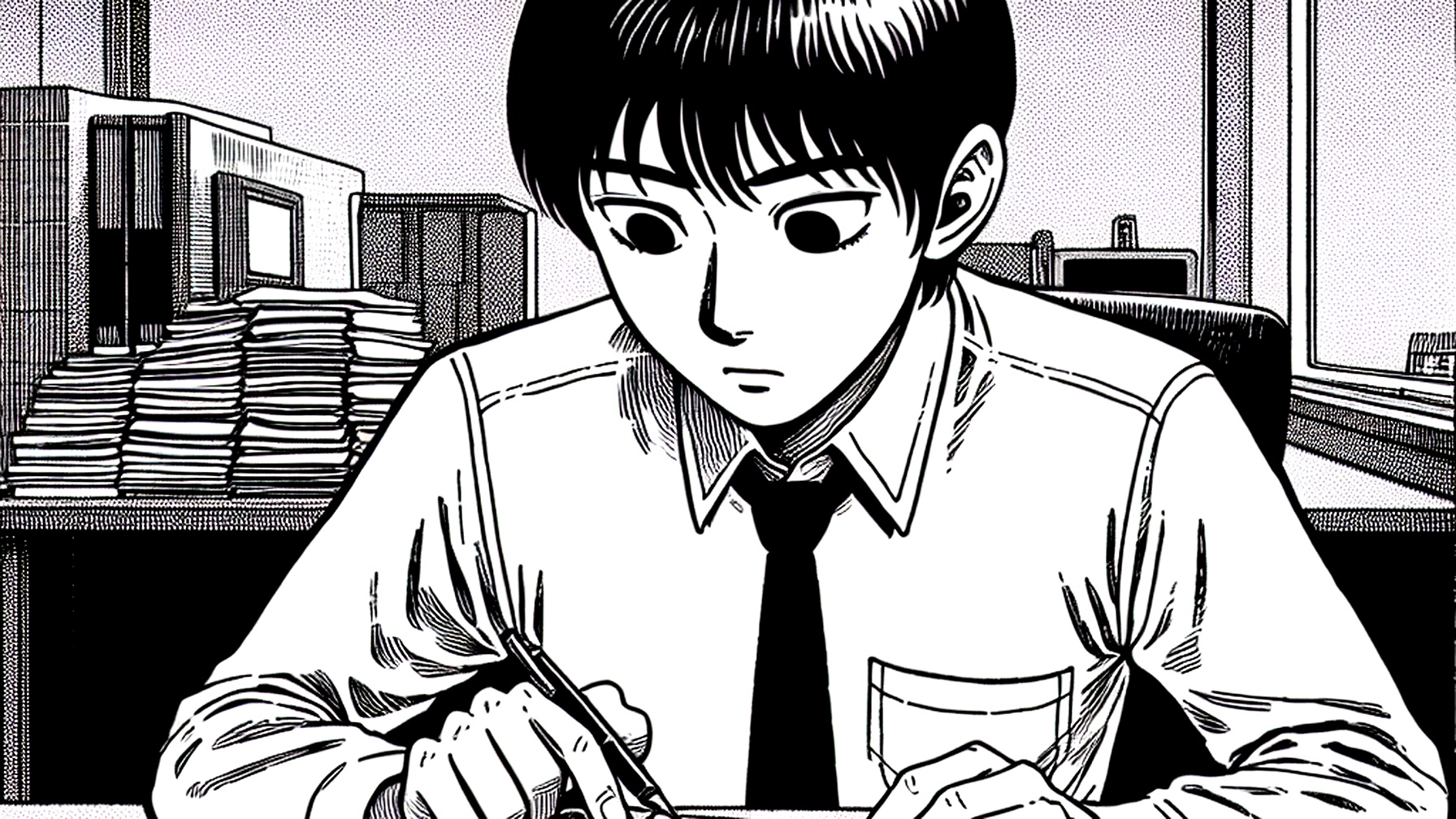
重要なのは、家賃収入から実際に手元に残る「純利益」を把握することです。家賃―空室損―運営費―ローン返済=キャッシュフローという式を覚えてください。運営費には管理会社への委託料、火災保険、固定資産税、将来の修繕積立が含まれます。国土交通省「賃貸住宅市場概況」によると、家賃に対する運営費率は平均25%前後です。また、都市部ワンルームなら年間空室率7〜10%が一般的ですが、築年数や立地で大きく変わる点に注意が必要です。
例えば、月額7万円で貸せる都内ワンルーム(価格1,800万円、金利1.5%・35年元利均等)の場合、年間家賃84万円。空室率10%、運営費25%とすると手取りは約56万円です。年間ローン返済は約66万円なので、このままでは10万円の赤字になります。ここで家賃を8万円に上げる、自己資金を300万円入れてローン額を下げるなど、複数のシナリオでキャッシュフローを黒字化する試算が欠かせません。
収支計算の手順と教育費からの逆算
ポイントは、子どもが進学する年にいくら必要かを先に確定し、それを賃貸収入でどう賄うか逆算することです。たとえば10年後に400万円の大学入学費を支払う計画なら、年間40万円の黒字を目指すとイメージしやすくなります。収支計算のステップは以下のとおりです。
1段落目:まず、購入価格と自己資金を決め、ローン返済額を計算します。金融機関のウェブサイトでシミュレーターを活用すると早いです。
2段落目:次に、家賃相場を不動産サイトや国交省「家賃指数」で確認し、利回りを算出します。表面利回りではなく、運営費と空室を差し引いた実質利回りを重視してください。
3段落目:最後に、年間キャッシュフローが黒字化するかをチェックします。黒字が足りなければ、頭金を増やすか、複数戸の購入で規模を取るか、もしくは物件を見送り、投資信託など別手段で補完する判断も必要です。
こうしてゴールから逆算することで、「いつ・いくら足りないか」が数字ではっきりし、無理のない投資計画が組めます。
リスク管理と時間軸の合わせ方
実は、教育資金目的の不動産投資で失敗する最大の原因は、修繕や金利上昇など予期せぬ支出が学費支払いのタイミングと重なることです。その対策として、築浅物件を選ぶか、外壁や配管の大規模修繕が発生する時期を購入前に確認しましょう。国交省のガイドラインでは、マンションの大規模修繕はおおむね12年周期とされています。子どもが高校を卒業するまでに修繕が来ない築10年未満の物件を選べば、資金負担の時期をずらせます。
さらに、固定金利型のローンを選び、教育費ピーク時の返済額を確定させる方法も有効です。2025年度の住宅ローン減税は自宅購入が対象ですが、賃貸併用住宅なら適用可能なケースがあります。家賃と減税効果を組み合わせると、手残りが安定しやすくなる点は覚えておきたいところです。
税制優遇と出口戦略で効率を高める
まず押さえておきたいのは、賃料収入が赤字になる年でも、給与所得と損益通算して所得税の還付を受けられる場合があることです。国税庁のタックスアンサーでも解説されているように、減価償却費を計上できる木造アパートは節税効果が大きい一方、償却期間終了後は税負担が増える点に注意が必要です。
また、2025年度まで延長された「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」(上限1,000万円)を使い、祖父母から学費を贈与してもらうと、自分のキャッシュフローを投資に回しやすくなります。出口戦略としては、進学費用を払い終えた時点で物件を売却し、売却益を老後資金に振り向ける選択肢も考えられます。日銀の不動産価格指数は緩やかな上昇を示しており、インフレヘッジとしても機能しやすい環境です。
まとめ
この記事では、教育資金を収益物件で準備するメリットと、失敗しないための収支計算のポイントを解説しました。学費という期限のある目標があるからこそ、家賃収入のキャッシュフローを逆算し、長期融資を活用する手法が有効になります。必要なのは、空室や修繕費まで含めた現実的な数字を出し、リスクとリターンを天秤にかける冷静さです。まずは進学時期と必要額を明確にし、信頼できる不動産会社や金融機関にシミュレーションを依頼するところから始めてみてください。行動に移すことで、未来の教育費への不安は着実に小さくなっていくはずです。
参考文献・出典
- 文部科学省「子供の学習費調査」https://www.mext.go.jp/
- 国土交通省「賃貸住宅市場概況」https://www.mlit.go.jp/
- 国税庁 タックスアンサー「不動産所得と損益通算」https://www.nta.go.jp/
- 日本銀行「不動産価格指数」https://www.boj.or.jp/
- 住宅金融支援機構「フラット35 金利情報」https://www.jhf.go.jp/
- 財務省「令和6年度税制改正大綱」https://www.mof.go.jp/

