不動産投資に興味があっても、公務員という安定した立場を崩したくないと悩む方は多いものです。休日が限られ、情報収集の時間も取りにくい中で「本当に自分に合う収益物件は見つかるのか」と不安になるでしょう。実は、公務員には信用力の高さという強みがあり、工夫次第で金融機関の優遇や良質な物件情報を引き出せます。本記事では、2025年10月時点の最新データを交えつつ、収益物件 探し方 公務員の視点で、物件選定から資金計画、リスク管理までを体系的に解説します。読み終えた頃には、明日からの行動ステップが具体的に描けるはずです。
公務員が不動産投資を始めやすい理由

まず押さえておきたいのは、公務員は給与が安定し、民間より融資審査で評価されやすい点です。住宅金融支援機構の2025年調査によると、地方公務員のフラット35利用者は全体平均の1.4倍に達しました。つまり、同じ自己資金でも金利や融資枠で有利になり、物件の選択肢が広がるのです。
一方で、就業規則が副業に厳しい自治体もあるため、事前確認は不可欠です。総務省のガイドラインでは、営利企業の役員就任や勤務を禁じていますが、不動産投資は一定条件下で容認されています。自己管理が難しい場合は、管理会社へ業務委託し「業務時間外の投資」と位置づけることで規則に抵触しにくくなります。
さらに、公務員共済組合は住宅ローンと同様に団体扱い保険料が割安になるケースがあります。保険料が下がるとキャッシュフローの改善につながり、長期保有戦略を取りやすくなります。安定収入という信用力を生かし、計画的にレバレッジを効かせることが、公務員ならではの王道と言えるでしょう。
物件タイプと立地の選び方
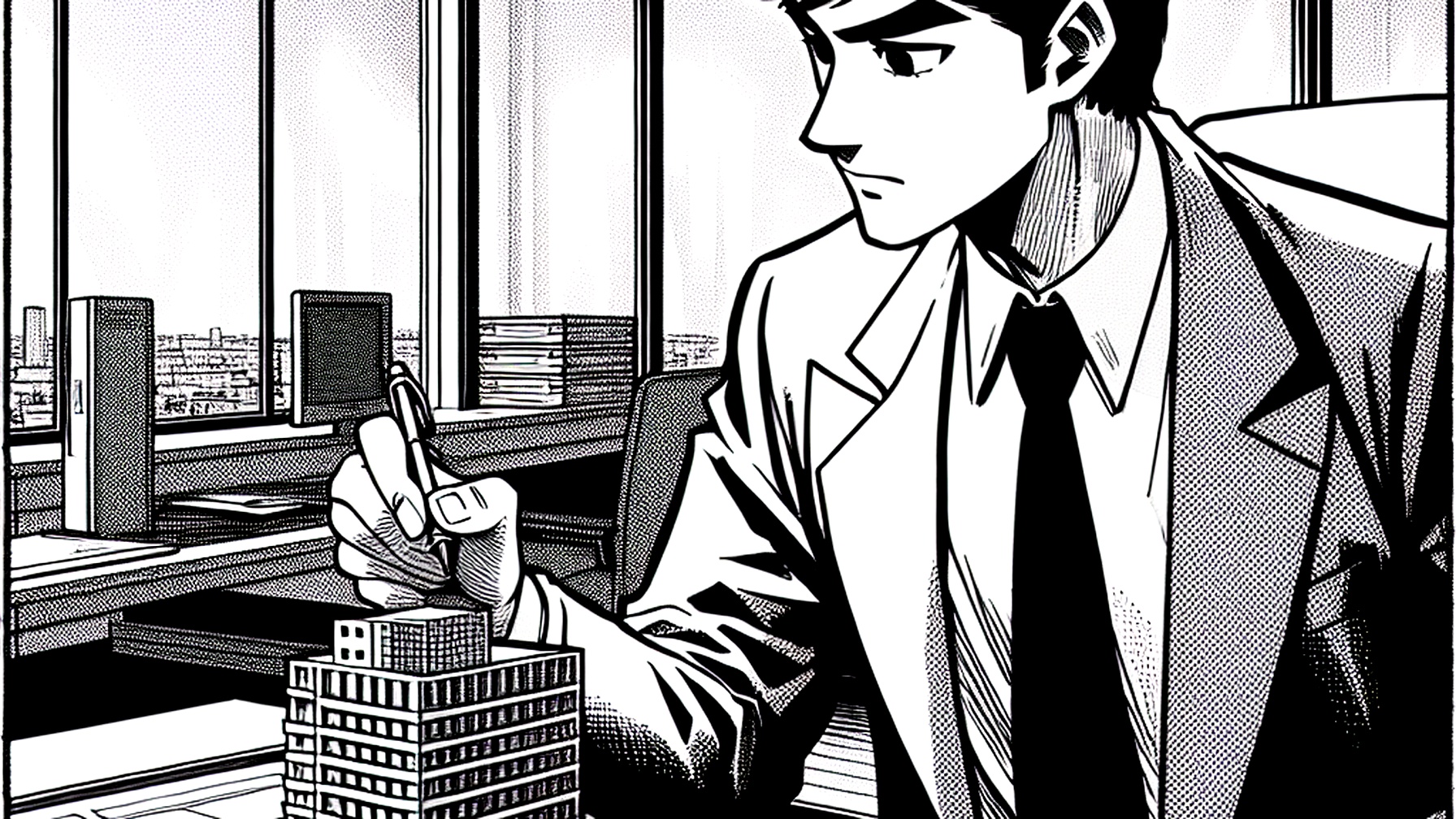
ポイントは、安定収益を優先するか、資産価値の上昇を狙うかを最初に明確にすることです。単身向けワンルームは初期投資が低く、都市部の賃貸需要が読みやすい反面、家賃下落リスクを抱えます。ファミリー向けマンションや戸建ては入居期間が長く、入れ替えコストが抑えられますが、購入価格が高めです。
実は、公務員が選びやすい立地は「人口10万〜30万の地方中核市」に多く存在します。国立社会保障・人口問題研究所の推計では、2025年から2035年にかけて地方都市でも中心部の人口は横ばいか微増が予想されています。この規模の都市は土地価格が都心より緩やかに変動し、利回りが6〜8%のバランス型物件が見つかりやすいのです。
一方で、将来の人口減少が鮮明なエリアは注意が必要です。自治体の都市計画マスタープランを閲覧し、再開発や大学移転などの動きを確認しましょう。立地調査の際は、平日昼と夜の二度現地を訪れ、通勤動線や周辺施設の稼働状況を体感することで、数字だけでは見えない賃貸ニーズをつかめます。
情報収集と現地調査のコツ
重要なのは、表に出回る前の一次情報にどれだけアクセスできるかです。不動産会社のレインズ(業者専用データベース)に登録される前に、担当営業から紹介を受ける仕組みを作ると、競争率の低い物件にめぐり合えます。そのためには、購入条件や資金計画を先に提示し、営業担当に「買える顧客」と認識してもらうことが近道です。
また、国土交通省の土地総合情報システムは、過去取引事例をエリア別に閲覧できる無料ツールです。成約価格と築年数の相場を把握しておくと、提示価格が割高かどうか即座に判断できます。とりわけ地方物件は情報の非対称性が大きく、数字の裏付けがあれば価格交渉を有利に進められます。
現地調査では、物件単体だけでなく徒歩10分圏の生活インフラを確認しましょう。コンビニや総合病院の有無は長期入居につながり、結果として空室リスクを抑えます。周辺に大型駐車場が不足している場合、車社会の地方では致命的な弱点になるため、必ず平面図と現地の動線を照合してください。
融資と資金計画を固める方法
まず、金融機関を選ぶ際は「勤務先の信用」「物件の担保評価」「自己資金率」の三要素が審査の柱となります。公務員は勤務先の信用が高く、自己資金を1〜2割に抑えても融資承認が出やすい特徴があります。しかし、自己資金を3割程度入れると、金利が0.2〜0.4%下がるケースが多く、総返済額を大幅に圧縮できます。
日本銀行の2025年金融システムレポートによると、変動金利は平均1.5%、固定金利(10年超)は平均2.2%で推移しています。金利差は0.7%ですが、3000万円を25年返済で借りると総支払額は約300万円変わります。言い換えると、金利選択は物件利回りと同じくらい重要な投資判断になるのです。
融資期間は建物の法定耐用年数を基準に設定されるため、築古物件を買う場合は残存耐用年数を確認しましょう。築20年の木造アパートなら耐用年数が22年のため、最長でも15年程度の融資になる可能性があります。毎月返済額が膨らみキャッシュフローを圧迫するため、積算評価が高いRC造なども選択肢に入れると、長期融資が引きやすくなります。
2025年度の税制優遇とリスク管理
基本的に、個人が賃貸住宅を新築または取得した場合、建物部分に対する減価償却費を計上できます。2025年度税制では、木造は22年、RC造は47年と耐用年数が維持され、節税効果の計画が立てやすい状況です。また、住宅取得資金贈与の非課税枠(最大1000万円)は2026年末まで延長されており、親族から資金援助を受ける場合は活用可能です。
一方で、インボイス制度により課税事業者の登録有無が家賃収入1000万円のラインで分かれます。将来的に複数物件を保有すると課税事業者になる可能性が高く、消費税還付や仕入控除の影響をシミュレーションしておく必要があります。税理士と連携し、長期のスキームを早めに固めることで、思わぬ追加納税を防げます。
リスク管理では、自然災害への備えも欠かせません。気象庁の統計では、2024年度の豪雨災害は過去10年平均の1.3倍に増加しました。ハザードマップと地盤情報を照合し、火災保険に水災特約を付けるかどうかを判断しましょう。年間保険料が1万円上がっても、床上浸水時に数百万円の補償を受けられれば、投資全体の安全性は格段に高まります。
まとめ
結論として、公務員が収益物件で安定収益を得るためには、信用力を最大限に活用しつつ、立地選定と資金計画を緻密に組み合わせる姿勢が不可欠です。まずは公務員向けの融資枠と就業規則を確認し、地方中核市のバランス型物件に狙いを定めてみてください。そのうえで、データと現地調査を連動させ、長期の税務戦略と保険を整えれば、不動産投資は副収入ではなく「もう一つの年金」として機能します。今日の小さな行動が、10年後の安心につながることを忘れず、一歩を踏み出しましょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 土地総合情報システム – https://www.land.mlit.go.jp/
- 日本銀行 金融システムレポート 2025年4月 – https://www.boj.or.jp/
- 住宅金融支援機構 フラット35利用者調査 2025年 – https://www.jhf.go.jp/
- 国立社会保障・人口問題研究所 将来人口推計 2024年版 – https://www.ipss.go.jp/
- 総務省 公務員制度ガイドライン 2025年度 – https://www.soumu.go.jp/

