収益物件に興味はあるものの、「税金が重くて利益が残らないのでは」と不安に感じていませんか。実は税制を理解して計画的に対策を打てば、キャッシュフローを大きく改善できます。本記事では2025年10月時点で有効な制度に限定し、減価償却から消費税還付まで、初心者が押さえるべき節税の基本と実践方法を解説します。読み終えた頃には、自分に合った戦略を組み立てる手順が見えてくるはずです。
収益物件で節税が重要になる理由
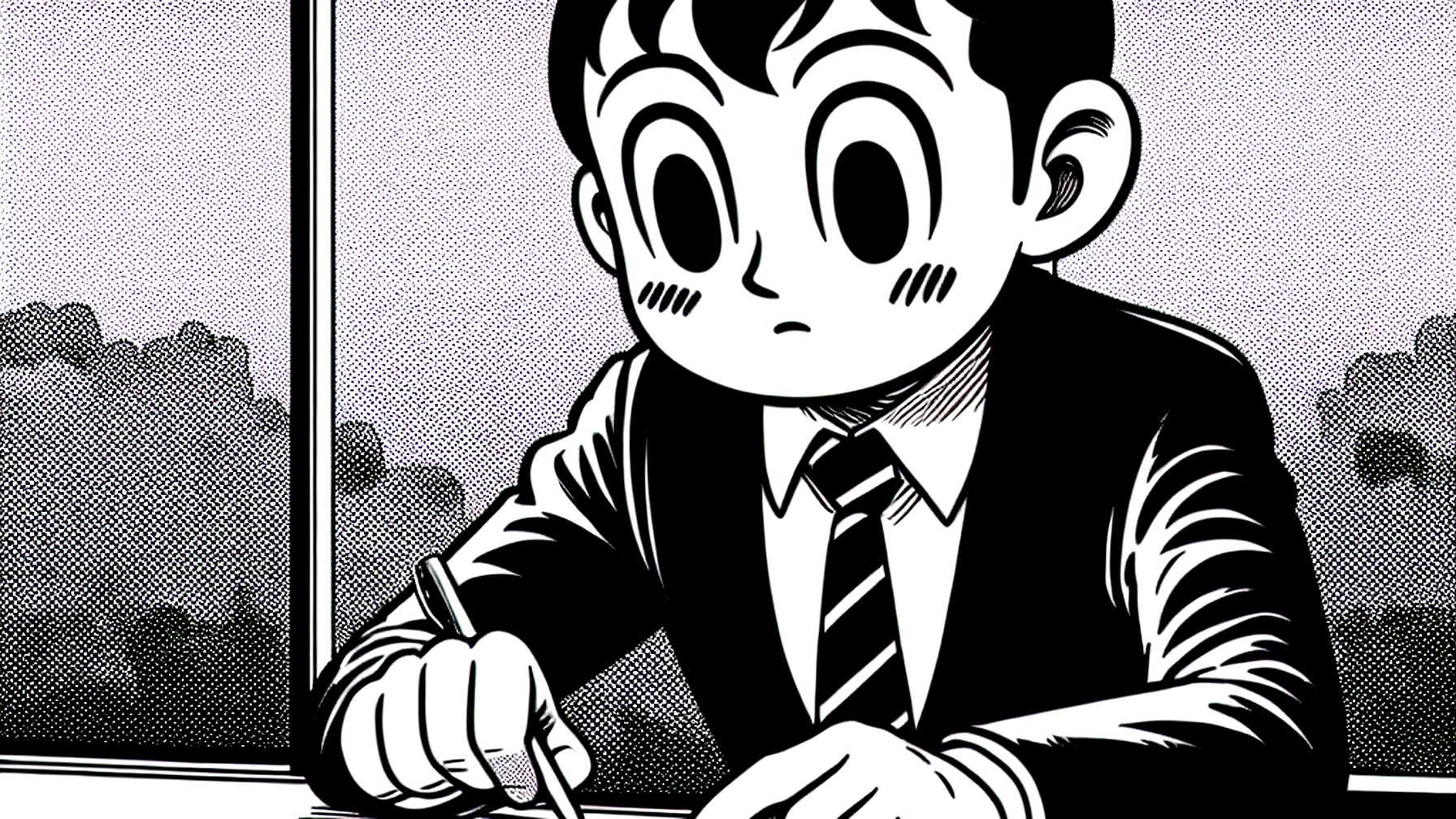
ポイントは、税金がキャッシュフローを左右する比率の大きさにあります。国土交通省の「賃貸住宅市場実態調査2024」によると、家賃収入から諸経費を差し引いた営業利益のうち、平均で約32%が税金に消えると報告されています。つまり節税策を講じるだけで、年間収益の三分の一近くを手元に残せる可能性があるのです。また税金は毎年発生するため、一度仕組みを作れば複利的に効果が積み上がります。
一方で、不適切な節税は追徴課税や資金繰りの悪化を招きます。国税庁が2025年3月に公表した個人事業主の税務調査結果では、不動産所得がある納税者の申告漏れ1件当たりの追徴税額は平均86万円でした。初心者が安心して投資を続けるには、合法かつ再現性の高い方法だけを選ぶ必要があります。ここからは代表的な仕組みを順序立てて見ていきましょう。
損益通算と減価償却を正しく使う
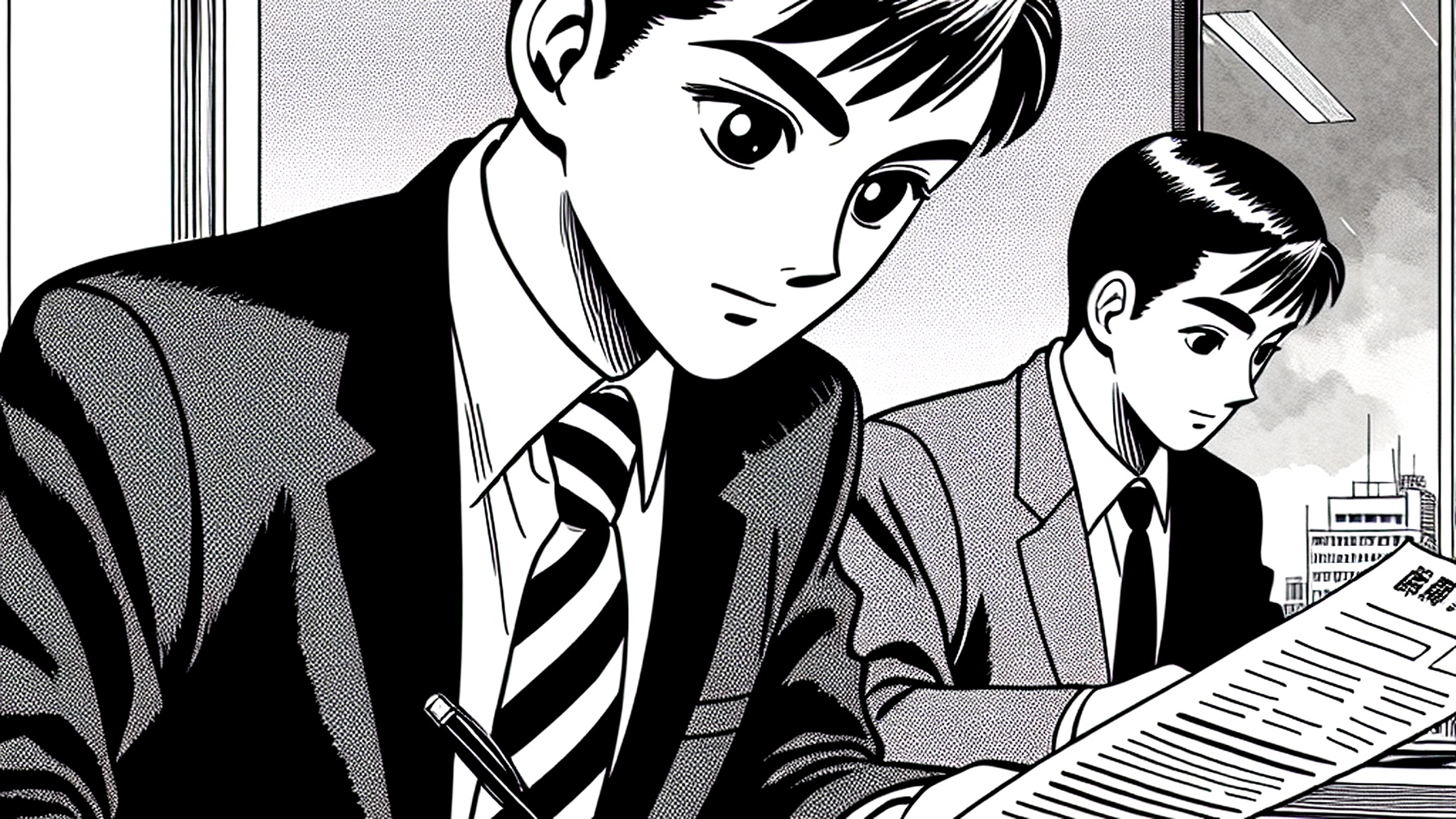
まず押さえておきたいのは、所得税法上の損益通算と減価償却が節税の土台になる点です。これを理解すれば年間の課税所得そのものをコントロールできます。損益通算とは、不動産所得の赤字を給与所得など他の黒字と相殺し、全体の税負担を減らす仕組みです。ただし赤字計上を目的とした過度な減価償却は、税務署から「租税回避行為」とみなされるリスクがあるため、耐用年数や償却方法を正確に適用しましょう。
減価償却は建物や設備の取得価格を耐用年数にわたって経費化する方法です。例えば木造アパート(耐用年数22年)を新築2,200万円で取得した場合、定額法なら年間100万円程度を経費にできます。この金額がそのまま所得を圧縮するため、実効税率30%の人なら30万円の現金流出を防げる計算です。重要なのは、設備部分を分けて計上する“区分償却”を行うことで、初年度の経費枠をさらに広げられる点です。
さらに建物の取得後でも、浴室やキッチンをリフォームすれば、その費用のうち資本的支出に該当する部分を追加で減価償却できます。修繕費との区別が難しいと感じたら、工事内容を写真とともに記録し、税理士に判断を仰ぐと安心です。この習慣が後の税務調査での説明資料となり、リスクを大幅に低減します。
消費税還付を活用するには
実は、課税売上5,000万円以上の事業者なら、建物取得時に支払った消費税を還付できる場合があります。これを「消費税還付」と呼び、資金効率を高める切り札となります。還付を受けるには、課税事業者選択届出書を取得の前日に提出し、翌々課税期間まで課税売上を維持する必要があります。手続きを誤ると、そもそも還付を受けられないため、スケジュール管理が欠かせません。
一方で、住居専用の賃貸は消費税の非課税売上に該当するため、単純計算では還付の対象外です。そこで2025年度も適用されている「短期貸し併用スキーム」のように、課税売上割合を50%以上に引き上げる方法が用いられます。しかし国税庁は同年4月の通達で、形だけの短期貸しは認めないと明示しました。実務ではホテル免許の取得や民泊新法に基づく届出など、実体ある運営が要求されることを忘れてはいけません。
個人と法人、どちらで保有するべきか
ポイントは、課税所得の規模と将来の相続対策に応じて最適な形態が変わることです。所得が上がるほど法人化のメリットが大きくなります。一般に個人所得が900万円を超えると、所得税と住民税の合計税率は33%に達します。一方で、資本金1億円以下の中小法人なら、2025年度も適用される特例税率15%(年800万円以下の所得部分)が使えます。この差を利用して法人名義で物件を取得すれば、節税効果はもちろん、経費計上の幅も広がります。たとえば役員報酬や社宅制度を活用すれば、個人の生活費を一部経費化できるからです。
ただし法人を設立すると、赤字でも年間7万円の均等割(東京都の場合)は避けられません。また、金融機関からの融資金利が個人より高くなるケースもあるので、トータルコストで判断する必要があります。さらに保有物件の売却益は法人税率で課税されるため、出口戦略まで含めてシミュレーションしましょう。言い換えると、法人化は万能ではなく、所得規模と保有期間がポイントになります。
2025年度に使える最新の優遇策
実は2025年度にも、不動産投資家が利用できる一般的な優遇措置が存在します。ここでは代表的な三つを紹介します。
まず、耐震・省エネ改修に関する固定資産税の減額特例です。築25年以上の木造住宅を耐震基準適合に改修した場合、翌年分の固定資産税が50%減額されます。工事完了後3か月以内に市区町村へ申告することが条件で、2025年12月31日までの改修が対象です。空室対策と節税を同時に進められるため、収益性向上に直結します。
次に、小規模宅地等の相続税評価減は、賃貸事業を営む被相続人が亡くなった際、土地評価額を最大50%減額できる制度です。相続対策として収益物件を保有する意義が高まり、後継者へスムーズに資産を引き継げます。そして令和7年度税制改正で延長が決まった「中小企業経営強化税制」も見逃せません。ZEB Oriented基準を満たす新築オフィスを取得した場合、即時償却か10%税額控除を選択できます。事業性と環境性能を両立させる動きは、将来の資産価値維持にも寄与するでしょう。
最後に、地方自治体の独自補助にも目を向ける価値があります。たとえば札幌市の賃貸住宅省エネ改修補助金(2025年度継続)は、断熱工事費の三分の一、上限100万円を支援するものです。国の制度と併用すれば、初期投資を抑えつつ競争力の高い物件を作れるでしょう。
まとめ
ここまで、損益通算や減価償却の基本から消費税還付、法人化、そして2025年度の優遇策まで、収益物件で節税するための全体像を整理しました。要するに、合法かつ持続的な仕組みを組み合わせるほどキャッシュフローは強固になります。まずは自分の所得規模と投資目的を確認し、専門家と相談しながら最適な手順を選びましょう。行動を起こした人だけが、税金を味方につけて資産を加速させられます。
参考文献・出典
- 国税庁 – https://www.nta.go.jp
- 国土交通省 住宅局 – https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku
- 東京都主税局 – https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp
- 総務省統計局 – https://www.stat.go.jp
- 中小企業庁 – https://www.chusho.meti.go.jp
- 環境省 – https://www.env.go.jp

