退職金をどう運用するか、年金だけで老後を乗り切れるのか。60代に差しかかると、こうした不安が現実味を帯びてきます。不動産投資、とりわけ毎月家賃が入る「収益物件」は魅力的ですが、探し方が分からず一歩を踏み出せない方も多いでしょう。本記事では「収益物件 探し方 競売 60代」という切り口で、競売物件を含む取得方法から資金計画、相続までを具体的に解説します。読み終えた頃には、ご自身に合った戦略が整理でき、具体的な行動に移る自信が得られるはずです。
60代でも間に合う収益物件投資の現実
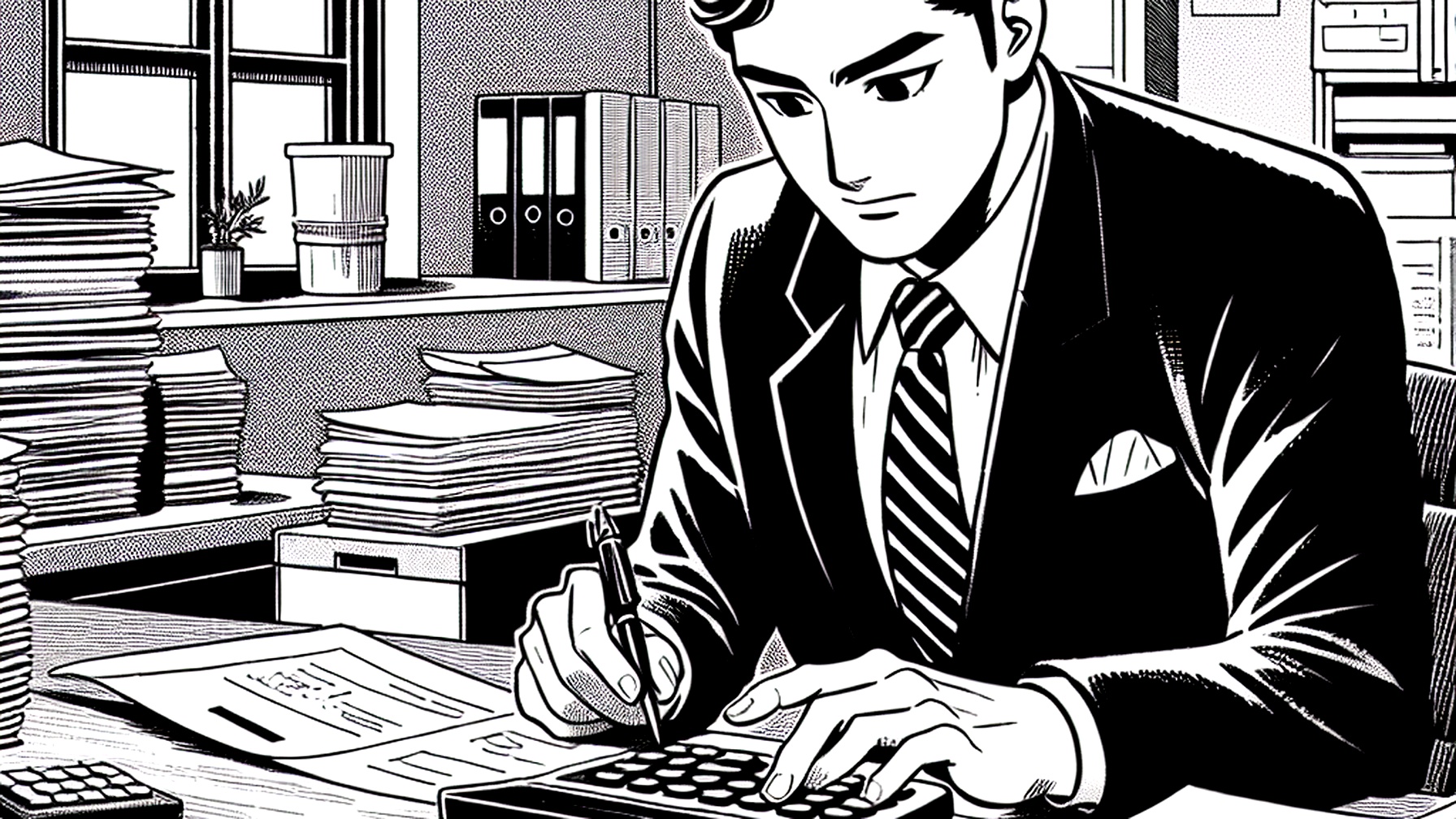
重要なのは、60代だからこその強みと制約を正しく把握することです。年齢を理由に諦める前に、現状の市場環境を確認しましょう。
国土交通省の「住宅市場動向調査2025年版」によると、個人投資家の新規参入年齢の中央値は54歳で、60代の比率も28%を占めます。つまり、60代で参入すること自体は珍しくありません。ただし融資期間が短くなるため、キャッシュフロー(手取り家賃収入)の設計が40代とは異なります。元金返済が重くなる分、自己資金を多めに投入し、表面利回りより実質利回りを重視する視点が欠かせません。
一方で、退職金や持ち家の担保評価など、他世代より自己資金や担保を確保しやすいメリットがあります。この資金的余裕は、築古の高利回り物件をリフォームで再生する戦略や、競売物件を現金購入で落札する戦略と相性が良いです。実は「年金受給者=融資が通らない」というのは誤解で、2025年現在、大手地銀3行は完済年齢80歳以下を条件にシニア向け賃貸経営ローンを提供しています。返済年数は15年前後と短いものの、物件収益で返済比率を50%以下に抑えれば審査通過の事例は多数あります。
したがって60代の投資判断では、利回りと返済年数のバランス、そして出口戦略としての相続設計までを同時に検討することが成功の鍵になります。
競売物件の基礎知識とリスクを押さえる
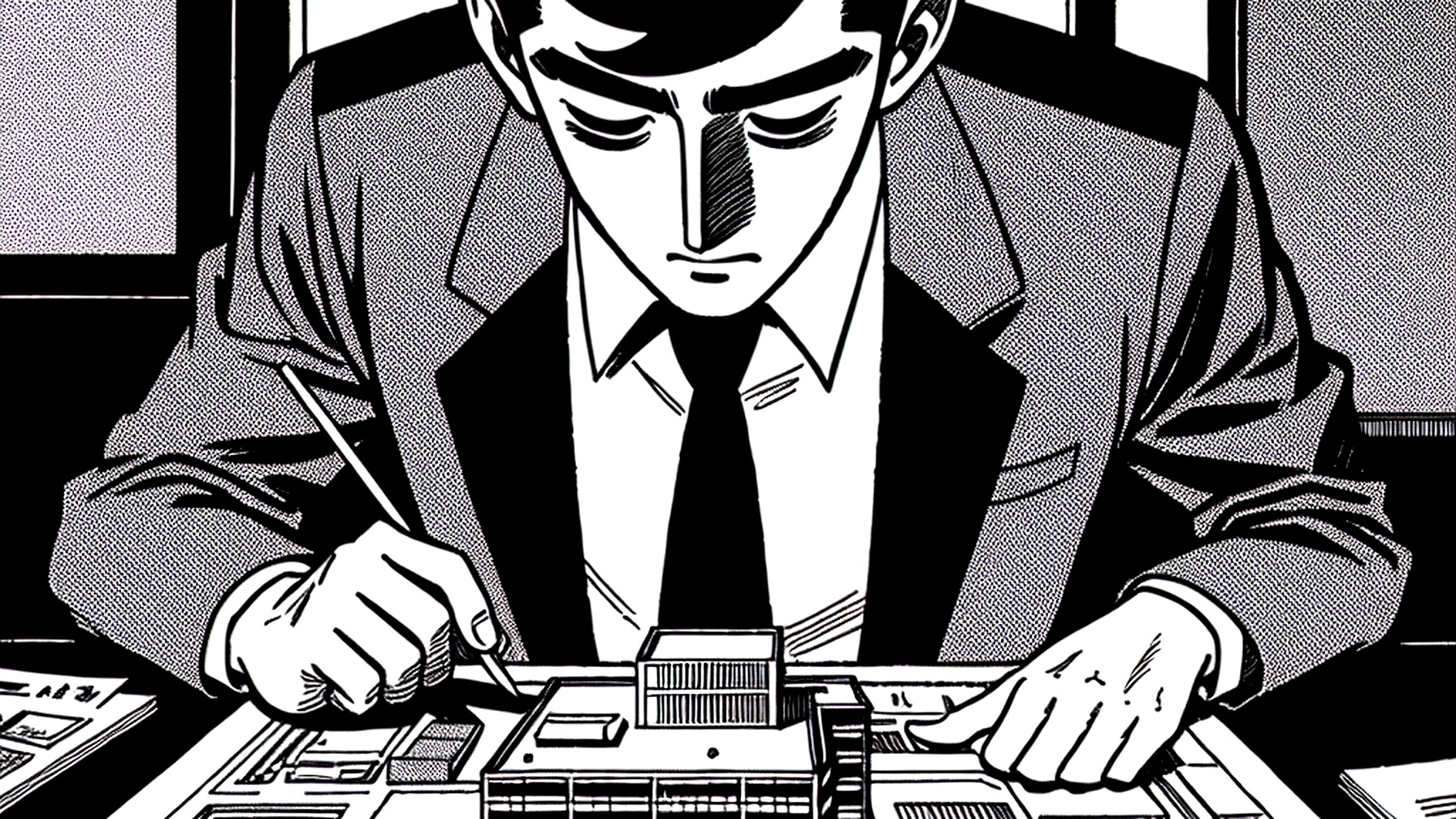
まず押さえておきたいのは、競売(けいばい)が裁判所主導で行われる公的な売却手続きである点です。一般の不動産広告に出ない物件を割安で取得できる一方、現況調査が限定的でリスクも伴います。
競売では買受可能価額(最低入札価格)が市場相場の6〜8割に設定されるケースが多く、表面利回りを高めやすいのが魅力です。しかし占有者の退去交渉、隠れた瑕疵(かし)への対応、リフォーム費用の不確実性があるため、落札価格だけで判断すると損失を抱える恐れがあります。特に60代の場合、トラブル解決に長期を要するとキャッシュフローが途絶え、精神的な負担も増大します。
そこで実践的な対策として、入札前に「現況調査報告書」と「評価書」を熟読し、外観確認(いわゆる現地調査)を必ず行いましょう。加えて近隣の成約事例をレインズ(不動産流通標準情報システム)で把握し、賃料相場と空室率をチェックすることが不可欠です。さらに、落札後の明け渡し交渉を専門家に依頼する費用と期間を試算に組み込むことで、予期せぬ支出を最小限に抑えられます。
このように競売はハイリターンを狙える反面、情報収集とリスク管理を怠ると損失が拡大します。特に時間的猶予が限られる60代は、落札から賃貸開始までのスケジュールを具体的に描ける物件に絞ることが安全策となります。
収益物件の探し方:競売サイトと民間情報の使い分け
ポイントは、公的情報と民間情報を並行して活用し、比較検討する姿勢です。競売だけに固執せず、通常流通物件と同時に見ることで、価格の妥当性が見えてきます。
まず競売情報は「BIT」(不動産競売物件情報サイト)を利用します。BITは全国の地方裁判所が公開するデータベースで、図面や評価額を無料で閲覧できます。検索機能が充実しており、所在地や物件種別、売却基準価額で絞り込めるため、収益物件の候補を効率的に洗い出せます。一方、民間の収益物件ポータル(楽待、健美家など)では賃料や利回りが明示され、写真も豊富に掲載されます。ここで相場観を形成したうえで、競売物件の利回りがどの程度割安かを検証します。
次に、地方自治体の空き家バンクも見逃せません。2025年度の総務省「空き家等対策推進事業」により、地方自治体が仲介補助を行うため、仲介手数料が低減されるケースがあります。競売よりリスクが小さく、価格交渉の余地がある点で60代投資家に向いています。また、地元の信用金庫や地銀が空き家再生ローンを扱っている場合、競売より融資を受けやすいのが利点です。
さらに、地場の管理会社に直接ヒアリングして未公開物件にアクセスする方法も効果的です。管理会社は空室対策に苦労するオーナーから売却相談を受けるため、一般市場に出る前の情報を握っています。実際に筆者がサポートした60代のお客様は、管理会社紹介の木造アパートを築30年で購入し、外壁と室内をリフォームして利回り12%を実現しました。このように複数チャネルを比較しながら、リスクとリターンのバランスを取ることが探し方の核心となります。
融資と資金計画:60代でも通るシナリオ
実は、金融機関選びと返済計画の組み立て方次第で、60代でも十分に融資を受けられます。大切なのは、返済期間を短く設定し、自己資金比率を高めることです。
2025年10月現在、都市銀行のアパートローンは完済年齢80歳未満という条件が一般的です。例えば65歳で15年返済なら80歳完済となり、まだ融資対象になります。ただし金利は変動で年2.3%前後、固定で年2.8%前後が相場です。賃料収入に対する年間返済比率を50%以下、できれば40%以下に抑えると審査が通りやすくなります。この比率は「DSCR(債務返済余裕率)」と呼ばれ、1.2倍以上を確保するのが目安です。
一方、競売を現金で落札し、リフォーム費用だけをリフォームローンで賄う方法もあります。リフォームローンは最長15年、金利は年1.8%〜3.5%が主流で、担保設定が不要なことが多いです。退職金を投入して初期費用を抑え、賃料収入を丸ごと老後資金に充てるプランは、返済リスクを大きく下げる点で60代向きと言えます。
融資を受ける際は、金融機関ごとにシミュレーションを作成し、空室率20%・金利上昇1%アップという厳しめの条件でもキャッシュフローが黒字になるか確認しましょう。さらに、団体信用生命保険(団信)の有無も要チェックです。団信に加入できれば、万が一の場合に家族がローン残債を負担せずに済みます。健康状態に不安がある場合は、ワイド団信(引受範囲を広げた団信)が利用できる金融機関を探すことが現実的な選択肢となります。
このように、60代でも融資を組む余地は十分にあり、自己資金とローンの組み合わせ次第で安定した投資計画が描けます。
運用後の出口戦略と相続対策を一体で考える
基本的に、60代の不動産投資では出口戦略と相続対策をセットで検討する必要があります。運用益だけでなく、将来の資産分配まで視野に入れることで安心感が高まります。
まず出口戦略としては、売却益を見込む「キャピタルゲイン型」と、安定賃料を長期で得る「インカムゲイン型」に大別されます。築古物件の場合はリフォーム後5年以内に売却益を狙うのが現実的ですが、競売取得なら購入価格が抑えられるため、利回りを稼ぎつつ出口を柔軟に選べます。ただし売却時には譲渡所得税が発生するため、保有5年超で税率が下がる長期譲渡を目指すかどうかも検討しましょう。
次に相続対策です。2024年の税制改正により、相続時精算課税制度の非課税枠は2500万円に拡大されました。2025年度もこの枠は継続しており、収益物件を子どもに早期贈与する手段が取りやすくなっています。さらに、不動産の相続評価額は路線価で算出されるため、市場価格より低く評価されやすい特徴があります。この差を活用すれば、現金を残すより相続税負担を抑えやすいというメリットがあります。
とはいえ、賃貸経営の実務を子世代が担えない場合、管理会社や家族信託の活用を早めに検討することが重要です。家族信託は、受託者(子ども)が管理運営を代行し、受益者(親)が賃料を受け取る仕組みで、成年後見制度より柔軟に資産管理ができます。公正証書で契約を結ぶため専門家費用がかかりますが、判断能力低下後の運営継続を円滑にする効果が大きいです。
このように、運用と相続を一体で考えることで、60代の不動産投資は単なる副収入源から、家族に資産を残す手段へと進化します。
まとめ
本記事では「収益物件 探し方 競売 60代」をテーマに、シニア世代が不動産投資を成功させるポイントを整理しました。60代には退職金や自宅担保などの強みがあり、競売物件を含めた幅広い選択肢が存在します。しかし融資期間の短さやリスク管理の難度は高くなるため、自己資金比率を上げ、精緻なキャッシュフロー試算を行うことが欠かせません。公的サイトBITと民間ポータルを併用し、相場観を養いながら物件を比較検討しましょう。さらに運用益だけでなく、相続や家族信託など出口戦略を早い段階で決めておくと安心です。まずは競売情報の閲覧と金融機関の事前相談から始め、数字で判断する習慣を身につけることが、安定した老後と家族の未来を守る第一歩になります。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅市場動向調査2025年版 – https://www.mlit.go.jp/
- 総務省 空き家等対策推進事業 2025年度概要 – https://www.soumu.go.jp/
- 最高裁判所 不動産競売物件情報サイト(BIT) – https://bit.sikkou.jp/
- 全国賃貸住宅新聞 2025年8月号 – https://www.zenchin.com/
- 日本銀行 金融システムレポート2025年4月 – https://www.boj.or.jp/
- 国税庁 相続税法令解釈通達(2025年7月改正) – https://www.nta.go.jp/

