60代で退職を控え、年金だけに頼らず安定収入を確保したいと考える方は多いものです。しかし、いざアパート経営を調べると「建築費はどのくらいかかるのか」「高齢でも融資が下りるのか」といった疑問が次々に浮かび、不安が先立つかもしれません。本記事では、アパート経営 60代 建築費という切り口で、最新の相場感や資金調達のポイント、リスク管理まで網羅的に解説します。読み進めれば、定年後の資産形成を自分らしく進めるための道筋が見えてくるはずです。
60代がアパート経営を始める背景とメリット
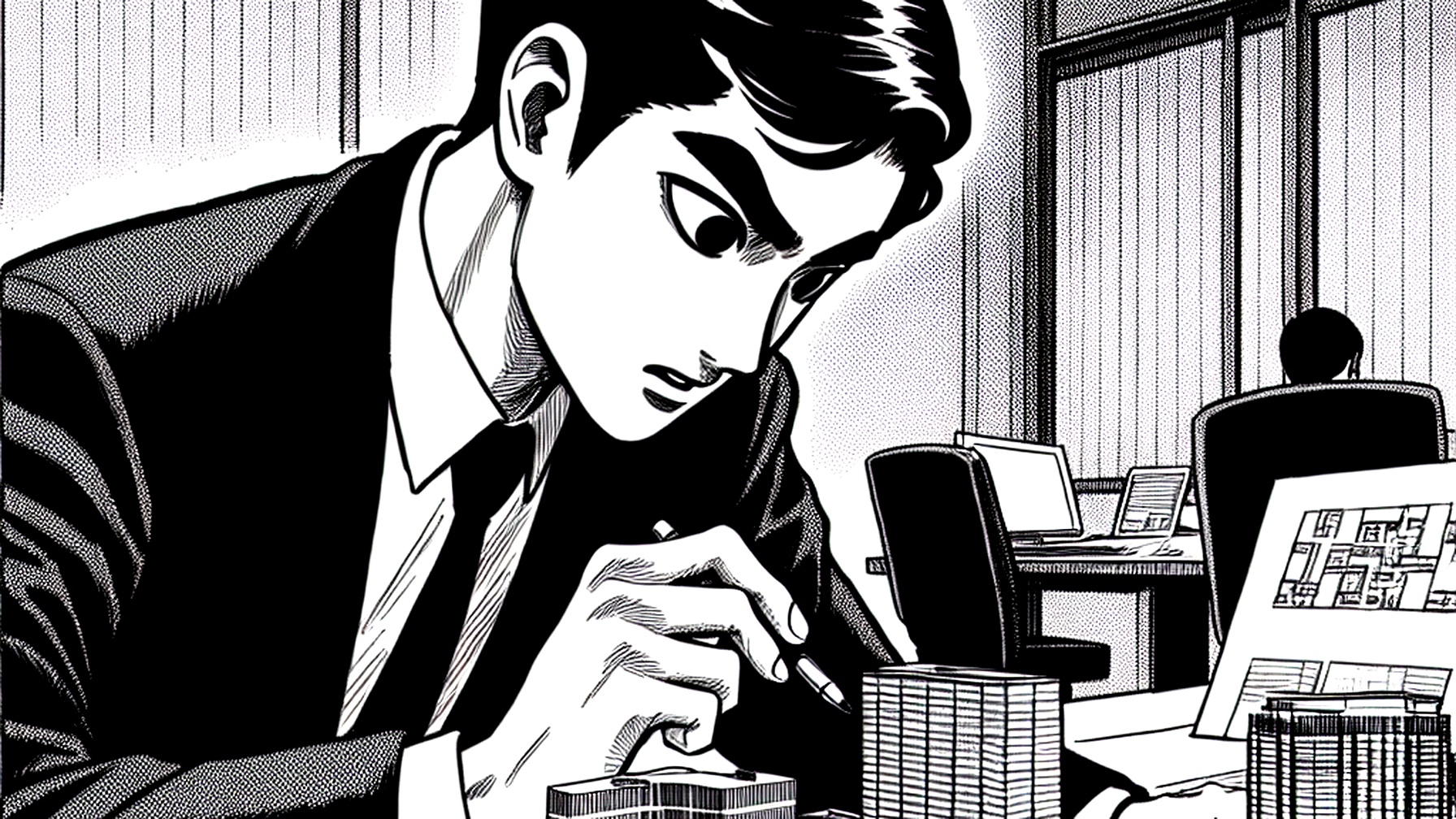
まず押さえておきたいのは、60代でアパート経営を始める人が年々増えているという事実です。国土交通省の住宅統計によると、2025年8月時点の全国アパート空室率は21.2%で前年よりわずかに改善しました。つまり全体として需要が底堅く、投資のチャンスはまだ十分に残っています。一方、退職金や長年の貯蓄を運用しないと低金利のもとでは目減りしやすく、家賃収入というインフレ耐性のあるキャッシュフローが重要になります。
具体的には、年金受給開始前後で収入の谷が生まれるケースにアパート経営が効くことがあります。家賃収入は毎月得られるため、年金支給月までの資金ギャップを埋めやすいのです。さらに最長35年の長期融資を利用すれば、自己資金を残しながら建物を所有できます。言い換えると、建築費を適切に抑えられれば、手元資金を生活費に充てつつ不動産資産を形成できるわけです。
一方で、年齢を理由に融資条件が厳しくなる現実もあります。そのために重要なのが、収益性の高いプランと出口戦略を同時に示すことです。具体例として、入居者ターゲットを単身者に絞ったコンパクトアパートは建築費も比較的抑えられ、銀行にとってもリスクの小さい案件になります。
建築費の基本構造と2025年の相場感
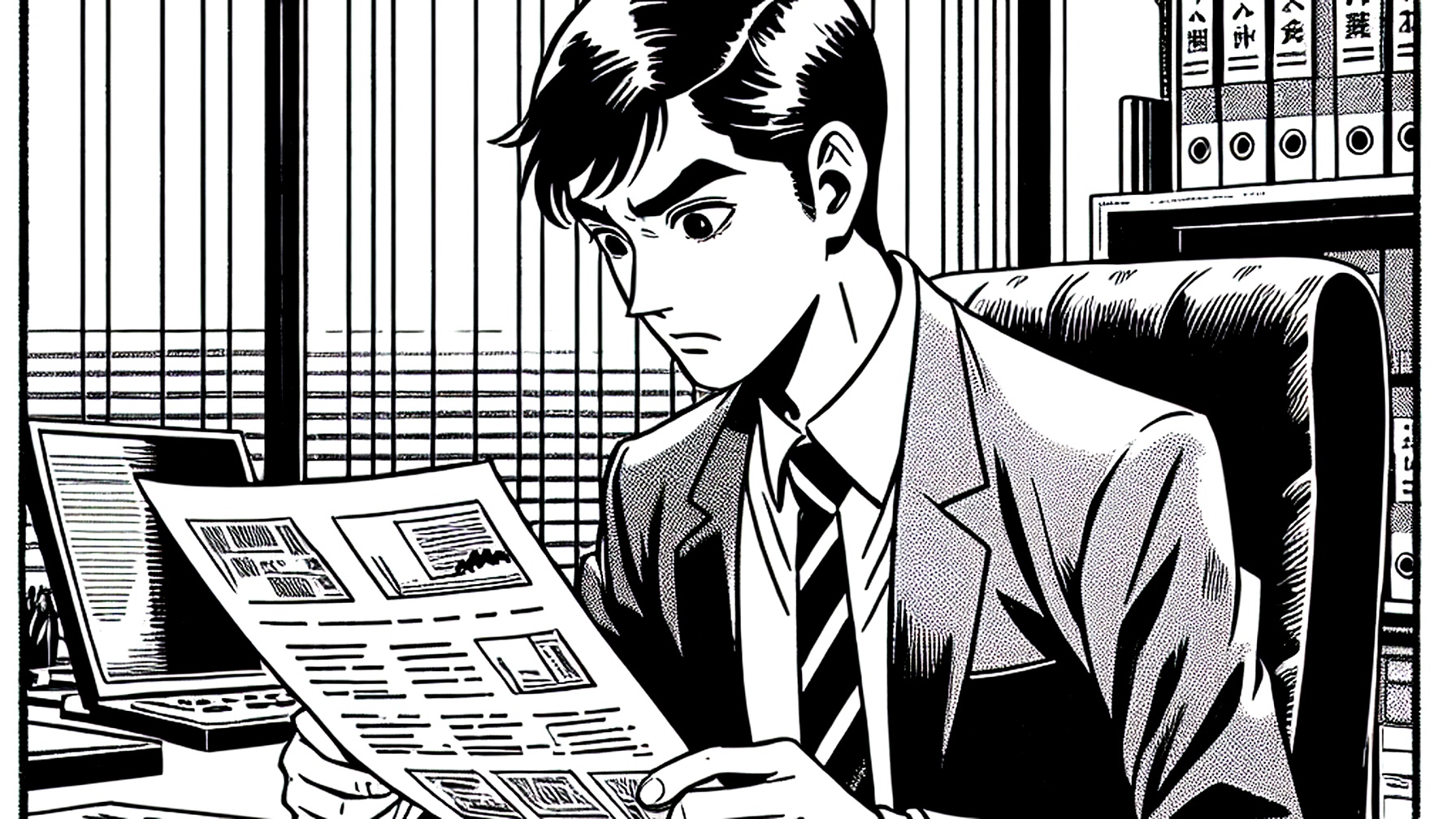
ポイントは、建築費を「本体工事費」「付帯工事費」「諸経費」に分けて把握することです。本体工事費は柱や床など建物そのものにかかる費用で、2025年現在の木造2階建てアパートの場合、坪単価は55〜65万円が目安です。また付帯工事費には外構や上下水道の引き込みがあり、建築費総額の15〜20%を占めます。
実は、建築費が高騰しやすいのは諸経費です。設計料、確認申請費、地盤改良費、近隣対策費など多岐にわたり、総額の10〜15%に達します。特に60代オーナーの場合、地盤改良の追加費用が発生するとキャッシュフローに影響が大きいため、事前の地盤調査を怠らないことが肝要です。
さらに、建物の構造選択もコストに直結します。例えば、木造2階建て延べ200㎡を想定すると総額は1.5億円前後で納まることが多い一方、鉄骨造3階建てにすると同規模で2億円を超えることも珍しくありません。それでも建物寿命や耐震性能が向上するため、長期所有を前提とするなら投資価値が高まります。つまり、建築費と耐用年数のバランスをどう取るかが成否を分けるわけです。
資材価格の高止まりを受け、ハウスメーカー各社は「規格型アパート」を推しています。同じ図面を複数物件で使うことで設計コストを圧縮し、坪単価を5万円程度下げる事例もあります。ただし画一的な外観は差別化しにくく、エリア内で供給が増えすぎると賃料下落のリスクがあります。ここでも立地とターゲットニーズの分析が欠かせません。
60代でも通る融資とキャッシュフロー設計
重要なのは、年齢を理由に銀行から断られないための準備です。金融機関は元金の完済時年齢を80歳前後に設定しており、60代で35年ローンは難しいのが現実です。そこで、自己資金比率を高めて借入額を抑える、あるいは返済期間を短くして月々の返済額を調整する方法が考えられます。
例えば、建築費1億6000万円の木造アパートを自己資金30%で建て、残り1億1200万円を20年返済で借りた場合、金利1.4%なら年返済額は約660万円です。対して満室想定家賃収入が年間960万円、運営費率30%とすると手残りは約10%の300万円。言い換えると、表面利回り6%以上を確保できれば、自己資金回収に約6年という計算になります。
また、日本政策金融公庫の「中小企業事業資金」は60代オーナーへの融資実績も多く、固定金利で最長20年の融資が可能です。これを民間銀行のつなぎ融資と組み合わせると、返済額が平準化し、フルローンに頼らずに済みます。
キャッシュフロー改善策として、2025年度も有効な住宅用太陽光補助金を活用し、屋根に10kW未満の発電設備を載せるケースが増えています。初期費用は200万円前後ですが、売電収入を家賃外収入として計算すると利回りが0.5ポイント程度向上します。
リスク管理と出口戦略を同時に描く
実は、アパート経営の失敗理由で最も多いのは「想定外の出費」と「出口の不在」です。まず大規模修繕の積立を怠ると10年後に1000万円単位の出費が発生し、キャッシュフローが一気に赤字化します。そのため、毎月家賃収入の10%を修繕積立に回すルールを設定し、口座を分けて管理すると強制力が働きます。
さらに、60代で始める場合は相続対策も視野に入れます。2025年度の相続時精算課税制度を利用すれば、子に2,500万円まで非課税で建築資金を贈与できます。これにより親子共同名義で融資を受けやすくなる利点も生まれます。
出口戦略としては、築15年を目安に「売却」「建替え」「持ち続ける」の三択を比較検討します。築20年時点での売却価格は新築時の6割前後が相場とされるため、借入残高が下回っているかを常にチェックしましょう。もし下回っていない場合でも、賃貸需要が強いエリアなら表面利回りを10%以上に上げて中古投資家へ売却する余地があります。ここで建築費を抑えたことが後々の選択肢を広げる鍵になります。
2025年度税制優遇と運用テクニック
まず、2025年度の固定資産税新築軽減は、賃貸住宅なら完成後3年間は税額が半分になります(床面積要件あり)。この効果は建築費を抑えた中小規模アパートほど大きく、年間数十万円の節税が期待できます。また、長期譲渡所得の特例により、築5年超・所有期間10年超で売却すれば税率が約20%へ下がります。
さらに、デフレ期に設定された住宅ローン控除は賃貸住宅には直接適用されませんが、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になれば、建築時に支払った消費税の一部を還付できる可能性があります。建築費が1.8億円の場合、内税消費税は約1,636万円。要件を満たせばその6〜7割が還付される事例もあり、実質建築費を圧縮できます。
一方で、制度を利用するには2年以上課税売上高が1000万円以上になる見込みが必要です。入居率や賃料単価を保つために、シニア向け見守りサービスを導入し、付加価値を高める工夫が求められます。空室対策が直接的に税制活用の可否を左右する点は見落としがちなので注意しましょう。
まとめ
結論として、60代からのアパート経営は建築費を適切に抑えつつ、長期的なキャッシュフローと出口戦略を描ければ十分に実現可能です。相場を知り、税制優遇や補助金を組み合わせれば、自己資金を効率的に運用しながら安定収入を得られます。まずは信頼できる建築会社と金融機関を比較し、試算表を作成するところから始めてみてください。行動を起こすことで、退職後の暮らしにゆとりと安心をもたらす第一歩となります。
参考文献・出典
- 国土交通省住宅局「令和7年度住宅市場動向調査」https://www.mlit.go.jp
- 国税庁「相続時精算課税制度の概要(2025年版)」https://www.nta.go.jp
- 日本政策金融公庫「中小企業事業融資のご案内 2025年」https://www.jfc.go.jp
- 日本銀行統計局「主要金利指標 2025年8月」https://www.boj.or.jp
- 不動産経済研究所「全国アパート建築費指数 2025上期」https://www.fudousankeizai.co.jp

