金融機関から1億円の融資を引き出して収益物件を購入できる人は、ごく一部の限られた層だけだと考えられがちです。しかし、実際には年収や自己資金だけでなく、物件評価やリスク管理能力など複合的な要素で審査が行われます。本記事では「1億円 誰が 収益物件 融資条件」という疑問に正面から向き合い、2025年10月時点での最新データと具体例を基に、初心者でも理解できるよう丁寧に解説します。読み終えるころには、どのような準備をすれば審査通過に近づけるかがイメージできるはずです。
1億円融資を引き出す人の共通点とは?
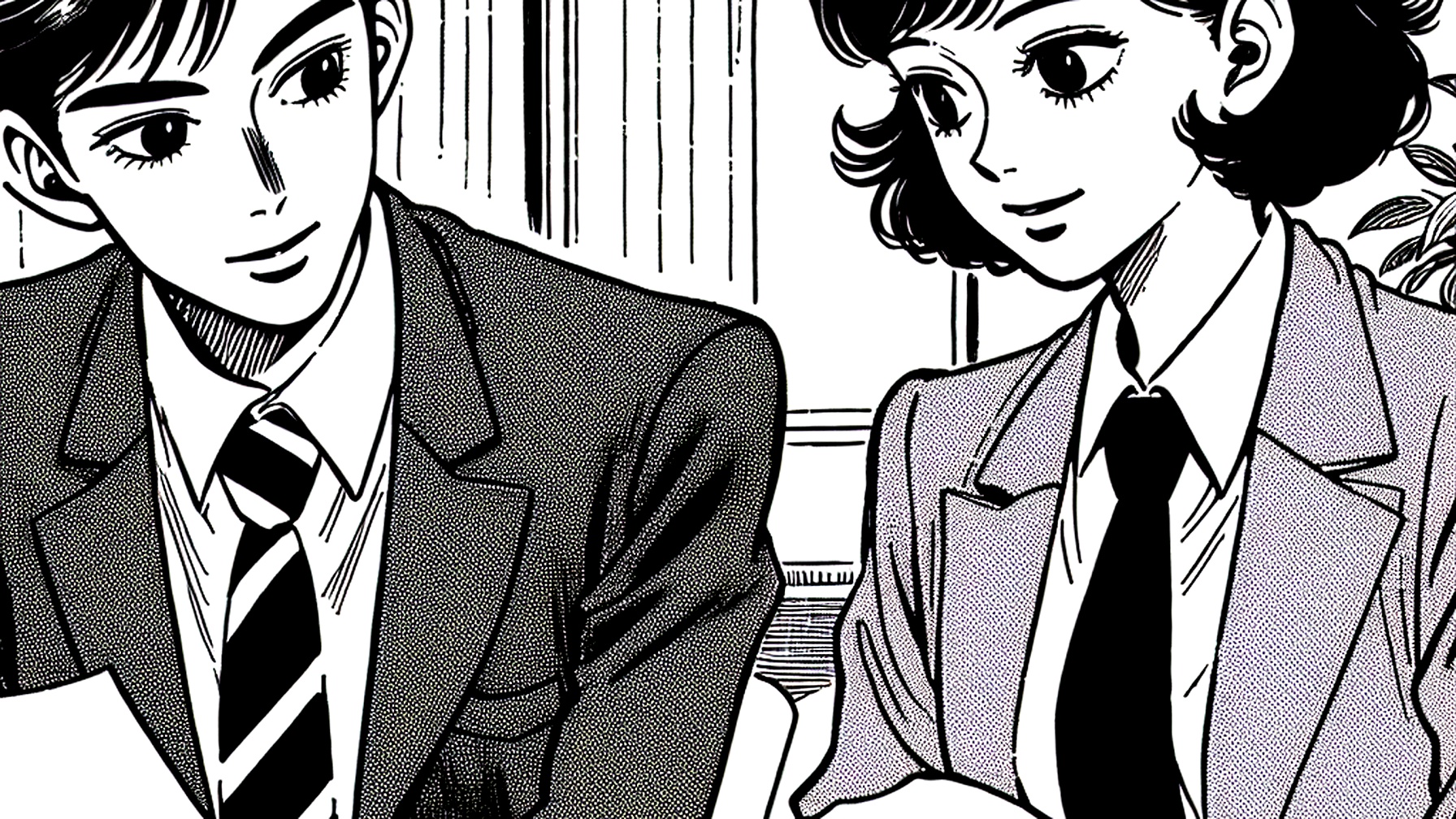
重要なのは、金融機関が評価する「返済能力」と「リスク耐性」を具体的な数字で示せるかどうかです。年収1000万円以上が一つの目安と語られることが多いものの、それだけで審査が通るわけではありません。
まず、自己資金の割合が大きいほどレバレッジが低下し、安全性が高まると判断されます。住宅金融支援機構の2025年度投資用ローン調査では、融資額1億円クラスを取得した個人の自己資金比率は平均22%でした。さらに、過去のクレジットヒストリーや副業収入の有無も重視されます。つまり、勤続年数が長く、複数の安定収入を証明できる人ほど1億円案件に近づきます。
次に、保有資産のポートフォリオがバランス良いかどうかもチェックされます。たとえば、株式や投資信託を数百万円単位で保有し、マーケット急変時に取り崩せる余力を示しているケースは好材料です。一方、借入が自動車ローンやリボ払いで膨らんでいると、返済比率が悪化し一気に評価が下がります。このように、1億円を借りられる人は単に高年収ではなく、資金管理の姿勢を数字で証明できる点が共通しています。
物件評価とキャッシュフローの影響

ポイントは、物件そのものが生み出すキャッシュフローが、個人属性を補完する役割を果たすことです。金融機関は「人」と「物件」の両面からリスクを測り、どちらかが弱いと判断すれば条件を厳しくします。
収益物件の評価で大きな鍵を握るのが「収益還元法」と呼ばれる計算手法です。国土交通省のガイドラインによると、年間家賃収入から経費を差し引いた純収益を、地域ごとの期待利回りで割り戻して評価額を算定します。たとえば、純収益700万円、利回り7%とすると評価額は1億円に到達します。評価額が実際の購入価格を上回れば、自己資金が少なくても融資比率を高めやすくなります。
また、キャッシュフロー計算書で「DSCR(負債サービスカバレッジレシオ)」が1.2倍以上あるかが重視されます。これは年間純収益が年間返済額の1.2倍を超えるかどうかを示す指標で、全期間固定金利のケースでも最低ラインとして扱われます。つまり、DSCRを高めるために修繕費の見積もりを正確に行い、家賃下落シナリオも織り込んだ計画書を提示することが審査突破の近道です。
金融機関ごとに異なる審査の着眼点
実は、同じ1億円の案件でも、どの金融機関を選ぶかで融資条件は大きく変わります。メガバンク、地方銀行、信用金庫、そしてノンバンクでは、審査の重み付けがそれぞれ異なるためです。
メガバンクは財務健全性を最重視します。最新の日本銀行「金融システムレポート」によれば、メガバンクの不動産向け融資残高は2023年比で微増にとどまり、リスク管理を強化する流れが続いています。そのため、自己資金3割超や年収1500万円超などハードルが高めです。
これに対し、地方銀行は地域活性化の観点から実勢利回りの高い物件に積極的です。2025年の全国地方銀行協会データでは、物件評価が高ければ自己資金1割でもフルローンに近い融資を出した例が報告されています。ただし、金利はメガバンクより0.3〜0.5%ほど上乗せされる傾向があります。
信用金庫や信用組合は、取引歴と地域貢献度を重視します。家族経営の法人を設立し、地域の管理会社を活用するといった「顔の見える取引」を好むため、事前に口座開設や定期預金を用意することが有効です。一方、ノンバンクはスピード融資が魅力ですが、2025年10月時点で金利3.5%超が一般的で、長期保有には負担が大きくなります。
2025年度の支援制度と最新金利動向
まず押さえておきたいのは、2025年度も引き続き「住宅取得資金贈与の特例」が投資用には適用されない点です。つまり、1億円案件の自己資金を親族から非課税で受け取ることは実質不可能です。代わりに個人版事業承継税制を活用し、将来の法人化を視野に入れる方法が現実的といえます。
金利動向について、日本銀行は2025年7月の金融政策決定会合で、長短金利操作(YCC)を柔軟化しつつもゼロ金利を継続しました。長期プライムレートは2.25%前後で横ばいですが、変動型の店頭金利は0.05%幅で上昇傾向にあり、融資期間20年以上の案件では固定金利を選ぶ投資家が増えています。固定金利1.8%、変動金利1.2%が市場平均とされる中、自己資金や物件評価が高ければさらに0.2%引き下げが可能です。
また、環境性能の高い賃貸住宅を建設する場合、2025年度の「ZEB・ZEH賃貸促進事業」により最大150万円の補助が受けられます。ただし、補助対象は新築に限られ、既存物件の購入には適用されないため、取得後に大規模リノベーションを行う計画でも補助金目当ての資金計画は組めません。こうした制度の適用可否を正確に把握し、無理のない返済計画を組むことが重要です。
リスク管理と出口戦略を描く
ポイントは、融資を受けた瞬間がゴールではなく、10年後にどう売却または再融資するかを描くことです。1億円の借入は長期にわたり大きな責任を伴うため、常に複数のシナリオを準備しておく必要があります。
まず、空室率が15%に達した場合でも手元キャッシュが枯渇しないよう、年間家賃収入の5%を修繕積立、同3%を緊急予備としてプールする仕組みを整えます。総務省「住宅・土地統計調査」によると、2023年の全国平均空室率は13.6%で、地方都市では20%に達する地域もあります。したがって、立地の選定段階から需要の堅いエリアを選ぶことがリスク低減に直結します。
次に、金利上昇局面に備え、固定金利期間満了前にリファイナンス(借り換え)を検討する余地を残します。具体的には、返済開始から7年目を目安に、貸出残高が8割以下に減った段階で金利交渉を行うと、コストを抑えつつ返済期間を短縮できます。このステップは、金融機関にとってもリスク低減につながるため、交渉の余地が大きい点が特徴です。
さらに、出口戦略の一環として、相続時の節税効果や法人化による所得分散も考慮しましょう。税理士と連携し、法人を活用して家族に給与を支払うスキームを組めば、手取りを確保しながら返済年数を短縮できます。言い換えると、長期的な資産形成とキャッシュフローの最適化は一体で考える必要があるのです。
まとめ
ここまで、1億円規模の融資を引き出すために必要な条件を「人」「物件」「金融機関」「制度」「リスク管理」の五つの視点から整理しました。年収や自己資金だけでなく、DSCRや物件利回りといった数値で安全性を示す資料を用意し、金融機関ごとの特徴に合わせて戦略を立てることが鍵です。さらに、金利動向や補助制度の最新情報を把握し、出口戦略まで描くことで一層審査通過に近づきます。行動に移す際は、今日から返済比率の改善と物件情報の収集を始め、半年後には具体的な試算表を提示できる状態を目指しましょう。そうすれば、1億円の壁は現実的な目標へと変わります。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産鑑定評価基準2024年版 – https://www.mlit.go.jp
- 住宅金融支援機構 2025年度投資用ローン調査 – https://www.jhf.go.jp
- 日本銀行 金融システムレポート2025年10月 – https://www.boj.or.jp
- 総務省統計局 住宅・土地統計調査2023 – https://www.stat.go.jp
- 全国地方銀行協会 地方銀行の不動産融資動向2025 – https://www.chiginkyo.or.jp
- 環境省 ZEB・ZEH賃貸促進事業2025年度概要 – https://www.env.go.jp

