金利が上がり始めると「ローン返済が重くなるのでは」と不安になる方が増えます。しかし視点を変えれば、金利上昇期は物件価格の調整や競合減少が起こりやすく、初心者にもチャンスが巡ってきます。本記事では、収益物件を選ぶ基準から融資の組み立て方まで、2025年10月時点の最新データを使って解説します。読み終えるころには、高利回りを確保しつつリスクを抑える具体的な行動手順が見えてくるはずです。
金利上昇が投資家に与える影響を正しく理解する
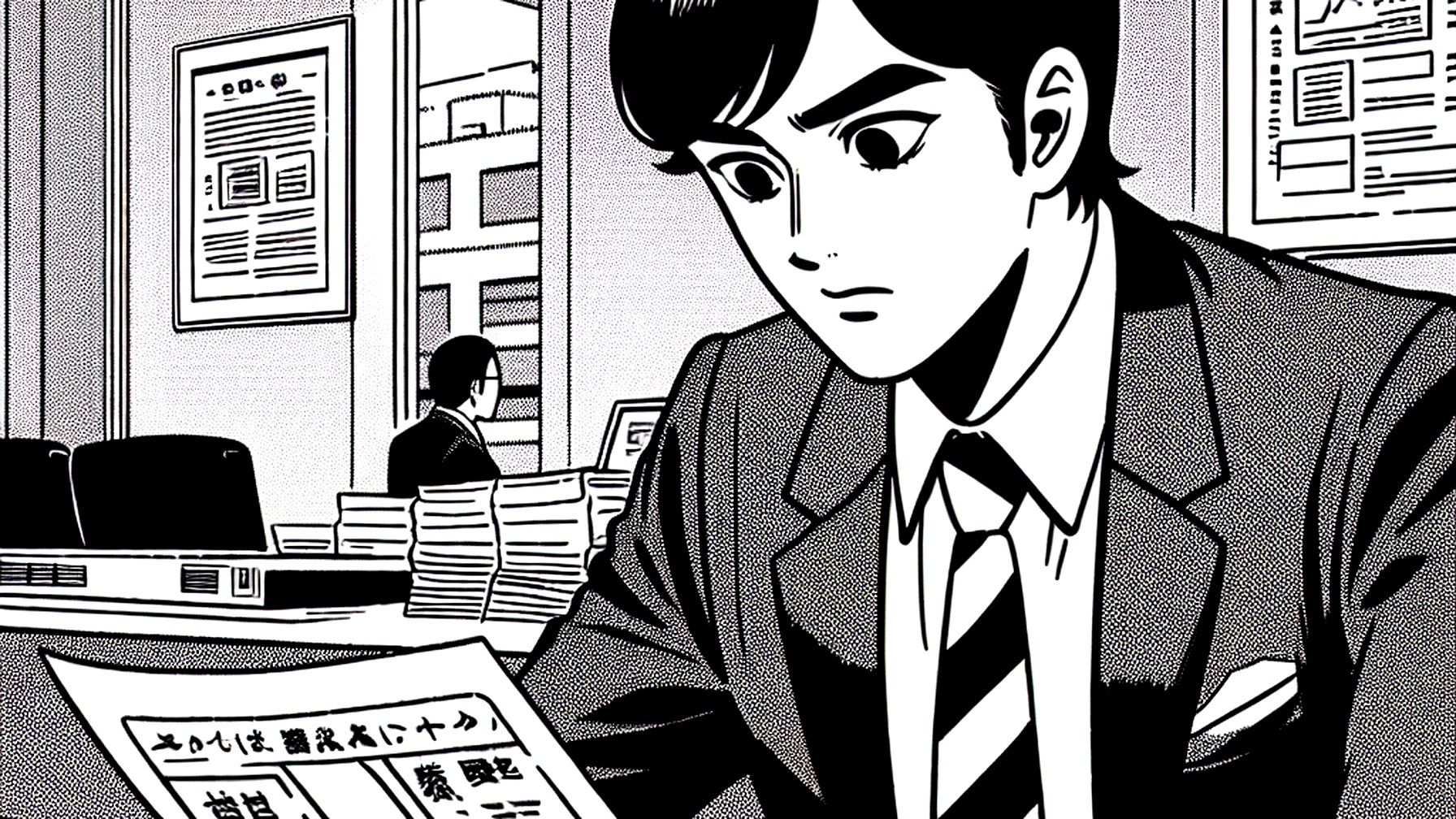
まず押さえておきたいのは、金利上昇期における収支構造の変化です。金利が1%上がると、35年ローン3000万円の場合は月返済が約1.5万円増えます。一方で、購入希望者が減るため物件価格が5〜10%下がるケースも少なくありません。つまり、利回り計算はローン返済額の増加と、値下がりによる投資額圧縮の両面で見直す必要があります。
次のポイントはキャップレート(期待利回り)の動きです。日本不動産研究所の2025年上期調査では、東京23区ワンルームの表面利回りが4.2%で前年同期比0.3ポイント上昇しました。これは投資家が金利リスクを利回りに転嫁した結果です。利回りが高まる局面で購入できれば、金利上昇による負担を一定程度相殺できます。
最後に、金利が上がると融資審査が厳しくなりやすい点を忘れてはいけません。返済負担率の上限は変わらなくても、金利が上がれば借入可能額は減ります。したがって、自己資金を厚くするか、収支計画をより保守的に組む工夫が欠かせません。
高利回りの定義と数字に潜む落とし穴
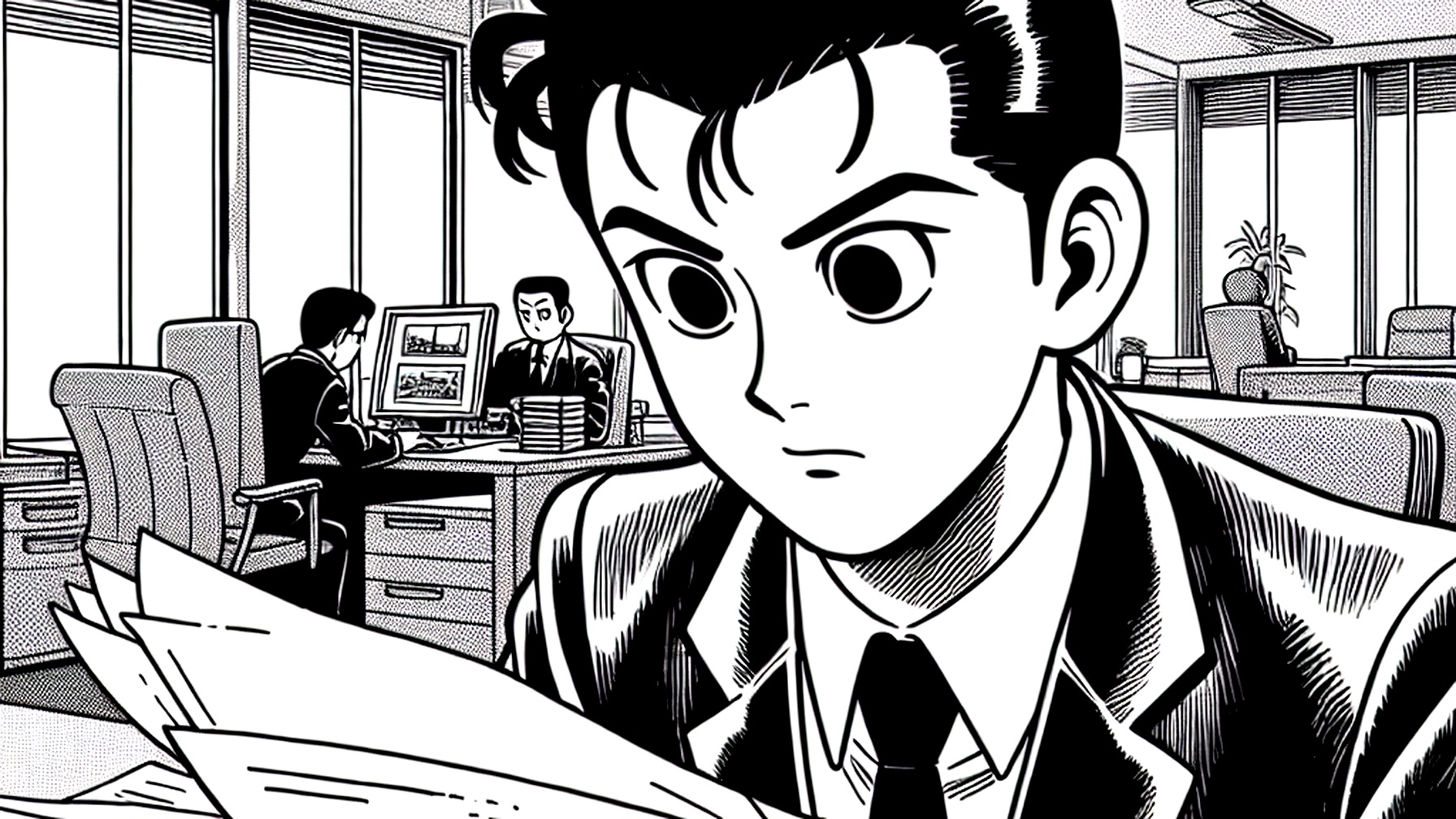
重要なのは「高利回り」の中身を見極めることです。表面利回り8%以上と聞くと魅力的ですが、固定資産税や管理費、修繕積立金を差し引いた実質利回りが4%を下回れば、金利上昇期には簡単に赤字化します。利回りを見る際は必ず実質ベースで評価しましょう。
実は、利回りが高い地域ほど空室率も高い傾向があります。国土交通省の2025年版住宅・土地統計調査によると、地方中核都市の空室率は平均17.4%で、東京23区の10.2%より7ポイント以上高くなっています。空室リスクを考慮せずに利回りだけを追うと、家賃収入が想定を下回りキャッシュフローが細る可能性が高まります。
さらに、築古物件は購入価格が低く高利回りに見えますが、大規模修繕費の時期が迫っていることが多い点に注意が必要です。屋根や外壁の改修は一度に数百万円かかるケースが珍しくありません。購入前に長期修繕計画と現状の積立金残高を必ず確認し、将来費用をシミュレーションに組み込むことが大切です。
金利上昇期に強いエリアと物件タイプを選ぶ視点
ポイントは、人口と雇用の安定度です。総務省「住民基本台帳人口移動報告」によると、2025年の東京都区部は依然として社会増が続き、特に単身世帯比率が高まっています。この動向を踏まえると、ワンルームや1Kの需要は堅調です。価格は高めでも空室リスクが低く、実質利回りが安定しやすい特徴があります。
一方で、高利回りを求めて郊外アパートに目を向けるなら、大学や企業研究所など“雇用の核”が存在するエリアを狙うと効果的です。たとえば、茨城県つくば市はつくばエクスプレスの沿線開発が進み、平均表面利回り6%台を維持しつつ人口流入が続いています。将来の再販価値(出口戦略)も視野に入れることで、投資リターンが底堅くなります。
また、東京23区内でもファミリー向け中古マンションは表面利回り3.8%とワンルームより低いものの、長期入居が多く原状回復費が抑えられるため、手取りベースでは競争力があります。金利上昇期は短期的な利回りだけでなく、修繕・退去コストまで含めた総合収益で比較する姿勢が欠かせません。
キャッシュフローを守る融資戦略と返済設計
まず、変動金利と固定金利の選択が鍵を握ります。日本銀行が2025年4月にマイナス金利を解除したことで、変動型は1%台後半、10年固定は2%台前半が一般的になりました。将来金利がさらに0.5ポイント上昇すると仮定し、返済負担率がどう変わるかを事前に試算することが重要です。
次に、融資期間を延ばすと月々の返済額は下がりますが、総支払利息は増えます。多くの金融機関では耐用年数内融資が基本ですが、RC造マンションなら築25年でも20年融資が組めるケースがあります。返済期間を物件耐用年数ギリギリに設定し、積極的に繰上返済の余力を残す方法が、金利上昇期には効果的です。
さらに、返済比率を家賃収入の50%以下に抑えると、空室や修繕が重なっても資金繰りが詰まりにくくなります。家賃収入50万円に対してローン返済25万円以下が目安です。返済比率を下げるには自己資金を増やす、利回りの高い物件を選ぶ、もしくは諸費用を含めた総投資額を圧縮するなど複合的な工夫が求められます。
2025年度の支援制度と税制優遇を味方に付ける
実は、制度を活用することで金利上昇リスクを一部ヘッジできます。2025年度も引き続き、住宅ローン減税の投資用物件への適用はありませんが、個人から法人へ切り替えることで、減価償却費を損金計上しやすくなります。法人税率は所得800万円以下で15%と低く抑えられるため、キャッシュフロー向上に直結します。
また、国土交通省が推進する「住宅エコリフォーム推進事業」は2025年度も継続しており、一定の省エネ改修を行うと1戸あたり最大60万円の補助が受けられます。築古物件を取得して断熱性能を高めれば、家賃アップと空室防止につながるうえ、補助金で実質利回りを引き上げることが可能です。
加えて、東京都は「賃貸住宅再エネ導入助成」を2026年3月申請分まで延長しました。太陽光発電や高効率給湯器の設置費用に対して上限100万円が補助されるため、電気代削減を家賃設定や入居促進に反映できます。制度の期限は必ず確認し、購入前に工事スケジュールを組むことが成功の近道になります。
まとめ
金利上昇期はローン返済負担が増える反面、物件価格調整や利回り上昇が期待できるタイミングです。本記事で取り上げたように、実質利回りを重視し、エリアの人口動態と雇用環境を見極めれば、安定収益を得るチャンスは十分あります。融資条件のシミュレーションと制度活用をセットで行い、高利回りを継続できるポートフォリオを構築しましょう。行動を先延ばしにせず、まずは気になるエリアの家賃相場と金融機関の融資条件を調べるところから一歩を踏み出してみてください。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp
- 国土交通省 住宅・土地統計調査 – https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/
- 総務省 住民基本台帳人口移動報告 – https://www.soumu.go.jp
- 日本銀行 金融政策決定会合資料 – https://www.boj.or.jp
- 東京都 環境局 再エネ導入助成 – https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp
- 国土交通省 住宅エコリフォーム推進事業 – https://www.mlit.go.jp

