不動産投資に興味はあるものの、「買うべきタイミングがわからない」「景気が変わったらどうしよう」と悩む方は多いはずです。実は、リスクそのものよりも“いつ”リスクが顕在化するかを読めるかどうかが成果を分けます。本記事では、2025年9月時点の最新データをもとに、市場サイクル・金利・空室率などのリスクがどのタイミングで高まるのかを解説します。初心者でも実践できる具体的な判断基準を示しますので、最後までお読みいただければ、少なくとも「不動産投資 リスク いつ」という疑問に答えられる自信が持てるでしょう。
なぜリスクの「タイミング」が重要なのか
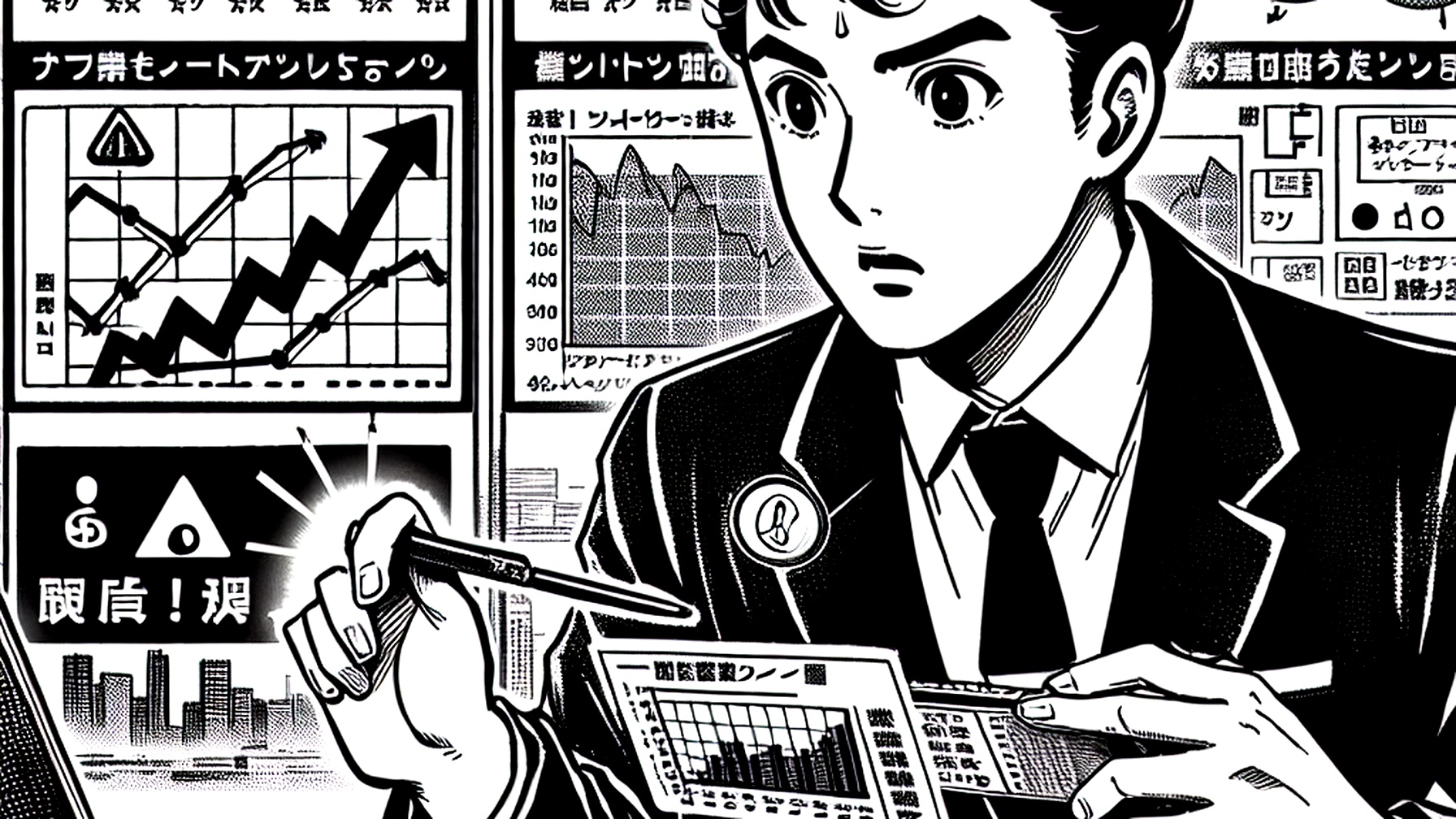
重要なのは、リスクがゼロになる瞬間など存在しないという現実を理解することです。不動産投資では、購入・保有・売却の各段階で異なるリスクが連鎖します。つまり、投資家は個々のリスクを順番に観察し、どのフェーズで大きくなるかを予測しなければなりません。
まず購入時は価格変動と融資条件が主な懸念点になります。国土交通省の不動産価格指数によると、首都圏中古マンション価格は2020年から2024年まで年平均6%上昇しましたが、2025年に入って伸び率が鈍化しています。この緩やかな減速こそ、値下がりリスクが高まり始めたサインと読めます。
保有中は金利や修繕費増大が響きます。日本銀行の統計では、政策金利は2024年から0.25%ずつ引き上げられ、2025年夏時点で0.5%です。返済額に直結するため、金利リスクが「いつ」本格化するかを想定しておく必要があります。
売却時には流動性が問題になります。実需の買い手が減ると出口戦略が難しくなり、値引きせざるを得なくなります。2025年度は相続税対策として買いを控える富裕層が増え始めたとの調査もあり、出口リスクを重視すべき局面といえます。
市場サイクルを読む基礎知識
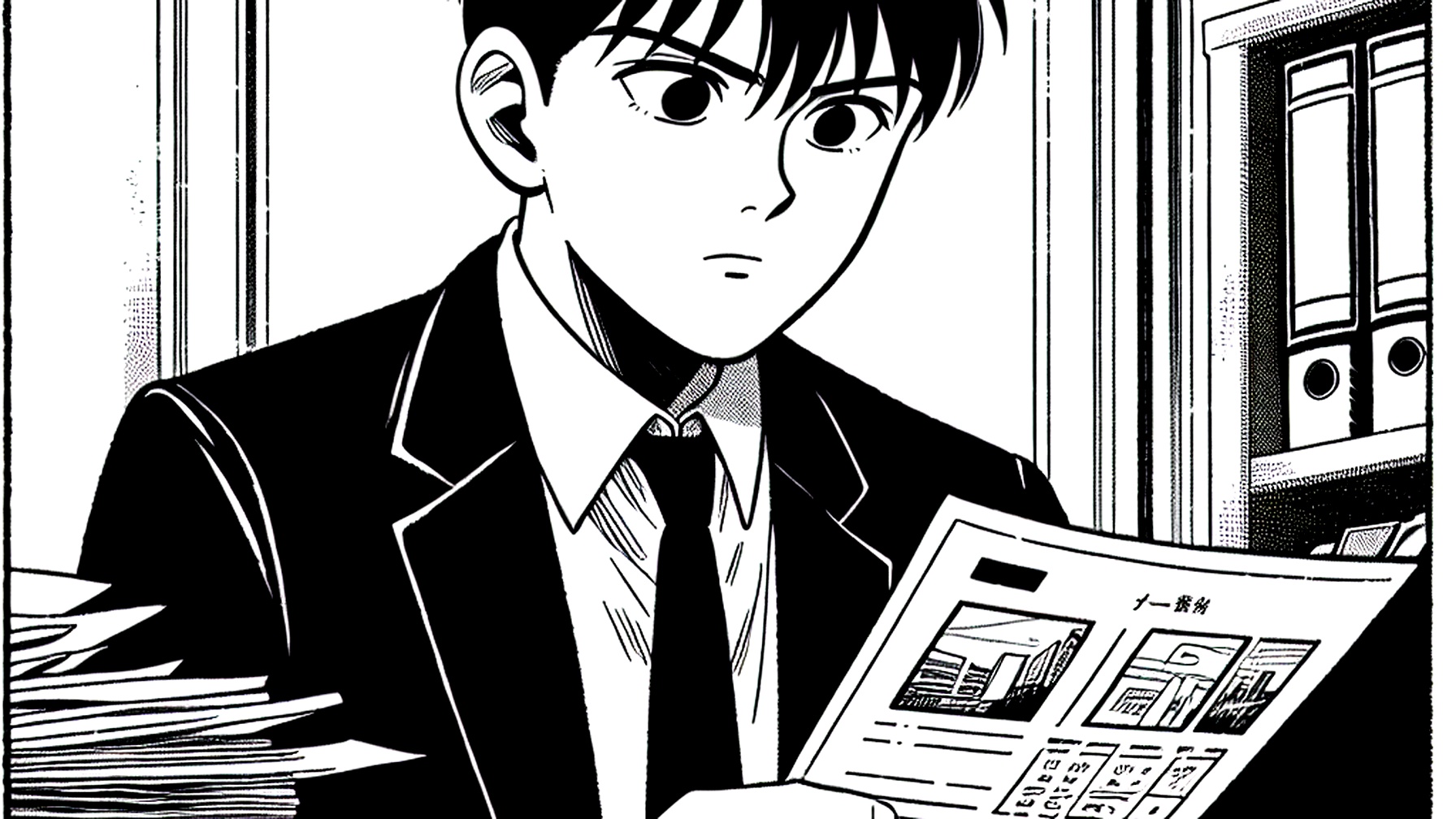
ポイントは、不動産市場が景気と歩調を合わせて「拡大」「ピーク」「調整」「回復」を繰り返すことです。金融機関の融資姿勢、開発許可数、取引件数といった指標を組み合わせると、サイクルの位置を大まかに把握できます。
たとえば国土交通省の建築着工統計では、2023年の着工件数が前年比7%増、2024年は2%増、そして2025年上半期は1%減に転じました。着工減は供給縮小のシグナルであり、調整局面入りを示唆します。また、不動産流通推進センターの取引データでも、2025年上半期の成約件数は前年同期比で4%減少しました。取引件数が減ると価格の天井感が強まり、リスクが拡大する局面になります。
一方で、調整期は買い場でもあります。供給が減り、売り急ぎ物件が出やすくなるため、キャッシュフロー重視の投資家には好機が訪れます。ただし、価格が底を打つ前に飛びつくと、想定外の下落を食らう恐れもあるため、利回りと賃料推移を慎重に分析しましょう。
金利上昇リスクはいつ訪れるのか
まず押さえておきたいのは、金利は政策だけでなくインフレ率や海外金利にも影響される点です。2025年9月時点で日本銀行は緩和縮小路線を続けていますが、総務省の消費者物価指数が前年比2.4%と上昇しており、市場では追加利上げ観測が強まっています。
日本政策金融公庫のアパートローン平均金利は、2023年の1.1%から2025年8月には1.6%前後まで上がりました。たった0.5%の差でも、3000万円を30年返済で借りた場合の総返済額は約250万円増えます。つまり、金利リスクは「いつ上昇が止まるか」よりも「いつまでに固定化するか」が鍵となります。
そこで有効なのが、2025年度も継続中の住宅ローン減税(一般住宅で年末残高上限2000万円・控除率0.7%)を活用した固定金利型借入です。投資用ローンには直接適用されませんが、自宅ローンを固定して家計の金利変動を抑えれば、投資用ローンは変動で攻める選択が可能になります。家計トータルで見れば、金利上昇リスクを分散できるわけです。
空室リスクの季節変動と人口動態
実は、空室リスクにも「いつ」が存在します。賃貸市場は1〜3月の繁忙期に需要が集中し、4〜8月は緩やか、9〜12月は法人異動で再び動くというサイクルを持ちます。したがって繁忙期直前に空室が発生した場合、家賃を下げずに埋められる可能性が高まります。
しかし、季節以上に長期的な人口動態が影響します。総務省の人口推計では、日本の総人口は2024年に1億2320万人、2025年には1億2285万人と減少が続いています。特に20〜34歳の若年単身世帯が減る地方都市では、空室率が3年連続で上昇している自治体もあります。この傾向は早晩、家賃下落リスクとして顕在化するでしょう。
それでも駅徒歩5分以内や大学近隣の物件なら、人口減でも安定需要が見込めます。地域ごとの人口変動を細かく確認し、「需要が底堅いエリアで空室期間を短縮できるか」がリスク軽減の軸になります。
リスクを抑える購入と売却のタイミング戦略
ポイントは、購入・保有・売却の3段階で異なる戦術を取ることです。購入時はサイクルが調整局面に入り、かつ金利が上がりきる前が狙い目です。2025年9月現在、首都圏中古区分マンションの成約価格は頭打ち傾向にあり、融資競争も落ち着きました。交渉余地が広がるため、インカムゲイン重視の投資家には好条件がそろいつつあります。
保有期間中は、修繕費の積立と金利固定のバランスがカギです。国土交通省の長期修繕計画ガイドラインでは、築15年までに外壁や屋上防水を行うと長寿命化につながると示されています。修繕が遅れるほど空室リスクと売却価値低下が重なり、リスクが複合化します。
売却のベストタイミングは、周辺で再開発が進み需給が改善する直前か、オリンピックなど大型イベント後の需要増を見込めるときです。2025年大阪・関西万博後は関西圏の地価上昇が想定される一方、短期急騰後に落ち着く可能性も指摘されています。売却益を狙うなら、イベント前に期待値で売るのか、完成後の実需で売るのかを決めておきましょう。
結論として、リスクを完全に避けることは不可能ですが、「いつ高まるか」を見極めれば大きな損失を防げます。サイクル・金利・人口の3要素を定点観測し、自分の資金計画と照らし合わせて行動時期を決めてください。
まとめ
ここまで、不動産投資のリスクが「いつ」顕在化するかを読み解く方法を解説しました。市場サイクルの位置、金利上昇のスピード、季節と人口動態による空室変動を押さえれば、過度に恐れる必要はありません。むしろタイミングを図ることで、割安購入や高値売却のチャンスをつかめます。まずは公的データを毎月チェックし、自分の投資計画をアップデートする習慣を身につけましょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp
- 国土交通省 建築着工統計 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省統計局 人口推計 – https://www.stat.go.jp
- 日本銀行 統計データベース – https://www.boj.or.jp
- 日本政策金融公庫 融資情報 – https://www.jfc.go.jp
- 不動産流通推進センター 成約動向 – https://www.retpc.jp

