不動産投資を始めたいけれど、ローンや団体信用生命保険(団信)の種類が多く、何を基準に決めればよいのか分からないと感じている方は少なくありません。実は、金利だけで比べると後から思わぬコストが膨らむこともあります。本記事では、投資用ローンに付帯する団信をどう見極めるかを中心に、金融機関の選定手順やシミュレーション方法まで詳しく解説します。読み終えた頃には「不動産投資ローン 団信 選び方」の疑問が解消し、具体的な行動に移せるようになるはずです。
不動産投資ローンと団信の基本を押さえる
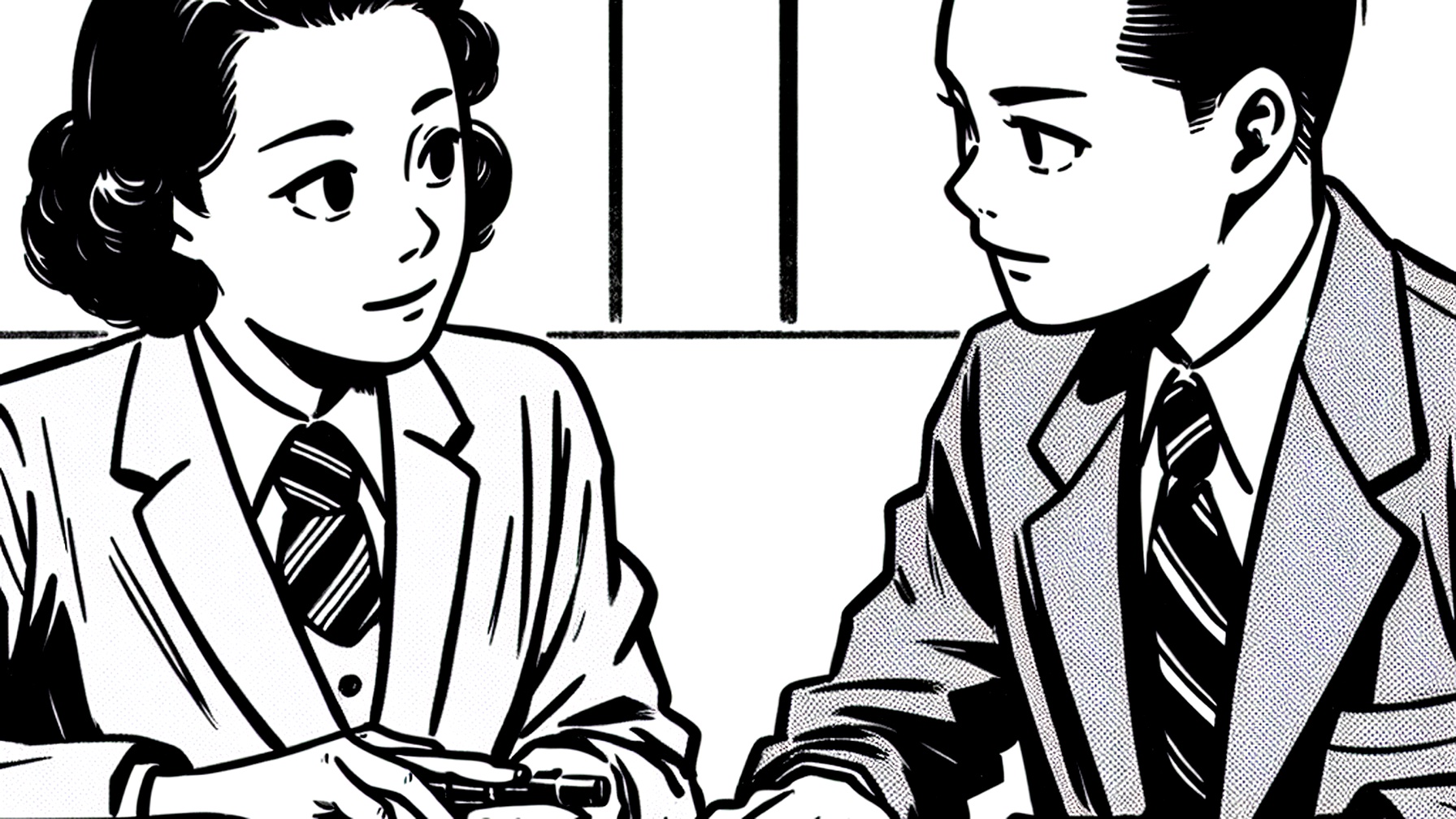
まず押さえておきたいのは、不動産投資ローンと自宅用住宅ローンでは審査基準も金利も異なるという事実です。団信とはローン契約者が死亡または高度障害になった場合に残債を肩代わりする保険であり、金融機関ごとに補償範囲と保険料が変わります。
国土交通省の2025年投資用住宅市場調査によると、投資ローンの平均金利は変動で年1.8%、固定10年で年2.7%となりました。ここに団信の保険料が年0.3〜0.4%上乗せされるケースが一般的です。ただし一部のネット系銀行では金利に保険料を内包しており、一見高く見えても総支払額は低いことがあります。
次に、団信は金融機関が契約者に義務付ける「原則加入型」と、自己判断で付帯を選べる「任意加入型」に大別されます。投資ローンは原則加入型が主流ですが、借入額が小さい場合や自己資金が厚い場合は任意加入型を選び、保険料を削減する戦略も考えられます。また、すでに複数の生命保険に加入している投資家は保障の重複にも注意が必要です。
つまり、ローン比較の起点は「金利+団信コスト」の合計値に設定し、保障内容と保険加入義務の有無を併せて確認することが欠かせません。これが後述するシミュレーションの精度を高め、リスク管理を容易にします。
団信のタイプ別メリットと注意点
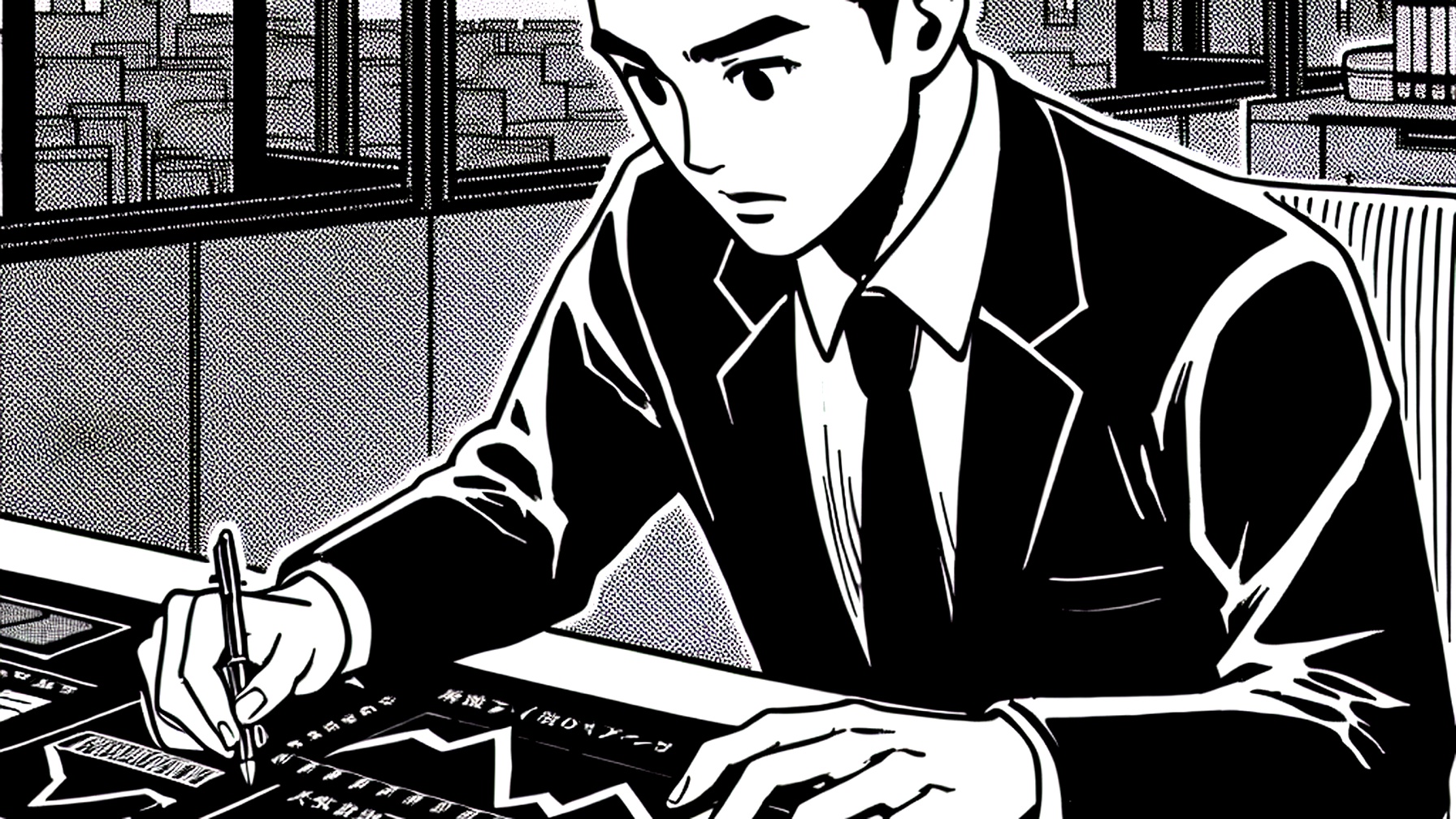
ポイントは、団信の補償範囲が広がるほど安心感は増すものの、保険料も比例して高くなるという単純な構造です。補償範囲は概ね「死亡・高度障害のみ」「がん保障付き」「三大疾病保障付き」「八大疾病保障付き」の四段階に分かれます。
死亡・高度障害のみの基本型は年0.2〜0.3%の保険料で済むため、キャッシュフローを重視する初心者には扱いやすい選択肢です。一方、がん保障付きは年0.1%程度の上乗せで、診断時点で残債がゼロになるプランが増えています。全国銀行協会の2025年データによれば、八大疾病保障付きの加入率は投資用ローンではまだ20%未満にとどまります。保険料負担が大きいため、長期の安定収益が確実な物件を持つ中上級者向きと言えるでしょう。
補償が手厚いほど審査時の告知事項も増えます。たとえば過去の病歴を詳細に申告する必要があり、内容次第では金利が上がったり、保険加入を断られたりするケースもあります。健康状態に不安がある人は、まずは告知項目が少ないネット銀行の簡易告知型を検討し、別途収入保障保険でカバーする発想も有効です。
実は、既存の生命保険を減額して団信で代替することで、毎月の保険料総額を下げることも可能です。このアプローチは家計の固定費を圧縮しながら、投資効率を高める効果があります。保険の見直しを同時に行うと、トータルで数十万円単位のコスト削減につながることも珍しくありません。
金利と保険料を総合して比較する視点
重要なのは、金利と保険料を分けて考えず、35年返済まで含めた総支払額で比較することです。住宅金融支援機構の試算では、借入額3000万円・固定10年2.7%・団信0.3%の場合と、金利3.0%に保険料込みのプランを比べると、総支払額はほぼ同水準になりました。つまり見かけの金利差だけでは優劣を判断できません。
比較の第一歩として、借入希望額と返済期間を入力するシミュレーターを活用し、「金利を0.1%動かした場合に総返済額がいくら変化するか」を確認しましょう。次に、同条件で八大疾病保障を追加し、総支払額がいくら増えるかを試算します。この二段階比較を行うと、保険料のコスト対効果が客観的に見えてきます。
さらに、2025年度も継続している「所得税の青色申告特別控除」を活用すれば、65万円の控除で実効税率を10%下げられるケースもあります。税引き後キャッシュフローをシミュレーションに織り込めば、手厚い団信を選んでも十分に黒字化できるかが判断しやすくなります。
ただし、金利は変動1.5%から2.0%の範囲で推移しており、今後上昇局面に入るリスクも指摘されています。固定期間終了後の金利上昇を1.5%とする厳しめのシナリオも用意し、その際にキャッシュフローが赤字化しないかを必ずチェックしてください。リスクシナリオで耐えられるプランを選ぶことが、長期投資成功の鍵となります。
初心者が押さえるべき金融機関の選び方
まず、投資用ローンを取り扱う主要プレイヤーは都市銀行、地方銀行、信用金庫、ネット銀行の四つに分けられます。それぞれで金利設定も団信の条件も大きく異なるため、最低でも三行以上を比較しましょう。
都市銀行は物件担保評価を重視し、都心のRC造マンションなら最大融資割合(LTV)80%まで伸びることがあります。団信は基本型のみ費用内包型が主流で、がん保障などはオプション扱いです。一方、地方銀行や信金はエリア内の顧客育成を目的に、経営者や医師など属性が高い顧客へ優遇金利を提示する例が増えています。信用金庫では固定3年1.6%に八大疾病団信込みというケースもあり、地元重視の人には魅力的です。
ネット銀行は手続きがオンラインで完結し、金利と団信保険料がワンセットのわかりやすい商品が特徴です。ただし、借入限度額が物件評価額の70%前後に制限されることが多く、自己資金を多めに用意できる人向けです。その分、最短1週間で融資実行まで完了するスピード感があり、競争入札が激しい都心物件では大きな武器になります。
審査に通りやすくなるポイントは、確定申告書の所得を安定させることと、自己資金比率を20%以上確保することです。前年度所得が下がっている場合は、経費計上を見直し、早めに金融機関へ相談することで審査前に改善策を講じる余地があります。結論として、金融機関選びは「金利と団信を含む総返済額」「融資スピード」「審査通過率」の三要素を軸に、物件の取得タイミングと照らして決めることが重要です。
シミュレーション事例で学ぶ判断手順
実例を通じて判断手順を確認しましょう。30代会社員Aさんは、東京都内ワンルームマンション(価格2500万円)を予定利回り4.5%で取得する計画です。自己資金は600万円用意し、ネット銀行の変動金利1.7%・団信込みプランと、地方銀行の固定10年2.6%・団信0.2%上乗せプランを比較しました。
まず、借入額1900万円・返済期間30年で試算したところ、ネット銀行プランは月々の返済額が6万9千円、地方銀行プランは7万5千円になりました。年間家賃収入は112万5千円を想定しているため、運営費30%を差し引くと年間キャッシュフローはネット銀行で約20万円、地方銀行で約13万円です。
次に、金利上昇シナリオとして、変動金利が10年後に1.5%上昇するケースを設定しました。この場合、ネット銀行プランの月々返済が8万3千円となり、年間キャッシュフローはほぼゼロになります。一方、固定金利プランは同期間据え置きなので、キャッシュフローの変動は限定的です。
最後に、団信補償の差を加味します。地方銀行プランは八大疾病保障を付与すると総支払額が約120万円増えますが、保障範囲が広がる安心感があります。Aさんは長期での金利変動リスクと、家族への保障を重視し、地方銀行プランを選択しました。シミュレーションを複数用意し、数字で比較するプロセスが決断の質を高める好例と言えるでしょう。
まとめ
投資用ローンの比較では、「金利+団信」の総支払額を基準にし、保障範囲と審査条件を合わせて検討することが成功への近道です。まず基本型団信で試算し、シミュレーション上のキャッシュフローに余裕があれば疾病保障を追加する流れが安全です。記事で紹介した手順を実践し、少なくとも三つの金融機関に事前相談を行えば、自分に合った最適なローンを選べるはずです。
参考文献・出典
- 全国銀行協会 – https://www.zenginkyo.or.jp
- 国土交通省 住宅局 – https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku
- 住宅金融支援機構 フラット35調査 – https://www.jhf.go.jp
- 総務省 統計局 家計調査 – https://www.stat.go.jp
- 金融庁 主要行等向けの総合的な監督指針 – https://www.fsa.go.jp

