会社の給料だけでは将来が不安、でも本業を辞める勇気もない――そんな悩みから副業を探し始めたとき、「どっちが自分に合うのか」と比較されやすいのが株式や暗号資産と、不動産クラウドファンディングです。少額で不動産に投資できる仕組みは魅力的ですが、リスクや手続きの複雑さをイメージしづらく二の足を踏む人も少なくありません。本記事では、2025年10月時点の最新ルールに基づき、不動産クラウドファンディングを副業として選ぶメリットと注意点、そして具体的な始め方を丁寧に解説します。読み終えるころには、あなた自身が「どっちを選ぶか」を判断できるようになるはずです。
なぜ副業で不動産クラウドファンディングが注目されるのか
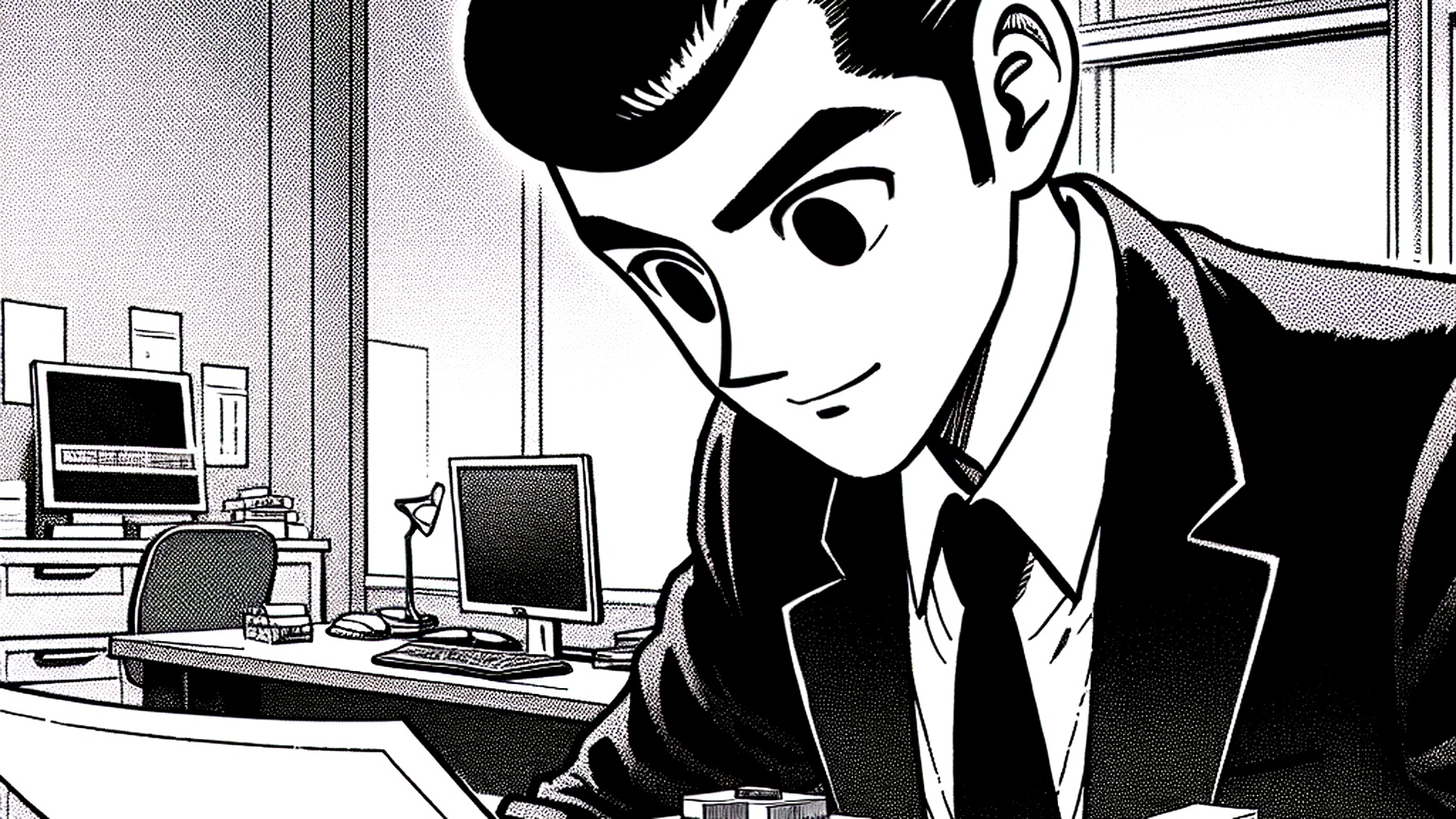
重要なのは、従来の現物不動産投資よりも低コストで始められる点と、運営管理を事業者に任せられる手軽さです。国土交通省の「不動産特定共同事業実態調査(2025年6月)」によれば、オンライン型ファンドの平均投資単位は一口約7万円とされています。
まず現物投資では物件取得とローン返済が重荷になりがちですが、クラウドファンディングなら自己資金の範囲内で分散投資が可能です。たとえば7万円を5つの案件に振り分ければ、空室や賃料下落といった個別リスクを抑えられます。また、運用期間が1〜3年程度に設定される案件も増え、資金を長くロックされない点が働きながらの副業に向いています。
一方で、プラットフォーム選びやリスク把握を怠ると想定外の損失を抱える恐れがあります。金融庁は2025年3月に、事業者の情報開示不足が投資家保護を揺るがす可能性を指摘しました。つまり、手軽さの裏には情報の非対称性が潜んでいるため、投資家側も基礎知識を持つことが欠かせません。
加えて、2025年10月現在、副業規定を設ける企業でも「資産運用型投資は届け出のみで許可」とするケースが増えています。就業規則を確認し、給与所得と雑所得の線引きを理解しておけば、会社員でも合法的に取り組める余地が広がっています。
仕組みとリスクを理解する
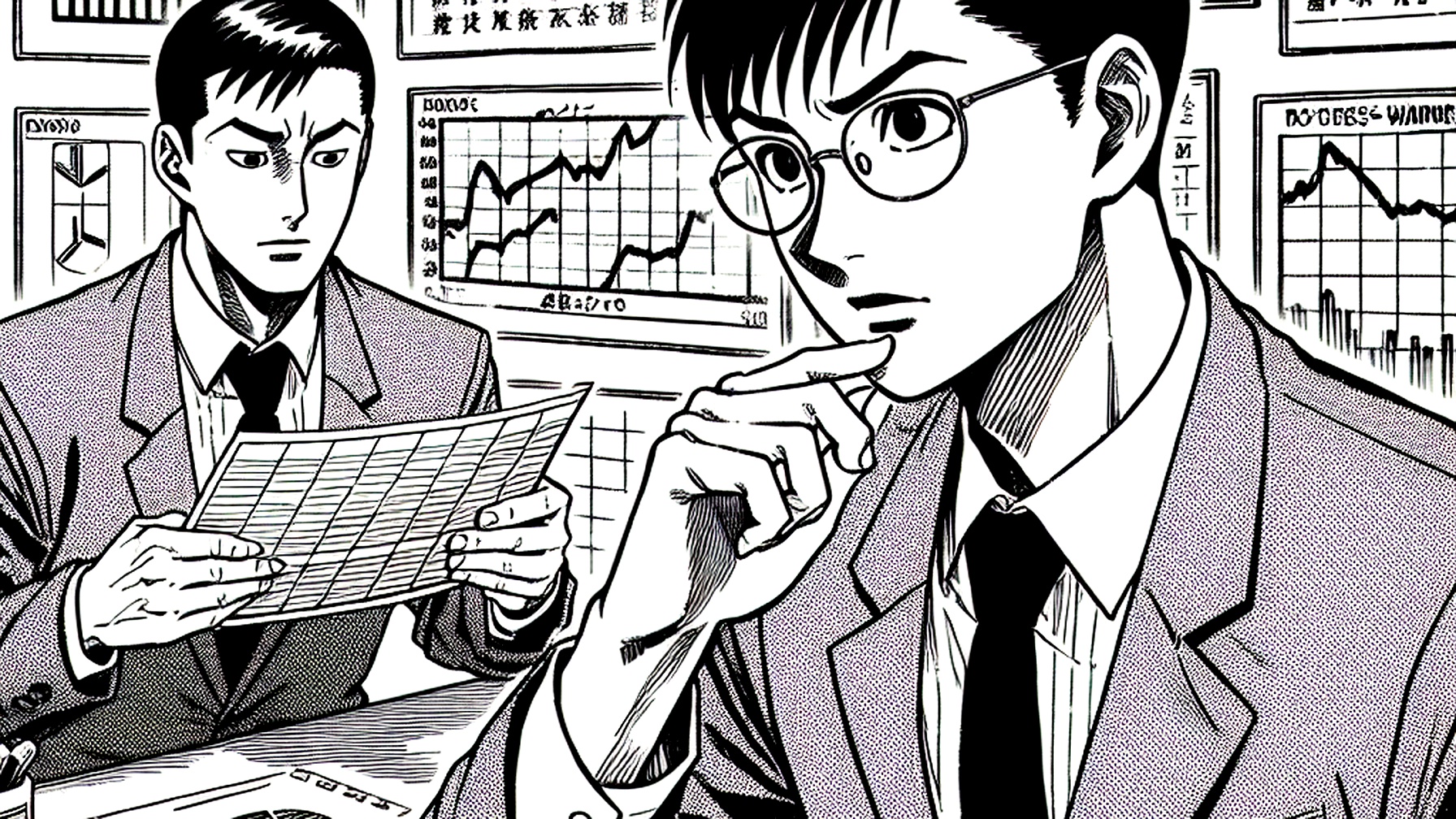
ポイントは、不動産クラウドファンディングが「不動産特定共同事業法」に基づくスキームで運営され、匿名組合契約または任意組合契約を通じて利益を分配する仕組みだということです。投資家は出資金を払い込み、運営会社が物件を取得・運営し、賃料収入や売却益を按分でもらう流れになります。
実は、この構造上のリスクは大きく三つに分類できます。第一に賃料や売却価格が予想を下回る「事業リスク」、第二に建物の自然災害や老朽化による「物理的リスク」、そして第三に運営会社の破綻や不正という「事業者リスク」です。総務省統計局の家賃指数(2025年上期)では、三大都市圏の平均家賃が前年同期比0.8%上昇しましたが、地方中核都市では0.5%下落しています。立地による差は依然として大きいといえます。
さらに、元本保証が禁止されている点も見逃せません。金融庁のガイドラインでは「元本毀損の可能性があることを明示する」ことが義務付けられています。言い換えると、高利回りを謳う案件ほどリスクが内包されているため、想定利回りだけで判断するのは危険です。
最後に分配金の税制を確認しましょう。2025年度のルールでは、匿名組合型は雑所得として総合課税、任意組合型は不動産所得として損益通算が可能です。所得が増えれば税率も変わるため、自身の課税所得帯と合わせてシミュレーションすることが必要になります。
始め方ステップガイド
まず押さえておきたいのは、口座開設から案件選定、入金、運用中フォロー、償還という五つの流れを理解することです。ここでは最短1カ月で初回投資を完了させるモデルケースを紹介します。
最初のステップは、事業者のWebサイトから投資家登録を行い、本人確認書類を提出することです。この際、メールアドレスのほかにマイナンバーカードのコピーが必須となります。登録完了後に、ログイン画面から募集前の案件情報を閲覧できるようになります。
次に案件選定ですが、重要なのは利回りと運用期間だけでなく、物件タイプやエリア、出資総額に占める自己資金割合をチェックすることです。たとえば運営会社が全体の20%を自己資金で保有している案件は、事業者と投資家の利害が一致しやすいと考えられます。また、運用期間1年の短期案件を初回に選ぶと、資金回収のタイミングを早く確認でき副業初心者でも安心です。
入金後は契約成立時書面が電子交付されます。内容を保存し、毎月または四半期ごとに送られてくる運用レポートと照合する習慣をつけましょう。途中で譲渡ができない案件が多いため、運用期間中は基本的に資金を動かせません。その点を踏まえ、生活防衛資金とは別枠で投資額を決めることが大切です。
最後に償還です。運用期間が満了すると元本と分配金が指定口座に振り込まれます。年間20万円を超える雑所得が出た場合は確定申告が必要になるため、年明けの1月中に年間取引報告書をダウンロードし準備しておきましょう。
プラットフォーム選びの比較ポイント
実は、国内でオンライン型不動産クラウドファンディングを行う事業者は2025年10月時点で70社を超えています。どっちのサービスを使うか迷ったら、次の四つの視点で比較すると絞り込みやすくなります。
第一に「運用実績の長さと償還率」です。金融庁のデータによると、2022年以前に設立した15社の平均償還率は99.2%、2023年以降の新規21社は97.5%でした。歴史の長い事業者ほどトラックレコードが豊富で安心感があります。
第二に「物件の開示情報量」です。住所を市区町村レベルまで公開し、鑑定評価書やデューデリジェンス(物件精査)報告を提示する事業者は透明性が高いと言えます。情報開示が不十分な場合はリスク上乗せで利回りが高く見える傾向があるため要注意です。
第三に「手数料体系」です。多くのプラットフォームでは投資家側の口座維持手数料は無料ですが、中途換金が可能なマーケットプレイス型では売却手数料が2〜5%かかる例があります。想定される運用スタイルに合わせてコストを試算しましょう。
第四に「独自の優遇サービス」です。例えば2025年度は、一定額以上を投資した利用者に優先抽選権を付与するキャンペーンを実施する事業者が増えています。限定利回り案件に参加しやすくなるメリットがありますが、継続条件を伴う場合があるため詳細規約を必ず確認してください。
税金と2025年度の優遇制度
まず、税金面で押さえておきたいのは課税区分です。匿名組合型の分配は雑所得として総合課税になり、最高税率は住民税を含め55%に達します。一方で給与所得者が20万円以下の雑所得しか得ていない場合、確定申告が不要となる特例があります。ただし、副業収入が20万円を超えた時点で全所得を申告する義務が生じるため注意が必要です。
2025年度の改正点として、不動産クラウドファンディングに直接的な税額控除制度はありませんが、設備更新費用に充当された部分を内部留保とみなして配当課税を繰り延べできる「利益準備金スキーム」に関する通達が4月に明確化されました。これにより一部案件では、分配の一部が元本返済扱いとなり実質課税を後ろ倒しできるケースがあります。制度適用の有無は案件ごとに異なるため、契約成立前書面を必ず読み込みましょう。
また、地方創生を目的とした「地域不動産クラウドファンディング支援事業(2025年度〜2028年度)」が総務省と国土交通省の共同事業としてスタートしました。対象案件に投資すると、年間5万円を上限に還元される電子地域ポイントが付与されます。ポイントは地元の物産購入や観光施設で利用できるため、利回りに加えインセンティブを享受できる仕組みです。ただし、予算枠に達した時点で終了するため早期に埋まる可能性があります。
さらに、副業としての所得が一定基準を超えた場合は住民税の納付額も増えます。会社への副業バレを避けたいなら、確定申告時に「普通徴収」を選択し、自分で納付書払いにする方法が有効です。ただし自治体によっては給与天引きしか選べない場合もあるので、事前に確認しておきましょう。
まとめ
今回は、副業として不動産クラウドファンディングを選ぶ意義と始め方を具体的に解説しました。少額・短期間・管理不要という特徴が忙しい会社員に適している一方で、情報不足によるリスクは看過できません。運営実績のある事業者を選び、案件内容と税制を十分に理解したうえで、小口から分散投資をスタートすることが賢明です。まずは就業規則と資金計画を確認し、最初の一歩を踏み出してみてください。副業で得た追加収入が、将来の選択肢を広げてくれるはずです。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産特定共同事業実態調査(2025年6月) – https://www.mlit.go.jp/
- 金融庁 クラウドファンディングに関するガイドライン(2025年3月改訂) – https://www.fsa.go.jp/
- 総務省統計局 家賃指数(2025年上期) – https://www.stat.go.jp/
- 日本証券業協会 不動産クラウドファンディング市場レポート2025 – https://www.jsda.or.jp/
- 一般社団法人クラウドファンディング協会 年次報告書2025 – https://jcf.or.jp/

