インフレ率が上昇し、銀行預金の金利では資産を守り切れないと感じていませんか。実は、不動産投資、とりわけ築古の収益物件は、物価上昇局面で価値が目減りしにくい資産として再注目されています。本記事では、投資経験ゼロの初心者でも理解できるように、インフレ対策として築古物件を活用する方法を体系的に解説します。読み終える頃には、物件選びから資金調達、運営のコツまで具体的な行動イメージが得られるでしょう。
インフレ下で不動産が頼りになる理由
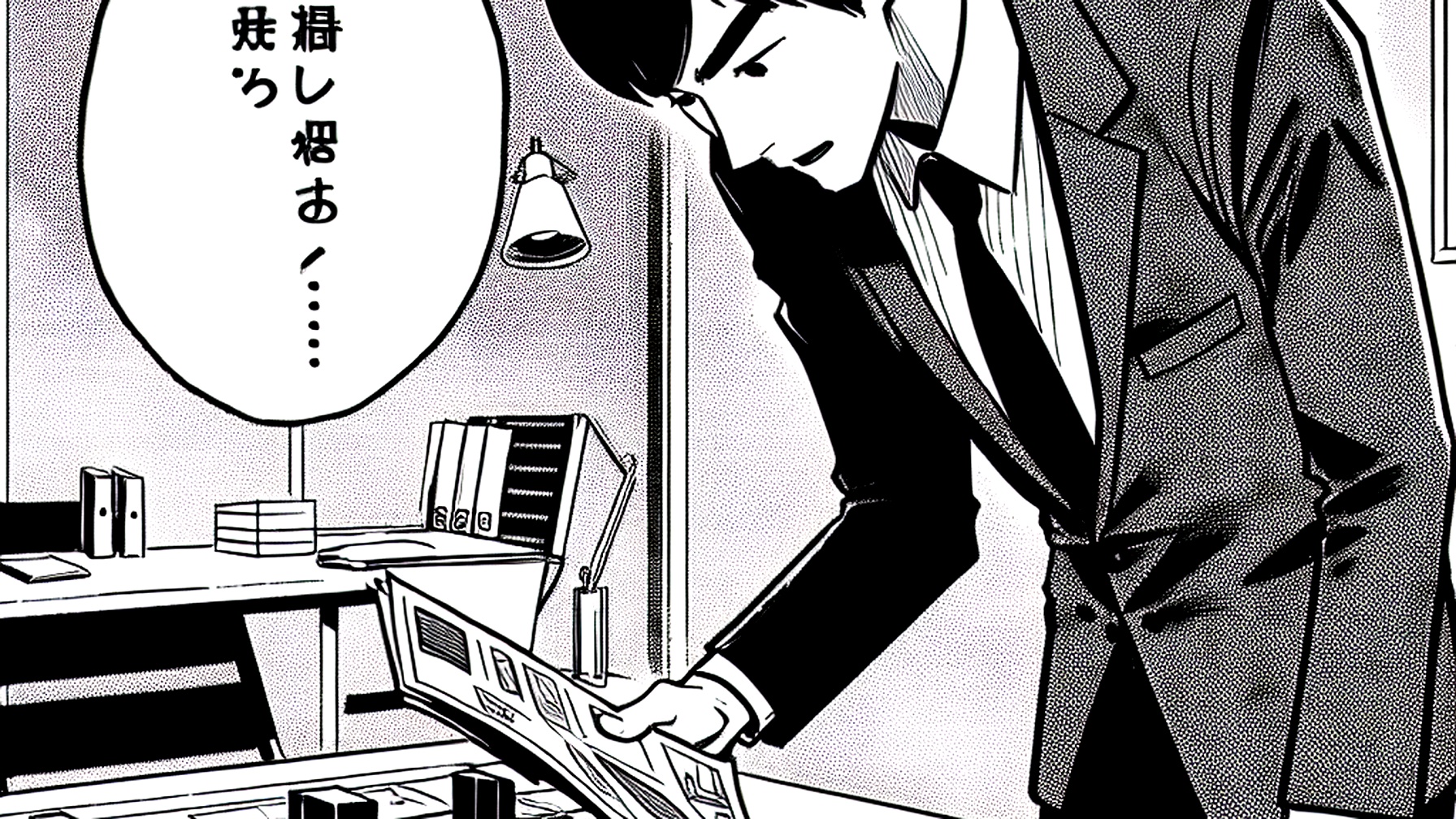
まず押さえておきたいのは、インフレ期に不動産が現金より相対的に強いという事実です。総務省統計局の消費者物価指数によると、2023年から24年にかけて物価は年2%超のペースで上昇し、2025年10月時点でも同水準を維持しています。現金をただ持つだけでは購買力が目減りする一方、家賃は物価に連動しやすいため、収益物件はキャッシュフローを守りやすいのです。
しかし、不動産なら何でも良いわけではありません。新築は表面利回りが低く、インフレによる家賃上昇があってもローン返済に回る割合が大きくなりがちです。対照的に、築古物件は取得価格が抑えられるうえ、建物部分の減価償却によって課税所得を圧縮できる点が強みです。つまり、インフレ下でキャッシュを働かせつつ、手残りも確保しやすい選択肢と言えます。
一方で、築年数が古いほど修繕リスクが高まる点は否定できません。そのため、後述する「運営術」で解説するように、購入前の調査と購入後のメンテナンス計画が成功のカギとなります。
築古収益物件の魅力と注意点
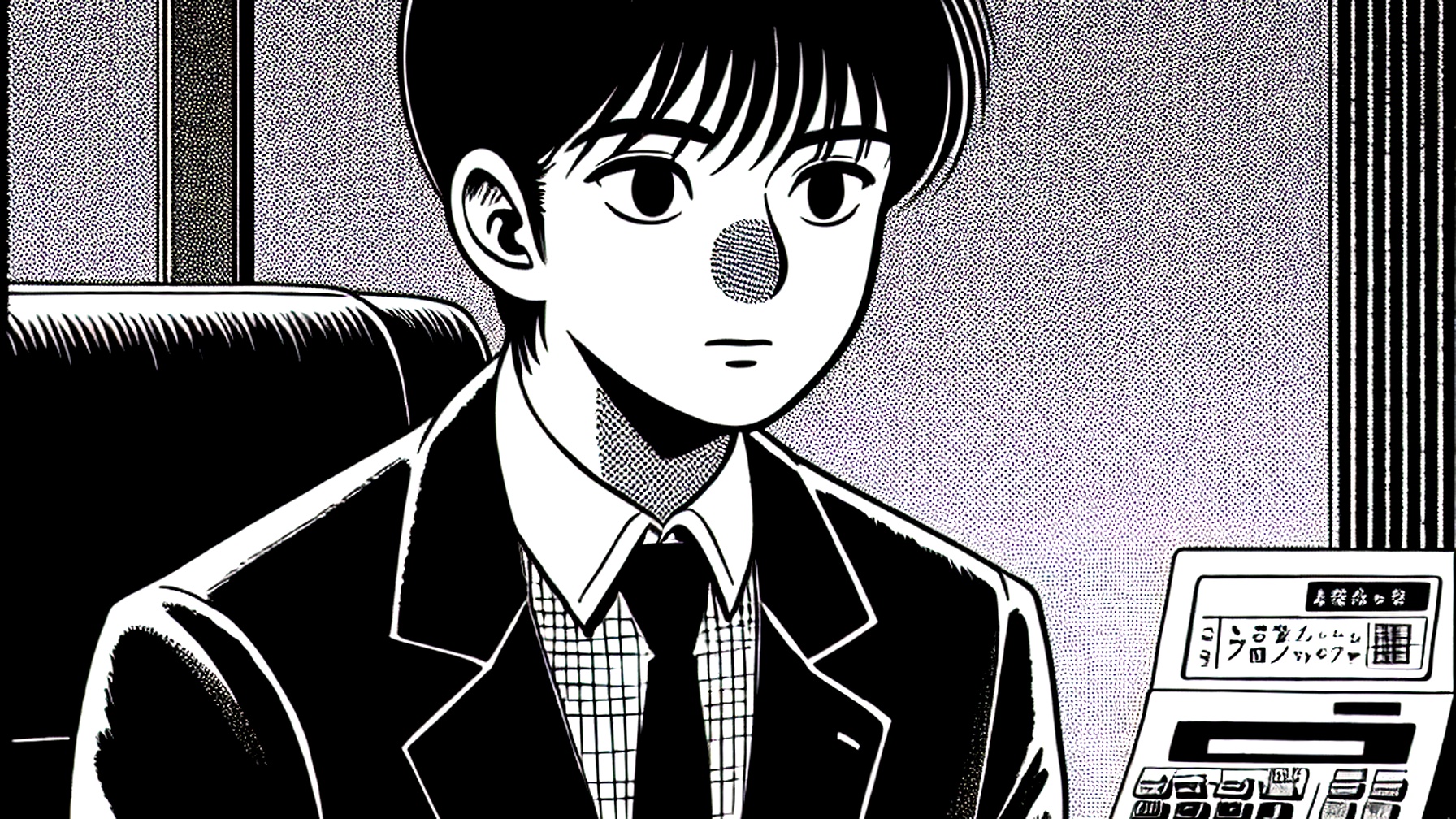
重要なのは、築古物件の利回りとリスクを正しく天秤にかけることです。日本不動産研究所のデータでは、築20年以上の木造アパートの想定利回りは都心近郊で7〜9%、地方中核都市で10%前後が平均とされています。これは築浅物件より3ポイント前後高い水準で、インフレ局面では手元キャッシュが早く回収できるため有利です。
ただし、設備残存年数が短いと金融機関の融資年数も伸びにくくなります。例えば、耐用年数切れの木造物件は最長で12年程度の融資しか受けられない場合があります。返済期間が短いと月々の返済額が増えるため、物件選びでは構造、立地、入居需要の三点を重ね合わせることが不可欠です。
加えて、築古ならではの隠れた修繕項目も見逃せません。屋根防水や給排水管の劣化は、外観からは把握しにくいものの、将来的に数百万円規模の出費となることがあります。購入前に専門家とともにインスペクション(建物診断)を行い、5年以内に発生しそうな修繕費を見積もることで、利回りの過度な楽観を防げます。
結局のところ、築古物件は「高利回り」と「高リスク」がセットになっています。後段で触れる運営術を含め、総合的に判断してこそインフレ対策の武器になるのです。
初心者でもできる資金調達と融資戦略
実は、築古収益物件こそ初心者にチャンスが開けています。理由は、物件価格が抑えられるため自己資金比率を高めやすく、金融機関の与信がまだ十分でない個人でも審査を通りやすいからです。具体的には、物件価格の20〜30%を自己資金として用意し、残りを金融機関から調達する形が一般的です。
2025年度も続く不動産投資ローンの主力は都市銀行ではなく、地銀や信用金庫です。金利は1.5〜3.5%が主流で、融資年数はRC造で法定耐用年数以内、木造なら残存耐用年数プラス数年が限度となります。複数行を比較するときは、金利差だけでなく融資手数料や繰上返済の条件を確認してください。0.5%の金利差は、3000万円を15年借りた場合で総返済額に約130万円の違いを生むため、軽視できません。
また、購入後のキャッシュフロー悪化を避けるには、金利上昇リスクにも備える必要があります。変動金利を選ぶ場合、ストレスシナリオとして「金利が2%上がる」「空室率が20%に達する」といった前提でシミュレーションを作成しましょう。無理のない返済計画が見えれば、金融機関との交渉でも説得力が増します。
最後に、自己資金を増やす手段として2025年度も利用可能な「小規模企業共済」や「iDeCo」を活用する方法があります。これらは掛金が所得控除になるため、節税しながら投資原資をつくれる点がメリットです。こうした補助制度を組み合わせると、初心者でも資金面のハードルを下げやすくなるでしょう。
購入後に価値を高める運営術
ポイントは、家賃を維持しながらコストを抑えるバランスです。築古物件で最初に取り組みたいのは、共用部の美観向上に直結する小規模リフォームです。外壁塗装より先に、照明のLED化やポスト交換、エントランス清掃の徹底など、投下資本に対して入居者満足度を上げやすい施策を優先します。
家賃改定はタイミングが重要です。国土交通省の賃貸住宅市場データによれば、同一エリアでの家賃差は築年数より室内設備の新旧で大きく開きます。そこで、退去が出た部屋から順に、Wi-Fi無料設備やスマートロックを導入することで、2〜3千円の家賃アップが見込みやすくなります。初期投資は1室あたり10万円台に収まる例も多く、投資回収期間が1〜2年と短い点が魅力です。
維持費を抑える手段として、管理会社の見直しも欠かせません。管理委託料は月額家賃の5%が相場ですが、複数社を比較すると4%台前半まで下げられるケースがあります。ただし、安さだけを追求して対応が悪化すると空室期間が伸びかねません。レスポンス速度や入居付け実績を確認し、総合点で選ぶ視点が大切です。
さらに、長期的なインフレ環境では金利動向を定期的にチェックし、固定から変動、またはその逆への借換えを検討することで、キャッシュフローを安定させられます。借換えには諸費用がかかりますが、残債2000万円・金利差1%・残期間10年なら、総返済額は約110万円変わる計算になり、検討に値します。
2025年度の税制と補助で得するコツ
まず、2025年度も不動産取得税の軽減措置が継続され、個人が住宅用物件を取得する際、評価額1200万円までの税率が1.5%に据え置かれています。これは築古物件でも要件を満たせば適用可能で、取得時コストを確実に下げられるため活用しない手はありません。
一方で、所得税の面では減価償却がキャッシュフローを守る強力な盾になります。木造なら築22年超で4年、RC造なら築47年超で10年の定額法が原則ですが、短期に大きく経費計上できるため、インフレによる名目家賃上昇分を税負担で相殺しやすくなります。加えて、青色申告特別控除65万円を確保するため、小規模でも帳簿を複式簿記で作成し電子申告する体制を整えましょう。
修繕費と資本的支出の区別も節税効果に直結します。修繕費として当期経費で落とせる範囲を明確にし、資本的支出に該当する場合でも複数年に分けて減価償却することで課税所得を平準化できます。税理士への依頼費用は経費にできるため、初心者ほど早めに専門家に相談するほうが最終的には得策です。
Finally, 2025年度から開始された「省エネ賃貸住宅改修補助金」は、賃貸住宅の断熱改修に対し費用の3分の1(上限200万円)を補助する制度です。工事完了後に申請する仕組みで、申し込み期限は2026年3月末までとなっています。築古物件でランニングコストを下げつつ物件価値を高める上、キャッシュフローを圧迫しにくい制度として検討してみてください。
まとめ
インフレが続く局面では、貨幣価値の減少に晒されにくい築古の収益物件が資産防衛の有力な選択肢となります。取得価格が低めで利回りが高く、減価償却や税制優遇を活用できる点が初心者にも魅力です。一方で、修繕リスクと融資期間の制約を見誤ると手残りが減るので、事前調査と長期シミュレーションが欠かせません。この記事で示した資金調達、運営改善、税制活用のステップを踏みながら、まずは小規模でも一歩を踏み出してください。行動することでしか、インフレに負けない資産形成は始まらないのです。
参考文献・出典
- 総務省統計局 – https://www.stat.go.jp/
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp/
- 国土交通省 賃貸住宅市場データ – https://www.mlit.go.jp/
- 全国地方銀行協会 金融統計 – https://www.chiginkyo.or.jp/
- 中小企業庁 省エネ賃貸住宅改修補助金要項 – https://www.chusho.meti.go.jp/

