ここ数年、株式よりも値動きが緩やかで配当利回りが高い金融商品としてREIT(リート)が注目されています。しかし「分配金は本当に安定するのか」「中古マンションを直接買うのとどちらが得なのか」と迷う初心者も多いでしょう。本記事では、REITの基本から中古不動産との比較、2025年度の税制を踏まえた運用のコツまでを丁寧に解説します。読み終えたとき、あなたは“中古”というキーワードを軸にREITを選ぶ方法と、分配金を最大化する具体策を理解できるはずです。投資経験が浅い方でも実践できる内容なので、ぜひ最後までお付き合いください。
REITの仕組みと分配金が生まれる流れ
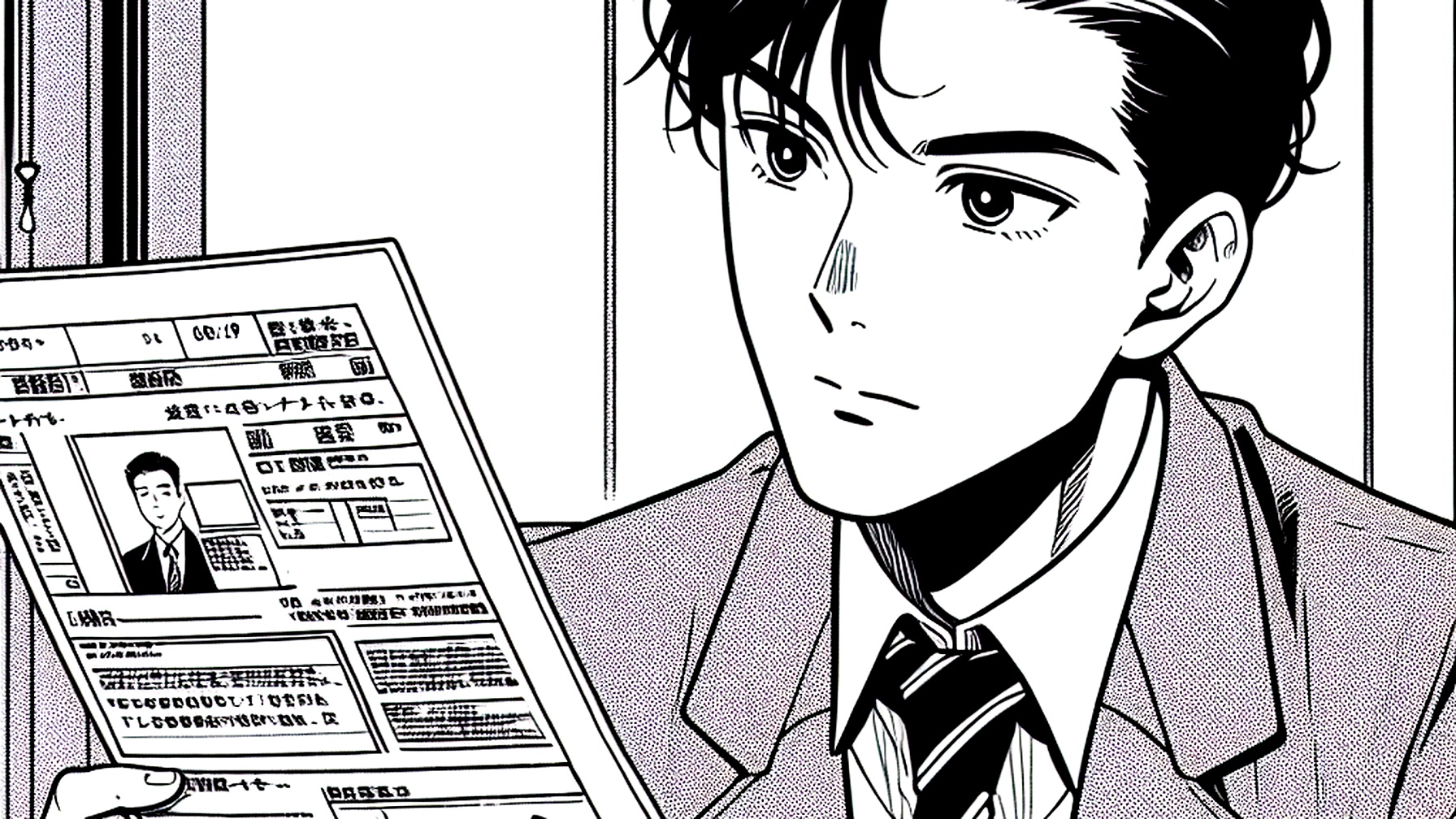
まず押さえておきたいのは、REITがどのように家賃収入を集めて分配金へと変換するかという基本構造です。REITは多数の投資家から資金を集め、その資金でオフィスや住宅、物流施設を購入し賃料を得ます。法律上、利益の90%超を分配すれば法人税が実質ゼロになるため、投資家には家賃収入の大部分が「分配金」として戻ってくる仕組みです。
一方で、分配金額は物件の稼働率や修繕費の増減に左右されます。国土交通省の不動産証券化統計によると、2024年度の住宅特化型REITの平均稼働率は97%前後で推移し、分配金利回りは3.5〜4.0%でした。つまり稼働率が高ければ高いほど分配金は安定し、家賃の下落や修繕費の膨張が起これば減額リスクが生じるというわけです。
重要なのは、REITではポートフォリオの入れ替えにより稼働率を維持しやすい点です。運用会社は空室リスクが高まる物件を売却し、人気エリアの物件へ資金を再投資できます。個人が中古マンション一棟を所有する場合と比べ、物件の流動性が高い分リスク分散が効くのがREITの強みと言えるでしょう。
中古マンション投資との比較で見えるメリット・デメリット

次に、REITと中古マンションを直接買う方法を比較することで、それぞれの利点と弱点を整理します。中古マンションは物件価格が新築より抑えられるため、利回りは高い傾向があります。国土交通省の2025年住宅市場動向調査では、築20年・都心5区のワンルーム実質利回りが平均5.2%と報告されています。
しかし、自己資金を数百万円単位で投入し、金融機関の融資審査を受け、管理会社との契約や修繕積立金の支払いなど、オーナーの負担は決して小さくありません。また、築年数が進むと大規模修繕や設備更新が必要になり、想定外のコストが発生します。
一方、REITは1口数万円から投資でき、物件管理をプロに任せられる点が初心者には魅力です。中古マンション特有の修繕リスクも運用会社が複数物件で平準化するため、分配金がいきなりゼロになる事態はまれです。ただし、市場価格は日々変動し、分配金が株主総会の決議で減額される可能性もあるため、相場チェックは怠れません。つまり、資金が潤沢で自分で管理を学びたい人には中古マンション投資、少額から分散投資したい人にはREITが向くと言えます。
分配金を安定させる中古REIT選びのポイント
ポイントは、ポートフォリオに中古物件を多く組み入れるREITの特徴を見抜くことです。中古物件は取得価格が低く、初年度から高い利回りを生みやすい半面、設備劣化が早く修繕費がかさむ恐れがあります。運用報告書を読むと、築年数と修繕計画が必ず掲載されているので、築15年以内の割合が過半かつ長期修繕引当金を十分に積んでいるか確認しましょう。
また、重要なのは立地分散です。中古物件を活用する住宅型REITのなかには、首都圏と地方政令都市をバランスよく配置し、稼働率を平準化している銘柄があります。地方物件は都心より賃料下落リスクが高いものの、取得価格が低い分、利回りを押し上げられます。このバランスがうまく取れているかが分配金の安定性を左右するのです。
さらに、スポンサー企業の資本力も忘れずに調べましょう。大手デベロッパーがバックにいるREITは、資金調達や物件供給を優位に進められます。結果として、賃料交渉力が高まり空室対策も迅速に行えるため、分配金の減額リスクが抑えられるのです。投資口価格が一時的に下落しても、分配金が維持されていれば長期投資では総リターンが安定するケースが多いと覚えておくと良いでしょう。
2025年度の税制とコストを踏まえた収益最大化のコツ
実は、税引き後の手取りを増やす工夫こそがリターン最大化の近道です。2025年度も上場REITの分配金には配当控除が適用されず、20.315%の源泉徴収が行われます。この税負担を和らげる方法として、新NISAの成長投資枠が有効です。年間240万円まで非課税でREITを保有できるため、5年間満額活用すれば最大1200万円の投資枠が確保できます。
一方、証券会社の売買手数料も要チェックです。大手ネット証券では既にREITの売買手数料を無料化する動きが広がり、2025年10月時点で主要3社はいずれも国内ETF・REIT取引を恒久無料としています。つまり、手数料コストは気にせず、タイミングを分散して購入しやすくなったというわけです。
分配金再投資も効果的です。例えば年4%の利回りで分配金を受け取り、そのまま同じREITを買い増す「DRIP(Dividend Reinvestment Plan)」を行うと、利回りによる複利効果が働きます。金融庁のシミュレーションでは、年4%で20年再投資すると元本は約2.19倍に増えると試算されています。NISA枠内でDRIPを続ければ、非課税と複利の二重効果が得られるため、老後資金づくりにも有効です。
最後に、外国税控除の落とし穴にも触れておきます。海外REIT ETFに投資すると、現地課税で10〜30%が差し引かれ、日本でさらに20.315%課税される二重課税が発生します。2025年度税制でも外国税額控除を確定申告で取り戻せますが、手間がかかるのが実情です。国内REITであればこの手間が不要なので、初心者が最初に選ぶのは国内銘柄が無難だといえるでしょう。
まとめ
ここまで、REIT 分配金 中古の三つのキーワードを軸に、仕組み、比較、選び方、税制対策を順に見てきました。ポイントは、中古物件を多く組み込むREITでも、築年数や修繕計画、スポンサー力を確認すれば分配金を安定させやすいという点です。また、新NISAや手数料無料化を活用すると、税負担と取引コストを抑えて実質利回りを引き上げられます。今後は経済環境の変化を見守りつつ、少額で複数銘柄を継続購入し、分配金を再投資する戦略が堅実です。まずは証券口座で運用報告書を読み比べ、あなたのリスク許容度に合ったREITを一口購入してみましょう。行動を起こすことで、不動産投資の第一歩が現実の成果へと近づきます。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産証券化統計月報 2025年9月号 – https://www.mlit.go.jp/
- 国土交通省 住宅市場動向調査 2025年度版 – https://www.mlit.go.jp/
- 金融庁 新NISA制度の概要 2025年改訂版 – https://www.fsa.go.jp/
- 日本取引所グループ REIT・ETF市場統計 2025年8月 – https://www.jpx.co.jp/
- 各社ネット証券 手数料比較表 2025年10月更新 – https://media.example.com/securities-fee-2025
- 総務省 統計局 家計資産調査 2024年度 – https://www.stat.go.jp/

